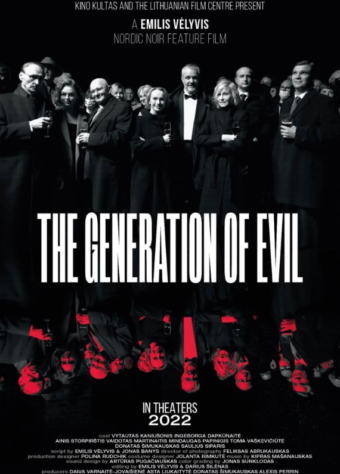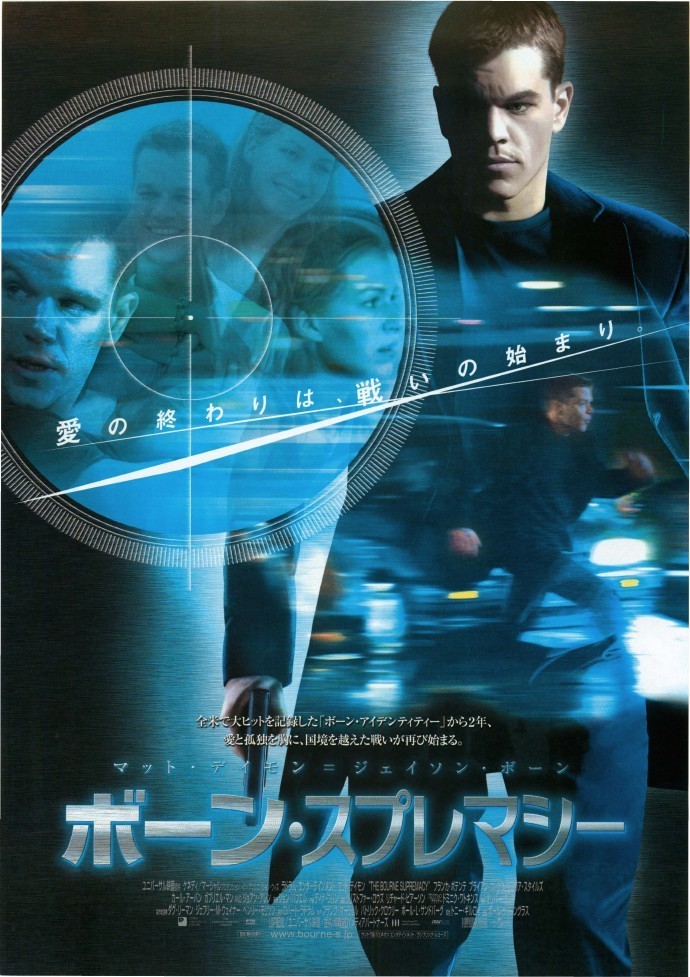あなたはなぜ“大嘘吐きの殺人鬼”の言葉を、それでも信じるのか?
死刑が確定した連続拷問殺人鬼。多くの少年少女を殺害し「爪」をコレクションしてきた彼は、立件された事件のうち1件は、「冤罪事件」だと青年に語り出した……。
映画『死刑にいたる病』は、櫛木理宇の同名小説を『孤狼の血』(2018)『凪待ち』(2019)など、社会とそこに生きる人間の闇を描き続けてきた白石和彌監督が映画化したサイコ・サスペンスです。
本記事では、映画『死刑にいたる病』の結末・ラストシーンで描かれたものの意味についてクローズアップ。
最後の面会室での場面で語られた「“いかにもな”連続拷問殺人鬼の哀しき物語」から見えてくる、映画が描き出す“死刑にいたる病”の別名こと“物語にすがる病”などを考察・解説していきます。
CONTENTS
映画『死刑にいたる病』の作品情報

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
【公開】
2022年(日本映画)
【原作】
櫛木理宇『死刑にいたる病』
【脚本】
高田亮
【監督】
白石和彌
【キャスト】
阿部サダヲ、岡田健史、岩田剛典、宮崎優、鈴木卓爾、佐藤玲、赤ペン瀧川、大下ヒロト、吉澤健、音尾琢真、岩井志麻子、コージ・トクダ、中山美穂
【作品概要】
櫛木理宇の同名小説を『孤狼の血』(2018)『凪待ち』(2019)などで知られる白石和彌監督が映画化したサイコ・サスペンス映画。
『彼女がその名を知らない鳥たち』(2017)の阿部サダヲが連続拷問殺人鬼・榛村大和を、『そして、バトンは渡された』(2021)の岡田健史が「冤罪事件」を調べる青年・筧井雅也を演じたほか、岩田剛典、中山美穂らが共演した。
映画『死刑にいたる病』のあらすじ

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
大学生・筧井雅也の元に届いた一通の手紙。
それは世間を震撼させた稀代の連続殺人鬼・榛村大和からだった。
「罪は認めるが、最後の事件は冤罪だ。犯人が他にいることを証明してほしい」
過去に地元のパン屋で店主をしていた頃には信頼を寄せていた榛村の願いを聞き入れ、事件を独自に調べ始めた雅也。
しかし、そこには想像を超える残酷な事件の真相があった……。
映画『死刑にいたる病』結末・ラストシーンを考察・解説!

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
“首根っこ”を押さえて褒める榛村
かつて少年時代に榛村と出会って弟との「痛い遊び」を強いられ、成長後の再会では根津かおるを“選ばされた”ことで榛村からの精神的支配に苛まれ続けていたという青年・金山一輝の証言により、殺人鬼・榛村が唯一「冤罪」と訴えた殺人事件も結局は彼の凶行だと察した雅也。
映画終盤、雅也は自身が感じとった真相を面会室内で榛村に告げますが、榛村は金山の証言の小さな矛盾点を指摘。「かおる殺害犯=金山説」を即座に語り上げた上で、警察すらも存在を知らなかったという金山との接触ができた雅也を例のごとく「すごいじゃないか」と褒めます。
称賛の言葉を語る声とともに、面会室の両者を断絶しているはずのアクリル板の壁を越えた榛村の幻影は、椅子に座る雅也の体に触れます。その触れ方はまさに榛村が演じてきた「父親」のように見えますが、一方でその触れ方に一つの「違和感」を覚えるのも事実です。

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
親が子を褒める時、親は子の体の“どこ”を触るか……その様子を映像としてイメージした方の多くは、「微笑みながら子の“頭”を撫でる親の姿」が脳裏に浮かんだのではないでしょうか。
対して、同場面での榛村が触れたのは、雅也の“首のうなじ”……それだけでは、「“撫でる”という動作でなくても、子の体に触れながら何かを褒める親もいるだろう」という言葉で済むかもしれませんが、映画作中の「雅也のうなじに触れる榛村の手」を強調するかのように映し出した画は、観る者に否が応でも“ある問い”をイメージさせます。
榛村が手で触れたのは、雅也の“首のうなじ”などではなく、彼の“首根っこ”なのではないか……「獣が、幼い児の首根っこを咥えてどこかへ移動するように」と言うと聞こえはいいですが、言葉の表面上では雅也を称賛しているにも関わらず、その言葉から雅也がイメージした榛村は自身の“首根っこ”を触れている……むしろ、“押さえている”。
それは、逮捕され裁判に至った現在でも「痛い遊び」を続けてきた榛村が、標的となった子どもたちにしてきた“支配”のあり方を最も象徴する画といえます。
“いかにもな”連続拷問殺人鬼の哀しき物語

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
子に愛情を与えることはなく、“与える者”としての男への依存によって生が形作られた母。そして母に集っては去っていき、その子である自身に対しては“一方的な暴力”を与えていった歴代の彼氏という“父のような獣”たち……。
そのような環境で幼少期を過ごした榛村が継続させ、果てには連続拷問殺人という行為にまで発展させたのが、「痛い遊び」でした。
別名「父親遊び」ともいえるその遊びで、榛村が「親に認められない子どもの“父親”かのように振る舞ったのち、拷問殺人という“一方的な暴力”を徹底的に与える」に及んだのも、母の歴代の彼氏たちに唯一与えられた“一方的な暴力”から着想した“ごっこ遊び”に過ぎないからなのかもしれません。
あるいは、「“親子”という支配・被支配の関係であったから、子の自身は母から愛情を与えられなかった」と認識した榛村は、「痛い遊び」を通じて“父のような獣”となることで、“父のような獣”にすがり続けていた母と近い心境にある、存在の肯定に依存するこどもたちから「母が“父のような獣”に向けていた感情」と“非なるが近いもの”を得たかったのかもしれません。
そして映画は、最後の面会にて雅也が尋ねた「榛村の母の爪は綺麗だったか」という問いに対する榛村の答えによって、連続拷問殺人鬼の知られざる物語を垣間見せるのです……。
“物語”にすがる者を嘲笑う物語

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
……しかしながら、それらの「連続拷問殺人鬼の知られざる物語」は、単なる想像で形作られたものに過ぎません。
そもそも映画作中、榛村は一度も「自身の心の内を語った」「自分は真実を語った」とは明確に発言していませんし、それは裁判中でも同様です。
そして自身の母の爪に関する言葉も、映画作中で多くの人間の心を弄び、その中で多くの嘘を吐き続けてきた榛村の発言である以上、もはや真偽を考えることすらバカバカしいといえます。
それではなぜ、大嘘吐きの連続拷問殺人鬼・榛村の母の爪に関する言葉を聞いた雅也、そして映画を観る者は、その言葉を信じてしまうのか。それは多くの人々が、人生や自己の肯定のためにこそ「物語」を求めてしまうためです。
人間は、他者の人生から“物語”を見出し、その意味を読み解くことで「彼は生涯、不幸であった」「彼女の人生は、最期まで幸福なまま幕を下ろされた」と好き勝手な解釈をした上で他者の認識・評価を下します。
それは自分自身であっても同様であり、元々意味も何もないはずの生を手放しに肯定できないがゆえに、その生に意味を見出すために“筋道が立てられた、自身を含め誰もが理解・肯定してくれる解釈”としての物語を求め、すがってしまうのです。

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
なお、映画及び原作小説タイトルの元ネタである哲学書『死に至る病』(1849)にて、著者である哲学者キェルケゴールは全ての人間が意識・無意識に関わらず“死に至る病=絶望”の状態にあり、その絶望を糧に“真の自己”へと辿り着くため神を真に信仰すべきだと語っています。
しかし、キェルケゴールが同著で信仰の対象に挙げたキリスト教もまた、神ヤハウェ及び神の子イエスを巡る“物語”の基づくものであり、そもそも宗教そのものが「長年人々の間で共有されてきた“物語”」といえます。それゆえに、神の信仰もまた「“生を肯定するための物語”を求め、すがる」という人間の性に過ぎないのかもしれません。
あれだけ多くの嘘に騙され続けてきたにも関わらず、母の爪に関する言葉を聞いただけで、連続拷問殺人鬼・榛村大和の人生に“物語”を見出そうとする雅也と、映画を観る者たち。
その瞬間、『死刑にいたる病』という物語は、どれだけ精神を消耗させられても“物語”で生を認識しようとする人間の性……“物語にすがる病”に蝕まれた人々を嘲笑うのです。
まとめ/“物語にすがる病”という死刑にいたる病

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
「自分の本当の父親は、連続拷問殺人鬼かもしれない」という物語に取り憑かれ、一度は人を殺めかけた雅也。その行動もまた、榛村に与えられた物語に惹かれてしまったがゆえに表面化した“物語にすがる病”の症状の一つといえます。
そして映画では、ラストシーンにて灯里というもう一人の“罹患者”を描くことで、キェルケゴールが『死に至る病』で語った絶望と同じく、“物語にすがる病”も全ての人間が罹っている病であると提示したのです。
自己肯定を渇望する“子どものような大人”も含め、“物語にすがる病”に悩まされる子どもたちへ、それぞれにうってつけの物語を与え、子どもたちが蕩けるような充足感を得た後に“一方的な暴力”で物語を取り上げるという行為を続けてきた榛村。

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
子どもたちに夢と希望を与える“大人”な児童文学作家と、老若男女問わずどこまでも残酷を求め続ける“子ども”の二面性でもって魅惑的な物語を紡ぎ続けた彼も、物語で人心を誑かし狂わすことでしか他者とのコミュニケーションができない人間……“物語にすがる病”の罹患者なのでしょう。
そして榛村は、物語を利用した「痛い遊び」を続けたことで逮捕され、ついに死刑判決へと至りました。
もしかすると、榛村を「痛い遊び」に駆り立てた“物語にすがる病”こそが、文字通り“死刑にいたる病”なのかもしれません。
ライター:河合のびプロフィール
1995年生まれ、静岡県出身の詩人。
2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部へ加入。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介