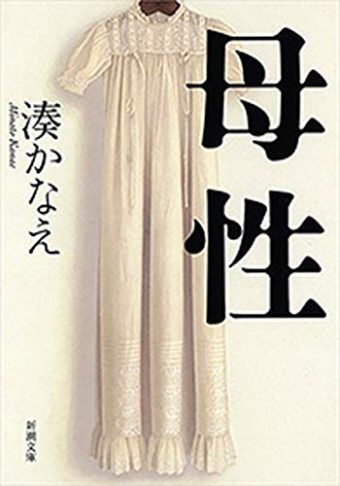第35回東京国際映画祭『あちらにいる鬼』
2022年にて35回目を迎える東京国際映画祭。コロナ感染症の影響も落ち着き、本格的な再始動を遂げた映画祭は2022年10月24日(月)に開会し、11月2日(水)まで開催されます。
作家・井上荒野が自身の父である作家・井上光晴と母・郁子、そして瀬戸内寂聴の男女3人の関係を描いた小説を、廣木隆一監督が映画化した作品がガラ・セレクション部門で披露されました。
その原作小説と同じタイトルを持つ作品が寺島しのぶと豊川悦司、広末涼子が出演した映画『あちらにいる鬼』です。
自由奔放に生きながらも、様々な葛藤を抱えた人生に区切りを付けようと出家、そして多くの人の心の支えとなる存在になった作家・瀬戸内寂聴。彼女と複雑な関係を結んだ、その複雑な人物像は原一男監督のドキュメンタリー・ドラマ映画『全身小説家』(1994)に描かれた井上光晴。
2人に翻弄されつつ夫の伴侶であり続け、寂聴とは良き友人となった井上郁子。彼らの複雑な物語は、どのように映画化されたのでしょうか。
【連載コラム】『TIFF東京国際映画祭2022』記事一覧はこちら
映画『あちらにいる鬼』の作品情報

(C)2022「あちらにいる鬼」製作委員会
【公開】
2022年(日本映画)
【監督】
廣木隆一
【原作】
井上荒野
【脚本】
荒井晴彦
【キャスト】
寺島しのぶ、豊川悦司、広末涼子、高良健吾、村上淳、丘みつ子
【概要】
井上荒野が目撃し、生前の瀬戸内寂聴に取材して書かれた実父と愛人、そして実母の奇妙な関係を描いた同名小説を映画化した作品です。
監督を務めたのはNetflix映画『彼女』(2021)の廣木隆一。彼の映画『母性』(2022)と『月の満ち欠け』(2022)も、本作と同じく第35回東京国際映画祭のガラ・セレクション部門で上映されました。
瀬戸内寂聴をモデルにした主人公を『空白』(2021)の寺島しのぶ、井上光晴がモデルの人物をハリウッド映画『ミッドウェイ』(2019)に出演して活躍の場をさらに広げた豊川悦司。
そして2人を見守り、原作者の母でもある井上郁子がモデルの人物は『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』(2022)の広末涼子が演じています。
映画『あちらにいる鬼』のあらすじ

(C)2022「あちらにいる鬼」製作委員会
1966年、作家の長内みはる(寺島しのぶ)は講演旅行のきっかけに、弱者に寄り添う姿勢で知られる人気作家・白木篤郎(豊川悦司)と出会います。互いにパートナーがある身ながら、2人は強く魅かれていきました。
新宿騒乱・東大闘争…激動の時代を背景に、自由奔放な上に嘘つきで自分勝手に振る舞う篤郎にのめり込んでいくみはる。そんな2人の関係を承知しながら、動揺する姿勢を見せようとしない篤郎の妻、笙子(広末涼子)。
奇妙な関係を続けながら7年の月日が流れた時、様々な経験を重ねたみはるはある決意を固めました。
ある日、みはるは篤郎に告げます。「わたし、出家しようと思うの」…。
映画『あちらにいる鬼』の感想と評価

(C)2022「あちらにいる鬼」製作委員会
2021年に亡くなった瀬戸内寂聴。様々な恋愛遍歴を経た上で作家としてデビュー、出家した後は自らの経験を踏まえて道を踏み外した者に寄り添い、迷える人々に提言を与え多くの人々から支持された人物です。
しかし彼女は夫がいる身でありながら不倫、夫と子を捨てています。そして作家活動を開始した時は師であり妻子ある作家、小田仁二郎と不倫関係になりました。
こういった経験を踏まえて書かれ発表された寂聴の小説は世間の注目を集めますが、同時に「ポルノ的だ」「(彼女は)子宮作家だ」という批判にも晒されます。
後年、出家した瀬戸内寂聴は女性を中心とした多くの人々に支持されますが、一方で前半生の経歴を許せぬ人々も存在していました。その多くが男性である印象があります。
さて、本作では寂聴をモデルにした主人公・みはると、井上光晴がモデルの篤郎は早々に出会いますが、寂聴の経歴と境遇は映画の主人公・みはるとは少し異なります。原作・映画共に事実にフィクションを交えて描かれました。
廣木監督作品には『ヴァイブレータ』(2003)以来何度も出演し、信頼関係を築いた寺島しのぶ。2人一緒に何か映画の仕事ができないかという話から企画が立ちあがり、その結果本作が誕生しています。
廣木監督作品が持つ独特の空気感、長回しが多く無駄がない撮り方が楽しい。寺島しのぶは本作を語った別の場所で、このように語っていました。
本当の主人公は「男の愚かさ、もろさ」を体現した豊川悦司?

(C)2022「あちらにいる鬼」製作委員会
力強く人生を生きたみはると、達観したしたたかさで家族とともに生きた白木篤郎の妻・笙子の姿を描いた本作は、間違いなく”女性映画”と呼べるでしょう。
しかし私は、私が男性だから感じるのかもしれませんが…。この映画の真の主役は篤郎を演じた豊川悦司だと感じました。
戦争の時代を知り、革命を求める時代の熱気に賛同し、弱者に寄り添うリベラルな姿勢を持つ作家・篤郎は、女性関係に関しては自由奔放な人物でした。
人気作家で言い寄ってくる女性に事欠きません。そんな女性を魅了する愛嬌も持ち合わせた、ある意味男性にとってあこがれの人生を歩んでいる知識人です。
ところが彼の姿勢は「女性は男性に都合よく付き従ってくれるもの」という、リベラル的思考とは真逆の男性優位の価値観への確信に裏打ちされたものでした。
彼は性的に自由奔放に振る舞い、女性に犠牲を強いても無関心を貫きますが、一方で妻子と共に暮らす平凡で幸せな家庭を築く願望を捨てる事が出来ません。そして関係を持った女性が反撃の姿勢を見せたり、あるいは強く迫られると動揺しうろたえます。
彼にとって愛人・みはる=寂聴と、妻・笙子=井上郁子は共に都合の良い女性であり、自分の弱さを支えてくれる拠り所であり、同時に自分のは無い強さと逞しさを持つ存在でした。
“あちらにいる鬼”というタイトルは、みはると笙子にとって互いを示す言葉でしょうが、篤郎にとっても2人の女性は理解できない強さと怖さを秘めた、”あちらにいる鬼”であったのでしょう。
経歴を偽ってまで自身を飾り立てた篤郎。女性に対し傍若無人に振る舞う姿も虚勢に満ちていました。豊川悦司は男の弱さと脆さを、滑稽さと悲哀を交えて見事に演じ切りました。
あの時代、変革を望んだ知的でリベラルな男たちが多数いました。しかし彼らの女性に対する姿勢は、彼らが否定した前世代の男と変わらぬ、旧体制で当然とされた価値観そのままでした。
この価値観は今も多くの男性に、男性優位の日本社会に根付いています。晩年の寂聴の姿を見ても、前半生の経歴を理由に批判した方々は、このような考え方の持ち主でしょうか。
女性を隷属的に扱う男性優位の考え方、封建的な組織運営や人間関係は今も日本のあらゆる分野に存在します。リベラルな政治団体、権力を批判するマスコミ企業もこの古い価値観に支配され、それ無視して他者を批判する態度を続けてきました。
残念なことに、そんな価値観に支配され続けた業界の一つが、セクハラ・パワハラ問題が表面化した日本の映画業界です。この事実がクローズアップされた2022年に本作が公開された事には、大きな意味があるのでしょう。
本作で豊川悦司が演じた篤郎の姿は、単に男の弱さを描いたものでしょうか。彼の醜態に似た振舞いは、古い価値観に固執する分野で多く見られるのではないのでしょうか。
篤郎は本作で、嘘と虚飾で隠した自分の弱さにどう向き合ったのでしょうか。我々には、そして日本の映画界には自身の愚行に目を背け続けた事実を認め、変わろうとする勇気が必要なのかもしれません。
ピンク映画という虚飾をかなぐり捨てたジャンルで監督デビューし、人間を深く掘り下げてきた廣木隆一が、本作に込めたメッセージに観客は様々な意味を見出すでしょう。
まとめ

(C)2022「あちらにいる鬼」製作委員会
瀬戸内寂聴と井上光晴、その妻郁子をモデルに、井上夫妻の娘・荒野が書いた小説を映画化した『あちらにいる鬼』。私なりの解釈を紹介しましたが、特に女性がご覧になれば異なるメッセージが見出される作品です。
そして本作は、観客に映画の価値を再確認させてくれます。登場人物が感情的に振る舞っておかしくない状況が次々と登場しますが、作中で彼らが激しい表情や振舞いを見せるシーンは決して多くありません。
本作のリズムは淡々しており、落ち着いた映像がゆったりと流れるテンポで編集されています。これこそ寺島しのぶが語った、廣木監督の”独特の空気感、長回しが多く無駄がない撮り方”でしょう。
映画には登場人物の感情の起伏だけでなく、日本が激しく揺れ動いた激闘の時代も描かれています。しかしこれらも強調せず粛々と見せる、映画らしいリズムが最後まで維持されています。
映像作品を映画館で見る従来の映画鑑賞スタイルは、誰もが動画を配信する現在ますます存在意義が薄れてきました。見せたい瞬間だけを見せ、見たい瞬間だけを見る。ながら見や早送り再生を駆使し、テレビ画面どころかスマホの画面で見る者も増えてきました。
その傾向はコロナパンデミックで映画館に行く機会が減少した時期を経て、さらに強まった感があります。そんな現在、廣木監督は観客をゆったりとした時間に包む本作を発表したのです。
落ち着いた展開の中にも、激しい感情が渦巻くドラマを描くことは可能だ。この時の流れこそ、現代とは異なるリズムで生活していたあの時代の人々を描くのに相応しい。そういった判断があったと推察します。
映画とは映画が刻む時の流れに身を任せ、画面に向き合い鑑賞する時間芸術の一つです。『あちらにいる鬼』はそんな映画の価値を再確認させる、廣木監督らしい作品と評すべきでしょう。
【連載コラム】『TIFF東京国際映画祭2022』記事一覧はこちら
増田健(映画屋のジョン)プロフィール
1968年生まれ、高校時代は8mmフィルムで映画を制作。大阪芸術大学を卒業後、映画興行会社に就職。多様な劇場に勤務し、念願のマイナー映画の上映にも関わる。
今は映画ライターとして活躍中。タルコフスキーと石井輝男を人生の師と仰ぎ、「B級・ジャンル映画なんでも来い!」「珍作・迷作大歓迎!」がモットーに様々な視点で愛情をもって映画を紹介。(@eigayajohn)