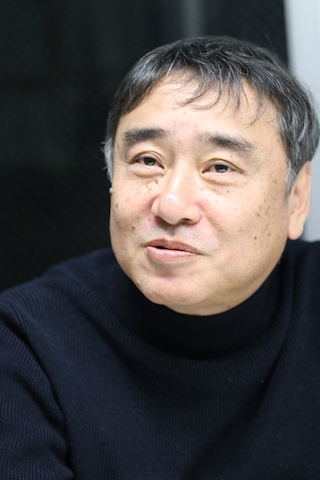連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第33回
こんにちは、森田です。
今回は2月23日から池袋シネマ・ロサ他で公開となる映画『空の瞳とカタツムリ』を紹介いたします。
4人の男女をめぐる愛と喪失の物語。ここでは本作で映画脚本デビューをした荒井美早氏が言及する村上春樹の小説を取りあげ、体と心を求めることの困難と救いを考えてみます。
映画『空の瞳とカタツムリ』のあらすじ(斎藤久志監督 2019年)

(C)そらひとフィルムパートナーズ
本作では女性2人、男性2人がそれぞれ対照的な性格で描かれています。
それはおもに「体」と「心」の対比です。
祖母の遺した古いアトリエでコラージュ作品を作りつづける岡崎夢鹿(縄田かのん)は、消えない虚無感を埋めるため、男とならだれとでも寝る生活を送っていました。
一方、夢鹿の美大時代からの友人である高野十百子(中神円)は極度の潔癖症で、性を拒絶し、夢鹿にしか触れられません。
そして2人の友人、吉田貴也(三浦貴大)は学生時代から夢鹿への想いを捨てきれないまま、いまはサラリーマンとして堅実に生きようと努めていました。
もうひとりの男性、大友鏡一(藤原隆介)は十百子のアルバイト先のピンク映画館に出入りしている客です。
この4人の「体」と「心」がすれ違って生まれるドラマを、その関係性からみていきましょう。
すれ違う体と心

(C)そらひとフィルムパートナーズ
彼らは無意識にも互いに欠けているものを求めあっています。
では「心には体を、体には心を与えればいい」となりますが、あえてそうさせないところが本作のポイントです。
すなわち「心と体を同時に手に入れることはできない」ということです。
まず夢鹿は十百子の“純血性”を汚してみせようとします。彼女に他のだれかと一度関係を持つことを強引に勧めるのです。
そこで十百子が見つけた相手が鏡一です。彼の体には重いアトピーの痕があり、彼自身はそれでも心から愛してくれる存在を欲していましたが、現れたのは別の思惑をもつ十百子という肉体でした。
また貴也はついに夢鹿に想いを打ち明け一晩を過ごすのですが、「一度寝た男とは二度と寝ない」という夢鹿の姿勢にあっけなく期待を裏切られてしまいます。
4人はそれぞれにすれ違っていることがうかがえますね。そして求めあうがゆえに傷つけあっています。
この関係は題名の“カタツムリ”に象徴的に示されており、雌雄同体のそれは交尾の際に「恋矢(れんし)」と呼ばれる鋭い矢を互いに突き刺します。
その“恋の矢”は交尾相手の生殖能力を低下させ、寿命すらもすり減らすそうです。
まさに“求めることでなにかが損なわれる”4人のつながりを表現するのにうってつけの言葉です。
夢鹿と十百子が腕を切って血を交わすショットは「恋矢」そのものを想起させますし、本作では心や体が「交わる」際に、つまり「生きるために殺しあう」ときに、長回しが使用されるのも特徴になっています。
脚本家が込めた問い

(C)そらひとフィルムパートナーズ
この関係性をもって問われているテーマはなんでしょうか。それは脚本を担当した荒井美早氏が本作に寄せたこのコメントに尽きるでしょう。
10代のころの苦しみと、20代のころの迷いを思い出しながら書きました。(…)好きな人の心と体、どちらかしか手に入らないとき、何を求め、どうすれば救われるのか。この映画が問いであり、答えとなりますように。
また製作を務めた松永佳紀氏との対談では、このようにも述べています。
体を手に入れている人が幸せなのか、心を手に入れている人が幸せなのか。私は心の方なんじゃないかなと思っていて。(…)心を手に入れている人はオンリーワンだけど、体を手に入れている人はオンリーワンじゃなくて、その時のナンバーワンなだけ。
かなり明確に答えが出されていますね。さらにこの発言に注目すれば、よりテーマが絞り込めそうです。
この間、村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を読んでいたら、夢の中で主人公が女の人に「心と体どっちかあなたにあげるけど、どっちかは別の人にあげなきゃいけないから、どっちか選んでほしい」って言われて、初めて嫉妬という感情を知ったっていう。だからそういうことなのかなって。心と体を捧げる相手が違うというのが生じる人たちがいるっていう。
村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』より

文藝春秋/2013
4人の“すれ違い”を的確にとらえる言葉が出てきましたね。それは“心と体を捧げる相手が違う”ということです。
荒井美早氏が村上春樹の小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文藝春秋/2013)を引きあいに言及したのは、この箇所です。(引用は文春文庫版より。)
「夢の中で、彼は一人の女性を何より強く求めていた。(…)そして彼女は肉体と心を分離することができる。そういう特別な能力を持っている。そのどちらかひとつならあなたに差し出せる、と彼女はつくるに言う。肉体か心か。でもその両方をあなたが手に入れることはできない。」P53
“つくる”とはタイトルにもあるようにこの小説の主人公です。彼は高校時代に非常に仲良くしていた4人の友人(男2人・女2人)がいたのですが、ある日、理由もなくそのグループから追放され、36歳の現在にいたるまで心の傷を負ってきました。
彼はその傷を忘れるために、長らく感情というものに蓋をして過ごしていましたが、この夢を見てから激しく動揺します。
「怒りが身体を震わせた。彼女の半分を誰かに渡さなくてはならないことへの怒りだ。(…)それから彼は理解した。あるいは直観を得た。これが嫉妬というものなのだと。」P54
“肉体か心か”の問いに直面し、彼のなかに眠っていた感情が目を覚ましました。
「嫉妬」とは恋愛だったり才能だったり、人生のさまざまな局面で立ちあらわれる感情ですが、いずれも「求めているものが手に入らない状況」が共通しています。
現実には年上の恋人から、こう言われます。
「もし私とあなたがこれからも真剣におつきあいをするなら、そういう何かに間に入ってほしくない。よく正体のわからない何かに。」P121
つくるは過去と向きあい、いまの彼女の「体と心」を手に入れるために、かつて自分を傷つけた友人たちに会いに行くことを決心します。
その“巡礼”は彼の傷を癒す反面、それをより深くえぐるような事実をも突きつけました。
また恋人の別の一面も垣間見てしまいます。彼女が別の男性と一緒に手をつないで通りを歩いている姿を目撃してしまったのです。
しかし、巡礼中の彼の心に芽生えたのは、もはや「嫉妬」ではありませんでした。
「彼が感じるのはただの哀しみだった。深く暗い縦穴の底に一人ぽつんと置かれたような哀しみだ。しかし結局のところそれはただの哀しみに過ぎない」P277
“嫉妬”から”哀しみ”へ。「肉体か心のどちらかを差しだす」という夢で見た状況に直面したのに、なぜか心境は変わっています。
彼は最後の友人と面会を果たし、彼女と抱擁したときに、以下の気づきを得ました。
「そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくるは理解した。人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結びついているのだ。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているのだ。悲痛な叫びを含まない静けさはなく、血を地面に流さない赦しはなく、痛切な喪失を通り抜けない受容はない。それが真の調和の根底にあるものなのだ」P350
『空の瞳とカタツムリ』の4人も、痛みとともに真の調和を目指していたといえ、ひとはそれを「モラトリアム」と言うのでしょう。
たとえ体も心も差しだせなくても

(C)そらひとフィルムパートナーズ
真の調和の根底には、痛みがあり、血が流れている。
「好きな人の心と体、どちらかしか手に入らないとき、何を求め、どうすれば救われるのか。」
最初に立てられたこの問いに対するひとつの答えは、こうでしょう。
「手に入らない痛みを知り、傷を抱えた者同士の真の優しさと哀しさをもって、より深くつながること。」
また「心と体を捧げる相手が違う」というのも、捧げる「対象」ではなく、捧げる「行為」に視点を移せば、4人はそれなりにきちんと務めを果たしたとみれます。
つくるは自分を「空っぽの容器。無色の背景。これという欠点もなく、とくに秀でたところもない」(P193)と思い、むしろ「自分からはなにも差しだせないこと」を悩んでいました。
色彩がない、とはこのことです。
でも、巡礼の最後に抱擁を交わした友人は「たとえ君が空っぽの容器だったとしても、それでいいじゃない」と語りかけ、つぎのように伝えます。
「自分自身が何かであるかなんて、そんなこと本当には誰にもわかりはしない。そう思わない? それなら君は、どこまでも美しいかたちの入れ物になればいいんだ。誰かが思わず中に何かを入れたくなるような、しっかり好感の持てる容器に。」P368
体と心が手に入らなくてもその哀しみがふたりを近づけるように、体も心も差しだせなくても真に調和できる関係がある、そう信じて生きるのがよいでしょう。