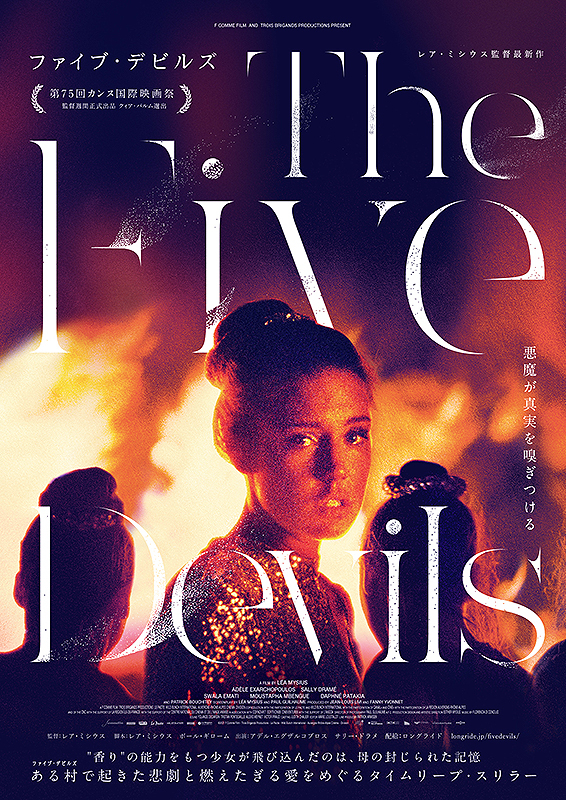ノーベル文学賞を受賞したアニー・エルノーの実体験をもとにした著作を女性監督オドレイ・ディワンが映画化
1960年代、法律で中絶が禁止されていたフランス。
大学生のアンヌは、大事な試験を間近に控え、妊娠していることに気づきます。
「何とかする」アンヌは強い意志で立ち向かい、様々な解決策を求め奔走しますが……。
2021年ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞に輝いた本作の監督を務めるのは、『ナチス第三の男』(2019)などの脚本を手がけ、本作が監督2作目となるオドレイ・ディワン。
主演は、『ヴィオレッタ』(2014)でデビューを果たし、本作でセザール賞を受賞したアナマリア・バルトロメイが務めました。
アンヌの視点を通して、観客も“あのこと”を体感するかのようなスリリングなカメラワーク、説明を排除した臨場感は、この映画の持つ普遍性を観客に訴えかけます。
映画『あのこと』の作品情報

(C)2021 RECTANGLE PRODUCTIONS – FRANCE 3 CINEMA – WILD BUNCH – SRAB FILM
【公開】
2022年公開(フランス映画)
【原題】
L’evenement
【監督】
オドレイ・ディワン
【脚本】
オドレイ・ディワン、マルシア・ロマーノ
【原作】
アニー・エルノー
【キャスト】
アナマリア・バルトロメイ、ケイシー・モッテ・クライン、ルアナ・バイラミ、ルイーズ・オリー=ディケロ、ルイーズ・シュビヨット、ピオ・マルマイ、サンドリーヌ・ボネール、アナ・ムグラリス、レオノール・オベルソン、ファブリツィオ・ロンジョーネ
【作品概要】
2022年度のノーベル文学賞を受賞した作家アニー・エルノーの小説を映画化。『シンプルな情熱』(2021)に次いでの映画化となりました。
主演を務めたアナマリア・バルトロメイは、12歳の頃『ヴィオレッタ』(2014)で映画デビューを果たし、『乙女たちの秘めごと』(2017)、『ジャスト・キッズ』(2019)ほか、1960年代の花嫁学校を舞台にしたコメディ映画『5月の花嫁学校』(2020)にも出演しました。
本作でセザール賞最優秀新人女優賞、ルミエール賞、ベルリン国際映画祭でシューティング・スター賞に輝き、今後期待の女優へと駆け上りました。
共演者には、『燃ゆる女の肖像』(2020)のルアナ・バイラミや『冬の旅』(2022)のサンドリーヌ・ボネールなどが顔をそろえます。
映画『あのこと』のあらすじとネタバレ

(C)2021 RECTANGLE PRODUCTIONS – FRANCE 3 CINEMA – WILD BUNCH – SRAB FILM
1960年代、フランス。文学を専攻しているアンヌ(アナマリア・バルトロメイ)は、友人のブリジット(ルイーズ・オリー=ディケロ)とエレーヌ(ルアナ・バイラミ)と共にクラブに出かけるため着飾っています。
クラブで目立つため、わざと体のラインを強調するようにしてクラブに向かいます。学生のふりをしてクラブにやってきた消防士に気に入られ、会話をしますがアンヌは素っ気ない態度です。
次の日、朝起きたアンヌは下着を脱いで確認すると手帳に「まだ生理がこない」と書きつけます。
そして病院で診察を受けたアンヌは医師から性行為をしたか?など質問されますが、したことないと答えます。アンヌのお腹をみた医師は妊娠しているとアンヌに告げます。
アンヌは何とかしてほしい、学び続けたいと懇願しますが面倒なことに巻き込むなと医師は拒絶します。当時中絶は法律で禁じられており、中絶を行ったものだけでなく関与したものも処罰の対象でした。
別の医者に行っても結果は同じでした、何とかならないかと懇願するアンヌに医師は注射を処方します。医師に言われた通り注射を打つも何も効果はありません。
アンヌは交友関係の広い男子学生のジャン(ケイシー・モッテ・クライン)に、中絶を経験した友人はいないかと聞きます。
困っているから助けて欲しい、他に頼める人がいないというアンヌに対し、ジャンは厄介ごとに巻き込んでくれるなと立ち去ろうとします。アンヌは諦めずジャンを追いかけます。
ジャンの家で食事に誘われアンヌが向かうと、「相手は誰だ?」「どんな感じだった?」と詳細を質問してきます。「関係ないでしょ」とアンヌが立ち去ろうとすると、ジャンは引き止め、キスをしようとします。
どういうつもりだと怒るアンヌに「妊娠してるならリスクないだろう」とジャンはいい、アンヌは呆れてジャンの家から帰ります。
時間だけが過ぎていき、悪阻と焦りからアンヌは勉強に身が入らなくなっていきます。
映画『あのこと』の感想と評価

(C)2021 RECTANGLE PRODUCTIONS – FRANCE 3 CINEMA – WILD BUNCH – SRAB FILM
1960年代、中絶することが法律で禁じられ、罪に問われるという事実に衝撃を受ける人も多かったのではないでしょうか。遥か昔のことではないにも関わらず、現代フランスにおいてもそのような時代があったことはあまり知られていませんでした。
監督を務めたオドレイ・ディワンは、自身も中絶の経験があり、その際にアニー・エルノーの小説に出会ったといいます。この小説を今、映画化することは何を意味し、監督は何を伝えたかったのでしょうか。
監督はあえて時代的な説明を避け淡々とアンヌの視点を通して物語が展開するようにしたといいます。アンヌの体験を通してそこに内包される問題の普遍性を観客に伝えようとしているのです。
今もなお中絶が法律で禁じられている国は存在し、ポーランドやアメリカでは、中絶を禁じようという動きが出ています。中絶にまつわる問題は決して過去のことではないのです。日本ではどうでしょうか、皆さんは日本の法律で中絶がどのように定められているのかきちんと知っているでしょうか。
日本において中絶は刑法堕胎罪で基本的には禁じられていますが、母体保護法により22週未満であれば条件の適応内において中絶が合法化されています。しかし、配偶者の同意が必要であったり(配偶者がいない、死別など条件により同意はなくてもよい)、中絶薬は認可されていないなど、いくつか問題も今なお残っています。それだけでなく、日本では緊急避妊薬が手に入れにくいということも問題になっていますがなかなか状況は変わりません。
『セイント・フランシス』(2022)では、主人公ブリジットは、初期段階の中絶であったため中絶薬による中絶を行っていました。外科手術より母体に安全な方法としてWHOにも推奨されていますが、未だ日本では認可されていない状況です。
アンヌは、大学の旧友の伝で闇で中絶を執り行ってくれる人に出会います。アンヌは12周での中絶のため、現代の日本の中絶方法では中期の中絶となり、薬で分娩のような状態を引き起こし流産のような形で堕胎させます。
アンヌに女性が施した手法も、流産しやすくなるようにするものでしょう。器具を入れて直接外科手術のようなことを行なってしまうと、何かが起きて病院に運ばれた場合に流産とカルテに書いてもらえなくなる可能性が高くなるのを避けるためでしょう。更に、子宮内を傷つける可能性もあるため、流産しやすくするのが限度であったのでしょう。
アンヌは一度目の処置では流産にならず、再び処置を受けることになります。自己責任でと忠告されたのはまさに奥まで器具を入れると子宮内を傷つけ炎症を起こしたりして病院に行かなくてはならないリスクが高まるからなのです。命懸けで中絶に臨むほかない緊迫感がありありと伝わってきます。
アンヌは自分に言い聞かせているかのように何とかする、処理すると繰り返し言います。しかし、劇中全く笑わない姿などから彼女の緊張感が伝わります。誰かに助けてもらいたい、怖い気持ちは当然あったと思います。
しかし、その弱さを吐露する場所も彼女にはなかったのです。様々な解決策を探していく中で、アンヌは誰にも頼れないということを身をもって知っていくのです。
現代の人々からしたらまず親に相談すれば良いのではないかと考える人もいるかもしれません。しかし、劇中から見て分かる通り、アンヌの家はあまり裕福ではありません。両親は労働者階級であり、アンヌが一度母親に「(試験を)受けた頃がないくせに」と言って平手打ちをされる場面があります。
アンヌの両親はおそらく時代的にも経済的にも大学に通うことができなかった世代なのです。そんな両親のアンヌにかける期待の大きさはアンヌ自身にもよくわかっていました。
大学内でも妊娠など様々な状況により大学を辞めざるを得なかった女性徒を目にしてきたというのもあります。何としても自分はうまく処理して描いた未来をみすみす諦めるわけにはいかないと強く思うのです。
実家に帰るたびにアンヌは母親に汚れた下着をまとめて洗ってもらっています。原作小説では、母親が下着を見て汚れた下着があることで、きちんと生理が来ているのだと確認していると書いてありました。そのような母親の監視は、大学を無事に卒業してほしいというプレッシャーでもあります。
アンヌは親に妊娠を悟られないため定期的に実家に帰ります。終盤でラジオが流れ楽しそうに話す両親と、二人の会話に合わせてアンヌが微笑む場面が映し出されます。
手術を控え、もし死んでしまったら両親に会えなくなるかもしれないといった複雑な思いを抱えながら、何とか悟られないよう笑顔を浮かべるアンヌの姿は突き刺すような苦しさがあります。
赤ちゃんポストを扱った映画『ベイビー・ブローカー』(2022)で、IU演じる赤ちゃんポストに赤ちゃんを預けた母親が、産んでから捨てるのと産む前に殺すのとどっちが悪いのかと突きつける場面がありました。
そのような問いかけの背後にあるのは男性の不在じゃないでしょうか。妊娠し、産むかどうか決めなくてはならないのも、下した決断によって断罪されるのも産む性である女性です。
アンヌが何とかしてくださいと医師に頼んでも受け入れるしかないと医師は突き放します、当時、女性は受け入れて当然だったのです。だからこそ、同じ同性であるアンヌの友人もどうするかは勝手にしていいから巻き込まないでと突き放すのです。
もう一人の友人は、自分も男性と性行為の経験があり、妊娠しなかったのは運が良かっただけだと言います。
フランスにおける中絶合法運動に一石を投じたのは、1971年に週刊誌に掲載された「343人のマニフェスト」でした。「343人のマニフェスト」はカトリーヌ・ドヌーヴやフランソワーズ・サガン、マルグリット・デュラス、アンヌ・ヴィアゼムスキーなどの有名人から主婦、学生など多くの女性が「私は中絶手術を受けた、法律に違反した」という署名でした。
アンヌが体験する出来事を通して、アンヌの体験は、遠い過去の話でもなく、遠い国の話でもないことを改めて私たちは知るべきなのです。
まとめ

(C)2021 RECTANGLE PRODUCTIONS – FRANCE 3 CINEMA – WILD BUNCH – SRAB FILM
ノーベル文学賞を受賞したアニー・エルノーは、映画化された『シンプルな情熱』において、年下の男性との恋を自身の体験を交え赤裸々に描いています。
『あのこと』(2022)の原作である「事件」も、女子学生の頃の妊娠中絶体験を後に回想する形でサスペンスフルに描いています。
しかし、その中においても当時の性に興味を持っていた自身の欲求を包み隠すことなくありありと描きます。その姿勢は、映画においても受け継がれています。
冒頭のアンヌは友人とクラブに行く前にわざとボディラインを強調させ、性的に見られることを意識しています。その上アンヌ自身はその結果として起こったことに対し、何で私だけがと悲観し、相手の男を追求したりはしません。
現実を受け止めた上で、何が何でも対処すると奔走するアンヌに対し、相手の男は解決策を見つけようともせず、友人らとの関係の方を優先させます。その姿は、無責任であり、現実を受け止められていないとも言えます。
更に、中絶した知り合いがいないかと相談したジャンも、最初は好奇心むき出しでアンヌに質問し、あろうことか妊娠しているならリスクがないと性行為をしようとまでします。
アンヌの危機感と男性陣の間には決定的な認識の差があり、どこまでも他人事でしかありません。その点で妊娠しなかったのは運が良かっただけだと思う同性の友人は自分と無関係ではないと認識しているのです。
アンヌという個の物語が持つ普遍性は脈々と現代にもなお蔓延っているものなのです。