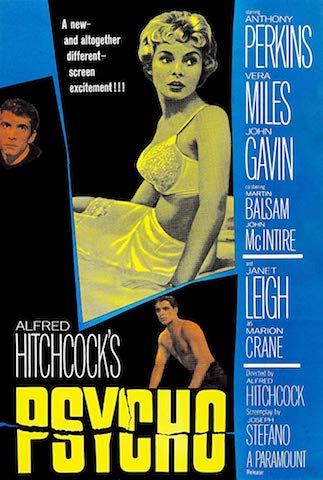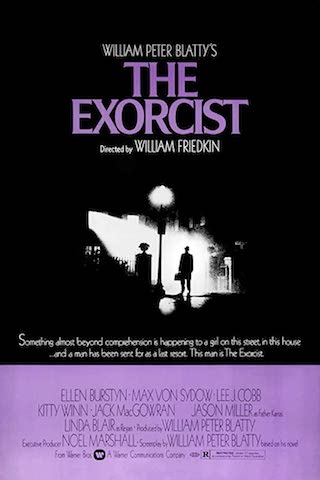卵が先か、殺しが先か。
知る人ぞ知る猟奇サスペンスが新バージョンで日本初公開!
2022年12月2日(金)より新宿シネマカリテほかにて全国順次公開される映画『殺しを呼ぶ卵[最長版]』。
その残酷描写により「マカロニ・ウェスタンのシュルレアリスム」と称された『情無用のジャンゴ』(1967)で知られるジュリオ・クエスティが監督・脚本を務めた本作は、機械により自動化された巨大な養鶏場で繰り広げられる猟奇サスペンスです。
このたび公開される「最長版」は、1968年の初公開時に世界配給された「国際版」ではカットされた残酷場面・異常場面を新たに追加したバージョンであり、日本では初公開となるバージョン。
本記事では、タイトルにも冠されている「卵」にこめられたさまざまな意味を中心に、ネタバレなしで映画『殺しを呼ぶ卵[最長版]』の魅力を紹介いたします。
CONTENTS
映画『殺しを呼ぶ卵[最長版]』の作品情報

(C)Licensed by MOVIETIME SRL-Rome-Italy. All Rights Reserved.
【製作】
1968年(イタリア・フランス合作映画)
【原題】
LA MORTE HA FATTO L’UOVO
【監督】
ジュリオ・クエスティ
【脚本】
フランコ・アルカッリ、ジュリオ・クエスティ
【撮影】
ダリオ・ディ・パルマ
【美術】
セルジオ・カネヴァリ
【編集】
フランコ・アルカッリ
【音楽】
ブルーノ・マデルナ
【キャスト】
ジャン=ルイ・トランティニャン、ジーナ・ロロブリジーダ、エヴァ・オーリン、ジャン・ソビエスキー、レナート・ロマーノ
【作品概要】
マカロニ・ウエスタン屈指の残酷描写で世界を騒然とさせた『情無用のジャンゴ』(1967)で知られるジュリオ・クエスティが監督・脚本を務めた猟奇サスペンス。巨大な養鶏場を営む夫婦とその周囲の人々による愛憎劇を通じ、資本主義社会の非情と人生の虚無を描き出す。
主人公マルコ役を2022年6月に死去した『男と女』『Z』『暗殺の森』の名優ジャン=ルイ・トランティニャンが、妻アンナ役をその美貌で一世を風靡したジーナ・ロロブリジーダが演じる。
「最長版」は初の劇場公開時に世界配給された「国際版」ではカットされた残酷場面を追加されたバージョンであり、日本では初の劇場公開となる。
映画『殺しを呼ぶ卵[最長版]』のあらすじ

(C)Licensed by MOVIETIME SRL-Rome-Italy. All Rights Reserved.
ローマ郊外の巨大養鶏場。社長のマルコは業界の名士として知られていたが、経営の実権と財産を握る妻アンナに対する苛立ちは日々強くなる一方だった。
マルコは同居するアンナの十代の姪、ガブリと愛人関係にあっただけでなく、妻への憎しみを女性へのサディズムで発散する異常性格者だった。
そして3人それぞれの隠された欲望が暴かれる時、事態は予想もできない展開と想像を絶する畸形ニワトリを産んだ!
映画『殺しを呼ぶ卵[最長版]』の感想と評価

(C)Licensed by MOVIETIME SRL-Rome-Italy. All Rights Reserved.
「死」と「復活」の象徴としての卵
「映画史上唯一の養鶏場サスペンス」とさえ銘打たれた本作において、最も重要なモチーフの一つである「卵」。古来より「豊穣」の象徴としても知られていますが、「卵」「象徴」と聞いて人々が一番思い出すものは、やはりキリスト教のイースター(復活祭)で作られる「イースター・エッグ」ではないでしょうか。
「イエス・キリストの昇天後、『イエスの復活は“赤い鶏卵”と同じほどにありえない』と口にした時のローマ皇帝ティベリウスに、マグダラのマリアが“赤い鶏卵”を献上した」という逸話をはじめ、イースター・エッグという習わしの由来は諸説あるものの、「静止した殻の中で新たな生命が宿り、やがて静止を破りこの世に姿を現す」という様に、キリスト教世界では卵に対して「死」と「復活」という象徴を見出し、イエスの復活を祝うイースターで用い続けてきたのです。
なお、“赤い鶏卵”の伝承における赤という色彩も、人類の再生を目指すイエス・キリスト自身の血、あるいは純粋に「生命」の象徴としての血を表しているといわれています。
養鶏家の主人公マルコが「売春婦の女性たちを刃物で切りつけ、彼女らの“流血”を楽しむ」という倒錯行為を抑えられないのも、妻アンナ個人への憎しみのみならず、「機械により自動化された養鶏場」「不況により商業主義が一層加速し、遺伝子組み換えに希望を見出す養鶏家協会」そして「冷め切った夫婦関係」という非生命的な環境で日々過ごす中で、彼が「生命」の象徴を欲するからなのでしょう。
突きつけられる「復活」の醜い現実

(C)Licensed by MOVIETIME SRL-Rome-Italy. All Rights Reserved.
映画中盤、妻アンナの姪であり愛人でもあるガブリとの逃避行を考えるマルコは「人生をやり直したい」と口にします。また後半部でも、とある事情により精神的に追い詰められた彼が、卵が殻の中でもたらす現象について思い耽りながら「僕も始めたい」とつぶやく場面が描かれます。
その様からも、生き詰まったマルコは「自身の人生をイチからやり直す」という意味で「復活」を求めていることが映画では明らかにされていきます。
それは妻アンナが、姪ガブリのまだ「新たな変化」が存在する若々しく美しい肉体に執着し、停滞する生命に新たな変化をもたらす「突然変異」に可能性を見出していたように、人生の佳境という取り返しのつかない瞬間を経てたどり着く「無変化」という死を恐れる、年齢を重ねれば重ねるほど実感が増してゆく普遍的な心理といえます。
なお、卵と人生のやり直しを結びつけてしまう「“復活”の欲望」がマルコ独自の欲望ではないと観る者に伝えてくれる場面は、やはり映画中盤で描かれる「夫婦交換ゲーム」でしょう。真っ白な何もない密室へ無作為に選ばれた男女がこもり「真実」をさらけ出す様は、誰もが卵を求めている証明といえます。

(C)Licensed by MOVIETIME SRL-Rome-Italy. All Rights Reserved.
「同じ死ならば、“復活のある死”を」……そんな思いから、現在の養鶏家としての社会的成功を収めた生活を捨ててでも、若く美しい、変化の可能性を見出せるガブリとの破滅的な逃避行を望むマルコ。しかし本作はマルコを裏切るかのように、見るもおぞましい「復活」の現実をマルコに突きつけます。それが映画序盤における偶然の事故により起こった突然変異で誕生した、畸形の鶏たちです。
「自身が望む“復活”は、こんな醜くおぞましい形ではない」……「突然変異」という新たな変化そのものに喜ぶ妻アンナに対し、強い怒りと恐れを露わにするマルコ。
彼がアンナとあまりに真逆な反応を示した理由、あるいは“復活”という幻想に対する夫婦間の認識が違う理由。それは映画作中でも描かれていますが、「分身」の象徴としても知られ画面内に何度も登場する鏡に注目すると、より本作の魅力に肉薄できるかもしれません。
まとめ/最長版で「卵の中身」はより美味く

(C)Licensed by MOVIETIME SRL-Rome-Italy. All Rights Reserved.
強烈・鮮烈な残酷描写により「マカロニ・ウェスタンのシュルレアリスム」とも讃えられた『情無用のジャンゴ』(1967)で知られる監督ジュリオ・クエスティが描く猟奇サスペンスである本作。
2023年に初の日本公開を迎えるその「最長版」では、1968年の初劇場公開時に上映された「国際版」にはない描写が追加されたことで、国際版からさらに深味と旨味の増した『殺しを呼ぶ卵』を観られます。
殻を破り姿を現すのは、畸形の鶏だけではない。猟奇サスペンスか、資本主義社会風刺か、キリスト教的宗教性か、普遍的な愛憎ドラマか。あるいはそれらが殻の中でドロドロと混ざり合うことで生まれる、「何だこれは!?」と言いたくなる何かか。
ロバート・ゼメキス監督作『フォレスト・ガンプ 一期一会』の「人生はチョコレートの箱のようなもの。開けてみないと分からない」という有名な名言とは一味違う、得もいわれぬ、しかし「これもまた人生」と思える味を体験できるはずです。
映画『殺しを呼ぶ卵[最長版]』は2022年12月2日(金)より新宿シネマカリテほかにて全国順次公開!
ライター:河合のびプロフィール
1995年生まれ、静岡県出身の詩人。
2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部へ加入。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介