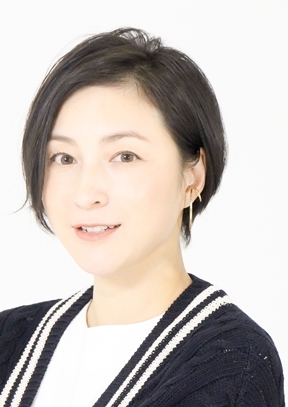映画『太陽の家』は全国順次ロードショー中!
優しく寛容である男が、人々との複雑な関係に思い悩みながらも自身の信念を貫いていく姿を描いた映画『太陽の家』。一本気で気立ての良い大工の棟梁・川崎信吾を中心に、複雑な家庭環境にいる親子や弟子などが寄り添いながら懸命に生きる様を映すヒューマンドラマです。
主人公の川崎信吾を演じるのは、21年ぶりに俳優として主演を務めるミュージシャン・長渕剛。その他キャストには飯島直子、山口まゆ、瑛太、広末涼子ら実力派俳優が集結しています。

(C)Cinemarche
今回は本作の劇場公開を記念し、近年では「相棒」シリーズ、『監査役 野崎修平』など数々のテレビドラマ作品を手がけ、本作にて演出を務めた権野元監督にインタビューを行いました。
本作の制作にあたり、キャストとのコミュニケーションを通じて見えた家族像や、映画の世界へと進んだきっかけ、監督という仕事への覚悟と想いなど、さまざまなお話を伺っています。
CONTENTS
俳優・長渕剛とのコミュニケーションが生んだ物語

(C)2019映画「太陽の家」製作委員会
──はじめに、本作の制作に携わった経緯を改めてお聞かせ願えませんか?
権野元監督(以下、権野):プロデューサーの遠藤茂行さんから「長渕剛さんが主演で映画を制作する予定なんですが、監督を務めてもらえないですか?」と声をかけていただいたのがきっかけです。「長渕剛さんほどのパワフルな方が主演を務められるということなら、監督として“猛獣使い”で知られる僕しか適任はいないんじゃないか」と思い至り、作品の内容も聞く前に「やります」と返事しました。
──権野監督が“猛獣使い”として知られているその所以とは何でしょう?
権野:最近の映画界・テレビドラマ界は助監督上がりの監督が少ない傾向にあるんですが、僕自身は助監督として活動していた期間が長いんです。スタッフ・キャストともにさまざまな方々と接し、現場全体の動きを見つめながらも撮影を進めるという仕事を長らく続けてきましたから、大御所の方々とも良好なコミュニケーション関係を結び、映画を完成させられる実力を持っていると周囲からも思ってもらえているのかもしれません。
本作も、長渕さんとのコミュニケーションの中で物語を作り上げていった側面が大きいですね。当初、物語における信吾の主人公像は「少しおばかな寅さん」として描かれていて、作品の雰囲気自体もだいぶ異なっていたんですが、長渕さんや脚本家の江良至さんと話し合ううちに、「信吾の起こす行動そのものよりも、元にある家族にフォーカスを置きながら、それぞれの人間の立ち回り方を描くほうが良いのではないか」という結論に至り、物語の方向性をシフトしていったんです。
またその後も続いた脚本の読み合わせ、何よりも長渕さんとの会話の中で、物語に盛り込めそうなエピソードが沢山出てきたため、それらをどう盛り込んでいくかを含め、何度も脚本を推敲しましたね。作品としての“芯”自体はぶれないように守りつつも、その芯の周りにある“血肉”を直していくことを目指しました。
映画だからこそ“真正面”で描ける

(C)2019映画「太陽の家」製作委員会
──長渕さん演じる主人公・信吾は人情に厚い、骨太な男として描かれています。また本作の物語自体も、昭和期の日本映画をどこか彷彿とさせる人情劇として描かれていますね。
権野:“日本的な映画”でありたいとは考えていました。
ただ、「では、“今の日本”をそのまま映し出したのか?」と問われると、それもまた少し違う。その微妙なニュアンスが“昭和テイスト”につながっているのかもしれないんですが、ある意味ではファンタジー性を含むべきといいますか、リアルにし過ぎる必要はないのかもしれないと感じていたんです。
例えば、山口まゆさん演じる柑奈は、信吾の実の娘ではないですよね。「実の娘」という設定にした方が、瑛太さん演じる高史との関係性の対比も作れてしまうわけですが、そういった映画論として、物語論としての都合で作品を考えるのではなく、「本当の意味での“家族”とはどういうものだろう?」という視点を長渕さんらとともに考え抜くことにしたんです。
「家族の結びつき」って、別に血のつながり云々ではなく、そこにただ愛情があれば十分“家族”としてつながることができると思うんです。その捉え方そのものは、昭和テイストというよりは、非常に現代的なのかもしれません。
“家族”というものを主題として真正面から撮ることは、映画だからこそできることではないかとも感じています。本作のようなまっすぐ過ぎる人情劇、「“家族”とは何か?」を主人公が真剣に語ろうとする物語は、現在のテレビドラマで撮ることはとても難しいですから。
“映画”として撮るのであれば、別角度から描いて“家族”というものの輪郭を匂わせるのではなく、真正面から描きたい。そう思いながら本作を手がけました。
“キャストを尊重する”という演出

(C)2019映画「太陽の家」製作委員会
──長渕さんをはじめ、キャストの皆さんそれぞれが俳優として、女優としての“色”を持っています。その中で権野監督はどのような形で演出を進められたのでしょうか?
権野:まず「映像的にどうなるのか?」という監督的な視点はいったん置いた上で進めようと考えましたね。長渕さんは俳優としても素晴らしい方ではありますが、同時にミュージシャンでもあり、何よりもアーティストであり続けてきた方です。計算された画作りをもって撮るよりも、彼の姿をどう捉えてゆくかの方が重要だと感じたんです。
その上で、言葉の通り「方向づけ」としての演出を心がけていました。長渕さんはもちろんのこと、本作のキャストのみなさんはディスカッションを怠らない方々だったので、僕自身もキャストさん個々人との会話の時間を十分に確保し、キャストさん同士の会話にも耳を傾けました。その中で、キャスト側における役柄の受け取られ方を把握し、監督として演出するための方向性を見定めていきました。
キャスト陣の会話を通じて見えてくるものの中から、本作にとって不可欠だと感じられた断片、本作がよりよいものになるために必要な断片を拾い上げていく。その上で、断片をお芝居として、映画としてどう伝えるべきなのかを吟味し、方向性について考えていったわけです。ですから、「一から作り上げて」というスタンスではなく、第一にキャストのみなさんがすでに持っている俳優・女優としての“色”、一人の人間としての“何か”を尊重することを演出の基本としていました。
──キャストのみなさんから拾い上げていった断片をもとに演出を決められていった一方で、権野監督ご自身がこだわられた点などはあるのでしょうか?
権野:一番は、家ですね。物語のとある場面で完成した家は、大道具さんによるスタジオセットではなく、本物の大工さんに基礎から何から作っていただき、実際に建てた家なんです。
長渕さんという人間をどう捉えるかにあたって、「長渕さん演じる信吾は映画の中のキャラクターではあるけれど、“作られた人間”のようにはしたくない」という思いがありました。だからこそ、「家を建てる」という主人公・信吾にとって一番重要な仕事を、CGを使用することで人間としての体温が感じられないものにしてしまうのはどうしても避けたかったんです。
制作側には負担をかけましたが、とても真摯に協力してくださった大工さんの見事な仕事も相まって、結果として非常によい画を撮ることができたと感じています。
巡り合わせを経て映画の世界へ

(C)Cinemarche
──権野監督は日本映画学校(現:日本映画大学)に入学される前から映画制作の現場でお仕事をされていたとお聞きしました。どのような経緯で映画制作の現場に入られたのでしょうか?
権野:浪人生だったころ、暇をもて余していた僕は当時のNHK・BSで放送されていた「ヤング・シネマ・パラダイス」という映画紹介番組をよく観ていたんですが、ある時、番組出演者による映画制作企画に向けて「時間・体力・お金の3つのうち、どれか1つでもある人がいたら協力してください」というスタッフ募集がかけられていたんです。「時間はあるな」と思った僕は応募の電話をかけ、「すぐに来てくれ」とたちまちその現場に呼ばれたのが全ての始まりでした。
当時は大阪に住んでいたものの「2週間程度で撮影は終わる」と聞いていたため、友人の家を泊まり歩けば大丈夫だろうと思った僕はそのまま東京の現場へと向かい、ボランティアスタッフとして撮影に参加しました。ですが実際の撮影は2ヶ月もかかり、お金もなくなり大阪へ帰るに帰れなくなってしまったので、その現場にいたプロのスタッフさんに「仕事はないですか?」と相談しそのまま現場で働き始めたんです。
2年ほど別のバイトをしながら映画制作の現場で働き続けたんですが、その反面、“映画”というものについてはほとんど知らないままでした。そのころに、周囲の先輩スタッフの方々から「一度、しっかり映画を勉強してみたらどうか?」という助言を受けたんです。最初は「今さら勉強ですか?」と思っていたんですが、今村昌平さんという偉大な監督からの「映画学校、行ってみろよ」という言葉に背中を押していただけたのが決め手となりました。
当時の日本映画学校は一般入試の倍率も非常に高かったんですが、逆にそれをチャンスだと考えて「映画学校を受験してみて、ダメだったら今の仕事も辞めて大阪へ帰ろう」という覚悟の中で受験しました。すると意外にも映画演出コースに無事合格したため、映画学校で勉強しながら現場での仕事もこなし、卒業後もこの世界を居続けたことで現在に至っています。
こうして考えてみると、全てのことが巡り合わせの中でつながってきたからこそ、今の僕はこうなっているのかもしれません。
現場という名のリングを作る

(C)Cinemarche
──本作の劇中では、主人公・信吾の“覚悟”が物語の一つのキーとして描かれています。権野監督ご自身は「監督」と呼ばれる現在のお仕事に対し、どのような“覚悟”をもって望まれていますか?
権野:一番は、「関わってくださる人たちにとって、よりよいものを作り上げたい」という思いですね。そのための準備は決して怠りたくないと考えています。天才タイプの監督であれば意図せずできることなのかもしれませんが、僕はそのタイプではない。だからこそ、作品に込められたテーマや作り手の思いが、きちんと観客のみなさんに伝えられるように意識しています。
また「伝える」という目的のために、スタッフ・キャスト陣にも心血を注いでもらうわけですから、みんなが全力を出せる土壌をどうにかして作るための努力は人一倍しますね。それもまた、自分が“猛獣使い”として知られている所以の一つなのだろうと勝手に思ってはいるんですが、僕は決して「人を上手く扱う」といった類いではなく、むしろプロレスのレフェリーを務めている感覚に近いんです。
撮影現場というリングを設営し、レフェリーとして一応の審判役を務めながらも、“映画”という名の試合をうまく展開させてゆくことが僕の仕事だと思っています。試合の最中に揉め事が起きても、自分が身を挺して止めればいい。ただレフェリーである以上、自分を無理矢理押し出していくことは控える。試合を最後まで成立させるためにも、常にどっしりと構えていようという覚悟は常に持っています。
──最後にお聞きしたいのですが、現在の権野監督にとって“映画”とは何でしょう?
権野:映画には、観た者の人生をも左右させるほどの力を持つことがあると感じています。何をまかり間違ったのかはわかりませんが、自分がそんな驚異的な存在の作り手側に回れたということ自体が、非常に幸せです。またこれまでの仕事を振り返ってみると、“継続できる力”が僕にとっての才能なのかもしれません。
そもそも、僕は現在の仕事を「自分には、これしかできない」という思いの中で続けているため、だからこそこれだけ必死になれるのかもしれません。これからも「必死で作り上げたので、すみませんが僕の作品を観てもらえませんか?」という心持ちの中で仕事を続けていきたいです。
インタビュー/出町光識
撮影/河合のび
構成/三島穂乃佳
権野元(ごんの・はじめ)監督のプロフィール
1972年生まれ、大阪府出身。日本映画学校(現:日本映画大学)映画演出コース卒業。
浪人時代に映画制作のスタッフとしてアルバイトをはじめ、のちに日本映画学校に通う。26歳で監督デビュー。30歳で再び演出を学び直すために助監督に戻り、『ソラニン』(2010)、『プリンセストヨトミ』(2011)、『脳男』(2013)などの様々なジャンルの話題作に携わる。
2014年以降はテレビドラマを中心に監督として演出を担当。また2016年からは大人気シリーズであるテレビ朝日系ドラマ「相棒」を手がけている。
映画『太陽の家』の作品情報
【公開】
2020年1月17日(日本映画)
【監督】
権野元
【キャスト】
長渕剛/飯島直子 山口まゆ 潤浩/柄本明 上田晋也(友情出演)/瑛太 広末涼子
【作品概要】
大工の棟梁とある母子との交流を、複雑な関係を持つ家族や弟子たちとのエピソードを絡めながら描きます。監督を務めるのは、ドラマ「相棒」シリーズなどを手掛けた権野元。脚本は、特撮ドラマ「牙狼」シリーズなどを担当した江良至が担当しています。
キャストには主人公の川崎信吾役を、ミュージシャンでテレビドラマ『とんぼ』や『英二』などで俳優としても活躍した長渕剛。
共演には信吾の妻の美沙希役を『メッセンジャー』などの飯島直子、信吾の弟子の河井高史役を「まほろ駅前」シリーズなどの瑛太、そして保険会社営業員である池田芽役を『20世紀ノスタルジア』『秘密』などの広末涼子が務めています。そのほか名優の柄本明やお笑いコンビのくりーむしちゅー上田晋也らが集結しています。
また長渕は、本作のためにオリジナル楽曲「Orange」を主題歌として提供しています。
映画『太陽の家』のあらすじ

(C)2019映画「太陽の家」製作委員会
人情に厚い川崎信吾(長渕剛)は、仕事を支え家庭を守ってくれている妻・美沙希(飯島直子)と年ごろの娘・柑奈(山口まゆ)がいるにもかかわらず、好みの女性には弱いという大工の棟梁。
ある日、弟子たちと現場に出ていた川崎は、ふとしたきっかけで保険会社の営業員・池田芽衣(広末涼子)と知り合います。
父親を知らない息子・龍生(潤浩)とともに、シングルマザーとして懸命に生きる芽衣。そんな彼女を気にかけ、信吾は人見知りな龍生の面倒を見るようになっていきます。その気遣いが、芽衣や自分の家族たちの思いに波紋を呼ぶとも知らずに……。
映画『太陽の家』は全国順次ロードショー!