ちば映画祭2019「清原惟監督特集」
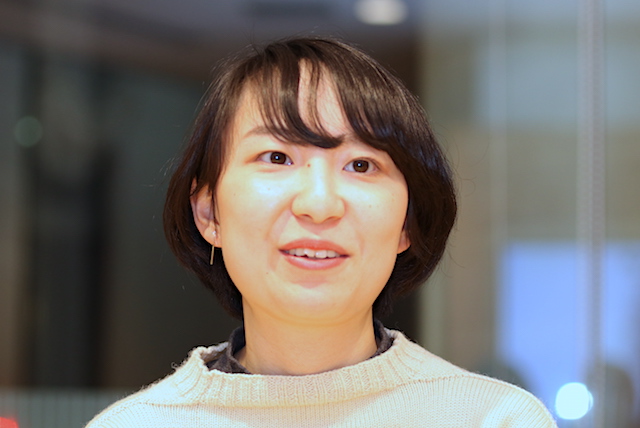 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
「初期衝動」をテーマに掲げ、2019年で10回目の開催となった「ちば映画祭2019」で特集された清原惟監督。
インタビューの後編では、2018年に渋谷ユーロスペースにて公開された初長編作品『わたしたちの家』の制作過程、音や小道具へのこだわりについて語っていただきました。
CONTENTS
建築映画としての“気配”と“手触り”
 (C)東京藝術大学大学院映像研究科
(C)東京藝術大学大学院映像研究科
──清原監督の作品は一般に建築映画と捉えられていますが、建築にもやはり興味がおありですか?
清原:私の作品は、一定の映画ファンの方たちが見てくれていると思うんですが、個人的に嬉しかったのは、映画以外の表現ジャンルをやっている人たちにも評判だったことです。映画だけに止まらならずに他のジャンルの人にもみてもらえることは嬉しいですね。
もともと建築には興味がありました。子供のころから、建物から一度外に出てまた戻ってくると、別の空間になってしまうんじゃないかという感覚があったり。家に帰ってくる時、なぜか家で怖いことが起きている妄想をしてしまい、ドキドキしながら帰っていました。
──『わたしたちの家』では、建物の空間概念が素晴らしく、建物の匂いや気配を感じました。
清原:手触りにも近いと思います。人間についてもそうですが、空間や建築といったものは、いつも変わらずそこにあり続ける、と思ってしまいがちですが、実際は生き物と同じように刻一刻と変化しているのだと思います。
──空間が一気に変転していく場面などは能楽の感覚なのかとも思いましたが。
清原:幽霊ということもそうですね。映画の面白いところであり難しいところは、そこに映っているものしか映らないことです。幽霊というものも基本的には映らないとされていて、能楽だったら姿形を持っていたりしますが、私が映したいものは、そこにもうすでにないものや、ここにはかつてあったけれど、なくなってしまったものです。それらは直接映すことは出来ませんが、それを感じてもらうことは絶対出来ると思っていて、それはいつも自分の挑戦としてあります。
例えば、セリのお父さん行方不明で、この家には今はいないけれど、お父さんがいたという事実は、まだそこにあるものたちによって立ち上がってくる気配があり得ると思うんです。
──亡くなった人の気配を映すということでは、よりリアルな小津とでも言うのでしょうか。畳の空間の使い方などをあのように効果的に使っている若い作家はあまりいないと思いますが、小津の影響はありますか?
清原:あの家に出逢ってしまったから、ああいう空間を撮ったということなので、もともと伝統的な日本家屋で撮りたかったということではありません。
確かに低めのカメラというのは小津を連想させるものがあると思うんですが、そこまで小津的なオマージュの画だという意識では撮っていないです。それに小津のカメラはもうちょっと低いかもしれないですね。
──あの家屋自体は見つけるのにかなり時間がかかりましたか?
清原:結構見て回って決めました。一軒の家に見えないとよく言われます。普通に繁華街というか商店街の近くに立っているんです。映画の中ではとある日本の港町というような、あまり固有の地名が浮かび上がってくるようにはしていません。
撮影現場の現実感覚
 (C)東京藝術大学大学院映像研究科
(C)東京藝術大学大学院映像研究科
──空間の使い方についてお聞かせください。
清原:人物はもちろん重要なファクターですが、それと同じくらい物や建築も主人公の一人という意識があります。人の会話やそこで起きているドラマの後ろや横にある物や建築は切っても切り離せないもので、こういう場所が人間の身体に与える影響は大きいと思うんです。
特に家というのはとても個人的な空間です。そこでの振る舞いというのは個人が滲み出るし、その家とその人との付き合い方は身体に現れてくる気がします。
役者さんたちも、演技をしつつも実際にその空間にいるという現実がある。そしてその空間から影響を受けています。その実感が映画を作る上での柱になって支えてくれるのではないかと思っています。
──現場では批評的な意識を持っていたりするのでしょうか?
清原:映画撮影の現場では、目の前に映画の現実が待っていて存在しているので、基本的には批評的なことはあまり考えていません。役者さんがいて、美術がどんどん出来上がるのを見ていると、この映画固有のものと向き合うことに、力をそそぐことが必要だと思うからです。
ただ、企画段階や脚本を書く時には、批評的な目線というのはあるとは思います。例えば、『わたしたちの家』でいうと、今までの映画の中での物語というものがどういう位置づけだったか、それに対して新しいことができないか、ということへのひとつの自分なりの回答として作りました。撮影に入る前は、他の映画があって自分の映画があるということは明確に意識しているつもりです。
緻密な音響の世界
 (C)東京藝術大学大学院映像研究科
(C)東京藝術大学大学院映像研究科
──音への拘りや意識についてもお聞かせください。
清原:音は自分にとってとても重要なものです。見ている人には音よりも視覚の方が言語化できる記憶として残ると思うんですが、ただ一方で音の存在はもっと人の潜在意識下に働きかけているかなと。受け取っていないように感じていても、音はその人が映画をみる上で深く印象に関わっていると思うんです。
私は音を聞くのが好きで、単なる音が音楽的に聞こえる瞬間がすごく好きです。大学の課題で音録りにいったことがあったんですが、野原で音を録って、その時に同時に写真も撮って、後でその写真をみながら音を聴き返すと、写真をみるよりも音を聞いた方がその時の感覚が鮮明に蘇ってきたんです。
視覚は情報ですが、音は波なので鼓膜に直接触れてきます。物理的に人の身体に距離が近いという意味で奥深くに働きかけるもので、映像と同じように音を大事に扱っています。
作家の直感
 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
──清原監督の作品をみた観客たちの反応はいかがでしたか?
清原:面白がってくれた人たちもたくさんいましたが、微妙な反応の方もいました。横浜で『わたしたちの家』を上映した時はちょっと怒ってる感じのお客さんがいて。(笑)
おそらくどう観たらいいのかわからなかったんだと思います。好きだと言ってくださる方たちは、構造やコンセプトが面白いとか、物語や人物が好きとか、ムードが心地よいだとか、それぞれ違う楽しみ方をしてくださっているのが、嬉しいですね。観る人が自由にみることができる映画を作りたいといつも思っています。
私の作品はコンセプチュアルな部分があるので、頭でっかちに撮っているような印象を受ける方もいます。むしろそれはリテラシーがありすぎる人というのか、論理的に考えすぎる人はそういうふうに捉える方もいますね。実は私はそんなに構造的に作っているわけではないんです。
──『ひとつのバガテル』も『わたしたちの家』にしても意味付けしていく感じは全く受けなかったです。
清原:そうですね、敢えて回収しないというのもあります。あまり他ではみたことない感じにはなったのかなとは思うんですけれども。
はっきりと結論付けることはせずに、割とビックリされてしまうような終わり方にすることが多いですね。これでいいのかと思う方もいると思うんですが、それによって作品が開かれていくと思うんです。映画が終わってもその映画が外に続いていける、向かっていけるような感じをいつも意識して、完結した世界にならないように心がけています。
今後の作品作りについて
 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
──おそらくこれから商業映画もやっていかれるとは思うのですが、抵抗はありませんか?
清原:まだ商業の世界を知らないので言えることは少ないですが、日本の商業映画で撮られている作品で自分がぴんとくるものはあまり多くはありません。お金を稼ぐことと、芸術作品として価値のあるものが、必ずしもイコールでないことは実感としてあります。そのあたりをどういうふうに折り合いを付けるか。映画監督という職業になることが目的ではなく、自分の撮りたい映画を撮ることができればと思っているので、どのようなバランスでいるのかが難しそうだなと思います。
──他の若手監督の活躍をみて思うところはありますか?
清原:商業の現場にいる友人たちからたくさん話を聞いています。やっぱり映画は幅広いなと。一口に映画と言っても、同じカテゴリーに入れていいのか分からない作品や私の作品があれば、対極にあるような作品も映画と呼ばれたりしています。
もちろん私はどちらも映画だと思うんですが、同じ映画とは言うけれど、比べて話すのは難しいです。勢いがあるのはとてもよいことだと思います。
──次回作のご予定を教えてください。
清原:今ちょうど新しい映画の準備中です。脚本を書いている段階なんですが、『わたしたちの家』
の続きとしての挑戦をしたいと思っています。
『わたしたちの家』では多元宇宙的な世界観ですが、それを発展させたような、SFではないんですが、さらに数を増やして色んな世界が同時に動いているような感じにしようと思っています。
二つの世界だと物語がどうしても一対一の関係になってしまうので、よりポリフォニックで、音楽的な複雑な調べを奏でたいです。
インタビュー/ 加賀谷健
撮影/ 出町光識
清原惟監督プロフィール
 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
1992年生まれ。東京都出身。
武蔵野美術大学映像学科卒業、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻監督領域修了。黒沢清監督、諏訪敦彦監督に師事。
東京藝術大学大学院の修了制作として手がけた初長編作品『わたしたちの家』が、ぴあフィルムフェスティバル2017でグランプリを受賞し、2018年には渋谷ユーロスペース他、全国各地で上映されました。
今、最も注目を集めるインディーズ作家の1人です。
清原惟監督作の作品情報
映画『ひとつのバガテル』

【製作】
2015年(日本映画)
【脚本・監督・撮影・編集】
清原惟
【キャスト】
青木悠里、原浩子、加藤周生、中島あかね、菊沢将憲、立原学、櫻井知佳、林暢彦、大高文人、小島智史、森曠士朗、古川美祥、橋本日香里、坂藤加菜、岩崎友哉
【作品概要】
2018年に『わたしたちの家』が劇場公開された新鋭・清原惟監督が、武蔵野美術大学映像学科の卒業制作として手がけた作品。
PFFアワード2015 入選、第16回 TAMA NEW WAVEコンペティション ノミネート。
タイトルにある「バガテル」は、小品のピアノ曲を意味し、本作の全編ではベートーベンの「6つのバガテル」が使われ、作品のトーンを決定付けています。
映画『わたしたちの家』

【公開】
2017年
【監督】
清原惟
【キャスト】
河西和香、安野由記子、大沢まりを、藤原芽生、菊沢将憲、古屋利雄、吉田明花音、北村海歩、平川玲奈、大石貴也、小田篤、律子、伏見陵、タカラマハヤ
【作品概要】
日本映画の新星・清原惟監督劇場デビュー作品。
圧倒的な映像感覚と音響世界によってスクリーン上に広がる多元宇宙は、多くの映画ファンを唸らせました。
2017年PFFアワードグランプリ受賞作品。第68回ベルリン国際映画祭・フォーラム部門正式出品されています。
映画『網目をとおる すんでいる』

【公開】
2018年
【監督】
清原惟
【キャスト】
坂藤加菜、よだまりえ
【作品概要】
東京藝術大学大学院の修了制作である『わたしたちの家』が2018年に渋谷ユーロスペースで公開され、大きな注目を集めた清原惟監督の最新短編作品。
2人の少女たちの間で交わされる何気ない会話から立ち上がってくる不思議な“清原ワールド”の虜になってしまいます。





































