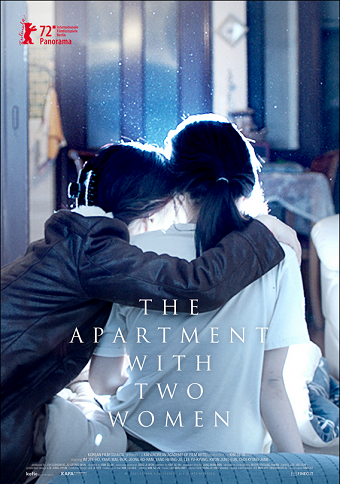連載コラム「新海誠から考える令和の想像力」第7回
新海誠監督の最新作『天気の子』がいよいよ7月19日に公開されます。
それも上映全劇場359館が、初日の午前9時に一斉上映をする“前代未聞”の試みでの封切りです。
あわせて、新海監督の過去作をすべて組みこんだ“スペシャル映像”が解禁されました。
「新海誠監督作品 2002年~2016年」と題されたこの予報では、それぞれの作品を象徴する言葉が取りあげられています。
「世界っていう言葉がある。」「世界はほんとうに綺麗なのに、ぼくだけが、わたしだけが、世界にひとりきり取り残されている。」「世界の秘密に近づきたい一心でぼくたちはそうやってどこまでいくのだろう?」「まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える。」「言おうと思ってたんだ。おまえが世界のどこにいようとも、おれが必ずもう一度会いにいくって。」
“セカイ”の連呼、オンパレードです。
そして今作『天気の子』においては「世界のかたちを変えてしまったんだ」というフレーズになります。
これらはこの連載の副題「セカイからレイワへ」と符合し、主人公の帆高と陽菜がそこから“どこへ”むかうのかを考察してきました。
スペシャル映像のなかで、帆高は言います。
この場所から出たくて、あの光に入りたくて、必死に走っていた。……そしてその果てに君がいたんだ。
新海監督が描こうとしている他者への愛。今回はそれをもう一つのテーマと読みこめる「祈り」とともに、まとめにかかります。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力』記事一覧はこちら
新海誠論の要約

(C)2019「天気の子」製作委員会
この連載では、新海誠監督作をふりかえることからはじまり、他のアニメーション作家との比較をふまえ、その作品の可能性の中心に「愛」があることをとらえてきました。
なぜ愛を見いだせるかといえば、その主人公の多くが、悲しみを知り、傷を負った存在だからです。
自分の弱さに気づいた者は、相手の弱さにも想いをめぐらすことができ、傷を負った者同士で、優しくつながりあえる。
これは決して“傷をなめあう”といった類のものではありません。傷から、弱さから、脆弱性から、より強くむきあえることを示しています。
一見、“強さ”というと、ああしろ、こうしろという力、突きつめれば自分の「欲望」や「所有欲」を満たす行為に付随しているものと思われがちです。
しかしほんとうの強さは、自分の弱さを他者のまなざしに感じとり、他者を他者として認め、かつ自分の傷をさらしながら手をさしのべられる人間にこそ、あります。
このようなことを、フランスの哲学者・レヴィナスの思想を援用しつつ述べてきました。
ここからは、前回まで引用してきたレヴィナスの主著『全体性と無限』の訳者を務めた熊野純彦氏の著書『レヴィナス──移ろいゆくものへの視線』より、その理解を深めていきます。
他者から生じる倫理

熊野純彦『レヴィナス──移ろいゆくものへの視線』(岩波現代文庫、2017年)
「きみとぼく」の関係において、新海作品では両者が時間的にも空間的にもすれ違い、相手が自分のいる世界からはみ出てしまうという特徴がありました。
ここにまず、相対する者が「他者」であることが確認できます。
他者をめぐる「観念」はじつは観念ではなく、「渇望」(desir)である、とレヴィナスはいう(82/116)。渇望されるのは、〈私〉から無限にはみ出してゆくもの、「〈他者〉、つまり〈無限なもの〉(l’Infini)」(82/115)なのである。他者は、私によってとりつくされることがない。他者とはつまり、私にとって〈無限〉である。 P73
「他者」とは私にとって「無限」である。熊野氏はつづけて言います。
他者との関係じたいが、あるいは私という「〈同〉のエゴイスティックな自発性」を問いただす「〈他者〉の現前」そのものが「倫理」と呼ばれる。すなわち「私の思考と私の所有にたいする〈他者〉の異邦性、つまり〈他者〉を〈私〉に還元することはできないということが、まさしく私の自発性を問いただすこととして、すなわち倫理として現成する」(33/46 f.)のである。 P79
私に還元できない存在、私と絶対的な差異がある者が、「倫理」を成り立たせる。
帆高は“100パーセントの晴れ女”という絶対的な他者の陽菜と出会うことによって、倫理のうえに愛を築く可能性を得ます。
というのも、愛こそ超越する志向であり、絶えず無限に開かれていくからです。
愛について

(C)2019「天気の子」製作委員会
愛は測りえない、語りえないという不可能性ゆえに、愛する対象は私によって毀損されない他者でありつづけます。
レヴィナスは、「愛」に「〈他者〉がその他性を保持しながら、欲求の対象としてあらわれる可能性」を、さらにはまた「〈他者〉を享受する可能性」をみとめている(285/392)。 P102
絶対的な他者は、現実的につながりあえないわけではありません。
たとえば愛撫という経験のなかでは、相手を十全に所有できない(他性をたもつ)一方で、私は他者との結びつきを享受しています。
愛撫とはなにも把持しないことであり、みずからの〈かたち〉から絶えず逃れて、未来へとおもむくもの──けっして十分に未来ではない未来へとおもむくもの──を懇望する。あたかもいまだ存在しないかのように、じぶんから溢れ出てゆくものを懇望するのである。愛撫はさがしもとめ、発掘する。愛撫は開示の志向性ではない。愛撫はさがしもとめる志向性であり、見えないものへのあゆみなのである。(288/397) P103
“愛(撫)はさがしもとめる志向性”である。ちょうど帆高が「家出」をし、「もう一度あの人に会いたいんだ!」と叫ぶように。
愛撫は、そのゆえに、「不断に増大してゆく飢えのうちにある」。かくして、「愛撫はその到達点よりも遠くへとおもむき、存在するもののかなたをめざす」ことになる。 P106
愛撫は愛を表現しますが、愛を語りえません。
この「愛」に対して、わたしたちはそれをどんなふうに言いあらわせばいいのでしょうか。
それも『天気の子』はうまく示唆しています。「祈り」という言葉、行為です。
祈りについて

(C)2019「天気の子」製作委員会
スペシャル映像では帆高が「思わず強く願いながら、彼女は鳥居をくぐった」と言って、陽菜が手をあわせるカットが挟まれています。
その鳥居は古びたビルの屋上にあるのですが、これは実在する「代々木会館ビル」を模しています。
陽菜は帆高を隣に「今から晴れるよ」と手を組むと、見あげた中心部から空が晴れあがるのです。
この「祈り」が「愛」と一緒に語られるべき重要なポイントとなっています。
それは一般的な言葉とは異なる面をもっています。
アリストテレスは、論理学的著作群のなかですでに、「文」(ロゴス)はすべて意味をもつが、しかし真偽を問えない文があること、つまり「命題」(アポファンシス)ではない表現が存在することに注意していた。その代表的な例としてとりあげられるのは「祈り」(エウケー)である。 P86
なにかをしなさいという「命令」や、なにかをするという「宣言」は、言葉と行為が密接にかかわりあっていますね。「約束」などもそうでしょう。
そのような行為をうながす言葉、すなわち「遂行的な言葉」のひとつに「祈り」があると考えられますが、熊野氏はこうとらえます。
唐突に結論を先どりするならば、だが、いっさいの言語行為、あるいはすくなくともそのうちで典型的なものは、かえってどこか〈祈り〉に似てはいないであろうか。というより、むしろ〈祈り〉そのものではないだろうか。 P86
すべての言語行為は「祈り」である。またはそれに近づいていくとは、なにを意味するのでしょう。
じっさい、「命令」(command)は、ときに「要求」(request)になり、あるいは「依頼」(ask)へと後退し、また「懇願」(beg)と交替する。それらはやがては「祈り」(pray)となりおおせるのではないだろうか。 P87
徐々に私が「他者」に仕えていくようです。
言語行為の諸事実がおしえているように、たしかに私はことばによって他者にはたらきかけ、他者をうごかすことができる。ただしそれは、ことばがあらかじめ呼びかけであり、祈りであることによってである。さきに触れておいたように、こうして、ことばによって他者に命令しようとするものこそがかえって、ことばをつうじて他者にかぎりなく仕えることになるのである。 P88
鳥居で陽菜が両手をあわすとき、または帆高がもう一度会いたいと叫ぶとき、愛は祈りのかたちをとって、他者に無限に仕えることになります。
ここに「きみとぼく」の関係は、互いの他性を侵すことなく、外部に開かれたままに美しく結晶します。
美しい背景について

(C)2019「天気の子」製作委員会
新海誠作品では必ずといっていいほど言及される背景の美しさ。
スペシャル映像でも「それはまるで、夢の景色のように、ただひたすらに、美しい眺めだった」という台詞がピックアップされています。
これも、大気や光、水や風景といった世界のすべてが生の糧であるというレヴィナスの思想に即してみることができます。
わたしたちが生きることは第一に、世界全体を享受している事実を明かします。
当たりまえでも忘れがちなその事実を、新海監督は美術で表現しつづけ、この世界に生きながらも存在の彼方を感じさせる視座を物語で提供してきたといえるでしょう。
『天気の子』は愛と祈りをもって、セカイ内に住まうわたしたちをその外部へと誘ってくれるはずです。
帆高の台詞を再度引くことで、公開前の段階の本論を一度締めます。
この場所から出たくて、あの光に入りたくて、必死に走っていた。……そしてその果てに君がいたんだ。
その果ては、いつなんどきも無限にむかって開かれており、だれも排除することのない果てしない愛を、この世界に到来させます。