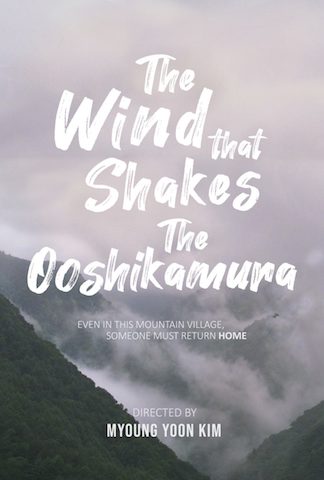サスペンスの神様の鼓動51
ある青年が、死刑が確定した殺人鬼が主張する1件の「冤罪事件」に関わったことから、次第に社会の闇へと陥り始めるサイコ・サスペンス『死刑にいたる病』。
櫛木理宇の同名小説を原作に、『孤狼の血』(2018)『凪待ち』(2019)など、社会の闇にスポットを当てた緊張感あふれる作品を多数手がけている白石和彌が監督を務めました。
24人もの人間を殺害し、世間を震撼させた殺人鬼の榛村(はいむら)。そんな彼に突然呼び出された大学生・雅也は「たった1件だけ、自分が関わっていない殺人がある」と告白され、その真相究明をにされます。
榛村が唯一関与を否定している殺人事件の真相を軸に、社会が侵された病魔をあぶりだす、本作の内容とは?
CONTENTS
映画『死刑にいたる病』のあらすじ

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
教育熱心な父親により、幼い頃から自由な時間を得られずに勉強ばかりをしてきた筧井雅也。
進学校に入学した雅也でしたが、大学はいわゆる三流大学に入学したため、父親は雅也のことを認めていません。また母親の衿子は昔から父親に家政婦のように扱われていたため、自分では何も決められない人間になっていました。
雅也は大学で、中学時代の同級生だった加納灯里と再会します。中学時代は地味な印象が強かった灯里が、明るい性格になっていることに雅也は驚きます。
祖母のお葬式に参列するため、雅也は実家に帰りますが、父親は雅也のことを目の敵にします。家でうんざりした気持ちになった雅也は、自分宛てで届けられていた手紙に気づきます。
手紙の主は、榛村大和。彼は雅也が中学生時代に通っていたベーカリーの店主でしたが、24人もの人間を殺害した上で被害者の爪を剥がしてコレクションにしていた「連続殺人鬼(シリアルキラー)」でもありました。
手紙を受けた雅也は、刑務所に収監中の榛村に面会しに行きます。すでに死刑判決を受けた榛村は自身の罪を認めていましたが、「立件された9件の事件の内、最後の1件だけは自分はやっていない」と告白します。
榛村以外にも殺人鬼が存在し、今現在も街に潜伏していることの恐怖を訴える榛村は、雅也に「真犯人を探してほしい」と依頼します。
面会から帰る途中、雅也は髪の長い男と話をします。「ある人に面会に来たが、会おうかどうか決められなかった。君に決めてほしい」と雅也に語りかける髪の長い男に気味の悪さを感じた雅也は、彼から逃げるように距離を置きます。
榛村を担当している弁護士の佐村から、24件の殺人事件に関する調書を読んだ雅也は、榛村が主張する9件目の事件だけが、その他の事件と異なる点があることに気付きます。
榛村の手口は、狙いを定めた「16~17歳の少年少女」と長い時間をかけて信頼関係を抱き、燻製小屋に連れ込んで拷問を行ったのち殺害するというものでした。
しかし、9件目の事件の被害者・根津かおるだけは「24歳の成人女性」であり、さらに「山中で首を絞めて殺す」という他の事件とは違う突発的な形で殺害していました。
一連の事件に違和感を抱いた雅也は、独自に調査を開始します。
サスペンスを構築する要素①「殺人鬼が主張する唯一の冤罪」

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
殺人鬼が主張する、たった1件の冤罪事件。
連続殺人鬼が告白した1件の「冤罪事件」の調査を依頼された雅也が遭遇する、人間の闇を描いたサイコ・サスペンス『死刑にいたる病』。
24人もの人間を殺害し、世間を震撼させた殺人鬼の榛村。彼は自身の犯行を認めていますが、立件された9件の内、9件目の殺人だけは自身の犯行ではなく「別に犯人がいる」と主張します。
全ての罪を受け入れて、既に死刑が確定した榛村が「何故、たった1件の冤罪にこだわるのか?」という謎が、本作序盤の鍵となります。
その榛村から、冤罪事件の真相の調査を依頼された、大学生の雅也。雅也は中学時代、榛村が営むベーカリーの常連だったのですが、榛村と特別に親しかったわけではありません。
「何故、榛村は雅也は選んだのか?」という疑問も、作品を構成する大きな謎となっており、のちに作品のテーマへとつながっていくのです。
サスペンスを構築する要素②「人の心を手玉に取る榛村」

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
本作では「何故、榛村は雅也は選んだのか?」という謎の一方で「雅也は何故、殺人鬼である榛村のために動くのか?」というのも気になる点ですが、その答えは榛村というキャラクターの特異性にあります。
16~17歳の真面目そうな学生を主な標的にし、24人もの人間を殺害した榛村は、信頼した相手を拷問にかけてゆっくりと殺すという恐ろしい殺人鬼です。
しかし榛村は周囲に異常なまでに愛想が良く、雅也もまた榛村を面会した際に「榛村さんとの時間は落ち着く」と口にしています。榛村の家の近所に住んでいた農家も「もし、今でも榛村さんに助けを求められたら、助けると思う」と雅也に語っています。榛村は、人の心に入り込み、いつのまにか手玉に取る術を知っているのです。
榛村を信じた人間は一種の洗脳状態になりますが、誰でもそうなるわけではありません。両親や周囲の人間に、何かしらのコンプレックスを抱いている人間が榛村の標的となるのです。
榛村が標的に選んでいたのも、勉強ができる真面目そうな10代の少年少女。厳しい家庭に育ったことで自由な時間を奪われ、不満を抑圧させて生きている、言わば、心に入り込む隙がある子どもたちでした。心に隙がある子どもたちを「凄いじゃないか!」と褒め肯定することで、自身に依存させていきます。
榛村に冤罪の調査を依頼された雅也も、厳しい家庭環境で育ち、父親の期待に応えられなかったことにコンプレックスを抱いています。それゆえに中学時代の雅也も榛村の標的に選ばれておりい、それは成長した今も変わりません。
また雅也の母親である衿子が過去に榛村と関係があったことが発覚し、雅也が「榛村は自分の父親ではないか?」と思い始めた辺りから、本作の視点が変わり始めます。
本作の中盤まで、観客は雅也の目線で「9件目の殺人事件の真相」を追いかけるのですが、中盤以降から雅也は榛村によって心に闇を抱えるようになり、榛村に依存し寄り添うようになります。
同じ目線だったはずの雅也ですら、信用できなくなる。これが『死刑にいたる病』の中盤以降の恐怖となります。
サスペンスを構築する要素③「感染する異常」

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
榛村によって心に闇を抱えながらも、事件の真相に行き着いた雅也。結局「9件目の殺人事件」も榛村の犯行であったことが分かり、榛村は「一度狙った相手は何年かけてでも命を奪う」という執念深さを持っていることが判明します。
では何故わざわざ榛村は、雅也に事件を掘り返させたのでしょうか? 幼少期にトラウマを植え付けた金山同様、中学時代に雅也の心を掌握した榛村は、「刑務所の中からでも人を操ることができる」と証明し、そのことに快感を得ていたのです。
最後まで恐ろしい榛村ですが、死刑が確定している以上榛村がこの世からいなくなれば全ては終わり……と思わせておいて、映画『死刑にいたる病』は原作小説とは違うラストを迎えます。
雅也の中学時代の同級生で恋人になった灯里も、榛村のかつての標的であり、雅也同様に手紙を受け取っていたことが判明します。
そして榛村に心酔している灯里は、榛村の指示を受けて雅也に接近していました。そして雅也が、灯里から榛村と同じ異常性を感じるというホラーテイストのラストシーンになっています。
榛村が何故あのような犯行に及んだかは本作でハッキリと語られていませんし、白石和彌監督も「意図的に分からないようにした」と語っています。
ただ、間違いなく榛村の殺人衝動には「病」ともいえる性質があり、その殺人衝動は灯里にも感染しています。
榛村の標的は何かしらのコンプレックスを抱いている人たちでした。それでは幸せな家庭に育ち「普通」に生きていれば、「病」のような殺人衝動は絶対に芽生えないのでしょうか?
『死刑にいたる病』で印象的なのは、世間体に囚われるが故に人々がストレスを抱える社会を、意図的に描き出しているという点です。
学歴にこだわる雅也の父親、三流大学に入り未来が見えず、真面目に生きる気力を失った大学生、日頃の不満を自分より弱い立場にぶつける会社員……作中の榛村のセリフにもありますが「人生を大事にしていない人たち」が世の中に溢れており、何かのキッカケで雅也同様心に闇を抱きかねない人ばかりです。
そして榛村の病的な殺意は「人生を大事にしていない人たち」に簡単に感染します。
「自分は大丈夫、自分は絶対にまともだと言い切れるのか?」「榛村のような人間につけ入られる隙が、誰にでもあるのではないか?」……それが映画『死刑にいたる病』のテーマです。
映画『死刑にいたる病』まとめ

(C)2022映画「死刑にいたる病」製作委員会
『死刑にいたる病』は、面会室という空間、人心掌握に長けた犯罪者が主人公を闇に引きずり込む展開など、同じ白石和彌監督作品の『凶悪』との共通点が多く、白石監督自身も『凶悪』を意識し「やるかどうか悩んだ」と語っています。
『凶悪』は、死刑囚のヤクザ・須藤と、須藤が「先生」と心酔していた男・木村の、2人の犯罪者の視点が物語の中心で描かれた作品でした。
しかし『死刑にいたる病』は雅也という、榛村の犠牲者の視点で描かれた、病的とも呼べる現代社会における、家族の物語にもなっています。
設定には共通点が多いものの、その切り口の変化によって、異なる社会の闇を浮き彫りにした作品を描き出す、白石和彌監督の手腕には驚かされます。