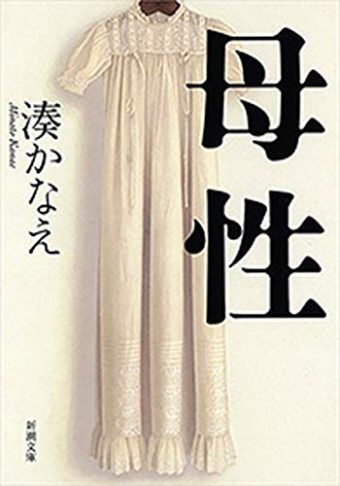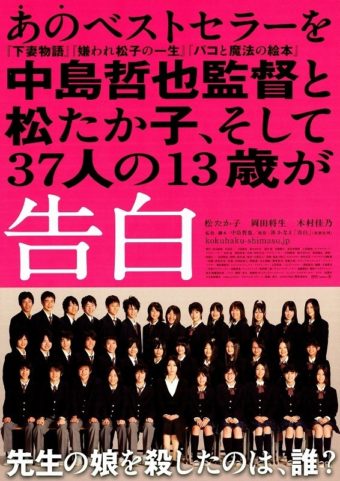原作小説と映画の比較から見えてくる
小説/映画ならではの「演出」の魅力とは?
ある未解決事件に秘められた真実を、「娘を愛せない母」と「母に愛されたい娘」という二人の語り手によって炙り出してゆくサスペンス・ミステリー映画『母性』。
原作は、『告白』などで知られるベストセラー作家・湊かなえが「これが書けたら作家を辞めてもいい」という覚悟で綴った同名小説。物語の語り手を務める「娘を愛せない母」ルミ子役を戸田恵梨香が、「母に愛されたい娘」清佳役を永野芽郁が演じました。
本記事では、
映画『母性』と原作である作家・湊かなえの小説『母性』の違いを特集。
ネタバレ言及を交えながら、映画・小説の相違点を通じて見えてくる湊かなえの小説『母性』における「章・節構成」による演出、映画『母性』の「映画」だからこその演出について解説してきます。
CONTENTS
映画『母性』の作品情報

(C)2022映画「母性」製作委員会
【公開】
2022年(日本映画)
【原作】
湊かなえ『母性』(新潮文庫刊)
【監督】
廣木隆一
【脚本】
堀泉杏
【エグゼクティブプロデューサー】
関口大輔
【キャスト】
戸田恵梨香、永野芽郁、大地真央、高畑淳子、三浦誠己、中村ゆり、山下リオ
【作品概要】
映画『母性』の原作は、湊かなえの同名小説。脚本を『ナラタージュ』(2017)の堀泉杏が担当し、監督を『ナミヤ雑貨店の奇蹟』(2017)、『PとJK』(2017)、『ママレード・ボーイ』(2018)、Netflix『彼女』(2021)の廣木隆一が務めました。
母・ルミ子を『あの日のオルガン』(2019)の戸田恵梨香、娘・清佳を『そして、バトンは渡された』(2021)『マイ・ブロークン・マリコ』(2022)の永野芽郁が演じています。
共演として、ルミ子の実母を大地真央、義母を高畑淳子、ルミ子の夫に三浦誠己。
映画『母性』のあらすじ
女子高生が遺体で発見された。その真相は不明。事件はなぜ起きたのか?
普通に見えた日常に、静かに刻み込まれた傷跡。愛せない母と、愛されたい娘。
同じ時・同じ出来事を改装しているはずなのに、二人の話は次第に食い違っていく。
母と娘がそれぞれ語る、恐るべき「秘密」……。
二つの告白で事件は180度逆転し、やがて衝撃の結末へ。
母性に狂わされたのは母か、娘か?
映画『母性』の原作小説との違いを解説・考察!

(C)2022映画「母性」製作委員会
映画は小説を「一対一」の物語へ
湊かなえの小説『母性』を映像化してゆくにあたって、映画『母性』では多くの物語設定・展開に変更を加えています。中でも特筆すべきなのは、原作小説の作中にてルミ子が妊娠した「もう一人の娘」の存在の有無でしょう。
実母の死と「美しい家」の焼失後、夫・娘と田所家の離れで暮らすようになったルミ子は、やがて第二子を妊娠。「母の生まれ変わり」と妄想したその胎児に「桜」と名付ける。しかし、田所家の長女・憲子の幼い息子に突き飛ばされて起きた流産で、彼女は「愛おしい我が子」であった桜を失ってしまう。そして桜を失った後、ルミ子は自身の「運命」を次々と占いで言い当てた霊感商法の詐欺師に騙されてしまう……。
それらの原作小説における物語展開を、映画『母性』は省略。小説では「田所家の次女」であった律子も、映画では「田所家の一人娘」として描写されています。

(C)2022映画「母性」製作委員会
娘という存在を絵画同様に「母に褒められるために手がける作品」として認識していたルミ子。田所家の人間のせいで自身が望んだ「花に因んだ名前」も名づけられず、自分の母に愛される努力も台無しにする清佳を「失敗作」とさえ感じていたであろう彼女が、火事の夜に口にした「子どもなんてまた産めるじゃない」という言葉通り、神秘的妄想という体裁の元に「作品」を再び手がけようとする。
ルミ子の深淵の、さらに深淵にまで続く母性の渇望。それを描いた原作小説での展開が映画にて省略された理由は、やはり「母と一人娘」という構図で統一し、実母とルミ子、ルミ子と清佳、田所家の義母と律子……そして、ニュースで報じられた名もなき「愛能う限り」の母と自殺を試みた女子高生の姿を重ねることで、映画で描かれる母娘像の輪郭をより濃く、より明確に描きたかったからではと考えられます。
「母と娘」という関係性を、115分という長いようで非常に短い時間……長編小説を読み切る時間に比べたら遥かに短い時間で、映画は語らなくてはならない。だからこそ、その語りをよりシンプルに、そしてより純度を高めるための演出として、原作小説の「女には2種類ある」という言葉通り、「母と一人娘」という形で「一対一」の関係性を強調したのではないでしょうか。
「章節」によって噛み締められる物語

(C)2022映画「母性」製作委員会
「母の真実」「娘の真実」「母と娘の真実」の3章構成によって物語が形作られている映画『母性』。
対して小説『母性』は、終章を含んだ7章で構成。
また終章を除く各章も、4節……教師となった清佳が自殺を試みた女子高生の報道記事について同僚と話す「母性について」、ルミ子が神父との交換ノートを通じて自身の母娘にまつわる半生を語る「母の手記」、清佳が自身の記憶とルミ子との母娘関係を振り返る「娘の回想」、そしてルミ子・清佳の母娘と縁があった詩人リルケの「愛」を謳う詩の引用で形作られています。
古くから人々が掲げ続けてきた「母性」と呼ばれるものを再考させられる「母性について」。母性が母性を、母が母を生み出すとは限らない例を提示する「母の手記」。母性を持たない母によって「情」を見失い、それでも母からの愛を求め続ける娘の「性」を提示する「娘の回想」。
そして、小説作中で象徴的に用いられていた「愛能う限り」という言葉と重なるように、「愛」と呼ばれるものを美しく……むしろ、仰々しく謳う、決して仲睦まじくはなかった夫婦のもとに生まれ育ったリルケの詩。
それらの節が章ごとに反復されることで、読み手は「“母性”とは何か?」「“愛”とは何か?」という問いを否応なく噛み締めさせられる。
細かい章・節で構成された小説『母性』だからこそ味わえるその鑑賞体験は、あまりに強烈な毒の味わいに眩暈を起こした際には本を閉じ、他の事柄に目を向けるという「箸休め」をしながら読み進められる「小説」という媒体だからこそ可能なものといえるでしょう。
まとめ/映画の「目を逸らされない」という演出

(C)2022映画「母性」製作委員会
前述の通り、映画『母性』の物語は3章構成であり、小説『母性』とは全く異なる形でその物語が構成されています。その理由もまた、映画に課せられた「時間」と深く関わっているといえます。
115分。それは確かに、長編小説を読み切る時間と比べたら遥かに短い時間ですが、YouTubeの台頭や「ファスト映画」の出現を経た2022年を生きる人々が観る映像の中では、非常に長い時間でもあります。
少しでも「飽き」を感じたら、人々は容赦なく目を逸らし、別の何を観始める。それは誕生から100年以上経った今も変わらない映画の現実であり、2022年現在だからこそ最も痛感できる映画の現実ともいえるでしょう。
「観客に目を逸らされない映画を」……それは2022年現在を生きる、多くの映画の作り手が意識する演出のコンセプトであり、母と娘の物語を描くにあたっての「一対一」の関係性の強調や章構成の変更もその一部とも考えられるのです。
そして原作小説とは異なるラストとして描かれた、映画『母性』の「子ども部屋」と「縫い針」を用いたラスト。それもまた、小説ならではの演出を行った原作のように、観る者の想像力を掻き立てさせ得る「目を逸らされない映画」ならではの演出だったといえるはずです。
ライター:河合のびプロフィール
1995年生まれ、静岡県出身の詩人。
2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部へ加入。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介