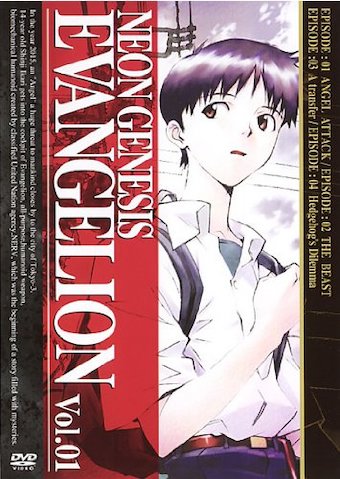連載コラム「新海誠から考える令和の想像力」第3回
「人間の感情という小さなものと、宇宙という極大なものがつながっていく物語」への強い関心。
これが新海誠監督自身の“セカイ”観であり、彼の作品群が「セカイ系」の範疇に入ることを許容するものでした。

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
今回は過去作をたどることで、その世界を形成する土台をより明確にしていきます。
具体的には「繰りかえし現れるモチーフ」から、新海作品に可能性として潜む「倫理観」をとらえてみます。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力』記事一覧はこちら
CONTENTS
初の劇場公開作品『ほしのこえ』の全モチーフの提示

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
ゲーム会社に勤めながら1999年に制作したモノクロの短編アニメ『彼女と彼女の猫』を経て、2002年に発表した映画『ほしのこえ』が、新海誠監督の商業デビュー作となります。
監督のみならず、脚本、作画、演出美術などそのほとんどを個人で手がけ、ひとりでフルデジタルアニメーションをつくってしまったことが、当時大きな話題を呼びました。
まずキャリアのスタート地点が“たったひとり”であったことは、その後の作品世界を理解するうえで見逃せません。
本作は、その孤独をひとり宇宙船に乗りこむ少女と、地球で彼女の帰還を待ちわびる少年に重ねあわせているようにみえます。
2046年、中学3年生の美加子は国連宇宙軍の調査団に抜擢され、「宇宙船」に乗って太陽系外に飛び立ちます。
彼女に想いを寄せる同級生の昇は、高校に進学した後は携帯メールで連絡を取ろうとし、「雨」の日も「雪」の日も、彼女からの返信を心待ちにする日々を送ります。
一方で美加子も、昇からのメールだけを心の支えとし、茫洋たる空間をさまよっていきます。
しかし宇宙船が地球から遠ざかるにつれ、メールの送受信にかかる時間も開いていき、大きな「すれ違い」が生じていくことに。
「届かぬ想い」はやがて8年間もの隔たりになり、美加子の前には異生命体の群体が立ちはだかって、物語は「切ない」幕切れを迎えます。
このあらすじで括弧に入れた言葉は、舞台がSFであっても日常であっても、そのまま新海誠作品を貫くモチーフとなっていきます。
(1)男女(きみとぼく)の関係が、(2)宇宙規模の大きさをもって語られ、(3)なにかしらの隔たりを利用し人情の機微を描き、(4)その届かない気持ちは天候で表現する、といった形式あるいは手法です。
とくに(3)の“なにかしら”に入れるものを1作ごとに変えて、毎度ドラマを紡いでいることがうかがえます。
さきに全作品を見渡してしまうと、“隔たり”のあらゆるバリエーションを物語の推進軸に据えています。
「南北に分断された日本」(『雲のむこう、約束の場所』/2004)
「引っ越し」(『秒速5センチメートル』/2007)
「生と死」(『星を追う子ども』/2011)
「歳の差」(『言の葉の庭』/2013)
「異なる時空」(『君の名は。』/2016)
2019年7月に公開予定の『天気の子』においても、その点に注目してみてください。距離を生むなにかが、設定に埋めこまれているはずです。
よく初監督作品には、その作家のすべてがあると言われますが、新海監督も例にもれません。
そのため、以下の各作品紹介では、そこでもっとも焦点があてられているものに着目して、“セカイ”のポイントを絞って解説します。
『雲のむこう、約束の場所』と「謎」

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
戦後、南北に分断された日本で、占領下の北海道に建てられた「謎の塔」を目指そうとする少年少女たちを描いた初の長編作品です。
本作の核心は原型となった短編漫画『塔の向こう』を取りあげるなかで、後述します。
『秒速5センチメートル』と「恋」

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
「桜花抄」「コスモナウト」「秒速5センチメートル」の全3話で構成された連作短編アニメーションで、それぞれ「出会いと別れ」「恋の苦しみ」「恋の思い出」を切りとっています。
互いの引っ越しを機に離れ離れになってしまった少年少女の、再び交わることのない運命を映像美と一緒に切なくみせてくれますが、それ自体はわたしたちの日常ではよくあることで、目新しさはありません。
初恋とは、そのようなものでしょう。成就するほうが珍しく、自然と思い出になっていきます。
ここで重要なのは、大人は心にいくつもの「傷」を抱えており、その「痛み」から今なにができるか、という問いです。
『君の名は。』では大人になった三葉と瀧が再会を果たすという、本作への返歌とも受けとれる結末を用意しました。
しかし、それだけが答えでしょうか。つまり、傷を癒すことが唯一の対処法でしょうか。
それでは「実らぬ者」に幸福は訪れなくなってしまいます。
そうではなくて、傷を抱えたまま、誰かともう一度つながることはできないか。
こちらにこそ、新海作品から垣間見れる想像力の可能性があります。
また、そのために彼は何度も痛みを呼び覚ますような切なさを描きつづけてきたと考えるほうが自然です。
『星を追う子ども』と「死」
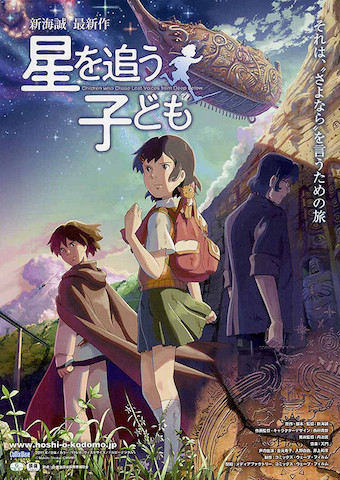
(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
痛みはなにも、恋だけがもたらすわけではありません。
誰かの「死」も、残された人々の心の大きな傷跡になります。
本作は、死者蘇生の伝承がある地下世界を目指す冒険ファンタジーです。
新海監督にとっては、それまで追い求めてきた「痛み」を、「正しい弔い」というかたちで乗り越えようとする試みであったとみることができます。
死者(過去)は蘇らない。人間は別の仕方で、再び他者と関係を結ぶことが必要なのです。
『言の葉の庭』と「孤独」

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
近くにいても、遠い存在。つまるところ、それが生きている人間同士の関係ではないでしょうか。
死者を蘇らせるほどとは言いませんが、人と人とが心を通わすことの難しさは、筆舌に尽くしがたいものがあります。
だから本作では、「言葉」の代わりに、断続的に「雨」が降りつづきます。
雨の日の庭園で、靴職人を目指す男子高校生と、人生をうまく歩めなくなった年上の女性(休職中の高校教師)が逢瀬を重ねます。
「孤悲」と書いて「恋」と読ませるように、ふたつの孤独な魂が、言葉にならない感情が、さまざまな雨音を立て絶妙な距離感を表現。
雨上がりに、自分のなかの新しい言葉を見いだしたふたりは、またそれぞれの道を歩んでいきます。
短編漫画『塔の向こう』と「歩み」
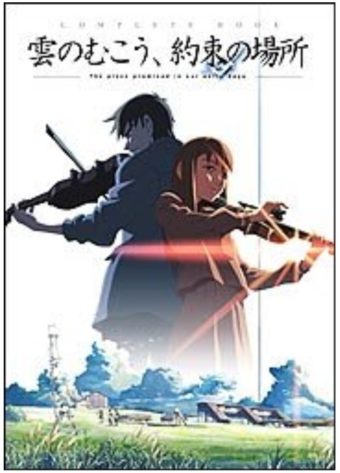
『雲のむこう、約束の場所 コンプリートブック』に再録/2005年角川書店刊
ここで一度、新海作品の“歩み”を整理してみましょう。
新海誠の短編漫画『塔の向こう』には、上述したすべてのキーワードが詰まっています。
これは映画『雲のむこう、約束の場所』のプロトタイプともいえる作品で、2002年9月に「新現実」創刊号に掲載されました。
高校3年生の夏、通学電車に乗らなかった少女は、いつも遠くに見える高い塔へと向かいます。
高架線沿いの道をひたすらに歩き、最初は気持ちよさを覚えたものの、心は徐々に内側に入りこんでいくのを感じます。
そして、例によって“モノローグ状態”に移ります。
彼氏はいないけど、好きな人はいる。話しかけたこともないが、その人から誰かを好きになる気持ちをもらえているだけで、幸せであると。
そう自分に言い聞かせますが、だんだんと曇っていく彼女の表情。「言葉」の代わりに、前述した特徴のひとつである「天候」が変わります。
家路につく途中、雨に降られた彼女は、「だめだ。もう我慢できない。」とまた独り語りをはじめます。
こんなのってひどい。あたしは何がつらいのか自分でもよくわからないけど、でも本当にひどいよ。
彼女にとってなにがそんなにも“ひどい”ことなのでしょうか。
世界はあたしを受け入れてくれない。あたしは今日も、今までだって、ちゃんと歩いてきたのに。
「世界」というキーワードの登場です。また『言の葉の庭』の女性も、朝からビールを飲みながら、同様のことをつぶやいています。
あたしはただ知りたいのに、ただ好きになりたいのに、好きになって欲しいだけなのに、ただ幸せになりたいのに。あたしは、あたしは……
これは新海作品に出てくるキャラクター全員の本音でしょう。高望みはしていない。ただ幸せになりたい。でも世界はそれさえも許してくれない。
ねぇ、誰か、あたしの声を聞いて。あたしは、もっと、ちゃんと強い人になるから。そうしたら、お願い。いつか、誰かちゃんと、あたしのことを見て。
『君の名は。』と「再会」

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films
この問いかけに対して、新海監督は『君の名は。』でようやく救いのようなものを示しました。
世界の危機は免れ、ふたりは別れずに済んだ。そして再会を果たす。
しかしながら、再会をもってハッピーエンドとしてしまっては、新海作品が本来持っていた可能性が潰えてしまいます。
繰りかえしになりますが、それは消えない「傷」であり、そこから生じる「痛み」を抱えたまま、もう一度他者と関係を築こうとする試みです。
『塔の向こう』の少女の「強い人になる」という決意に反し、人間の弱さ、繊細さ、脆弱性から、人とのつながりを描いてきたのが、新海作品のいちばんの魅力です。
またそれが、戦争の時代であった昭和や、結果として格差社会となった平成のつぎの時代、「令和」の礎になるべきものではないでしょうか。
そして『君の名は。』にはもうひとつ、難点があります。他者との「同一化」の問題です。
文字どおり身体が入れ替わることで、互いの愛情を深めていったふたりですが、「相手と同一になること」が本当に他者理解にたどり着くかは疑問です。
むしろ、そのような理解の仕方では、自分か相手のどちらかが「他者性」を失い、最終的には相手の全存在を損なう危険性があります。
新海誠という作家は、他者を征服しない“弱さ”をもって、巧みにそのあたりの問題を回避してきました。
ここに「令和の想像力」の根源があるとみて、つぎの章にあたる第2章・第1節からは、他のアニメーション監督との比較から、新海誠独自の「倫理観」にせまっていきます。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力──セカイからレイワへ──』記事一覧はこちら