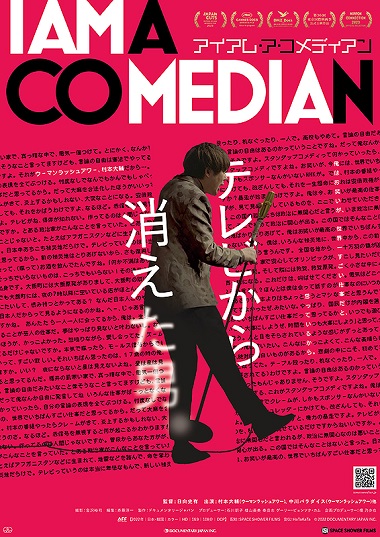連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第34回
こんにちは、森田です。
今回は村上春樹の小説を原作としたイ・チャンドン監督の映画『劇場版 バーニング』を紹介いたします。
原作を大きくアレンジしたことが話題になっていますが、あえて原作の世界観に考察の目をむけることで、映画化された作品の本質に迫ってみたいと思います。
CONTENTS
映画『バーニング 劇場版』のあらすじ
(イ・チャンドン監督 2019年日本公開)
 (C)2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved
(C)2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved
村上春樹の短編「納屋を焼く」(1983年発表)を『ペパーミント・キャンディー』『シークレット・サンシャイン』『ポエトリー アグネスの詩(うた)』などの韓国の名匠、イ・チャンドン監督が映画化。
舞台を韓国に移し、物語も大幅に脚色したミステリーです。
本作は第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最高賞のパルムドールを『万引き家族』と最後まで争い、最終的に「国際批評家連盟賞」を受賞しました。
まず、あらすじを「3つの謎」に焦点をあてて説明します。
小説家を目指しながら運送会社のアルバイトで生計を立てる青年イ・ジョンス(ユ・アイン)は、デパートの店頭で広告モデルを務める女性に呼び止められます。
それは整形してすっかり美しくなった幼なじみのシン・ヘミ(チョン・ジョンソ)でした。
再会してすぐに親しくなったふたり。彼女は自分がアフリカ旅行に行く間、自宅にいる猫の世話をジョンスに頼みます。
ところが不思議なことに、ジョンスが彼女の部屋を何度訪れても、その猫は姿をあらわしません。
餌を与え、猫のフンだけを確認する奇妙な日々がはじまります。
最初の謎は「猫の有無」です。
そして半月後、ヘミは見知らぬ青年のベン(スティーブン・ユァン)を連れてアフリカから帰ってきました。
彼女は彼とケニアのナイロビ空港で知りあったと言います。
貧しく、田舎的な風貌のジョンスに対し、ベンは見るからに金持ちで、都会的なセンスを漂わせています。
ここには「財力の有無」が読みとれますね。
実際にジョンスがベンのマンションに行ってみると、自分とは住む世界が違う、桁違いの裕福さを目の当たりにします。
ジョンスは思わず「ギャツビーだ」とつぶやきますが、彼が好きな作家であるウィリアム・フォークナーとは対照的です。
『グレート・ギャツビー』を書いたF・スコット・フィッツジェラルドもフォークナーも、おなじ“ロスト・ジェネレーション(失われた世代)”の時代を生きながらも、その“喪失感”には格差がありそうです。
おそらくジョンスは、お金では太刀打ちできないベンを前にして、ヘミをいつ失ってしまうか気が気でなかったはず。
ヘミは7歳のころ井戸に落ち、ジョンスに救われたときから彼に好意をもちました。
しかし地元のひとは、ヘミとジョンスの家の近くにそんな井戸はなかったと“記憶”を正します。
つぎの謎に「井戸の有無」が浮かびあがってきましたね。
そしてそのジョンスの実家に、ベンがヘミと一緒にやってきます。
3人は玄関先にテーブルを置いてワインをあけ、大麻を吸い、夕暮れの風景を見つめます。
ヘミが眠ってしまったあと、ベンはジョンスに自分の秘められた“趣味”を打ち明けます。
それは「古いビニールハウスを選んで燃やす」ことでした。
そろそろまた燃やすころで、今日はその下見に来たのだとベンは言います。
この日を境に、ヘミは姿を消してしまいます。電話にも出ず、マンションも空で、仕事先にも見つかりません。
最後の謎は「ヘミの有無」です。彼女はだれかに殺されたのか、それとも借金に追われて逃げたのか。
ジョンスは彼女を探しながら、ミステリアスな状況に巻き込まれていきます。
メタファーの意味を尋ねるヘミ

(C)2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved
状況証拠からすると、ベンがもっとも怪しくみえます。
失踪したヘミと入れ替わるかのように、彼のそばには新しい“彼女”の姿。
また、ジョンスがヘミにプレゼントした腕時計がベンの家の抽斗から出てきたり、ベンが飼いはじめた猫がヘミのアパートでの呼び名に反応したりと、ベンを“黒”だと思わせる十分な推測が成り立ちます。
そしてベンはビニールハウスを燃やす理由を、こう語っていました。
韓国にはビニールハウスが多い。役立たずで汚くて目障りなビニールハウス。僕に焼かれるのを待っている気がします。
ビニールハウスを「弱者」や「持たざる者」と置き換えることは、容易にできるでしょう。
ベンがヘミを「煙のように消えました」と表現するのも、じつに示唆的です。
彼に“燃やされて”しまった存在は、決して少なくないことがうかがえます。
というのも、作中ではベンがパーティー中に「あくび」をするショットが何回も挟まれます。
彼が退屈しのぎに薄っぺらい“ビニールハウス”たちを集めていることは、想像に難くありません。
しかし、本作を観る時間を「犯人探し」だけに費やすことは、おもしろさの半分を見逃すことになります。
もう半分は、やはり村上春樹の小説を“読解”するように、「比喩」や「象徴」を丹念に追っていくことが求められるでしょう。
ベンがジョンスとの会話で「メタファー」と口にしたときに、ヘミはこう聞きます。
「メタファーってなに?」
わざわざ質問するということは、映画全体に潜むメタファーも注意深くみていったほうがいいかもしれません。
それぞれのメタファーの意味

(C)2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved
ここから、あらすじで触れた「猫」「井戸」「ヘミ」の謎をメタファーとしてとらえていきますが、その前に浮遊する若者たちの特徴を、すなわち「失われた世代」が“なにを失っているのか”を示しておきます。
それはヘミがアフリカに行く理由として告げた以下の台詞がすべてです。
知ってる? アフリカのサン人にはふたつの“飢えた者”がいるんだって。リトルハンガーはおなかがすいた人。グレートハンガーは人生に飢えた人。なぜ生きるのか、人生の意味は何なのか。それを知ろうとする人。
“リトルハンガー”は、物質的豊かさをある程度獲得した社会では、減っていきます。
一方で“グレートハンガー”は、社会が豊かになればなるほど、ますます増えていく存在です。
つまり、持たざる者の代表であるジョンスも、借金をしながら美しくあろうとするヘミも、暇を持て余しているベンも、「人生の意味や物語を求めている」、という点で共通しています。
彼らは“グレートハンガー”として、この現代社会を生きているということです。
その観点からまず、「井戸」が意味するものを村上春樹と心理学者の河合隼雄の対談からみていきます。
井戸=無意識
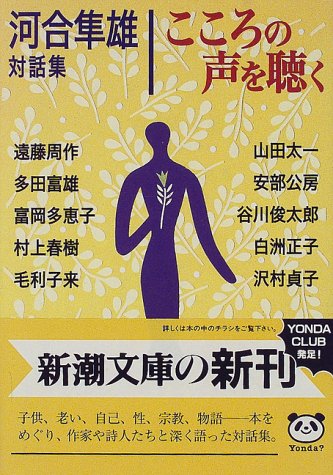
新潮文庫/1997
村上春樹の小説では、「井戸」が重要な役割を果たしているのはつとに知られています。
やや言葉遊びの印象もありますが、「井戸」は精神分析の用語でいう「イド(id)=無意識的な心的エネルギー」とおなじ発音です。
では、ヘミが井戸の底で救いを待っていたのは、どういう心理的状況だったのでしょう?
1994年にプリンストン大学でおこなわれた村上春樹と河合隼雄の講演会では、このような言葉が交わされています。(『こころの声を聴く―河合隼雄対話集』(新潮文庫)より引用。)
河合「恋愛の場合、後から思うとどう考えても選ぶべきでなかった人が、すごく美人に見えたりするでしょう。あれはあっち側とこっち側のイドが呼応するんです。(…)それでイドの力が弱くなると、日常の現実が見えてくるということがあるわけです。」P248
村上「確かに恋愛に似てるという感情はものを書いているときにすごく持つんですね。(…)今の河合先生のお話、恋愛でイドのところまで行くというお話を聞いて、納得できるところはありますね。」P250
まさに“恋愛でイドのところまで行く”ことが、ヘミとジョンスのあいだにはあったのでしょう。
本作が謎めいているのも、“日常の現実”とは別の“イドの世界”の出来事を描写しているからに他なりません。
村上「みんなが自分の井戸に入って、ほんとの底のほうまで行くと、ある種の通じ合いのようなものが成立するんじゃないかと僕は感じるんですよ。(…)僕が小説で書こうとしてるのは、ほんとの底まで行って壁を抜けて、誰かと〔存在〕というものになってしまうのがいちばん理想的な形だと思うんです。」P272
河合「自分の井戸の中に深く入れば入るほど相手の井戸と共有できるわけです。」P273
「個」を越えた「存在」となって交わる領域。
ヘミがジョンスを信頼していることに、ベンは「嫉妬した」と語る場面があります。原作にはない言い方です。
退屈しのぎに殺す、というよりは、嫉妬したから殺す、といったほうがベンの行動が理解しやすいですね。
猫=魂

新潮文庫/2002
また「猫」も村上春樹作品には頻繁に登場します。
そしてその存在はたいてい主人公の精神的次元と深く結びついており、危機時によくいなくなります。
前述の河合隼雄も著書『猫だましい』のなかで「猫を通して人間のたましいについて語りたいと思っている」と述べています。
ヘミの部屋で猫の姿が見えないのは、それが「魂」であるから、と考えてみてはどうでしょう。
ジョンスはそれを取り戻すために、「自分の問題」を片づけなくてはならなかったのです。
ヘミ=存在

新潮文庫/1987
ジョンスはヘミを失う予感に脅かされてはじめて、自分のなかにある「激しい感情」を認めていきます。
畜産業を営む彼の父親は気性が激しく、あるとき障害事件を起こして逮捕されました。
一方ジョンスはそんな父を反面教師にしたのか、いつも物静かな様子で、あまり取り乱すことはありません。
しかし結果的にそれが彼の「魂」を損ない、“グレートハンガー”の飢えをもたらしていたといえます。
彼は心を“燃やす”ものを欲していた。
それはベンのように退屈しのぎで“燃やす”ものではない。
弱いからこそ、身を焦がすほどの行動がジョンスにはできる。
彼が自分の父親の胸中を察することができたとき、ヘミに対して自分がすべきことも明らかになります。
原作の短編「納屋を焼く」では、ヘミに位置する女がいなくなったあと、ベンの立場の男が主人公にこう告げます。
「僕はよく知っているんだけれど、彼女はまったくの一文なしです。友だちもいません。住所録はぎっしりいっぱいだけど、あの子には友だちなんていないんです。いや、でもあなたのことは信頼してましたよ。お世辞じゃなくてね」P82 『螢・納屋を焼く・その他の短編』(新潮文庫)より
「ヘミがどこに消えたか」ではなく「ジョンスがどこに向かったか」

(C)2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved
ヘミが寂しい人間だとすれば、自分も同類である。
「井戸」の底では、ヘミは自分であり、自分はヘミである。
ヘミを探すことは、自分を探すことであり、ヘミへの罪は自分が贖う。
そうやってジョンスはベンを殺しますが、ヘミはベンに殺されたのか、真実は闇の中です。
問題は「ヘミの失踪」ではなく「自分の喪失」だったのであり、自分自身の“飢え”を自分の手で満たそうとした青年の事実だけが、ただ残されました。