連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第13回
 (C)2018「SUNNY」製作委員会
(C)2018「SUNNY」製作委員会
こんにちは、森田です。安室奈美恵さんが来る9月16日をもって芸能界を引退します。
彼女の軌跡をふりかえるに今もっとも最適な映画は、『SUNNY 強い気持ち・強い愛』以外にないでしょう。
“アムラー”をはじめとし、90年代のあらゆるカルチャーを詰めこんだ玉手箱のような本作は、大根監督らしいセンスと音楽愛に満ちあふれています。
CONTENTS
オリジナルの韓国映画『サニー 永遠の仲間たち』(2011)
一方で「友情」に焦点を当てているオリジナルの韓国映画『サニー 永遠の仲間たち』(2011)と比べますと、日本リメイク版は「過去」の文化が物語の中心に入りこんでいるため、おもしろさを発見する手立てが求められるかもしれません。
肌を焼いたコギャルに、数々のマストアイテム。そして時代を彩るダンスミュージック。
劇場に明かりがついたとき、座席でポカンと固まっている女子高生たちの姿が印象的でした。
使用されている楽曲や小道具などは、スマホで調べれば事実として確認できるでしょう。
しかし、もっと深く作品世界を理解するためには、より大きな時代背景を共有する必要があります。
なぜコギャルが生まれ、どんな未来をみて、そのときを生きていたのか。
今回は、90年代の音楽マーケットを文化状況として見据えつつ、社会状況の考察には社会学者・宮台真司氏が95年に提唱した「終わりなき日常」「さまよえる良心」という概念を用いて、本作の見方を広げてみます。
映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』のあらすじ
(大根仁監督、2018)
『モテキ』『バクマン。』などの大根仁監督が2011年の韓国映画『サニー 永遠の仲間たち』をリメイク。前作の『奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール』(2017)も話題を呼びましたね。
映画の舞台は80年代の韓国から、90年代の日本へと移されています。
専業主婦として平凡な日々を過ごす奈美(篠原涼子)。
女子高生だった90年代は、仲良しグループ「サニー」の一員として青春を謳歌していました。
奈美は母の見舞いに訪れた病院で、末期がんに痛み苦しむ女性の姿を見かけ、一目でリーダーの芹香(板谷由夏)だと気づきます。
再会を喜ぶ2人。しかし芹香には残された時間がありません。
「もう一度みんなと会いたい」という芹香の願いを叶えるため、奈美はメンバーを探す決意をします。
その過程で、自分たちの過去が90’sのJ-POPとともによみがえってくるのでした。
韓国の80年代と民主化
 (C)2011 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED
(C)2011 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED
オリジナルでは80年代の韓国。
軍事クーデターを利用し政権を握った全斗煥大統領による独裁的な統治がつづいていた時代です。
それは同時に、民主化運動が高まりをみせていった時代でもありました。
韓国版サニーでは、学生や労働者たちが警官隊と衝突するシーンが描かれ、そのなかでサニーと敵対するグループも市街戦を繰り広げるという一幕も。
なぜ、舞台を日本に移すと、これらの設定が90年代に置き換わるのでしょうか。
日本の90年代と終末観
そのねらいを幅広い層に届けるためか、大根監督は劇場用チラシを使って考えを明かしています。(「監督 大根仁×プロデューサー 川村元気 時代を創るトップクリエイター対談!!!」より。)
「大根:あの頃はバブルが弾けてから数年経って、世紀末の不穏なムードもあったし、先の見えない不安や恐怖をたくましくサヴァイヴする感覚が若い子たちに生まれたと思う。象徴的な現象が女子高生のコギャル化ですよね。それは韓国の80年代に起きた抜本的な社会変化にも引けを取らない」
「川村:当時のコギャルが今はすっかり普通の大人になって生きている。その過去と現在のギャップが面白いなって。例えば過激な政治運動やってた団塊世代のおじさんがしれっと企業人やってる、なんてことに近い」
韓国の社会変化と日本のそれとが、80年代と90年代でそれぞれ符合するといいます。
“世紀末の不穏なムード”とは、1995年に起きた阪神淡路大震災とオウム真理教による地下鉄サリン事件をさすのでしょう。
たしかにそこは、現代につながる日本の転換点ではありました。
しかし、はたして当時の女子高生に“たくましくサヴァイヴする感覚”があったのでしょうか。
また、「女子高生が社会を動かしていた時代」は本当だったのでしょうか。
文化状況の解説 90年代の女子高生とJ-POP
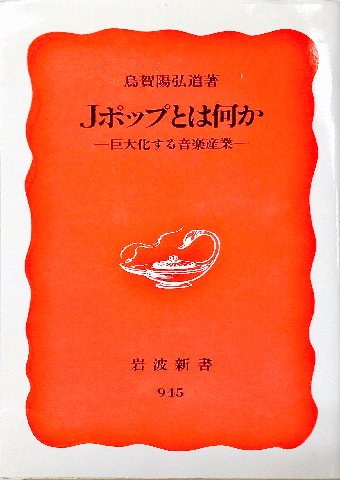
『Jポップとは何か』(岩波新書/2005)
ここから、日本版サニーの重要な要素である「女子高生とJ-POP」の関係にせまっていきましょう。
広瀬すず演じる高校生の奈美は、淡路島から引っ越してきました。父親が運よく東京で仕事を見つけたとのこと。
ということは、95年の阪神淡路大震災で被災した家族だといえます。
物語の具体的な時代は、95年~96年あたりとみることができ、それらは劇中でかかる「LA・LA・LA LOVE SONG」「そばかす」「SWEET19BLUES」などのヒットソングからもわかります。
日本のCD販売枚数と生産枚数は98年で最高を記録しますから、本作の音楽シーンはまさに絶頂にむかう時期です。
サニーのメンバーたちも倉庫のような空き教室で楽しく踊っていましたが、実際、彼女たちがどの程度の影響力を持っていたのかを『Jポップとは何か』(烏賀陽弘道著、岩波新書、2005年)から確かめてみます。
ヒットの影に“流行ビジネス”
著者はAMラジオ・ニッポン放送が95年11月から99年3月まで放送した「ゲルゲット・ショッキングセンター」(毎週月~木曜、夜10時から翌1時)という番組に注目。全国に150万人のリスナーがいたそうです。
「その中に『ハイスクール・ランキング』というチャートがあった。モデルをしたり、ファッションリーダーになりそうな首都圏の高校生200人に『気になる曲』を3曲書いてもらう。人気投票ではない。『これから当たりそうな曲』の意識調査だ」
そして、「気になる曲」が発売後にヒットした例として、パフィーの「アジアの純真」やUAの「情熱」、相川七瀬の「夢見る少女じゃいられない」、そして“小室哲哉ファミリー”の楽曲の数々があげられます。
より踏みこんで、首都圏の女子高生に集中的にマーケティングをして「流行りをつくる」ビジネスがあったとも分析。
「ポピュラー音楽も、お得意先のひとつだった。安室奈美恵や浜崎あゆみが人気を集めていたエイベックス社は当時、どの曲をシングルカットするか、歌手にどんな服を着せ、どんな歌を歌わせるかまで、女子高生にリサーチを依頼していた」
リサーチのみならず、こんな手法もとられたそうです。
「これから売り出そうとしている音楽のサンプルテープやCDを高校生数十人に渡し、校内放送で流してもらうのだ。つまり、校内放送の方がテレビやラジオのヒット番組より早くヒットソングを放送していたのだ。(…)以上は95年から97年前後の話である」
ちょうど本作の時代設定に一致します。
これらは女子高生の影響力を見こんだものではありますが、むしろ彼女らはビジネス的、システマティックに組みこまれていた存在ともいえ、「踊っていたのではなく、踊らされていた」とみるべきではないでしょうか。
すくなくとも、先述の“たくましさ”のイメージとはほど遠い。
社会状況の解説 「終わりなき日常」と「さまよえる良心」

『終わりなき日常を生きろ』(ちくま文庫/1998)
そうではなく、90年代半ばの女子高生たちは、“脱力”して、“まったり”と生きていた。
同時代にそう分析したのが、社会学者の宮台真司氏です。
著書『終わりなき日常を生きろ』(ちくま文庫、1998)から、彼女たちを包んでいた社会状況を見わたしてみます。
なお、ここで立てられている「戦略」は、社会変化のスピードと彼女たちのその後の人生によって、再提言されていくことになりますが、それもふくめて当時の状況を示す貴重な資料として、また「終わりなき日常」はいまもつづいているという観点から、そのまま引用させていただきます。
「輝きのない未来」を生きて
宮台氏は、95年に露見した日本の状況に対して、「ブルセラやデートクラブの女子高生たちが絶対にサリンをばらまかないのは、いったいなぜなのか?」と問いかけます。
「クラブやデートクラブで『まったりと』脱力して生きている彼ら・彼女らは、『終わらない日常』を生きる術に長けている。だからこそ、90年代に入って、女の子的終末観が勝利したのである」
「終わらない日常」とは、もはや社会全体が共有できる物語も、個人が希望をもってみる夢もなくなってしまった状態をさします。
行き場のない閉塞感や、ハルマゲドン的な終末観にもとらわれることなく、女子高生たちは生きている。どうして可能なのでしょうか?
「女の子たちのほうが、男の子たちよりもはるか以前から、『輝きのない未来』に耐えてきたからだ。90年代に入るとバブルが崩壊して、ようやくどんな男の子たちにも例外なく『輝きのない未来』が共有されたけれども、女の子にとっては結婚が輝きを失った70年代後半にはすでに、『輝きのない未来』は自明なものになっていたということだ」
つまり、彼女たちの多くは「耐える」という感覚もあまりなく、「終わらない日常」を戯れるスキルを身につけていたというわけです。
「私がながらく取材を続けてきたブルセラやデートクラブの女子高生、クラバー・キッズ、スケーター、ナンパ師、ゲーマーたちは、別に『熱烈な恋愛』をしていないし、『宗教』にはまってもいない。かといって、コンプレックスに駆られてコミュニケーションから退却しているわけでも、自分らしい自分を探してあせっているわけでもない。(…)それを彼ら自身は『まったり生きる』という」
映画『サニー』に登場する女子たちも、コミュニケーションの回路を開いたまま、みな自分のペースを保っています。
日本版サニーをみて「昔の女子高生は元気だった」と感じるひとが、出演者をふくめているようですが、元気の裏には「輝きのない未来」と「終わりなき日常」があるのです。
映画『寝ても覚めても』 朝子の良心
そして、現在公開中で、カンヌ国際映画祭にも出品された映画『寝ても覚めても』(濱口竜介監督、2018)の登場人物「朝子」にも同様の問題が確認できます。
朝子(唐田えりか)は現実感に乏しい人間です。
一目しか見ていない麦(東出昌大)に突然のキスを許し、関係がはじまります。
麦の失踪後、おなじ顔をした亮平と出会い、平穏な日々を築いてともに暮らす約束をしますが、再び麦があらわれて、いとも簡単にまた心を翻してしまいます。
まったく、「自分」というものがないのです。
夢を食らう“バク(獏)”のせいか、何年経っても「ふらふら」としています。
しかし、さきほどの「終わりなき日常を生きる女子」を引きあいにだせば、“自分らしい自分を探してあせっているわけでもない”のだなと推察でき、「ふらふら」は「まったり」の感覚に近いのでしょう。
朝子のボランティア
 (C)2018「寝ても覚めても」製作委員会/COMME DES CINEMAS
(C)2018「寝ても覚めても」製作委員会/COMME DES CINEMAS
そんな朝子も、東日本大震災で被災した宮城の漁港へボランティアに通っています。
のちに彼女は「正しいことをしたかった」と周囲に漏らすのですが、ここでまた、宮台氏が『終わりなき日常を生きろ』で提唱した「さまよえる良心」を援用することができます。
それは「良心的存在でありたいのに、何が良きことなのか分からない」という問題で、わたしたちが良心的存在であろうとする限りにおいて露わになる、といいます。
宮台氏は、阪神淡路大震災でボランティア活動に勤しむ学生をみて、こう感じたそうです。
「ボランティア精神にめざめたのなら、震災ボランティアが終わっても、東京なら東京という地元でボランティア活動に熱くなれるはずである。ところがそんな学生はまずいない。奇妙なことに、彼らが必要としたのは、『廃墟の中の』ボランティア活動だったのだ」
朝子も「廃墟」を必要としていました。亮平に心を開いたのは、東日本大震災で首都が混乱した日だったわけですから。
良心の空白に、善悪の図式を注入する「偽物の父親」が入りこむと、オウム真理教の問題のようにやっかいなことになります。
朝子の「さまよえる良心」は、すべての物語を委ねられる「麦=偽物の父親」に2度取って代わられました。
しかし、最終的には、赦されることはもうないと知りつつも「亮平と一緒に生きたい」と踵を返して戻ってきます。
宮台氏は「薄汚れた自分をまるごと浄化することの危険性」を前掲書で説きますが、朝子もすんでのところで「薄ぼけた自分を抱えたまま生きる」ことを決めたのです。
この「赦しのない再生」を描いたことは目新しく、カンヌのコンペティションに出品された理由だとわたしは考えています。
広瀬すず世代の「終わりなき日常」とは?
 (C)2018「SUNNY」製作委員会
(C)2018「SUNNY」製作委員会
宮台氏は95年の女子高生に「終わらない日常を生きる知恵」と「終わらない日常のなかで、何が良きことなのか分からないまま、漠然とした良心を抱えて生きる知恵」を見いだしました。
しかしながら、すぐに使用をやめてしまいます。
ここでは詳しく述べませんが、96年に早くも渋谷から「解放区」が消えたこと、高度に流動する社会では健全な内面を保つことは難しいこと、いわゆる“メンヘラ化”してしまい、心の健康に問題が生じたことなどが語られています。
映画『寝ても覚めても』の朝子も、いってみれば「メンヘラ」です。恋人や友人たちをふりまわし、人間関係を破壊しつづけます。
そのため、漠然とした良心を抱えたまま(赦しのないまま)、亮平と生活をするのは厳しいはずです。
一方で『SUNNY 強い気持ち・強い愛』の女子高生たちは、大人になって「社会化」されました。
専業主婦の奈美、起業家の芹香、不動産営業の梅(渡辺直美)、セレブ妻の裕子(小池栄子)、雇われママの心(ともさかりえ)は、90年代的な流動性を手放す代わりに、内面の安定を得たともいえます。
大人の姿がみえない池田エライザ
池田エライザが演じた奈々だけ、大人の姿が見えないのは象徴的です。
「終わらない日常」と、「さまよえる良心」をもっともよく体現していた奈々が、「メンヘラ」にもならず、「社会化」することもなしにどのような大人になったのか、わたしたちはうまくイメージできないでいるからです。
オリジナルの『サニー』でも、モデル役の女子高生の現在の生活は明かされないままで、もし、大根監督がリメイクする際にそこの答えを導いていたら、別の評価が生まれていたことでしょう。
過去を演じた広瀬すず、山本舞香、野田美桜、田辺桃子、富田望生たちも「終わりなき日常」を生きています。
それを生き抜くスキルは、90年代をひっくり返しても見つかりません。もう使えない武器なのです。
だったら、いまの高校生たちに絶大な人気を誇る「広瀬すず世代」の“知恵”をなにかしらの形でイメージ化することのほうが、重要である気がしてなりません。
奈美たちの「今」、朝子の「未来」から、生き抜くためのつぎの考察が求められています。



































