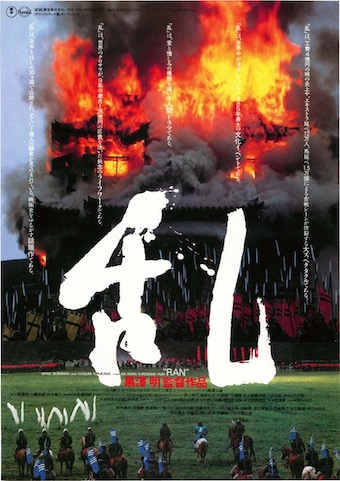巨匠・黒澤明の名作が再び!
愚直な男が最期を知り、人生に輝きを取り戻す物語。
今回ご紹介する映画『生きる LIVING』は、1952年の巨匠・黒澤明監督による名作『生きる』のリメイク作。ノーベル賞作家カズオ・イシグロが脚本を書き下ろし、オリヴァー・ハーマナスが監督を務めました。
リメイクにあたって、物語の舞台は日本から第二次世界大戦直後のロンドンへ。本作は第79回ベネチア国際映画祭で上映され高い評価を得ると、第95回アカデミー賞でもノミネートを果たしました。
1953年。役所の市民課に勤めるウィリアムズは、ピン・ストライプの背広に山高帽を目深に被り、同じ時刻の列車・同じ車両で毎日通勤。仕事は書類にサインをするだけ、家にも居場所はなく、自分の人生は空虚で無意味だと感じていました。
そんなある日、彼は医者から末期のガンであること、そして余命は半年であることを突然告げられます……。
CONTENTS
映画『生きる LIVING』の作品情報

(C)Number 9 Films Living Limited
【日本公開】
2023年(イギリス映画)
【原題】
Living
【監督】
オリヴァー・ハーマナス
【原作】
黒澤明、橋本忍、小国英雄
【脚本】
カズオ・イシグロ
【キャスト】
ビル・ナイ、エイミー・ルー・ウッド、アレックス・シャープ、トム・バーク
【作品概要】
主人公ウィリアムズを演じたビル・ナイは、演劇界・映画界で数多くの賞を受賞している名優。代表作には『幸せの答え合わせ』(2018)、『マイ・ブックショップ』(2019)などがあります。
マーガレット役には、Netflixシリーズ『セックス・エデュケーション』や映画『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』(2021)に出演したエイミー・ルー・ウッド。また『パーティで女の子に話しかけるには』(2017)、Netflix映画『シカゴ7裁判』(2020)のアレックス・シャープがピーター役を演じます。
監督オリヴァー・ハーマナスは初監督作品『Shirley Adams』(2009)がロカルノ国際映画祭・トロント国際映画祭に出品されると国際的に注目され、本作でもさらに大きな話題を集めています。
映画『生きる LIVING』のあらすじとネタバレ

(C)Number 9 Films Living Limited
第二次世界大戦後の1953年。郊外で暮らすロンドン市役所の公務員たちは、毎朝同じ汽車に乗って出勤しています。
新人のピーターは駅で同僚たちの顔を見つけると、足早に合流し挨拶を交わします。先輩職員は「“多忙”で手が足りなかった」とピーターを歓迎します。
汽車が次の駅に差しかかると同僚の一人が、次の駅で上司の課長が乗車するから、礼儀正しくするよう教えてくれます。到着すると山高帽を被り、ピンストライプのスーツを着ている、いかにも英国紳士といった姿のウィリアムズが窓越しに立っています。
彼らが一礼すると、ウィリアムズも山高帽のつばをつまみ挨拶を返しますが、彼らと乗り合うことなく別の車両へ。駅に着いても同僚たちは一定の距離を保ち、付かず離れず役所に入っていきます。
市民課の課長を務めるウィリアムズは、厳格で気難しそうな雰囲気を醸し出していましたが、山積みとなった書類を感情なく処理し、就業時間になると帰宅する日々を送っていました。
ピーターの席にも書類が山積みとなっていますが、前の席に座っているマーガレット・ハリスはピーターに「山積みの書類は忙しいフリができる」と教えます。
その後、役所には「大戦の爆撃で荒廃した空き地が、下水により不衛生になっているため、整備した上で公園として再開発してほしい」と陳情する女性たちが訪ねてきます。
ウィリアムズは陳情書を見て、その案件は「公園課」だと指示しますが、女性たちは公園課の職員に同じことを言われていたらしく「“たらい回し”にされている」と怒りだします。
ウィリアムズは「市民課の人間が付き添えば、対応してくれるだろう」とピーターにその役を指示。ピーターは意気揚々と女性たちを案内しようとしますが、すでに女性たちの方が行き慣れていました。そして、公園課から下水道課と部署から部署へとたらい回しにされます。
結局ピーターは「市民課の管轄だ」と言われて戻り、ウィリアムズに書類を差し出すと、彼はそれを受け取り、目を通すことなく書類の山に追加するのみでした。
役所の職員たちは、自分や部署のペースを崩すことなく、ただ仕事を回すだけでした。「誰も余計なことをしない」が所内での暗黙のルールです。
しかし、無遅刻無欠勤を貫いていたはずのウィリアムズはその日、珍しく午後に早退しました。彼が向かったのは病院です。
主治医はウィリアムズを見ながら、淡々と検査結果が出たと切り出し、「末期ガンで余命は半年」「長くとも9ヶ月だ」と宣告をしました。
ウィリアムズは息子マイケルと彼の妻と同居しています。二人は「映画の日はウィリアムズの帰りが遅い」と話しながら帰宅し、父の遺産をアテに新居の購入を話し合います。
ところが、真っ暗なリビングで佇むウィリアムズを見て、マイケルの妻は驚きます。マイケルが心配し声をかけるとウィリアムズは「話しておきたいことがある」と切り出しますが、息子夫婦は「朝が早いからもう休みたい」と2階の部屋に行ってしまいます。
茫然自失のウィリアムズは、リビングの棚に飾られた亡き妻の写真を見つめながら、妻の葬儀の日以降の息子マイケルと暮らした日々を思い出します。
すると、2階からウィリアムズを呼ぶマイケルの声がします。彼は息子と会話できることを期待しましたが、マイケルは「ドアの鍵をかけて」と伝えるだけでした。
規則正しい生活を崩さなかったウィリアムズが、次の日から役所に来なくなりました。同僚たちにとってそれは驚くべきことであり、原因を考えても心当たりさえ浮かびませんでした。
映画『生きる LIVING』の感想と評価

(C)Number 9 Films Living Limited
日本の“生きる”と英国の“LIVING”の意味
1952年に公開された黒澤明監督の『生きる』は第二次世界大戦で敗戦国となった日本・東京が舞台であるのに対し、本作『生きる LIVING』は終戦後の復興途上にある、1953年のイギリス・ロンドンが舞台でした。
1952年(昭和27年)の日本は、GHQからの占領解除やサンフランシスコ平和条約が発効され、アメリカと日米安全保障条約を結び、独立国家として動き出した年でした。戦後7年経ったとはいえ占領下であったため、東京の真の復興はこの年からといって過言ではないでしょう。
行政機関の業務は加速化を求められますが、抱えた問題は山積み……「市民課のデスクの上に山積みになった書類」は、当時の日本の行政を物語っています。
そして朝鮮戦争(1950)の「特需」で経済的に豊かになった日本は、“高度経済成長”の幕開けという経済復興の光が見え始めてきます。それは、役人や政治家は“あやかりたい”がため、身の保全に躍起だった時代でもありました。
一方、1953年のイギリスはエリザベス女王2世の戴冠式があり、祝福ムードの中でしたが、街のそこかしこには第二次世界大戦での爆撃の跡が残り、砂糖と肉は配給制で庶民の不満があふれていました。また経済停滞にあった当時のイギリスでは、役人や政治家は“安定した収入と就労”を守るために躍起だったこともうかがい知れます。
“市民生活のため”に躍起にならなければならない立場の行政が、やるべきことを棚上げにしている……そんな、風刺の意味もこもった作品でした。
ただ、イギリスは混沌とした時代の中にありましたが、若くて誠実な女王の誕生は明るい未来を予想させるものでした。そうした出来事も、ピーターとマーガレットの恋に結びつけたのだと想像させます。
黒澤明の“問い”とカズオ・イシグロの“答え”
映画『生きる LIVING』の脚本を手がけたノーベル賞作家カズオ・イシグロは、黒澤明作品のファンであると公言している他、『生きる』との出会いは彼の子ども時代にまで遡ると語っています。
当時のイシグロ少年は『生きる』で描かれている、一生懸命に努力した結果であっても、周りから認められたり称賛されることを、モチベーションの糧にしてはならないというメッセージにショックを受けました。そして、いつか誰かがイギリス版の『生きる』を制作するべきだと、期待し望んでいたとインタビューで答えています。
彼は知人であるプロデューサーのスティーヴン・ウーリーに、同じく知人である俳優ビル・ナイを主演にしたらどうかと、アイデアを出したのをきっかけに、本作の脚本を手がけることに。
イシグロは『生きる』が庶民の姿を描いていることから「小津安二郎監督の作品に近い」と感じ、小津作品の常連俳優・笠智衆を主役にしたらと想像を巡らしていたため、「イギリス版を作るなら、主演はビル・ナイがそのイメージにはまる」と考えていました。
また、日本人の気質と英国人の気質、文化の違いを鑑みてストーリーを考えると、日本人の回りくどさや忖度などのじれったさが削ぎ落され、伝えるべきことだけを明解に表していると感じます。
子どもの頃、カズオ・イシグロが黒澤明監督作『生きる』に感じとった印象そのものを映像化したことで、現代の日本人にもストンと腑に落ちるわかりやすさがありました。
黒澤明の『生きる』は市民課の若き職員が、一石を投じようとして諦めて建設した公園の上の橋をトボトボと歩いて終わり、事なかれ主義の日本を象徴するようでした。
一方、本作はラストでピーターとマーガレットがカップルになった場面で終わり、若い世代が未来を牽引し平和で豊かな世界にすることを示したように見ることができました。
黒澤明の「称賛なき努力は報われたか?」という問いに呼応するような答えが、『生きる LIVING』には描かれているのです。
まとめ

(C)Number 9 Films Living Limited
映画『生きる LIVING』は妻に先立たれた男が20数年間、狭い規律の中で暮らし家族とのコミュニケーションもままならぬ孤独の中、余命宣告されたことで人生を意義あるものに塗り替えた物語でした。
黒澤明の不朽の名作『生きる』のストーリーラインはそのままに、舞台を同時期のロンドンに変え、黒澤明が投げかけた問いにカズオ・イシグロが答えたような作品です。
『生きる』は名作として生き続け、称賛なき地道な努力と生きる意味を観る者に問いかけ、対して『生きる LIVING』は生きぬくための努力は未来永劫に続くものだと観る者に感じさせます。
そして、諦めてしまったらそこで終わる人生が、挑み続けることで輝きに変えることができる。そして、そのタイミングはいつでも始められるとこの作品は伝えていました。