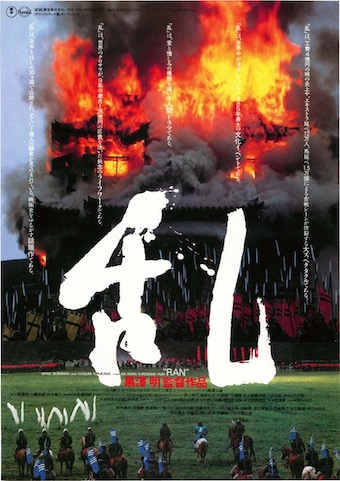黒澤明監督が描いた、ヒューマンドラマの頂点にして最高傑作!
世界な映画監督として今もなお影響を与え続けている巨匠・黒澤明が、1952年に公開した人間賛歌の映画『生きる』。
映画以外のリメイク版も多く、名優・志村喬の演じた辺勘治役を、2007年放送のテレビドラマ版では9代目松本幸四郎が演じ、2018年には舞台ミュージカル劇として、宮本亜門の演出で市村正親と鹿賀丈史が務めています。
また2020年に発表された情報では海外リメイク版の制作が決まり、ノーベル賞作家カズオ・イシグロが脚本を手掛け、ビル・ナイを主演に迎えて、『Moffie』のオリバー・ハルマヌス監督の起用される予定です。
黒澤明監督の映画『生きる』は、いつの時代も錆びることのない普遍的なテーマ。何より語り部としてのストーリーテリングの巧みな演出は、“世界の巨匠”としての名を証明するのに容易い名作中の名作です。
映画『生きる』の作品情報
【公開】
1952年 (日本映画)
【監督・脚本】
黒澤明
【脚本】
橋本忍、小國英雄
【撮影】
中井朝一
【音楽】
早坂文雄
【キャスト】
志村喬、日守新一、田中春男、千秋実、小田切みき、左卜全、山田巳之助、藤原釜足、小堀誠、金子信雄、中村伸郎
【作品概要】
『野良犬』『静かなる決闘』(1949)や『七人の侍』(1954)など、黒澤組に欠かせない俳優である志村喬を主演に迎え、演出はヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞を受賞した『羅生門』(1950)ほか、世界各国の映画祭でも評価の高い、巨匠・黒澤明監督。
役場で働く公務員の姿を通して官僚主義を批判し、余命宣告を受けた人間が生きることを見つめ直すヒューマンドラマで、ベルリン国際映画祭でベルリン市政府特別賞を受賞しました。
映画『生きる』のあらすじとネタバレ
市役所に勤務し、市民課長を務める渡辺勘治。そんな渡辺は書類の山を前に判子を押す、時間つぶしのような日々を送っていました。
そのような働き方ですので、役所内では働かない縄張り意識ばかりが蔓延り、住民が陳情に訪れても、幾つもの場所にたらい回しにされるなど、形式のみの対応がはびこっています。
ある日、渡辺は体調不良のため休暇を取り、病院で診察を受けました。医師から胃潰瘍だと告げられた渡辺でしたが、実際は「胃がん」にかかっていると悟り、ひどく落ち込みます。
余命いくばくもないと考えて渡辺は、予期せぬ死への不安などから、これまでの自分の人生の意味を振り返ります。
渡辺は、市役所を無断欠勤し、これまで貯めたお金を引き出し、飲み屋で独りお酒に溺れていると、偶然、知り合った小説家に連れられ、これまでには行ったことのないパチンコやダンスホール、ストリップショーなど、夜の街を徘徊します。
しかし、そのような一時の放蕩に渡辺は、虚しさだけが残ります。病気の事情を知らない息子や息子の嫁からは白い目で見られるようになっていました。
その翌日、渡辺は職場の部下である小田切とよとも、偶然、出会います。彼女は市役所の体質に嫌気が差しており、玩具会社の工場作業員への転職を考えていると伝えて、小田切は、退職届を提出するために、渡辺の判子が欲しいと言われます。
その後も渡辺は明るく元気な若き女性、小田切と何度となく食事などを共にします。一緒に過ごす時間は、渡辺にとって、若い彼女の奔放な生き方と生命力に惹かれるものでした。
しかし、渡辺にとって夢のような時間も、若い女性の小田切にとっては退屈なものに変わってしまい、食事を共にすることを彼女は拒むようになります。
それでも諦めのつかない渡辺は、小田切の働く玩具工場にまで行き、彼女を食事に誘います。あまりにしつこい渡辺の誘いに根負けした小田切は、最後の一回限りと伝え、食事の誘いを承諾しました。
その後、食事をするカフェで、小田切は渡辺が自分へ寄せる思いや執着が気味が悪く怖いと告げます。すると渡辺は、自分は「胃がん」であると彼女に告白しました。
映画『生きる』の感想と評価
黒澤演出の「リアクション」観察
黒澤明監督の作品として本作品『生きる』は、『七人の侍』と人気を2分するほどの代表作であり、脂の乗りきった黒澤演出の真髄を知ることのできるおすすめです。
映画の冒頭は、志村喬演じる渡辺勘治の胃袋のレントゲン写真から始まり、主人公の外見ではなく、中身を透けて見せるというユニークなスタイルで物語は幕を開けます。
これは画期的な導入の方法で、登場する主人公の渡辺よりも先に映画を見ている観客は、渡辺は「胃がん」であることを知らされます。
つまり、“観客は神の視点”という「主人公の運命を先に知る」状態で、物語の進行を見守ることになります。しかも、渡辺の様子を語る同僚たちの噂ばなしや会話が、いかに身勝手でトンチンカンな決めつけであることも観客は情報として受け取ります。
実はこれらは演出として、映画の後半の通夜の席のシーンへのフックとして重複しており、味わい深いことが映画全体で仕掛けられた仕組みとなっています。
さて、そこで映画が10分以上を経過して、ようやく渡辺が病院に行く場面が登場します。その折に通院患者が渡辺に話しかけてくるところが、実に怖く注目の演出となります。
通院患者の彼が医者からの診断で「胃潰瘍」と告げられたら、それは「胃がん」だと渡辺は教えられるのです。
しかし、観客は既に主人公の渡辺は「胃がん」である事実を知っているのですから、すんなりとシークエンスを受け入れも、渡辺の医師からの宣告をじっくりと見ることができるのです。
つまり、黒澤明監督は『生きる』という作品で、観客にどのような「反応」、「リアクション」をするのかを映像で読み取らせるという仕掛けを作っているのです。
ズバリ、本作品の演出の注目のポイントの第一は、「リアクション」を読む楽しさといえます。
この『生きる』という作品では志村喬をはじめに、セリフを語っている人物よりも、そのセリフにリアクションをしている表情や様子という演技こそが見どころで、人物たちが無言ながら雄弁に語っています。
これこそが黒澤演出であり、日本特有の行間を読む、空気を読むといった言語表現ではない絵画手法や、まるでサイレント映画のように雄弁な映像に仕上げているところが大きく評価される点です。
志村喬の演じる渡辺にリアクションする、伊藤雄之助演じる小説家や、小田切みき演じる小田切とよの芝居は見る者の心を鷲掴みにします。
何より無言の最たるものは、遺影となった渡辺自身。お通夜の場面で好きなことを語る同僚たちに対して、もっと無言のリアクションを見せたのは遺影という粋なリアクション。
これらの黒澤演出は、映画はリアクションで構成され、また俳優の芝居は受けや返しであることを強く指摘しています。
まとめ
巨匠、黒澤明の名サック中の名作『生きる』は、ビル・ナイ主演、1952年のイギリス・ロンドンが舞台でリメイク版が制作されることが決まりました。
ノーベル賞作家カズオ・イシグロが脚本を手掛け、オリバー・ハルマヌス監督が演出を務めます。
イシグロは次のように意気込みを語りました。
「この物語は、人生に意味と満足感をもたらすのは、私たちひとりひとりの責任であることを示唆しています。困難に直面しても、人生に誇りを持ち、幸せになる方法を見つけようとすること。毎日長時間、机やスクリーンに張り付いて過ごさなければならない多くの人々に語りかけることができると信じています」
オリジナルの黒澤明版の『生きる』は、非人間的な官僚主義を批判するとともに、人間が生きることについて示した作品で市役所の市民課長という設定でしたが、リメイク版は、第2次世界大戦後のイギリスを再建するための官僚機構の歯車となって働く公務員のウイリアムが主人公です。
リメイク版はいかなる内容になり、オリジナルの黒澤演出とは、おそらく全く異なる作品になるでしょう。
それは海外、特に西洋文化は、言語を用いて議論や論破する表現をしていく文化ですし、日本映画である黒澤明の『生きる』では、主人公演じる志村喬が、何か明確に雄弁に何かを語る場面はありません。
渡辺の好む大正の歌『ゴンドラの唄』ですら、その内容は明確ではなく、意味不明と読めます。
それよりも、渡辺の家族や同僚たち、あるいはエピソードに登場人物が次々に現れて、無言で志村喬の演じた渡辺に対して、ショット内のフレームでリアクション、あるいは、カットバックによって単独のリアクションを見せます。
まさに“沈黙は金なりの極上の演出は要注目”。言葉ではない芝居で観客に「生きる」ことの正体を伝えた点で、本作は映画史に唯一無二な存在としての価値のある作品なのです。