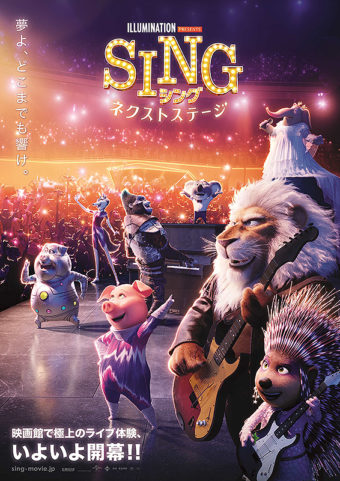映画『天気の子』は2019年7月19日(金)より全国ロードショー!
7月19日より全国448スクリーンで上映がはじまった新海誠監督の最新作『天気の子』は、公開から3日間で動員116万人、興行収入16億4千万円をあげました。
これは前作『君の名は。』(2016)対比で128.6%となる好スタートです。
またすでに、140ヵ国での配給が決定している本作は、世界興行収入にも注目が集まっています。
新海誠監督やその作品をマネジメントしているコミックス・ウェーブ・フィルム(CWF)取締役の角南一城氏は、こう述べます。
CWF角南取締役:村上春樹がヒットするところでちゃんと人気が出るといわれていて、文学性を見てくれてるのかなと。(日経エンタテインメント2019年8月号 P26)
この発言を受け、ここでは『天気の子』考察に村上春樹の小説『海辺のカフカ』と、石田祐康監督の映画『ペンギン・ハイウェイ』の補助線を引き、「家出少年の選択」や「魚が降ることの意味」を読み解いていきます。
CONTENTS
映画『天気の子』のあらすじ

(C)2019「天気の子」製作委員会
高1の夏。離島から家出し、天候不順がつづく東京にやってきた帆高(声・醍醐虎沙郎)。
新宿・歌舞伎町のマンガ喫茶に泊まりながらアルバイトを探すも、生活はすぐに行き詰まってしまいます。
孤独な日々の果てにようやく見つけた仕事は、フェリーで出会った須賀(声・小栗旬)が営むオカルト雑誌のライター業でした。
帆高は事務所で仕事をする大学生の夏美(声・本田翼)とともに、雑誌の企画で“晴れ女”の取材をしていくなか、かつて困窮していた日々にハンバーガーをおごってくれた少女の陽菜(声・森七菜)と再会します。
母親を亡くし、弟とふたりで暮らす陽菜。彼女には「祈る」ことで空を晴れにできる不思議な能力がありました。
その能力を知った帆高は、陽菜と一緒に人々の“晴れにしたい”という希望をかなえるビジネスを立ちあげ、雑踏ひしめく都会の片隅で、ようやく”自分たちの居場所”というものを見つけはじめました。
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』から『海辺のカフカ』へ
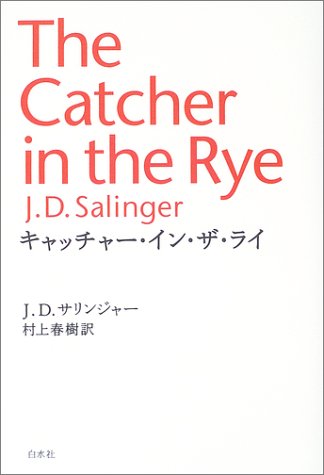
J.D.サリンジャー著・村上春樹訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(白水社、2003年)
離島から家出してきた帆高の手には、J・D・サリンジャー著『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(1951年刊)があります。
この小説は、成績不良で退学処分を受けた“16歳”の少年・ホールデンが、学校にも家庭にも“居場所”を失い、社会や大人たちの欺瞞に抗いながら“放浪”する物語です。
このあらすじは、息苦しさから逃れるために東京にでてきた“高1”の帆高の“家出”とその言動にかさなります。
これだけなら、主人公の心情を示すただの小道具としてみれますが、この本が“村上春樹訳”であることから重要な視点が浮かびあがってきます。
村上春樹も、同小説を意識した“家出少年の小説”を書いています。
2002年に刊行した『海辺のカフカ』です。出版年からすると、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』と同時期に執筆していたと考えられます。
そして結論を先どりすれば、『天気の子』は『海辺のカフカ』の“家出少年”に対するアンサー的な作品であるといえます。
空から降ってくる魚
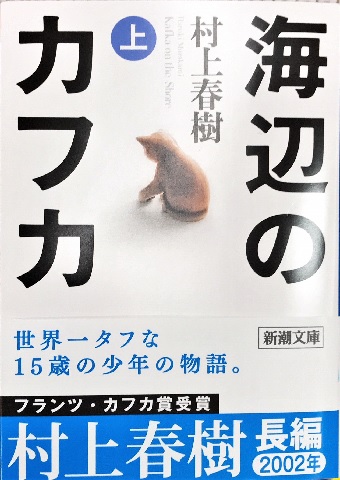
村上春樹『海辺のカフカ』(新潮文庫、2005年)
『海辺のカフカ』は、家出をした“15歳”の「僕(カフカ少年)」が、ギリシャ神話のオイディプスの悲劇(父を殺し、母と交わる)を想像的になぞりながら、現実世界とのあいだを行き来する物語です。
まずここから、1点わかることがあります。
映画の終盤で、帆高が編集プロダクションで世話になった須賀に銃を発砲するのは「恩知らず」なのではなく、象徴的な「父殺し」をおこなったということです。
須賀は帆高を事務所から追いやる際に、「大人になれよ」と言います。
エディプス・コンプレックスを持ちだすまでもなく、“大人になる”ためには自分のまえに立ちはだかる大人=父的存在を倒さなくてはなりません。
帆高は須賀の言葉どおりに、それを実行したのです。そして陽菜に会いにいくという“自分の道”を手に入れます。
『海辺のカフカ』においては、「猫と会話できるという不思議な能力」をもつナカタさんが、夢と現実のはざまで、ジョニー・ウォーカーの格好をした男を刺殺します。
するとつぎの日に、町は空から魚が降ってくる現象に見舞われます。
父殺しとイワシ

(C)2019「天気の子」製作委員会
ナカタさんは、(カフカ少年の魂とリンクしている)みずからの“父殺し”を自首しに、交番にいきます。
そこで警官に対して、こんな予言をします。
「空から雨が降るみたいに魚が降ってきます。たくさんの魚です。たぶんイワシだと思います。中にはアジも少しは混じっているかもしれません」 上巻 P356
そして実際に、大量の魚が降ってくるのです。
翌日実際に中野区のその一角にイワシとアジが空から降り注いだとき、その若い警官は真っ青になった。何の前触れもなく、おおよそ2000匹に及ぶ数の魚が、雲のあいだからどっと落ちてきたのだ。多くの魚は地面にぶつかるときに潰れてしまったが、中にはまだ生きているものもいて、商店街の路面をぴちぴちとはねまわっていた。 上巻 P356
これは陽菜が「天気を晴れにできる不思議な力」を使うと、“空から魚が降ってくる”という現象が起こるのと酷似しています。
人々は、一瞬で消える“水の魚”を写真で撮ってはSNSに投稿して大騒ぎ。
陽菜の弟の凪は、小学校から田端のアパートに帰って開口一番に「きょうはイワシが!」と叫びます。
数多くある魚のなかで、わざわざ“イワシ”と叫ばせる(台詞に入れる)のです。
『海辺のカフカ』の影響がないと考えるほうが、無理があるでしょう。
ナカタさんも陽菜も「不思議な力」を行使して魚を降らせますが、ナカタさんは“父殺し”と引き換えにその力を失います。
陽菜も東京の狂った天候を“治療”する代わりに、人柱となって存在そのものを消してしまいます。
「空から降る魚」は「力の代償」を示すと同時に、「帆高の父殺しを予言していた」ことも推察させます。
須賀はどのような大人の立ち回りをしても、銃を向けられる運命にあったのです。
『海辺のカフカ』から『ペンギン・ハイウェイ』へ
魚が降ってくることの意味について、2本目の補助線を引いてみます。
今度は「ペンギンをだすことのできる不思議な力」をもつ女性が登場する映画『ペンギン・ハイウェイ』(2018)です。
主人公のアオヤマ君は小学4年生。投げたものからペンギンを生みだせる歯科医院のお姉さんを研究対象にしています。
ふたりがよくチェスをする場所は、「海辺のカフカ」ならぬ「海辺のカフェ」と呼ばれています。
研究していくなかで、「お姉さんは元気だとペンギンをつくり、弱るとペンギンを食べるジャバウォックをつくる」ことが判明。
そしてそのペンギンは、学校の裏の森に浮かぶ「海」という球体を壊すこともわかり、やがて「海の大小とお姉さんが連動している」ことまで解明されます。
つまりお姉さんは、世界の裂け目に生じた「海」をペンギンによって消滅させるための存在であると、結論が導かれるのです。
時空の歪みが正されると、お姉さんは消えてしまいます。
ペンギンは魚ではありませんが、“海”と密接にかかわる動物であることから、“降ってくる魚”の延長線でとらえられるでしょう。
『天気の子』と『ペンギン・ハイウェイ』の類似

(C)2019「天気の子」製作委員会
空の上は海よりも未知である、との台詞が『天気の子』にはありますが、「天地の調和をもどせる力」で「水棲生物」が生まれ「代償に女性が消える」というプロットは、『ペンギン・ハイウェイ』と共通しています。
ただ、おなじ『海辺のカフカ』を土台としながらも、「消えた女性」のあつかいと、「残された少年」の選択は異なっています。
ここから、新海誠監督独自の答えが導かれるはずです。
アオヤマ君は、女性(他者)という謎を「論理では推し量ることのできない物ごと」と受けとめることにより、精神の調和を保ちます。
ぼくは世界の果てに向かって、たいへん速く走るだろう。(…)世界の果てに通じている道はペンギン・ハイウェイである。その道をたどっていけば、もう一度お姉さんに会うことができるとぼくは信じるものだ。これは仮説ではない。個人的な信念である。
“もう一度会いたいと信じること”は帆高も同様ですが、彼は“世界の果て”に陽菜を見つけ、世界が再び不調和となっても彼女を連れて帰ります。
帆高は、離島にいたころの夢をこうふりかえっています。
この場所から出たくて、あの光に入りたくて、必死に走っていた。……そしてその果てに君がいたんだ。
“世界の果て”へ希望を託し、世界に調和を感じとるアオヤマ君と、“世界の果て”から希望を得て、世界の不調和を選びとる帆高。
これは監督自身がこういうように、明らかです。
やりたかったのは、少年が自分自身で狂った世界を選び取る話。別の言い方をすれば、調和を取り戻す物語はやめようと思ったんです。(公式パンフレットより)
まとめ

(C)2019「天気の子」製作委員会
あらためて両作品の母体となった『海辺のカフカ』における少年の選択、最後の居場所をみてみます。
これはカフカ少年の内なる声です。
「たとえ世界の縁までいっても、君はそんな時間から逃れることはできないだろう。でも、もしそうだとしても、君はやはり世界の縁まで行かないわけにはいかない。世界の縁まで行かないことにはできないことだってあるのだから」 下巻 P527
“世界の縁まで行かないことにはできないこと”はなんなのか、当時多くの読者が疑問に思ったことでしょう。
新海監督のアンサーは、“世界の縁(果て)で愛にできること”を想像してみせることでした。
それはおそらく、『海辺のカフカ』のこの部分を踏まえています。
いや、そうじゃない。僕がなにを想像するかは、この世界にあっておそらくとても大事なことなんだ。 上巻 P280
また、カフカ少年は名前について問われたときに、こう答えているのもポイントです。
「それは僕のほんとうの名前じゃない。田村というのはほんとうだけど」
「でも君が自分で選んだんだろう?」
僕はうなずく。名前を選んだのは僕だし、その名前を新しくなった自分につけることをずっと前からきめていた。
「それがむしろ重要なことなんだ」と大島さんは言う。上巻 P336
“少年が自分自身で狂った世界を選び取る”とは、“変わらない世界を新しく名づけてみせる”行為を指します。
帆高は、カフカ少年が世界の果てでとるべきひとつの選択を提示したといえるでしょう。
村上春樹も新海誠も、家出少年に「想像力」を大事にするよう説いていますが、それを補足する連載コラム「新海誠から考える令和の想像力」もあわせてご覧ください。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力』記事一覧はこちら