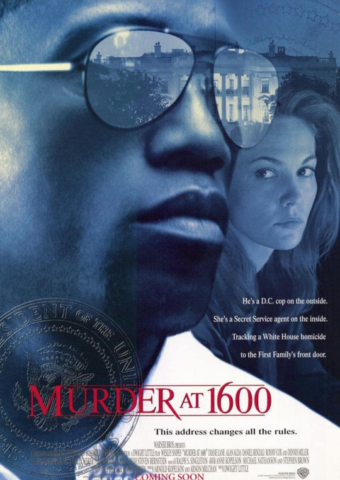連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第35回
こんにちは、森田です。
今回は2月8日よりテアトル新宿ほかで公開中の映画『21世紀の女の子』を紹介いたします。
“21世紀の女の子に捧げる挑戦的短篇集”を謳う本作から、「他者」と向きあい、それを愛することの困難さと必要性、そしてその可能性を考えてみます。
CONTENTS
映画『21世紀の女の子』のあらすじ
(企画・プロデュース山戸結希 2019年公開)
 (C)2019「21世紀の女の子」製作委員会
(C)2019「21世紀の女の子」製作委員会
『おとぎ話みたい』『溺れるナイフ』の山戸結希監督が企画・プロデュースを務めたオムニバス映画です。
「自分自身のセクシャリティあるいはジェンダーがゆらいだ瞬間が映っていること」を共通のテーマとし、15名の新進女性映画監督がそれぞれ8分以内の短編を制作しました。
監督公募には約200通もの応募があり、キャストオーディションにいたっては総勢2000名の参加があったそうです。
第31回(2018年)東京国際映画祭の「日本映画スプラッシュ」部門では、インターナショナル版が上映されています。
ここでは山戸結希監督が本作に込めた意図、つまりは現代社会に立てた問いを、導入の代わりに引用します。
山戸結希監督の問い

©2018 TIFF
山戸結希監督は「映画館で10本に1本は、女性の手による映画作品に出会えるかもしれない」としたうえで、こう問いかけます。
それは、多いのでしょうか、少ないのでしょうか。わたしたちがこんなにも映画を求めていることと、その現実は、釣り合っているのでしょうか?
実際に日本でメジャー映画を撮った女性の比率は、この20年間で3%といいます。
映画は芸術としても産業としても、もっとも広く社会に届けられる表現であるにもかかわらず、現実の男女比とはかけ離れた数字です。
また山戸監督は監督公募にあたり、こう宣言しています。(公式パンフレットより)
きっと、映画よりも、女の子の魂を欲している芸術はありません。
字義通りにとらえれば「映画は圧倒的に少ない女性のつくり手を求めている」と考えられますが、「そもそも“女の子”とはだれを指すのか」まで問いを広げてみると、より深い考察が可能になります。
結論からいうと、それは「他者」という存在です。
“女の子”とはだれか? それぞれの監督の言葉から

(C)2019「21世紀の女の子」製作委員会
「女の子」が「他者」を意味することを、公式パンフレットに寄せられた各監督の言葉から確認していきます。
コミュニケーションのこと
まずはオムニバス1本目「ミューズ」を監督した安川有果さん(『Dressing Up』『永遠の少女』他)の言葉から。
男性と女性は別の生き物だと思われがちだけれど、同じ“人間”として生きていくうえで大事なものはそこまで大きく変わらないと思う。
このように語る安川監督にとって、山戸結希監督の問いは単に性別を指すのではない、ということがわかります。
でも、別の生き物としてとらえてしまうことで、とても遠くに追いやられて、そこでコミュニケーションが終わってしまう気がする。
つまり、そこにあるのは男女の距離ではなく、人間同士のコミュニケーションの隔たりです。
大人になること

(C)2019「21世紀の女の子」製作委員会
では、コミュニケーションはなぜいつも困難に感じられるのでしょうか。
4本目の「回転てん子とどりーむ母ちゃん」の監督、山中瑶子さん(『あみこ』他)がポイントとなる発言をしています。
21世紀とか女の子とか、どうでもいい、ただなぜか大人になるにつれての日々はちょっとずつしんどい。
大人になるにつれて、それ以前にはなかったような“しんどさ”が積み重なっていきます。
子どもだったころを思い出してみてください。怖さも臆病さもあまりなく、周囲と向きあっていませんでしたか?
もちろん、ただ子どもに戻ればいい、という話ではありません。
人が大人になることは不可避ですし、子どものコミュニケーションでは限界があります。
子どもは自分の世界がすべてであり、自分中心で物事をみていたので、恐怖もなにも感じなかったに過ぎないからです。
他者と出会うこと
あらためて、「大人になる」とは、どういったことでしょう。
5本目「恋愛乾燥剤」監督の枝優花(『少女邂逅』他)さんのこの言葉が大きなヒントになります。
山中監督が東京国際映画祭で言っていたように、「私たちが分かり合えないのは女の子/男の子だからではなく、そもそも他人だから」だと思うんです。元々違う他者が共存する社会に対して、私は何ができるのか。
わたしたちは「男女」である以前に、それぞれが、それぞれにとっての「他者」です。
子どもは往々にして「自分が見ている世界を相手も見ている」と信じており、自他の境界が曖昧です。
しかし成長する過程でその“幸福な誤解”はとけていき、“自分は自分でしかない”ことに気づきます。
これはとても孤独で、寂しいことです。だれも自分の人生を生きてはくれないし、だれかと完全につながることもできない。
他者と出会うこと、それが大人になることです。
他者を愛すること
こう書くと、大人になるなんていいことではないと、早合点してしまいそうですが、そうではありません。
9本目「愛はどこにも消えない」監督の松本花奈さん(『脱脱脱脱17』他)は、他者との関係に別の主題を見いだします。
山戸さんからテーマをもらって、いちばん思い浮かんだこと。それは、セクシャリティ(男性と女性)という概念が生まれた根底には、「他者を愛する」という想いがあるということでした。
他者と出会った先には、“愛する”という可能性が生まれます。
もし、世界が自分だけであったなら、だれも愛することはできません。これが本当の孤独です。
逆に、世界に自分とは違う他者がいるからこそ、時に傷つきながらも孤独から抜け出る道が開かれるのです。
11本目の「セフレとセックスレス」を監督したふくだももこさん(『父の結婚』『おいしい家族』他)はこう言います。
すべての人間関係においてですが、自分のことも相手のことも大切にして、大切にされてほしいと願っています。
シンプルですが、他者との関係のうえで、これほど重要なことはないでしょう。
また12本目「reborn」を監督した坂本ユカリさん (『おばけ』他)は、「私は私のままで、あの子はあの子のままで、心からの尊敬と慈しみの行為を、あの子とし合ってみたいな」と語っていますが、人はその“行為”を名づけて“愛”と呼ぶのではないでしょうか。
心からの尊敬と慈しみ。そのためには他者を他者として見つめるまなざしが必要になります。
21世紀=来るべき他者のために

(C)2019「21世紀の女の子」製作委員会
自分とは違うものを排除しようする動きが、この21世紀に入り、ますます際立ってきました。
それは政治経済の世界から、個々人の関係にいたるまで蔓延してきています。
“21世紀の女の子”が目指す地平は、突きつめれば“21世紀の他者”がちゃんと生きられる社会です。
映像ジャーナリストの金原由佳さんと山戸結希監督の対談では、このように語られています。(公式パンフレットより)
金原「もしも次があるなら、『他者ってなんだろう?』っていうテーマも面白い反応が出てくるかもしれない。」
山戸「映画だけの問題意識ではなくて、どれだけ普段他者の存在を感じているのか。自分自身の中に他者を求めるという傾向性もあるかもしれません。」
本作と本コラムの終着点に来ました。
人間は自分だけでは生きられないことは、だれもが納得できるはずです。
すなわち、生きるためには「他者」という存在が不可欠であるのに、人間にはそれを遠ざけようとする矛盾した心理が働きます。
それはおそらく「怖い」からだと考えられます。
日本ではとくに同調圧力が強く感じられますが、相手に「同質性」を求めるのは恐怖の裏返しです。
でも決してその先に安心はありません。いつも「他者」の影に怯えつづけるだけです。
そうではなく、最初から「異質性」を自分のなかに、社会のなかに受け入れていれば、恐怖は生じません。
そこでは異質なものとどう向きあっていくかという、ポジティブな視点に切り替わります。
それがもっとも難しいことはたしかです。
人は大人になるまでに、あるいは大人になってからも、たくさんの傷を抱えます。
だから大人は臆病です。他者との接触を避けたくなる気持ちも十分にわかります。
逆にいえば、だれもが抱えている“傷”というものが、他者との関係を築くうえでの土台になるかもしれません。
大人は自分の弱さも傷口もよく知っている。ゆえに、相手の弱さや傷口に心を通わすことができるのではないでしょうか。
それが、他者を愛することの出発点です。