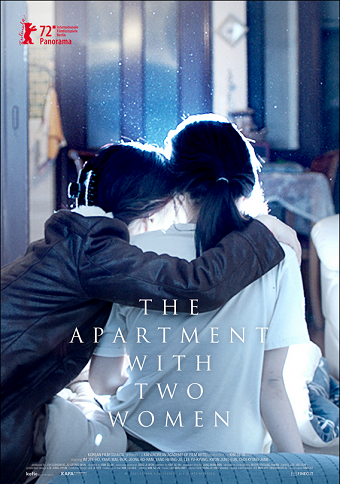東京フィルメックス2022『石門』
第23回東京フィルメックスのコンペティション9作品のひとつとして上映された『石門』。妊娠をテーマにした本作では、ホワン・ジー&大塚竜治が共同監督を務めました。

このたびの東京フィルメックス2022でのジャパンプレミアを記念して、Cinemarcheではホアン・ジー監督、大塚竜治監督にインタビューを敢行。
『卵と石』(2012)『フーリッシュ・バード』(2017)に続き『石門』でも主演を務めたヤオ・ホングイの演技力の成長、また女性に対する抑圧のある状況や、中国の困難な就職事情など、作品に込められた貴重なバックボーンについてお話を伺いました。
【連載コラム】『東京フィルメックス2022』記事一覧はこちら
抑圧を強いる社会への入り口

──女性を取り巻く社会問題が含まれた『石門』というタイトルは、ホワン・ジー監督、大塚竜治監督のおふたりで考えられたのでしょうか。
大塚竜治監督(以下、大塚):タイトルは脚本ができる前から決まっていました。内容についてシノプシスはあったものの、主人公を演じているヤオ・ホングイは素人に近い役者なので、彼女の実態に合わせてストーリーを作り変えていきました。
最後までどういう風に出来上がるのか分からないまま進めた結果、本作は彼女と母親、彼女と彼氏との関係を軸にした構成に仕上がりました。
我々はいつも作品を作るにあたりキャラクターを定義付けたくないようにしています。定点カメラで離れた位置から観測するような感覚で被写体とは意図して距離をとっています。
10ヶ月間という長いスパンの中で母親がマルチ商法まがいのビジネスを始めたり、スキンヘッドにしたのも本当に起こった話なんです。ドキュメンタリーのように現実で起こった出来事を取り入れたれた上で、彼女がどう動くかを離れた場所から見守っていました。
ホアン・ジー(以下、ホアン):『卵と石』(2012)、『フーリッシュ・バード』(2017)と続き、本作『石門』を含めて3部作となっています。全ての作品で主演を務めたヤオ・ホングイは14歳、19歳、本作では22歳と成長する彼女の姿をずっと追ってきました。1作目は村から始まり、2作目では町へ。そして本作では町から都市へ出て行く…という、時間の変化とともに場所も移動していきました。
『石と卵』(2012)は村の少女が将来孵化して小鳥になるのか、それとも石になるのかという話でした。『フーリッシュ・バード』(2017)は町の少女が空を飛びたいけれども、その飛び方を知らず苦悩するという話。本作では少女が都市に出て様々な職種、階層の人たちと出会っていきます。より広い世界で門を越えていきたいと思うものの、なかなかその門を開けることはできないのです。
彼女の周囲の大人たちは「どう折り合いをつけて歩んでいけば良いのか」を教えてあげたいけれども、その大人たちは自分本位の指図をするばかりで、彼女自身がどうしたいかを最優先に考えてくれません。彼女が開けようとしている門の前に大人たちが重いプレッシャーをかけてしまっています。
現実の成長と理想の展望との誤差

──若いときに感じる大人からのプレッシャーとはホアン監督ご自身が抱いていた感覚なのでしょうか。
ホアン:女性は幼い頃から大人になる間に色んな人から自身の希望とはそぐわないことを「こうしなさい」と押し付けられます。気の向かないことを強制されたとき、女性はどう反応を示せば良いのか分からず、アドバイスされてから反応し行動するまでに時間がかかってしまいます。
なので本作で大塚監督と考えたのは、一つの空間に彼女を当てはめて、周囲が期待する行動と彼女自身との行動のズレ。「本来期待されるスピード感が思うように出せない」という部分です。そういった周囲と彼女との誤差を画面に収めたいと思っていました。
女性は最初からとても聡明で色んなことができるわけではありません。長い人生の中でゆっくり学習しながら獲得していく。その必要なプロセスを経て、ようやく自分がどうあるべきか徐々に分かってくるのです。
──これまで大塚監督やホアン監督がヤオさんに対してされてきたことは、彼女に対しチャンスを与える、彼女自身の視界を広げてあげているということでしょうか。
ホアン:2作目『フーリッシュ・バード』(2017)撮影時のヤオは高校3年でした。彼女自身進路に悩んでおり、役者の道に進むかどうか尻込みしていたので、私たちは背中を押してあげようと色々サポートしたのですが、なかなか自分から行動に移さなかったんです。
夫である大塚監督と一緒に映画を撮ることができ、私自身現在とても幸せな状況にあるので、今後もヤオと一緒に順調にステップアップしていけると思っていたんですよ。当時は彼女と衝突することも多く、まるで何を言っても動かない石門のようでした。
中国には本作の主人公リン・センのように田舎から都会に出ても馴染めずに田舎へ帰る若者がとても多いです。田舎に戻れば親の庇護の下、幸せに暮らせますし。ヤオも私もそうなんですけど、田舎の人が都会へ出ると心理的に緊張してしまい、思い通りの行動に移せないことがあるんです。
人生設計を見据えるには困難な社会

──女性だけに限らず田舎から出てきて働くには激しい競争を伴うと思います。現在の中国の就職事情などお聞かせください。
大塚:大学を卒業して就職するのが、日本の一般的なイメージですが、残念ながら中国の場合そのパターンが一番少ないんです。最も多いのは本作で描かれたような、地元の専門学校に入り、職業訓練を受けるというパターンですね。
本作に出てきたキャビンアテンダントの学校は別にキャビンアテンダントだけの専門ではなくてサービス業全般の基礎を学ぶ場所で、外見が綺麗だったらキャビンアテンダントになれるかもしれませんが、しかしながら卒業しても職が無く、厳しい状況です。皆それを理解した上で、専門の他に英語を習ったり、他の技能を身に着けるんです。
ただ中国では、人脈を広げることが社会での生き残り方とよく言われています。自分から動ける人なら、別に学歴がなくてもどんどんチャンスが掴めます。
どうしてもそれができない人は、本作のリン・センのように店の前に6時間ぐらい立つだけのバイトで生活を凌いでいます。最終的にはそれも続かず、実家に戻り、またチャンスを見て都会に出るのです。結局のところ、生まれた場所によってその人の働く環境が決まってしまうのです。
ホアン:私達が本作を撮り終えた2021年頃から、大学の授業でも専門的な教育システムをカリキュラムとして取り込むようになりました。
しかしヤオが専門学校で勉強していたときはまだ実践的な教育を採用されていなかったので、本作で描かれるように自分でお金を出して英語だけ勉強するために別の塾へ行かねばなりませんでした。
現在はSNSで色々な情報交換ができるのでそこで仕事も探せます。冒頭のところで英語の学校の先生が「あまり自分の人生を先にデザインしてしまわない方がいい」と言っていますよね。
冒頭のこのセリフがリン・センに対し啓示的な呼びかけになっている。これは中国の社会事情を外国人である大塚監督の目で観察できたからだったと思います。
インタビュー/出町光識
ホアン・ジープロフィール
1984年、湖南省生まれ。
北京電影学院(2003-2007) の文学科で脚本を学ぶ。大学時代、生まれ故郷である湖南省で撮影したドキュメンタリー『Underground』で監督デビュー。2010年に、短編『The Warmth of Orange Peel』の脚本・監督を務める。2012年、初長編『卵と石』でロッテルダム国際映画祭タイガーアワードを受賞し、2013年、アンドレイ・タルコフスキー国際映画祭グランプリを受賞した。2017年、大塚竜治と共同監督した長編第2作『フーリッシュ・バード』が、ベルリン国際映画祭でジェネレーション14+部門で、国際審査員のスペシャルメンションを獲得した。
大塚竜治プロフィール
1972年、東京生まれ。
日本のテレビ番組でドキュメンタリー制作に従事した後、2005年に中国に移住。社会問題をテーマにしたインディペンデント映画を制作する。ホアン・ジー監督の作品は勿論、リウ・ジエ監督『再生の朝に-ある裁判官の選択-』(2009)やイン・リャン監督『自由行』(2018)などの撮影監督も務めた。
2013年、ドキュメンタリー作品『Trace』をホアン・ジーと共同監督。翌年には、初の単独監督作品『Beijing Ants』(2014)を発表する。2015年、ベルリン国際映画祭(Berlinale Talents)に参加し、2017年『フーリッシュ・バード』を共同監督。
映画『石門』の作品情報

【日本公開】
2022年(日本映画)
【英題】
Stonewalling
【監督】
ホアン・ジー&大塚竜治
【出演】
ヤオ・ホングイ
【概要】
2022年・第23回東京フィルメックス・コンペティション部門出品作品のホアン・ジーと大塚竜治による共同監督作品『石門』。
女性の妊娠・出産を題材にした『石門』には、『卵と石』(2012)から続けてヤオ・ホングイを主役に起用しています。
2022年度のヴェネチア国際映画祭ヴェニスデイズ部門を皮切りに、トロント国際映画祭、NY映画祭など、アジア映画として大きな躍進を続けています。
映画『石門』のあらすじ

英語を学びながら、客室乗務員を養成するための学校に通っている20歳のリン。
彼女は同じ学校に彼氏ができ、妊娠に気づきますが、子供を持つことも中絶も望みません。
彼氏には中絶したと告げ、診療所を経営している両親の元へ戻ります。
その頃リンの母親は、診療所で死産の医療訴訟に巻き込まれ、資金繰りに悩んでいました。
リンはそんな両親を助けるために、ある決意をします。