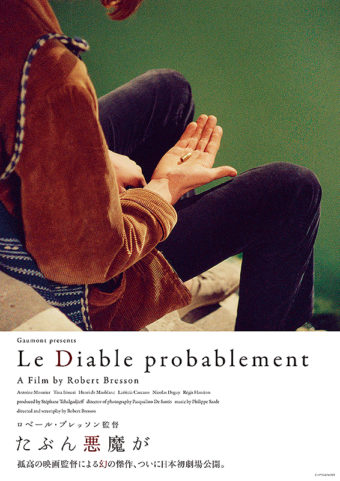メキシコの誘拐ビジネスの闇に迫った衝撃作
映画『母の聖戦』は、誘拐ビジネスの多いメキシコを舞台にした社会派サスペンスドラマ。テオドラ・アナ・ミハイ監督が実話を基にして極悪犯罪に怒りを込めて描きました。
ある日、愛する娘を誘拐された‟母”シエロ。ごく平凡な主婦のシエロですが、犯人の要求通りに身代金を払いますが、娘は帰って来ません。娘を取り戻すため、シエロは奔走し始めます。
年間推定約6万件もの誘拐事件が発生するメキシコを舞台に、誘拐された娘の行方を追う母親の執念を描くサスペンスを、ネタバレ有りでレビューします。
映画『母の聖戦』の作品情報

(C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
【日本公開】
2023年(ベルギー・ルーマニア・メキシコ合作映画)
【原題】
La Civil
【監督・脚本・共同製作】
テオドラ・アナ・ミハイ
【共同脚本】
アバクク・アントニオ・デ・ロザリオ
【製作】
ハンス・エヴァラエル
【共同製作】
ジャン=ピエール・ダルデンヌ、リュック・ダルデンヌ、クリスティアン・ムンジウ、ミシェル・フランコ、エレンディラ・ヌニェス・ラリオス
【編集】
アラン・デソヴァージュ
【キャスト】
アルセリア・ラミレス、アルバロ・ゲレロ、アジェレン・ムソ、ホルヘ・A・ヒメネス
【作品概要】
誘拐ビジネスが横行するメキシコを舞台に、我が子を取り戻すべく奔走する母親の姿を、実話をもとに描く社会派サスペンス。
『その手に触れるまで』(2020)のダルデンヌ兄弟、『4ヶ月、3週と2日』(2007)のクリスティアン・ムンジウ、『或る終焉』(2016)のミシェル・フランコといった錚々たる監督がプロデューサーを担当、ルーマニア出身のテオドラ・アナ・ミハイの長編フィクションデビュー作となりました。
主演はメキシコで最も多忙かつ多方面で活躍する女優アルセリア・ラミレス、共演に『アモーレス・ペロス』(2000)のアルバロ・ゲレロ。
2021年の第34回東京国際映画祭では『市民』のタイトルでコンペティション部門上映され、審査員特別賞を受賞しました。
映画『母の聖戦』のあらすじとネタバレ

(C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
メキシコ北部の町に住むシエロは、家計に余裕がない生活ながらも、一人娘のラウラと2人で暮らしていました。
ある日、ボーイフレンドと会うと言ってラウラが外出。シエロも買い物をするために車で外出します。
するとシエロの前に見知らぬ男が姿を現し、ラウラを誘拐したと告げます。男は身代金として15万ペソと別居中の夫グスタボの車を要求、明日までに用意しなければ娘の命はないとして、警察や軍にも通報するなと忠告するのでした。
15万もの大金を持っていないシエロは、グスタボを訪ねます。彼は若い女ロシと暮らしていました。
グスタボに身代金を工面してもらい、翌日、身代金と車を受け取った脅迫者の男は、15分後に墓地の前で娘を解放する」と言って立ち去ります。
シエロたちは墓地に向かうも、ラウラの姿はありません。彼女の従兄リサンドロにも探してもらうも、やはり見つかりませんでした。
さらに追加として5万ペソを要求されたシエロは、地元の実力者であるドン・キケに金を用立ててもらいますが、やはりラウラを引き渡すという約束は反故にされてしまいます。
やむなく警察に相談するシエロでしたが、応対した刑事は虚偽事件ではないかとして、まともに取り合ってくれません。そこで、市街で見かけた軍のパトロール部隊を率いるラマルケ中尉に協力を直談判し、連絡先を入手します。
その夜、不振な無言電話をもらって不安に苛まれたシエロは、翌朝の女性の首が切断された遺体が発見されたというニュースに居ても立っても居られず、遺体が安置されていた葬儀社へと向かいます。
遺体はラウラではなかったものの、町の犯罪組織から遺体の処理を隠密に済ませるようにと常々脅されていると葬儀社の責任者から聞かされたシエロは、翌日から葬儀社の前で張り込みを開始。
そこに姿を現した一味を尾行し、食料品店やアジトに入っていく様子を撮影した後、シエロは客を装って店に入ります。
 (C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
(C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
半年前に息子を誘拐されたというその店の女性店長から、誘拐した組織のリーダーがイネスという名の赤毛の女であることを突き止めたシエロ。しかし、それに気づいた組織が夜に彼女の自宅を襲撃し、車に火を放ちます。
途方に暮れるシエロの元に現われたのはラマルケ中尉。町に赴任して間もないラマルケは、犯罪組織を一掃するため、シエロが収集した情報と引き換えにラウラの捜索に協力することを約束します。
シエロの情報を元に、ラマルケはイネスとその仲間を拘束して手荒に尋問し、誘拐した少女たちがいるアジトの場所を吐かせます。
組織一味との激しい銃撃戦の末に、ラマルケはアジトを制圧、監禁されていた少女たちを救出するも、ラウラはいませんでした。
映画『母の聖戦』の感想と評価
 (C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
(C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
横行する誘拐ビジネスの実態
メキシコを舞台に、娘ラウラを誘拐した組織と対峙する母親シエロを通して、犯罪ビジネスの闇に迫った本作『母の聖戦』。実際に娘を誘拐され殺された女性ミリアム・ロドリゲスが、シエロのモデルとなっています。
本作の監督テオドラ・アナ・ミハイはドキュメンタリー映画からキャリアをスタートした人物。そのため本作も、当初は犯人を独自で捜索するミリアムに密着したドキュメンタリーにする予定でした。
しかし、ミリアムが犯人を捜して立ち入る地域があまりにも危険で、それに密着する撮影スタッフの身の安全を鑑みた結果、彼女に密着して集めた資料をベースにフィクションドラマに転換したとのこと。
監督と初めて会った際、「毎朝起きるたびに、拳銃で自殺するか人を撃ちたくなる」と語ったというミリアム。普通の主婦がなぜこのようなことをつぶやくようになったのかという衝撃が、本作を制作する最大の要因となったのです。
 (C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
(C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
本作はフィクションドラマでありながら、劇伴が一切流れないばかりか、感情を揺さぶる演出を徹底的に排除しています。
カメラの被写界深度を浅くして、シエロの不安や情操感を観る者にも容赦なく味わってもらおうという狙いは、まさにドキュメンタリータッチ。ドキュメンタリー映画出身のミハイ監督ならではであり、製作に携わったダルデンヌ兄弟の作品にも通じるものがあります。
麻薬取引と人身誘拐は密接に関係した犯罪ビジネスです。治安の良い日本で暮らしているとピンと来ないかもしれませんが、それらの犯罪が身近に存在しているのは、メキシコに限った話ではありません。
原題の『La Civil』とは「市民」の意味ですが、シエロに降りかかる悲劇は全市民に起こり得ることなのです。
母なる証明で子を探す
 (C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
(C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
2014年の初長編ドキュメンタリー『Waiting for August』で、外国に出稼ぎに行った母親の代わりに6人の兄妹の面倒を見る15歳のルーマニア人少女に密着したミハイ監督にとって、‟母性”は重要なモチーフです。
「母親には原始的な強さがあり、ライオンの雌のように子どもを守るためには何でもやる」と監督が語るとおり、警察は何もしてくれず、別居中の夫も当てにならないとして、頼れるのは己だけと単独で動き、ついには軍隊をも巻き込んでいくシエロ。
子を思うあまり、一線を画していく母親が主人公の映画を、筆者は“「母なる証明」もの”と独断で定義しています。言うまでもなくポン・ジュノ監督作から着想したこのジャンルでは、近年だと『ブリング・ミー・ホーム 尋ね人』(2020)や『ドライビング・バニー』(2022)が印象的でした。
“「母なる証明」もの”で描かれる社会背景には、貧困による生活苦が共通してあるように思います。さらに言うと、行動が逸脱していくシエロや誘拐を実行した組織の事情を見せることで、「主人公(=被害者)は善、加害者は悪」という二元論で割り切れない不条理を描いている点でも通底しているといえましょう。
参考映像:『母なる証明』(2007)
まとめ

(C)MENUETTO FILM, ONE FOR THE ROAD,LES FILMS DU FLEUVE, MOBRA FILMS&TEOREMA
本作のラストで、家の前で佇んでいたシエロの前に現れた人物は、はたして誰だったのか。
シエロのモデルとなったミリアム・ロドリゲスは、娘の誘拐殺人に関わった10人もの犯人を突き止めて逮捕へと導くも、2017年の母の日に、組織の報復により自宅前で銃撃を受けて殺害されています。
「明日あんたの身に何か起こったら、俺のことを思い出せよ」という誘拐実行犯プーマの脅迫めいた言葉が伏線になっていたとしたら、もしかしたらシエロも……という結末がよぎるかもしれません。
ただ、本作を観ずしてミリアムが亡くなってしまったことを悲しんだ監督は、「彼女(ミリアム)とその他多くの犠牲になった方々へのリスペクトから、この映画がポジティブな変化をもたらすことを願っている」と語っています。
あくまでも観た者の解釈に委ねるも、目の前の人物を見て微笑んだようなシエロの表情が、すべての答えだと言えます。