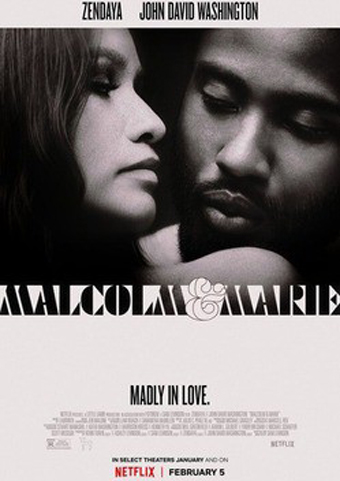連載コラム「シネマダイバー推薦のNetflix映画おすすめ」第30回
日本発のNetflix映画、2021年第一弾として配信された廣木隆一監督作品『彼女』が2021年4月15日からNetflixで配信されています。
「キラキラ映画の三巨匠」の一人として、これまで数多くの少女漫画原作作品を手掛けてきた廣木隆一監督が、中村珍原作コミック『羣青』を水原希子、さとうほなみ主演で実写化した本作。
高校時代から片思いをしていた七恵が夫から壮絶なDVを受けていることを知り、その夫を殺害したレイ。罪から逃れる2人の逃避行を描きます。
【連載コラム】「Netflix映画おすすめ」記事一覧はこちら
映画『彼女』の作品情報

(C)2021 Netflix Worldwide Entertainment, LLC.
【公開】
2021年(日本映画)
【監督】
廣木隆一
【キャスト】
水原希子、さとうほなみ、新納慎也、田中俊介、鳥丸せつこ、南沙良、鈴木杏、田中哲司、真木よう子
【作品概要】
中村珍のコミック『羣青』を原作に、『軽蔑』(2011)『ここは退屈迎えに来て』(2018)などで知られる廣木隆一監督が、水原希子、さとうほなみW主演で映画化。テーマ曲とキーアートを細野晴臣が手掛けています。
また主演の水原希子の提案により、本作はインティマシ―・コーディネイターが採用された革新的な日本映画となりました。
インティマシ―・コーディネイターとは、性的な描写の撮影において俳優を守り、その負担を軽減するために制作側と俳優とを仲介する相談役のことで、撮影体制の健全化に一役買っています。
映画『彼女』のあらすじとネタバレ

(C)2021 Netflix Worldwide Entertainment, LLC.
タクシーを降り、夜の街へ繰り出すレイ。向かった先は賑わうクラブでした。注文した飲み物を隣の男、篠田へ渡します。
「この店で一番、さみしそうだったから」。篠田はレイを気に入り、酒を酌み交わしました。
篠田はレイを家へ連れていきます。篠田との行為の最中にレイは、「あなたの奥さんちょうだい」と言います。
次の瞬間、レイはカバンからナイフを取り出し、篠田の首筋に突き刺しました。
その前日、整形外科医として働くレイは仕事を終え、彼女である美夏の部屋へと帰ってきました。
美夏の誕生日を祝う準備をしているところに、高校時代の友人、七恵から電話がかかってきました。
「今から会えない?」という唐突な電話に戸惑いながらもレイは「行くよ」とだけ返事をしました。
10年前、七恵はレイに借りていた300万を返しました。
「結婚に5年もかからなかった」という七恵に対し、「幸せにね」とだけ返し、ランチ代を割り勘。
七恵は「もう会うことはない」と言い、テーブルに550円を置いていきました。
それから10年ぶりに再会したレイと七恵。「愛している」という七恵を信用しないレイ。七恵が服を脱ぐと、彼女の身体は全身あざで覆われていました。
「旦那が死ぬかあたしが死ぬか」旦那が死ぬべきと即答するレイに「旦那を殺して」と頼むレイ。
次の日レイは血まみれの篠田が横たわる部屋でうずくまっていました。「終わったよ。証拠も残してきた」と七恵に電話するレイ。
七恵はレイを連れて車での逃避行に出ます。「誰もあんたを蹴らない、殴らない」ふたりは一抹の幸せを嚙みしめていました。
ホテルでシャワーを浴びるレイの身体は篠田の血でまみれていました。レイの姿を見て驚愕する七恵。
殺されかけたことを打ち明けたレイに対し、七恵は「刺し違えてあんたも死ねば、丸く収まったのにね」と冷たい態度をとります。
わざとらしい七恵の突き放し方も、レイは理解していました。
ふたりは郊外で入院している七恵の父親のもとを訪れます。何年間も植物状態の父親の枕元へ七恵はそっと婚約指輪を置いていきました。
その後、「あんたのこともっと知りたい」というレイの要望により、ふたりは七恵の実家に向かいました。
七恵の実家で、彼女の不幸な生い立ちを聞くレイ。七恵はタバコを吸いに外へ出ていきました。
レイは棚に飾られたトロフィーに目をやります。高校時代、陸上部だった七恵。部活している彼女の姿を眺めていたレイは、他の陸上部から煙たがられていました。
自費で私立高校に通えないほど、家庭が貧乏であった七恵は、シューズを万引きしたところをレイに助けられていました。
レイは、退学まで追い詰められた七恵の残りの高校生活を買い取ると言い、5年以内に返せなかったら七恵の貞操を奪うことを条件に、彼女に300万円を貸します。
その夜レイは明日自首することを七恵に告げます。七恵の実家を後にすると、外にいた警官に呼び止められます。
咄嗟に2人は飛び出し、新聞配達のスクーターに乗り込んで逃走しました。ガス欠になったスクーターを捨て、定食屋に向かった2人。そこで知り合った男、秋葉に駅まで送ってもらいました。
翌日の始発列車が来るまで、ホームで寝込む七恵。秋葉と親睦を深めたレイは、彼の車で行為にふけります。
レイがホームに戻ると、七恵はまだ眠っていました。公衆電話で一昨日黙って飛び出したきりの美夏に電話するレイ。
彼女を心配する美夏に対して、レイは謝罪の言葉を重ねることしかできません。美夏は「さよなら」とだけ言い、電話を切りました。
映画『彼女』の感想と評価

(C)2021 Netflix Worldwide Entertainment, LLC.
矛盾することを選んだ原作
原作者である中村珍は、本作に「原作の人物に寄り添って頂けることも幸いですし、映画化にあたっては同じルーツの物語が別の姿で愛されるかもしれない機会を得ることに最良の意義を感じています」とコメントを寄せ、映画版は原作の再現ではなく、あくまで原作をルーツとした作品であるという説明をしました。
本作のルーツとなった原作コミック『羣青』は、賛否両論、様々な評価がされた作品です。連載当初より、女性に対する容赦のない追い込みが話題を呼びました。
そしてそれらの描写には、書き手が女性であっても、明らかな女性差別表現がありました。それはマジョリティ側に対する屈折したカウンターの類のものでもありませんでした。
原作コミック読了後の感覚として、ヘテロセクシャルというマジョリティを「普通」とした男性優位社会で、マジョリティ的思考を内面化させ続けてきた同性愛者、及び女性に対する畏怖や蔑視を、作品内の価値観がそのまま受容してしまっているという印象を受けました。
およそ80話をかけて、女性たちの直面する種類豊富な自己憐憫が手練手管で繰り出され、定型的な幸福を徹底的に否定していくという作品に読者は揺さぶられ続けます。
例えば、レズビアンを自認する美夏は、プライベートな会話の中で「恋人が」と性別をぼかした話し方が出来たとしても、わざわざ「彼氏が」と嘘をつく。
内側にささくれを作り続ける彼女たちは、もはや自分だけでなく他人すらも傷つけることを厭わなくなっていきます。
読み進めていく中で抱いてしまう登場人物たちへの憐れみや同情もことごとく拒絶されるのです。
作品内で描かれる同性愛には、常に劣等感、疎外感が付き纏っています。作者は、登場人物たちの不幸を描くためだけに「同性愛」という属性を付与したのでしょうか。
前提として、作者個人の性的指向に作品は還元できるものではないのですが、レズビアンを自認している作者が、どんな形であれ自身の一部を投影したキャラクターに劇中で描かれるような業を背負わせるのは、自虐的で自己破滅としか言い表せません。
それでいて作品は、同性愛者の「何気ない日常」を描くことで共感や理解、逃げ方の分からないDV支配など、現実の問題をリアリティの側面からあぶり出すようなものではないので、簡単に「自己言及」へと帰結するものでもない。
では、「羣青」の魅力とは何なのか。共感できるわけでも、現実社会での生き辛さを描いているわけでもない。
具体的な言葉で形容するのは難しいですが、「矛盾していること」に集約できるのではないでしょうか。
DV夫を殺してほしいけど、殺してほしくなかった。‟わたし”の人生には、‟あーし”しか残されていなかったのに、生きたくない30年間を生きてしまった。やりたくないのにやりたい。登場人物の相反する心情と行動が一致しない姿を繰り返し描くことで、非人間的な人間を人間らしく描いています。
それは作品世界が、フィクションに見える隙間にさえ入り込んで、相反するリアリティを共存させてしまうほどの「矛盾」です。
コミックという媒体だからこそ「矛盾させたまま」力技で完結させることが出来たのではないでしょうか。
つまるところ「羣青」は、釈然としないまま読み進めていくうちに、無理やり納得させられます。その不条理さが面白いのですが、その構造を分解して読み解くことは、一筋縄ではいきません。
原作から近くて遠い映画版

(C)2021 Netflix Worldwide Entertainment, LLC.
映画と原作は、主要人物の配置、印象的なセリフを除き、すべて異なっています。
中村珍のコミック『羣青』を水原希子、さとうほなみで実写化と聞けば、七恵とレイのキャスティングは逆であると誰しもが思います。
しかし、完成した作品を観ると、水原希子演じるレイの奔放さ、さとうほなみ演じる七恵の陰鬱な佇まいが、コミックから角度を変えた解釈としてしっくりきます。
「女性らしさ」を明確に定義せず、ノンバイナリーも解釈幅に備えた‟わたし”と‟あーし”の人物像とは対照的に、映画版の七恵とレイは、予めふたりを女性と定義した上で、共依存のような関係性が構築されていく、か弱さ、脆弱な人間性が強調されたキャラクターとなっています。
従って、より表面的な人間性を描いた映画版では、教唆の手段として同性愛を利用するという、あからさまなレベルの搾取は意図的に廃しています。
映像作品になったことで、作中のアクセントとなったのは、豊かな楽曲。通常の日本映画では、権利が高く使用できない楽曲がふんだんに使われたことで、逃走劇を鮮やかにしています。
ノラ・ジョーンズやチャールズ・チャップリンなど、日本映画らしからぬ楽曲使いは、今後もNetflix邦画の定番になるのではないでしょうか。
女性同士の逃避行、恋愛と聞くと、『テルマ&ルイーズ』(1991)や『アデル、ブルーは熱い色』(2014)のような作品を連想されるかもしれませんが、印象的な海のシーン、すれ違い続けるふたりの姿、楽曲使いなどから思い起こさせられるのは、同じNetflixで配信されているオムニバスシリーズ「ブラック・ミラー」のエピソード、「サン・ジュニペロ」です。
どちらの作品も、鑑賞後に劇中曲が頭の中でリフレインし、ふとした時に曲を聴くと、もはや条件反射で涙してしまいます。
エポックな2人のラブシーンを除いて、印象的なシーンとして挙げられるのは、クライマックスの別荘からの脱出。
レイが「行くよ」と合図した上で、七恵と同時に2階の窓から飛び降りる様子を2人の背中越しに捉えたショットは、非常に映画的で、豊かな表現でした。
その後、兄の車で脱走する際に、兄嫁の悠と一悶着あるくだりは、映画版ならではの解釈を代表する、浪花節的美学に基づいたやりとりで、原作コミックが纏っている作風から、映画が最もかけ離れた瞬間を見事に映し出しています。
このように原作とは異なったバランスのとり方をしているので、非現実性は原作より強調されているようです。
しかし、取っているバランスこそ違えど、原作から流用した印象的なセリフ、「生きていればいいことがある」「家族がいることをささやかな幸せ」といった「世の中」の言説に、2人の人生が打ち負かされるという悲観的な着地は、原作、映画ともに共通する精神性、せめてもの慎ましさでしょう。
観客は、その慎ましさを素直に受け取れるほど、無実な存在なのでしょうか。同性愛者が同性愛を後ろめたいことと感じ、申し訳なさそうに自虐する姿勢の責任は、受け取る観客側にこそあるのではなのでしょうか。
殺した・殺させた2人をジャッジする視線は、映画には登場しません。
同性愛という属性が生まれ持った不幸であると、世間(観客)に消費され、許されない罪を犯した2人を観客が裁くことは出来ません。
本作をレズビアンを真っ当に取り扱った映画と評価することは出来ませんが、作り手にも、受け手側にも、純粋な被害者がいなかった事実をさらけ出した映画であったことは間違いありません。
まとめ

(C)2021 Netflix Worldwide Entertainment, LLC.
登場人物の配置から、印象的なセリフの流用など、原作コミックファンにはその名残が印象深い本作ですが、2時間の映画作品になったことで、矛盾し続ける心情表現と行動が起承転結と共に整理されています。
しかしエンターテイメントとして消費される悲劇には、矛盾したままで許されない映画の外の問題が続いていることを、本作は伝えるほどの余裕を持っていません。
原作と切り離しても、分かりやすい女性同士のシスターフッド模様を描いてみせたり、感情表現豊かにお互いをさらけ出し合うレイと七恵の関係性、人情に訴えかけるような兄夫婦のやりとり、浪花節を感じさせるような終盤の展開があり、本作は原作コミック未読の人の鑑賞にも耐えうる作品です。
【連載コラム】「Netflix映画おすすめ」記事一覧はこちら