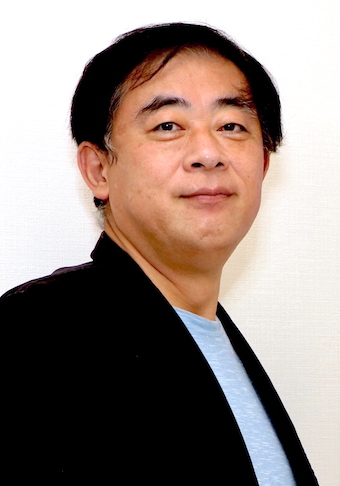映画『クローゼット』は、2020年10月30日(金)よりテアトル新宿、11月6日(金)より大阪・シネリーブル梅田にて公開ロードショー!
若い女性が歌舞伎町のビルで飛び降り自殺した実話をベースに、人生に絶望した一人の男性が「添い寝屋」としてさまざまな女性と触れ合うことで心を動かされていく物語『クローゼット』。
 (C)2020映画【クローゼット】製作委員会
(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
本作は新鋭・進藤丈広監督が「日本駆け込み寺」や実在の「添い寝屋」、毎日新聞記者等に綿密な取材を重ね製作された物語で、30年の歴史あるアメリカ・シネクエスト映画祭をはじめイギリス・フ ランス・イタリア・ロシア、アジアなど世界各国の国際映画祭で話題を呼びました。
主演には本作が商業映画初主演作品となる俳優・三濃川陽介。またWヒロインとなる栗林藍希と新井郁をはじめとした若手キャストのフレッシュな演技を、草村礼子、渡辺いっけいらベテラン俳優が支えます。
今回は進藤監督と主演の三濃川さんにインタビューを実施し、本作のテーマに向けた思いや物語を構築していくにあたり意識したこと、撮影の様子などをうかがいました。
CONTENTS
取材から着想を得た“孤独を抱えた人たち”の物語
 (C)2020映画【クローゼット】製作委員会
(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
──本作は「心に弱さを抱えた人」をクローズアップしています。進藤監督が作品作りに至る経緯をお伺いできますか。
進藤丈広監督(以下、進藤):プロデューサーの美斉津明子さんから、“孤独”ということをテーマにして映画制作を行いたいと、声をかけていただいたのが企画に参加したきっかけです。
その時には「添い寝屋」を舞台として、主人公は男性機能不全の男性、登場人物は実在のあった歌舞伎町のビルから飛び降りて死んでしまった若い女性や、頑張り過ぎているOLといったプロットがある程度出来ていたのですが、やるからにはしっかり取材して進めたいということから始まり、美斉津さんと脚本家の澤田文さんと僕の3人で実際の「添い寝屋」に行き取材をおこないました。
最初にこの「添い寝」という仕事に対してある意味で、「ホストクラブのちょっと個人的なバージョン」みたいなイメージを抱いていましたが、実際に利用するキャストの方やオーナーとお会いして取材していくうちに、本当に人と人が寄り添う大切な空間だと理解していきました。
そこから「孤独を抱えた人たちの群像劇的物語」として身体的に問題を抱え、一度は人と向き合うことを辞めたジンという主人公がいろんな女性と接して、人とまた向き合っていくという物語にしていくことを決めていきました。
──監督が作られた『ヌヌ子の聖★戦~HARAJUKU STORY~』『青の生徒会 参る! season1 花咲く男子たちのかげに』といった作品は、一見ポップでも何らか「心に弱さを持つ人」をクローズアップしているように感じられますが、そういった傾向を『クローゼット』でも活かしたいという考えがあったのでしょうか。
進藤:特に意識してはいませんが、やっているうちにだんだんとそうなっていったと思います。
今回の取材でおうかがいした「日本駆け込み寺」という場所も、ホストクラブで苦労している女の子などが訪れることがあります。だからそういう悩みを持つ人たちが救われる映画にしたいと思ったりもしました。その一方で、実際に救われない人も多々いるわけなので、例えば「人を救いたい」という綺麗ごとだけを言うつもりもありませんでした。
その意味ではあの取材を行った時に、そんな人が十人いる中で、一人でも二人でも救えたらいいな、そんな思いを込めて取材をしていました。
──また先述の二作に比べると、本作は大分カラーの違う感じの作品ですが、このようなカラーで作ろうという方針は、どのように決めていったのでしょうか。
進藤:『ヌヌ子の聖戦~HARAJUKU STORY~』を作った後は、若い子に向けた作風の仕事の話が結構増えたんですが、その一方で胸の内では、本作のような別の雰囲気を持った作品もやってみたいという気持ちもあったんです。
そしてこの企画をいただいた時に「だったらどちらかというと大人の話みたいなものもやってみたい」と思って、挑戦的な思いも抱いて今回はその方向に舵をとってみたわけです。
俳優が膨らませた役柄のイメージ
 (C)2020映画【クローゼット】製作委員会
(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
──本作ではキャスティングに対して、かなりのこだわりがあったと伺いましたが、キャスティングで重視されたポイントはありましたか。
進藤:脚本の役に関して、オーディションで見た人がその役を演じたことによって「この役が生きた」と直感的に思えて、その人がすごくマッチすることを感じられる人に決めていきました。
取材の時のことなんですが、「添い寝」の仕事はホストとは違って「相手が今どんなことを思っているか」という点を観察して対応していく、結構高度な技術を求められると思いました。
実際に「添い寝」のキャストの方も言われていたんですが「自分がしゃべりたいことをしゃべるということは、相手を殺すことだ」って。相手の気持ちを読む力が必要だということなんです。
この話を三濃川さんとしていて気が付いたんですが、三濃川さんは僕と二人で会った時には喋るし、質問をしてもちゃんと答えてくれるけど、大人数だと自分からガツガツと話に割り込んでいかないという感じで、それが「添い寝屋」のイメージに合っていると思って決めたんです。
その意味では、逆にやりながら徐々に三濃川さんのほうにこの物語の人物を寄せていったところもありました。それは三濃川さんに限らず、他のキャストの方も、ご自身の性質に合わせたところがあります。
一方、三濃川さんが研修を受けられ「添い寝」の仕方とかを勉強して実践した時に、結構スムーズに添い寝ができる感じになって(笑)。そこを「ジンというキャラクターはどこか不器用で、誠実に女性と向き合う」みたいな感じに、意図的に作ったところもあります。
──このテーマを三濃川さんは、オファーを受けられた時にどのような印象をおぼえましたか。
三濃川陽介(以下、三濃川):やりながら感じていったと思います。僕はまず「添い寝」という職業があることすら知らなかったので、今回はそういったものを調べるところから始まりました。
でも、調べただけではその世界がどう広がっていくのか、「添い寝屋」としてどう人と接するのかとか、イメージをつかむのも難しかったんです。だから、進藤監督たちが取材をやっていく時に同行させていただき理解を深めていき、「添い寝屋」で研修なんかもやらせてもらいました。
誰しも「幸せになりたい」という思いの一方で、将来にポジティブなものを描けなくなる時もあると思うんです。今回の物語では人との出会いがあったからジンも救われたと思うし、「人と寄り添うこと」の大切さ、人生とは人との出会いで成り立っているんだと、作品テーマを感じられるようになりました。
「受け」の芝居の難しさ
 (C)2020映画【クローゼット】製作委員会
(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
──ジンの思いは、仕事を重ねるたびに積もっていく様子ですが、撮影時に意識されたところはありましたか。
進藤:三濃川さんの役はほとんどが「受け」の芝居ですが、「受け」って結構難しいんですよね。役者の方って自分の感情を出すとか、溜まっているものを吐き出すことのほうが、意外にやりやすいと思うんです。
相手が感情を出したことに対して、それを受け止めてリアクションもせず、時にはそれをため込んで…ということを表現するのは結構難しいはずなんです。でもそれを三濃川さんに「孤独と戦いながら、溜め込む」という格好にしてもらいました。
実際ジンという人は、過去に起きた事故で男性機能が不能になったという問題もあって、さまざまな闇を抱えています。それを乗り越える部分でも、やっぱり受けの芝居となっていて、自身の中で頑張って作ってもらうしかなかったです。その意味で三濃川さんには演技で十分応えていただきました。
ジンの心理状態としては、最初のお客さんの時に失敗してしまい、その後に渡辺いっけいさんが演じられた下田譲というゲイ男性とのシーンがあり、そこからは添い寝屋としてお客さんとの向き合い方を変えていきました。
渡辺さんのときは、ジンはお客に逆にリードして添い寝のやり方を導いてもらった感じで、その後に次の女性が出てきて…という感じで流れていくわけです。そういった流れはリハーサルも行っていろんな話をしました。撮影は準撮りではなかったのですが、そこはお互いに相談しながら作っていたこともあって、流れとしてはうまく構成できたと思います。
また結構他の女性キャストの方々も事前に本をしっかり理解していただき、現場でそれ以上のものを出そうと努力をしていただきました。だから現場では「あっ、そうきたか」と前向きにいいものを引き出していただいたと思います。
主人公ジンと「添い寝屋」の意味
 (C)2020映画【クローゼット】製作委員会
(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
──三濃川さんはご自身に主演が決まった段階で、役に対しどう向き合おうと考えられたのでしょうか。
三濃川:この脚本は登場人物たちに対する人生の転換期のようなもの、物語の何年か後に「あの時があったから今がある」と思える瞬間を書いていると感じました。
そのことを踏まえ、作品テーマは「人と寄り添うこと」と考えて、ジンという人物が「添い寝屋」という職業をしている中でその相手役とどう向き合っていくかという点や、先程監督もおっしゃっていましたが、その仕事の中で「何を求めているかなというものを観察すること」というポイントを意識することがとても大切だと思いました。
──ジンという役柄はセリフより、演技だけでいろんな表現を見せるというところが多いですね。ハードルが高い作品だという感じもあったのでしょうか。
三濃川:脚本をいただいた時に、セリフがすごく少ないというところは感じていて、僕は「言葉の便利さ」を使えないという点で、やりやすさよりは難しさを感じていました。
そこでまずジンのキャラクターを考えたんですが、彼は結構相手役の方にリードしてもらう格好なんですね。本来プロフェッショナルであるはずの添い寝屋という職業で、お金をもらっている以上、プロフェッショナルであるはずだけど、彼にはどこか欠けている部分があって、お客さんにも欠けている部分がある。
プロフェッショナルは自分が与えることに徹するものだと思うんですが、その意味でジンはちょっと違って、お客さんに与える部分の一方でこちらに与えられる部分もある。それが彼の成長にもつながっていく部分にもつながっていく部分だと思うんですが…
一方で渡辺さんと男性同士で添い寝というのをやらせてもらう中で「男性同士」であることを忘れて「人と添い寝している」という感じになったんです。
その意味では「役として生きた」という感じもあるかと思うんです。本当に「添い寝屋」になっちゃったような感じも(笑)。撮影自体も一日に何人か添い寝をする日もあったりしたので、その火は本当に添い寝屋さんになったような感覚もありました。
──渡辺いっけいさん、草村礼子さんの二人のベテランも、現場では大きな支えになった様子がうかがえます。
三濃川:本当にそうですね。お二人には本当に包んでいただいたような感覚で胸をお借りしたという感じでした。
進藤:本当に渡辺いっけいさんも、そういう意味ではすごくジンを引っ張ってくれたので助かりました。また、おばあちゃん役の草村玲子さんは、リアルに僕とか三濃川さんのおばあちゃんになるような世代の方ですが、本当に優しい女性という存在感でとても安心できる空間を作ってもらえたので、現場を良くして三濃川さんが演じる主人公の助けになったことは多かったと思います。
「人と寄り添う」という意味を再考してほしい
 (C)2020映画【クローゼット】製作委員会
(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
──物語のエンディングは良い意味であいまいな感じで描かれ、何か浮遊感のような感覚をおぼえました。登場人物たちのこれからのさまざまな姿について想像を掻き立てられました。
三濃川:クライマックス近くでジンはオーナーの高木に「辞めて一度実家に帰る」と伝えるところがあるんですが、この後一度東京から離れ自分の求めていたものに向き合うんだろう、と僕もおぼろげに思っていました。でもその後どうなるかについては正直わからない、まさしくジン次第ですし。だからこそ、このエンディングにつながったと思います。
進藤:まさしくそうなんですよね。だから物語のその後は、あのエンディングによって見た人が、ぞれぞれに感じて考えてもらえたらと思ったんです。
──本作はコロナ禍という厳しい状況の中での公開となりましたが、今の時期にこういった映画が公開できる意味を、どのように考えられますか。
進藤:例えば今回のこの状況で、さらにつらい立場になった人も多々おられると思うんです。この状況でさらに人と会うという機会も減って、人同士の関係が希薄になっている。でもできればそんな時代の中で、この映画を見て改めて人と向き合うことをもう一度考えてもらいたいと思います。
話さなくてもいい、無言の中で二人でお茶をしているだけでもいいと思う。ひと時でも同じ空間を共有するというだけで、何か人の助けになることがあるのではないかということを、本作を作って改めて感じたので、そんな空気を是非スクリーンで感じてもらえればと思います。
三濃川:僕も同じように「人と人が寄り添う」ということの意味を強く感じます。あの「添い寝」という距離は、今はなかなか難しいでしょう。でもただ心で寄り添い合う、理解し合うということは自分次第でいろんなやり方ができることだと思うんです。
その意味で本作は静かな作品ではあるんですが、とても普遍的な部分で人同士がつながっていくということを大切にした作品だと思っていますので、できれば大きなスクリーンで是非この作品を観ていただければと思っています。
インタビュー/桂伸也
進藤丈広監督プロフィール
1984年生まれ、東京都出身。日本映画学校を卒業後、深川監督作品の『神様のカルテ』『ガール』や、青山真治監督『共喰い』、パク・チャヌク監督『お嬢さん』など、助監督として数多くの映画に参加します。
2016年には自主制作『敏感に喜ぶ』で福岡インディペンデント映画祭で優秀作品賞受賞、TAMA NEW WAVEある視点部門入選、2017年、Amazonプライムドラマ『チェイス第一章』1、4、7話を監督して商業デビューを果たしました。
2018年11月には長編映画デビュー作『ヌヌ子の聖★戦〜HARAJUKU STORY〜』が公開。2018年11月9日(金)に渋谷シネクイントで先行公開、満を持して11月16日(金)に全国ロードショーを迎えると、ネットでの作品の口コミもあり、2週目の週末興収が初週の2倍強を記録しました。
三濃川陽介プロフィール
1988年生まれ、愛知県出身。名古屋の劇団で舞台に取り組んでいる際に映画出演への思いが湧き2012年前に上京。自主短編映画「ライクダディ」で初主演を果たしデビュー、以後映画、テレビドラマ、舞台と幅広い活躍を展開。本作が商業映画主演第一作作品となりました。
企画・製作総指揮:美斉津明子コメント
 (C)2020映画【クローゼット】製作委員会
(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
最近、普段はニコニコしている若い人が、突然自殺しちゃうというという話をよく聞くんですが、例えばコロナSOSというのも要因の一つでもあるけど、孤独で人と会えなくなるというものがその要因の一つではないかと思うんです。
今回、映画公開が延期になった後、「ソーシャルディスタンス」時代となったこの時期に公開できるというのは、そんな時代だからこその映画という気もして、これが私には不思議と必然的なものとして感じられました。
「寄り添う」というと綺麗な言葉ですが、心のSOSというのはみんな持っていると思うんです。「弱者」と呼ばれる人がいますが、そういった方だけではなく一見強い立場に見える人、強そうに見える人も、実は心の中では弱くなっている時が必ずあって、誰かに何かを吐き出したいと思っていたり。自殺してしまったという方にはそういう相手がいたら死ななかったという人もいるだろうに、と。そんな局面もあると思うんです。
この作品にはこの「寄り添う」という面についていろんな語り方が、いろんな年代といろんな立場で存在していますので、誰に感情移入をするかというところも、見ている人自身の立場でいろいろな受け方があると思います。
私は経営者という立場なので、あの「添い寝屋」の店長の高木さんに感情移入します。ジンが店を去ると口にした時、自分の思いを出さず「頑張れよ」とエールを送るところでは、あの笑顔の裏で泣いてるだろうなとか。いろんな思いがこみ上げたり。
例えば若い人が、一人の「おばあちゃん」役の方に感情移入することもあるかもしれません。そんな風にいろんな立場の人を、いろんな人が見て、誰かに感情移入するという点でさまざまに面白い意見があると思いますし、その意味では広くご覧いただけると幸いです。
(美斉津明子)
映画『クローゼット』の作品情報

(C)2020映画【クローゼット】製作委員会
【日本公開】
2020年(日本映画)
【監督】
進藤丈広
【脚本】
澤田文
【音楽】
桃井聖司
【ポスターイラスト】
浅田弘幸
【企画・製作総指揮】
美斉津明子
【キャスト】
三濃川陽介、栗林藍希、新井郁、尾関伸次、永嶋柊吾、篠田諒、青柳尊哉、宮下かな子、中込佐知子、渡部遼介、中村祐、美子、水島麻理奈、門下秀太郎、工藤孝生、碓井玲菜、安野澄、枝川吉範、井上賢嗣、白畑真逸、飛磨、正木佐和、草村礼子、渡辺いっけい
【作品概要】
交通事故で男性機能が不能になった男・ジンを主人公として、心のSOSを周りに出せない孤独と、寄り添うことをテーマにした人間ドラマ。キャストには、2度のオーディションを勝ち抜いた俳優たちが多数出演。主人公の「ジン」役には三濃川陽介、Wヒロインを栗林藍希と新井郁が務めます。
ネクストブレイク必至の若い俳優たちや映画・ドラマ・舞台等で活躍する実力派俳優たちが、真摯な思いを込めて生き生きと熱演し、ストーリーを牽引する一方、ベテランの草村礼子、渡辺いっけいらベテランが静かな存在感を出し、物語を力強くバックアップしました。
映画『クローゼット』のあらすじ
交通事故で“男性機能“が不能になった男性「ジン」。愛する女性を幸せにできない悔恨、無念、絶望、葛藤、孤独…。絶望した彼は婚約者から黙って逃げて東京にやって来ます。
街中のある居酒屋でかつての先輩と出会い、彼がたどり着いた場所は「添い寝屋」。そこはさまざまな思いを抱える男女のお客が、つかの間の安らぎを求めて訪れる人間交差点でした。癒やしを求めて人々がたどり着く場所、そのお客が心に抱えるのは耐え難い不条理感、そして孤独感。
30歳のSEXがしたい処女、10歳も年下の男性に恋する36歳の派遣社員、19歳のホストクラブに嵌った女子大生、恋人に死なれた50代のゲイ、「死を看取って欲しい」という80代の老女、家庭生活に孤独を感じている40代の主婦、職場で一生懸命に人の命を救う看護師。
はた目には幸せに見える生活の中で、周りの人に心のSOSを出せない大人たち。彼女、彼らと巡りあい、闇の中をさまよっていたジンは、静かに自身の光を取り戻してゆきます。
そしてある日、一人の少女に「一緒に死んでくれる?」と乞われたジンの選択は…?
映画『クローゼット』は、2020年10月30日(金)よりテアトル新宿、11月6日(金)より大阪・シネリーブル梅田にて公開。