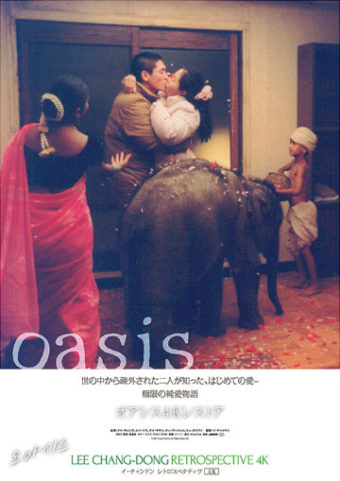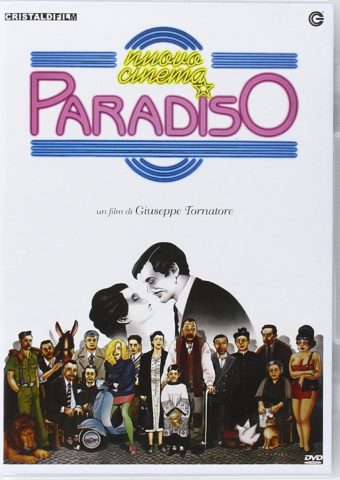「ふたつの世界」があると感じた大が、ひとつの世界に生きていると知った実話
今回ご紹介する映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』は 、『そこのみにて光輝く』(2014)、『きみはいい子』(2015)の呉美保監督が9年ぶりに手掛けた長編作品です。
原作は作家でエッセイストの五十嵐大の自伝的エッセイ「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」です。
宮城県の小さな港町に暮らす、耳のきこえない夫婦に男の子が誕生し、大(だい)と名付けられます。大は聴覚障害のある両親と祖父母のもとで、たくさんの愛情を注がれ育ちます。
大の聴覚は正常で幼い頃は、日頃、母の“通訳”をすることも普通でした。しかし、小学校にあがるとともに、その母が周囲から好奇な目で見られたり、蔑視されていることに気づきます。
悲観的でない母は明るく育児や家事に勤しみますが、思春期になる頃の大は母を疎ましく感じ、20歳になると父の勧めで上京するのですが…。
映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の作品情報
 (C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
(C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
【公開】
2024年(日本映画)
【監督】
呉美保
【原作】
五十嵐大
【脚本】
港岳彦
【キャスト】
吉沢亮、忍足亜希子、今井彰人、ユースケ・サンタマリア、烏丸せつこ、でんでん、原扶貴子、山本浩司、河合祐三子、長井恵里
【作品概要】
耳の聴こえない両親の長男として生まれ、コーダとして育つ五十嵐大役は、「キングダム」(2019~)シリーズで若き王・えい政役で、第43回日本アカデミー賞で最優秀助演男優賞を受賞し、NHK大河ドラマ「青天を衝け」で主演を務め、CMでは違った一面を見せる吉沢亮が演じます。
母・五十嵐明子役の忍足亜希子と父・五十嵐陽介役の今井彰人をはじめとする、劇中に登場するろう者役には、すべてろう者の俳優が起用されています。
他に祖父役にでんでん、祖母役に烏丸せつこ、上京し務めた出版社の編集長、河合幸彦役にユースケ・サンタマリアと個性豊かな俳優陣が脇を固めます。
映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』のあらすじとネタバレ
 (C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
(C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
宮城県の小さな港町。漁船の塗装作業をする五十嵐陽介は、昼休憩のサイレンが鳴っても作業を続けています。親方が彼の背中を叩き腕時計を指しながら、仕事を終えて帰るよう促しました。
陽介は耳が聞こえません。その日は生まれた彼の長男のお食い初めの日でした。身近な親類たちとささやかなお祝いをするため、陽介は急いで帰宅します。
家で陽介の帰りを待つ妻の明子も耳の聞こえないろう者です。明子と陽介は実家で母・広子、父・康雄と共に穏やかに暮らしています。
広子は茶飲み友達の平野と大をあやし、伯母の佐知子は料理を居間のテーブルに運びます。帰ろうとする平野に佐知子は、料理のおすそ分けがあると呼び止めます。
そこに陽介が帰宅し平野は「おめでとう」と言い、自分の耳を指さしながら、大の聴覚に異常がなくてよかったと、何気なく言います。
お祝いの料理がテーブルいっぱいに並べられ、宴が始まると昔、「蛇の目のヤス」と呼ばれたヤクザだった祖父の康雄が年長者として、お食い初めの儀式を任されます。
ところが康雄はお箸も使わず指でアワビをつまむと、大の口元に押し付け泣かしてしまい、大きな声で泣く大をみながら、男は声の大きさで決まると豪快に笑いました。
広子はそんな康雄を情けないと嘆き、明子と陽介は何が起きているのか、意味不明という顔をしてポカンとしました。
佐知子はそんな明子と陽介を見ながら、大を育てていけるのか一抹の不安を感じ、広子に2人を助けてほしいと頼みます。
明子は大が大泣きしていることに気づけないこともあり、料理を噴きこぼすこともありました。歩くようになり内職をする明子の後ろで、いたずらをする大にも気がつきません。
五十嵐家の家族団らんは両親の「手話」で賑やかであり、大も4歳になる頃には手話で少し会話できるようになります。
広子は宗教にはまりますが、手話を学ぼうとはしません。康雄はいつものんだくれていました。母と多くの時間を過ごす大は、自然と「通訳」のような役割を持って育ちます。
大が明子と買い物に出かける時は、店員の言うことを母に伝えたり、母の伝えたいことも大が伝え、母を支えて暮らすそんな日常が普通でした。
しかし、大が小学校に入学し学年が上がっていくと、平穏な家族に変化が訪れます。大の同級生が家に遊びに来た時、明子が一生懸命に声を発声しようとしたのを「変な話し方」と指摘します。
それ以降、大は授業参観のお知らせも渡さず、少しづつ母を遠ざけるようになります。明子は大に「お母さんのこと恥ずかしい?」と尋ねますが、大は答えることができません。
明子は大を買い物に誘って帰りに喫茶店に入り、手話で会話をしていると近くに座っていた客が、興味本位で話題にしますが、大は「聞こえてます」と指摘し、苺パフェを母に一口食べさせます。
学校でも大の“手話”が友達の間で興味を持たれ、ろう者への理解を得られそうになりますが、手話を茶化すクラスメイトのせいで、その機会を奪われてしまいます。
そんなある日、学校帰りの大が近所のおばさんに呼び止められます。近所の家のプランターが荒らされ、“耳の聞こえない親の子”という理由だけで大の仕業だと決めつけられます。
大は世の中の偏見にショックを受け、悔しさでその場から泣きながら逃げ出すのでした。
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の感想と評価
 (C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
(C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』は原作者でありコーダとして育った、五十嵐大の自伝を描いたヒューマンドラマです。
五十嵐氏は映画化にあたり、「ただ消費されるだけのお涙ちょうだい的な作品になることだけは避けてほしい」と、呉監督と脚本の港武彦に要望しました。
物語は要望に沿った展開となっており、地方の小さな港町という閉塞感のある土地柄から、偏見の強さが生々しく表されていると感じます。
周囲のどうせ聞こえていないとでもいう、デリカシーに欠ける言葉、子供たちの無邪気さゆえの残酷さが、時代とか地方という背景によってより濃く出ていました。
それでも映画では五十嵐氏が体験したことのごく一部が、演出されているだけと解釈でき、実際はもっと過酷なできごとがあったのだろうと想像できます。
本作はコーダである主人公の心境や立場が軸に描かれています。家族だったとしても、きれいごとではやりきれない本音があり、理解をしているからゆえに苦悩が大きいことも描かれています。
作中、陽介が「(健常者の家庭)他の家でも子育てに悩みがあるのは同じ」といい、息子を信じ話すシーンがありますが、子を持つ親御さんは共感したのではないでしょうか?
身体にハンディキャップがなくても、子育てにおいて苦悩するのは親として共通し、そこになんの差もないとわかります。
身体的な障害はさまざまありますが、見えない・聞こえないことは安全面で、不安材料が多いだけで日常生活の中では、実はできることが多いことに気づかされます。
健常者では気づきにくいことも、大はコーダであるが故に気が利きすぎてしまいます。それは自立する機会が少なかった母を助けてきた経験によるものでした。
大の母・明子は中学1年まで普通学校に通い、中学2年からろう学校へ通っています。そのため、聞こえない明子は学業の遅れが顕著でした。
昔のろう学校では手話に頼らず、口話する訓練に重きを置いていた時代があります。両親が明子の自立できる機会を摘んでいなければ、大の育った環境も少しは違っていたでしょう。
時代は変わりましたが五十嵐氏は自分の経験を通し、社会が健常者と障がい者という壁を作らず、共生できる仕組みを築いていく大切さを伝えたいのだと感じました。
まとめ
 (C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
(C)五十嵐大/幻冬舎 (C)2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会
映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の原作エッセイは「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」と長いタイトルです。
五十嵐氏は聞こえない世界と聞こえる世界という“境を失くす”方法はないのか?と、エッセイの中で模索し、ふたつの世界を行き来していたからこそ、できることがあると信じ執筆してきたのだと思います。
「ぼくが生きて来た、ふたつの世界をひとつに…」そんな理想が込められていたように感じる本作ですが、2016年に「障害者差別解消法」が施行されています。
これは全国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いの人格と個性を尊重し、共生する社会の実現を目指した法律です。
目に見えない偏見というものは、根強く残るかもしれませんが、法によって障害による差別をなくす動きが進み、2024年4月からは事業者に対しても「合理的配慮の提供」が義務付けられました。
別々の世界に生きていたと感じていた五十嵐氏も、法の整備が進む中少しずつ物理的な共生を感じながら、次は精神的な共生が進むことを望み書籍にまとめ、映画化にも期待を込めたのでしょう。