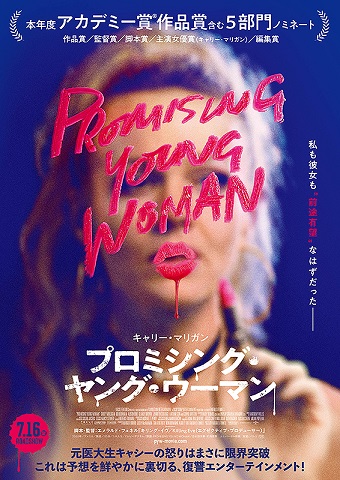新人アシスタントが気づいた、映画業界の闇。
“黙認の現実”を浮き彫りにする社会派ドラマ!
『ジョンベネ殺害事件の謎』(2017)で知られるキティ・グリーン監督が、2017年に巻き起こった「#Me Too」運動を題材に自身初の長編劇映画を手がけました。
数百にも及ぶ労働者へ対して行われたリサーチとインタビューによって掘り下げられたジェーンというキャラクターは、英語で「匿名の女性」を指す「Jane Doe」に由来しています。
名門大学を卒業したジェーンは、有名エンターテインメント企業に就職しました。
業界の大物である会長のもとでアシスタントとして働き始めたものの、仕事内容な雑用ばかりで、常態化しているセクハラに晒される日々。
将来のチャンスのために耐えていたジェーンでしたが、とある疑惑が確信に変わり会社の闇に気づいてしまったジェーンは行動にうつしますが……。
映画『アシスタント』の作品情報

(C)2019 Luminary Productions, LLC. All Rights Reserved.
【日本公開】
2023年(アメリカ映画)
【原題】
The Assistant
【監督、脚本】
キティ・グリーン
【キャスト】
ジュリア・ガーナー、マシュー・マクファディン、マッケンジー・リー、クリスティン・フロセス、ジョン・オルシーニ、ノア・ロビンズ
【作品概要】
「#Me Too」運動を題材に、主人公の女性ジェーンの一日を通じていろいろなハラスメントの現状を描いた作品。
映画業界など様々な業界に働く人々にリサーチと取材を行い、劇伴や大がかりな演出を排した上で細部を緻密に描き出すことで、「自分と重なり得る誰かの物語」と感じ取れる身近でリアリティのある映画へと仕上がっています。
本作が初の長編劇映画となったキティ・グリーン監督は、ウクライナの挑発的なフェミニストを追ったドキュメンタリー『Ukraine Is Not a Brothel』(2015)でデビューし、Netflixドキュメンタリー『ジョンベネ殺害事件の謎』(2017)も手がけています。
主人公ジェーン役を務めたのは『オザークへようこそ』(2017)や『肉』(2013)で知られるジュディ・ガーナー。グリーン監督は『アシスタント』に続く2作目の長編劇映画でも、再び彼女とタッグを組んでいます。
映画『アシスタント』のあらすじとネタバレ

(C)2019 Luminary Productions, LLC. All Rights Reserved.
夜明け前に自宅を出発し、タクシーに揺られながら一番に会社に着くジェーン。流れ作業のように会社に電気をつけ片付けをし、流し場で立ちながらシリアルで朝食をとります。
少しずつ陽が上り始め、会社にも徐々に人がやってきます。ジェーンの同僚の2人の男性アシスタントもやってきます。
男性アシスタントは、会長の妻からの電話に出ようとせず、ジェーンに出るように言います。ジェーンが電話に出ると電話口の会長の妻はクレジットカードを止められたと怒り、会長がやったに違いないと、関係ないジェーンを巻きこんで怒りをぶつけてきます。
ジェーンが自分は知らないと説明しようとしてもきかず、一方的に電話を切ってしまいます。困惑していると今度は会長から電話がかかってきて「お前には失望した」と一方的に怒られます。
理不尽な怒りを向けられ納得がいかなくても、耐えるしかないと諦め、ジェーンは即座に会長に謝罪のメールを入力し始めます。その様子を見た同僚は彼女に「与えられた機会に感謝し、二度と失望させません」と文面に入れるようアドバイスします。
その他の業務といえば、電話でホテルの手配をしたり、脚本を人数分コピーしたり、女優の写真をコピーしたり、どれも単なる雑用ばかり。それだけでなく会長の部屋の掃除などをしていたジェーンは、ソファの隙間に落ちたイヤリングを見つけます。
イヤリングを取りに来た女性は会社の女性ではなく、見たことのない女性でした。そして突如「新しいアシスタントが来たから案内してくれ」と言います。
アシスタントが来ることはジェーンだけでなく、同僚の男性アシスタントにも聞かされていませんでした。しかし女性を見た男性アシスタントの一人は、「以前見かけたことがある」と知っている様子です。
ジェーンは「シエナ」と名乗る新しいアシスタントをホテルまで送り届けることに。ホテルに向かうタクシーの中で、シエナは業界未経験だが、会長と知り合いになりアイダホからやって来たと自分の話をします。
「ジェーンが新しくアシスタントとしてやって来た時も、ホテルを用意してくれたのか」とシエナに聞かれ、ジェーンは「私の時はなかった」と答えます。
シエナとの会話で嫌な予感を感じていたジェーンでしたが、会社に戻り同僚や制作部の人々が笑い話として話している内容を聞いて、その予感は確信に変わっていきました。
いてもたってもいられなくなったジェーンは、マフラーをつけ上着を羽織り、誰にも何も言わずに会社を抜け出します。そして、隣の棟にある人事課のオフィスを訪れます。
映画『アシスタント』の感想と評価

(C)2019 Luminary Productions, LLC. All Rights Reserved.
「#Me Too」運動を題材に作り上げられた映画『アシスタント』は、主人公ジェーンの一日を通して、単調な作業の中にある、意志を奪われ従うしかない女性の姿を浮き彫りにします。
様々なリサーチや取材を基に細部までこだわって演出された本作は、セリフではなくジェーンの動作や表情で、ジェーンの置かれた状況をリアリティをもって描き出します。
例えば無機質で薄暗いオフィスで響き渡るタイピングの音、電話のブザー、話しかける際に紙を丸めて投げつける同僚の姿などが際立って演出されることで、ジェーンにとってオフィスそのものが抑圧された空間をなっていることを表しています。
子どもの世話、会長夫人の電話、荷物の受け取り、コピーなど、面倒な雑務は全てジェーンの仕事として回され、同僚であるはずの男性アシスタント二人は基本的にパソコンに向かっているだけの仕事しかしません。
それでいてジェーンが何かミスをした時には、「簡単な仕事すらできないのか」と会長に怒られるジェーンのフォローもせず、することといえば会長に送る謝罪メールのアドバイスだけです。
「機会を与えていただき感謝します」「二度と失望させません」といった文面が謝罪メールに含まれていますが、会長はジェーンに機会など与えていませんでした。プロデューサー志望のジェーンに代替可能な雑務ばかり押しつけ、キャリアアップのチャンスなど何一つ与えていません。
「#Me Too」運動で問題となり糾弾された人々の多くは、権力を持つ上の立場の人間たちでした。本作はそのような上の立場である会長の姿を一切映すことなく、声と存在感だけでジェーンが感じている抑圧・恐怖を表現し、トップだけでなく、組織全体でその状況と黙認してきた構図を浮き彫りにしています。
映画業界を取り巻く性搾取やハラスメントの現状は、
糾弾された上層部を排すれば改善されるのではなく、組織全体で蔓延っている問題/span>であること。それは映画業界だけでなく他の業界にも言えることであり、もちろん日本の様々な企業にとっても決して他人事ではないのです。
ジェーンの同僚の男性アシスタントも、制作部の社員たちも、会長が自分の好みの女性に対し「仕事を与える」と言って性搾取をしていたことを知っていたはずです。しかし、“そういう現実”と黙認することで自分の地位を守ってきたのでしょう。
また黙認してきたのは、男性だけではありません。ある女性社員がジェーンに対し「あの子はうまく利用するから大丈夫」と発言する場面にて、その女性社員も会長の性搾取に加担した加害者として描かれていますが、彼女もまた「女性は“そういう現実”で生きているからこそ、仕事を得るためには我慢すべきことだ」と考えてしまっているのです。
仕事の機会は平等に与えられるべきであり、そのために性的な行為という対価を払わせようとすること自体が異常な状況という認識がなく、あったとしてもジェーンのように声を上げたところで「声を上げる側がおかしい」「本人に問題がある」と問題点をすり替えられて黙殺されてしまうのです。
また人事部も、下の立場の人の声を聞く部門ではなく、上の立場に忖度して下の立場の声を揉み消す部署と化してしまっている現状が浮き彫りになります。
もっと早く声を上げればよかった、と「#Me Too」運動を経て思う人もいるかもしれませんが、声をあげ、その声が届くということはそう簡単なものではないのです。勇気ある一人の声が届いたことで他の声も届くようになる、そのような積み重ねが「#Me Too」運動につながったのです。
「今なお蔓延っている“そういう現実”に対し、映画を観終えた“わたし”は、どうする?」と突きつける本作は、簡単に無関心な加害者となり得てしまう“わたし”たちの胸に強く突き刺さります。
まとめ

(C)2019 Luminary Productions, LLC. All Rights Reserved.
ジュリア・ガーナー演じるジェーンのセリフはそう多くはありません。しかし、おそらく一日のルーティーンになっているのであろう作業や、仕方なく引き受けている様子が彼女の動作や表情で伝わってきます。
ジェーンが流し場で食器を片していると、雑談しながら入ってきた制作部の女性社員2人が、雑談後部屋を去る時に、無言で飲んでいたコップを洗わずに置いていきます。
それを眺めていたジェーンは、諦めたように手に取って洗います。性別・役職関係なく、誰もが彼女を下に見て雑用係だと思っている姿が、それだけのシーンでも手に取るように分かるのです。
「#Me Too」運動以後、映画業界に蔓延る問題が徐々に浮き彫りになっている今、その流れは日本の映画界にも波及しています。そんな日本の映画業界の現状を浮き彫りにした短編映画に、大富いずみ監督の短編『SHIBUYA, TOKYO 16:30』(2020)があります。
同作では小川あん演じる主人公が脚本を見せに行くと、脚本の感想ではなくセクハラを受けてしまうといった物語を描いていますが、相手の男は「勘違いさせた、過剰に反応した女側に問題がある」と言わんばかりの態度をとります。
『SHIBUYA, TOKYO 16:30』も『アシスタント』も、性搾取の問題を題材にしつつも、エンタメとして消化するのではなく、真摯な姿勢で描き上げています。
そのような細部までこだわったリアリティのある映画の必要性が特に高まっていると感じさせる映画でした。