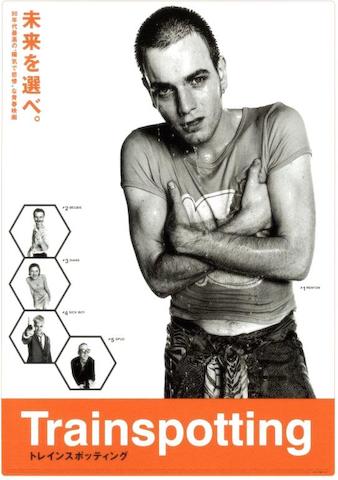ユアン・マクレガー初長編監督作『アメリカン・バーニング』考察解説!
1996年から60年代を振り返り、順風満帆な人生を送っていたはずの家族が崩壊していく様を描いた映画『アメリカン・バーニング』。
主演を務めたユアン・マクレガーの初の長編映画監督作となった本作は、アメリカ近現代史を描いたフィリップ・ロスの小説「American Pastoral」を映画化したものです。
キャストにはユアンのほか、妻役を『トップガン マーヴェリック』のジェニファー・コネリー、娘役を『500ページの夢の束』のダコタ・ファニングが集結。
1960年代のアメリカを席巻したカウンターカルチャーの潮流は、田舎でのどかに暮らしていた誰もが羨むような理想の夫婦を翻弄していきます。
CONTENTS
映画『アメリカン・バーニング』の作品情報

(C)2016 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED
【公開】
2016年(アメリカ・香港合作映画)
【原題】
American Pastoral
【原作】
フィリップ・ロス『American Pastoral』(1997)
【監督】
ユアン・マクレガー
【キャスト】
ユアン・マクレガー、ジェニファー・コネリー、ダコタ・ファニング、ハンナ・ノードバーグ、オーシャン・ジェームズ、ピーター・リーガート、ルパート・エヴァンス、ジェリー・レヴォフ、ウゾ・アデューバ、モリー・パーカー、ヴァロリー・カリーサマンサ・マシス、デヴィッド・ストラザーン
【作品概要】
フィリップ・ロスが1997年に発表した小説を基にユアン・マクレガーが監督・主演を務めたドラマ映画。本作がユアンにとって初の長編映画監督作であり、共演にジェニファー・コネリー、ダコタ・ファニングなど豪華キャストが脇を固めています。
当初は『ブラインド・フューリー』(1989)や『今そこにある危機』(1994)で知られるフィリップ・ノイスが監督に予定されており、ジェニファー・コネリーと実際の夫であるポール・ベタニーが主演を務めるはずでしたが、数年にわたる構想の結果、現在の形に至りました。
映画『アメリカン・バーニング』のあらすじとネタバレ

(C)2016 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED
1996年。作家のネイサン・ザッカーマンは同窓会に出席すべく、地元ニュージャージーに里帰りしていました。そこで同窓生のジェリー・レヴォフと再会します。
ジェリーは兄シーモアの葬式ついでに立ち寄ったのだといいます。アメフトに野球、トップアスリートとして活躍し、花盛りの高校生活を謳歌したシーモア。しかし弟ジェリーの語る、その後の彼の生涯は悲惨なものでした。
第二次世界大戦から帰還したシーモアは、州代表としてミスアメリカの大会に出場した経験を持つ絶世の美女にして学園のマドンナであったドーンとの結婚を認めてくれるよう、父親のロウのもとを訪ねました。父親ロウがなかなか首を振らないのにはワケがありました。
シーモアの一家は敬虔なユダヤ教徒の家庭ですが、ドーンはカトリック教徒。子どもの割礼や洗礼でドーンとロウの意見は衝突し、「キリスト教の洗礼?あり得ない」というロウに「洗礼を受けないと子どもは原罪を背負ったままになってしまいます」とドーンは引き下がりません。
結果ロウが折れ、ふたりは無事結婚。ふたりの間に一人娘のメリーが生まれます。やがて父の会社を継いだシーモアは、高級住宅街に一軒家を構え、人生は順風満帆でした。
一方で、一人娘のメリーは吃音に悩まされていました。言葉がうまく出てこない。そんな彼女を心配し、シーモアとドーンは心療カウンセリングに相談をします。
カウンセラーは「メリーは完璧な両親の間に生まれた子どもとしてコンプレックスを持っている」「美しい母親と比較されるのを恐れて、吃音を起こしているのだ」と分析します。
結局明確な解決法も見つからぬまま、シーモアはメリーを連れて父と娘ふたりでキャンプに出掛けます。その帰りの車内。メリーは詰まりながらも「キスをして」とシーモアにせがみます。
微笑みながら頬にキスをするシーモア。しかし「ママにするみたいに」というメリーの言葉に、思わず声を荒げて叱りつけます。メリーは「わるいのはわたし」「いつも何かを しようとすると 度を越してしまう」とだけ言うのでした。
吃音をチェックする日記を親子で見ているある夜のこと。学校の宿題で「人生とは何か」という問いに「人生とは人が生きている短い時間」と答えたメリー。その意味を聞かれたシーモアは「わかる気がする」とだけ答えたのでした。
テレビでは連日、アメリカとベトナムとの戦争の様子を報道しており、その日は1963年の6月11日。サイゴンのカンボジア大使館前で起きた、ティック・クアン・ドック焼身自殺を報道していました。思わずテレビを消すドーン。
夜、メリーは泣きながら両親の寝室に駆け込んできました。「遠い国の出来事だよ」となだめる両親にメリーは「誰も良心がないの?」と悲観に暮れるのでした。
高校生に成長したメリーは当時のジョンソン政権に対して反対姿勢を明らかにします。シーモアとドーンは「もちろんパパたちも戦争には反対だ」と答えるものの、政治的話題を避けようとしました。
世界で起きていることに見向きもしないドーンを「戦争に興味ない中産階級のくせに」と非難するメリー、「あなたは戦争だけじゃなく全てに反逆しているじゃない」と返すドーンの口論は平行線のまま。
シーモアはメリーの部屋で過激な反戦運動の数々を目にします。壁に貼られた標語には〝白人どもの既成秩序に反対し破壊する″とありました。
黒人タクシー運転手に対する警官の暴行を発端にニューヨークで起きたデモ行進にメリーも参加しに行ったのではないか。その夜、駅に迎えに行ったシーモアはメリーに問い詰めます。メリーは「アメリカ人誰しもがベトナムで起きていることに責任を感じるべきだ」とシーモアに訴えますが、彼はただ自身の娘の身を案じるだけでした。
帰りの車内。通りには黒人のグループが。「出ていけ」「ここは我々の場所だ」そういう彼らにメリーは“ブラックパワー”と声をかけるのでした。
家に戻り街での暴動を心配するドーン。「あれは暴動ではなく革命よ」メリーは市議会に黒人の議員がいないこと、失業率、貧困を説きますが、両親は答えに困るのみでした。
会社の前で州兵との暴動があったことを聞きつけたシーモアは会社に戻ります。そして「この会社には黒人の従業員がいる」という張り紙をして一晩を過ごしました。
朝、外へ出ると辺りは荒れ、誰ひとりいなくなっていました。
ある日シーモアは反戦運動の方法をメリーに説きます。「ニューヨークへわざわざ行かなくてもこの町でやったらいい」と。「田舎で革命は起こらない」ふたりはお互いの考えのすれ違いを感じたまま会話を終えます。
次の日の早朝。シーモア一家とも顔なじみの郵便局で爆発がありました。
前の晩、帰ってこなかったメリー。「戦争を痛感させてやる」と日頃訴えていた娘が爆破の犯人ではないかと疑い始めます。認めようとしないふたりのもとへ警察の家宅捜索が入りました。娘はもう一人の女性と共謀して犯行に及んだのだと警察は言います。
「娘はハメられた」「洗脳されているに違いない」とふたりは警察の話を信じようとしません。そして警察よりも先にメリーを探そうと奔走します。
しばらくしてシーモアの会社に一人の女性が訪ねてきました。メリーの使いだという彼女。
メリーの居場所を掴む手掛かりになるとシーモアは単身、彼女の指定したホテルへ向かいます。金を渡せば、居場所を教えてくれるはずだ。しかしシーモアの考えとは裏腹に彼女はベッドへと彼を誘います。シーモアに挑発を続ける彼女。シーモアは部屋を後にします。
唯一の手掛かりを失ったシーモア。途方に暮れる彼に、さらに追い打ちをかける事態が起こります。
映画『アメリカン・バーニング』の感想と評価

(C)2016 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED
108分という上映時間は小説を原作としたドラマにしては非常に短いです。場面が転換する度に60年代の実録映像が挿入され、映画の背景で起こっていた実際の出来事を補足する役割を果たしていますが、それも十分ではありませんでした。
例えば、高校生になったメリーが参加した暴動は劇中にてわずかに言及があるのみで、描写としても、まるで黒人と警官の抗争であったかのような描きぶりです。これはメリーが揶揄するところの政治に興味ない中産階級のシーモアの立場からしてみれば、その程度の認識であったことを表していますが、実際にそこで起きていたことは今でも続いている黒人に対する警官の暴動です。
もちろんこの映画が主軸として描いているのは娘の失踪とそれを追う父とその家庭であるため、ひとつの出来事を丁寧に描くことは不可能です。当時の状況はキャスリン・ビグロー監督の実録映画『デトロイト』(2017)と合わせて観ることでより鮮明になります。
カウンターカルチャーの時代が描く不幸な人々

(C)2016 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED
今作は小説を基にした映画としては短く、語られている物語も最小限にとどまっていますが、登場人物のやりとりから想起させられる映画は多いです。それはアメリカン・ニューシネマというムーブメントの発生により映画産業自体が、時代の潮流と密接に関係しているからでもありますが、多くの暴力・残虐行為から目を背け、誰もが何もしないでいることが出来なかった当時の状況を映画『テル・ミー・ライズ』(1968)が詳細に描いています。
ジャーナリスト、戦争レポーター、アメリカ大使館の公務員、歴史家、そして今作にも登場したティック・クアン・ドックと同じ宗派の僧侶など様々な立場の人が白黒つかないかたちで政治参加をしていくセミドキュメンタリーで、当時の人々がリアルタイムの情勢について語る様子を粗削りで答えの出ない議論として描きます。
当時を振り返り、「分極化が進み、極端な選択を誰しもが迫られた時代であった」と『テル・ミー・ライズ』監督のピーター・ブルックは語ります。「ベトナム戦争に反対するということは、左派の全ての考えに全面的に賛同することを意味していた」(パンフレット掲載インタビューより)一つの視点を囚われず、全てのグレーゾーンに入り込むことが本当の政治参加を意味します。今作のメリーは選択を極端に迫られ、無理に白黒をつけてしまったのでしょう。
報われない不幸な人物の死により幕を閉じたこの映画は、単なる後味が悪い映画なのでしょうか。つまり、本当に不幸なのはシーモアでしょうか.実は本当に不幸なのは、「人とは互いを理解し合うことが出来ないものだ」と諦めることしか出来ない語り手のネイサンその人です。
「幸せそうに見えたシーモアにも不幸な一面があった」と語る彼が、映画の最後に残す言葉は少なく、とても抽象的です。映画から飛躍した解釈かもしれませんが、諦めることしかしなかったドーンやネイサンは何を得たでしょうか。何も得ていないのです。
これは何もしないより何かした方がマシという話ではなく、シーモアとメリーの顛末を切り取って“行き過ぎたアクティビズム・白黒つける極端さが招いた悲劇”と一緒くたに切り捨てることこそが、社会や個人同士の分断に繋がるということを意味します。
確かに分かり合うのは大変で、ネイサンの言う通り、人は誤解をし合ったまま傷つけあうかもしれません。そこでシーモアのように沈黙することは簡単です。またなぜ沈黙が現実社会でも賢い世渡りのように語られているのかも明確です。「障らぬ神に祟りなし」といったことわざや勇気ある人の訴えをもみ消すようなトーンポリシングは、なんの解決にもならないどころか相互理解のきっかけを殺すものです。
シーモアが晩年ひたすらメリーを待ち続けたのは現実逃避のひとつであり、自ら(と家族)が「罪なきアメリカ人」で居続けるためです。
議論の機会を損ねる「コールアウト」への恐怖

(C)2016 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED
取り返しのつかない犯行に及ぶ前のメリーは「アメリカ人の誰しもが、ベトナムで起きていることに責任を感じるべきだ」と訴えていました。
彼女のアクティビズムがどこでかけ違っていったのか。明確な原因は描かれませんし、そこにこの映画の答えはありませんが、訴える娘にキチンと向き合うことをしなかった両親がその一因であることは、短いストーリーからでも十分読み取ることは出来ます。
シーモアにはメリーが言うところの“責任”を受け入れることは到底できないでしょう。表面的なことをいえば、シーモアたちは世界大戦を生きた最後の世代で、その子ども世代は戦争を肌では知らない世代です。ニュースで漏れ聞こえてくる情報に対する受け止め方の違いは確かにあるでしょう。
カラーの映像で初めて観た戦争はメリーにとってどれほどの衝撃であったか。抗議活動の原動力にはその時のショックが間違いなくあったはずですし、そこに両親が共感を抱くことは難しいでしょう。目先の幸福に興じることの喜びを戦争経験者は誰よりも知っているからです。
シーモアにそんな幸福にうつつを抜かすなというのは少し厳しい物の言い方だと思います。順風満帆な人生を手に入れた自分とその周りは(自分の視点から見れば)皆平和に暮らしている。この平和の土台にはベトナムの悲劇があり、世界大戦で築かれた大勢の屍があるなどと認めてしまっては、最早自分は別のものに変わり果ててしまうのではないか。彼にはそんな恐怖が常にあったのでしょう。
それは、今の現実社会でいうところの‟コールアウトされることへの怯え“に近いものです。最近ではキャンセルカルチャーともいわれている一連のボイコット運動のことで、それが過去のものであれ最近のものであれ、SNSでの言動に対し、文脈や背景に関係なく問題視し糾弾することを指します。
シーモアは娘に政治的意見を訊かれるたびに口ごもります。それは娘を変な思想に目覚めさせないよう慎重な言動を心がけているからでしょうが、それこそ自称リベラルが犯す間違いの典型です。
何か自分が間違ったこと、配慮を欠いた発言をしてしまった際に相手から完全に拒絶されてしまうかもしれない。そんなことに対する恐怖が彼を沈黙させ、「障らぬ神に祟りなし」と妻と娘の口論も中立を保つような中途半端な態度をとらせたのです。結果、彼は妻も娘も失いました。昔の自分たちの生活は一体何に奪われてしまったのか、気づきを得る術もなく。
まとめ

(C)2016 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED
原作の小説に対してストーリーが短縮された映画ではありましたが、俳優陣の鬼気迫る演技が見事で、作品のポテンシャルを底上げしていました。
中でもジェニファー・コネリーの演技が特に素晴らしく、加害者の家族としての責任から逃避するため残酷な自己防衛で身を滅ぼしていく姿は、『葛城事件』(2016)にて南果歩演じる加害者の母親に匹敵する狂気・恐ろしさを感じました。ユアン・マクレガーも監督と主演を同時にこなし、抑えるべきところはキチンと抑えていました。
分かり合えない他者と(とりわけ家族は分かり合っているものと錯覚しがちですが)共有を続けることは、己の無知を晒すようで恐ろしく、相手を理解するのも簡単なことではありません。しかしドーンのように諦めず、シーモアのように加害性や真実を拒絶しなければ最悪の事態は免れるかもしれないということを映画は逆説でもってその重要性を説いていました。