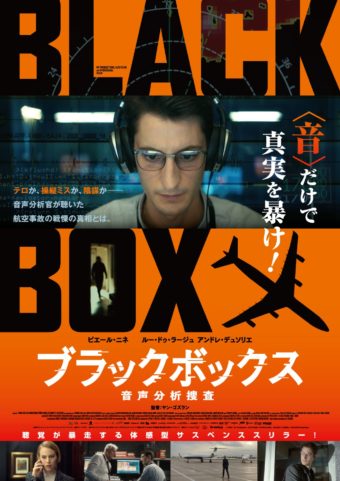連載コラム「映画道シカミミ見聞録」第3回
みなさんこんにちは。森田です。
映画クレヨンしんちゃんシリーズや、『河童のクゥと夏休み』(2007)などの作品で知られる原恵一監督。
実は私が同郷で、大学の授業などで直接お話する機会があり、いろいろなお話を伺ったことがありました。
北関東出身の原恵一監督

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2001
原監督の故郷は群馬県館林市。
その名前を聞いたことがあるとすれば、夏場の天気予報で、その日の最高気温をめぐり埼玉県の熊谷市や岐阜県の多治見市とデッドヒートを繰り広げている様子からでしょう。
それ以外には、大きな特徴のない北関東の内陸の町です。
「なにもない」とは、いまやどの地方をも指す枕詞になりつつありますが、ここで問題にしたいのは、とりわけ「映画館がない」こと。
映画館なくして作家は生まれうるのか…。
正直、わたしが原監督の名前を脳裏に焼きつけたのは、大人たちの共感を呼んだ『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』(2001)でも『カラフル』(2010)でもなく、「あの町から映画監督が!!」という同郷ゆえの驚きでした。
失礼を承知でその衝撃を原監督に伝えると、やはり「文化的な環境には乏しかったよ」と言います。
そしてお隣の足利市(栃木県)まで出むいていたことを明かしてくださり、ときには自転車で行くこともあったそうです。
また「生まれた土地」という意味での“故郷”にはあまり良い思い出はなく、自身の作品に与える影響をきっぱりと否定。
むしろ館林から東武伊勢崎線上の終着点にある浅草の「花やしき」に家族といった記憶などが、あたたかな「原風景」として心に刻まれているとのことでした。
まずここに、原監督の描く「家族像」の秘訣がみえます。
それはただ生まれた故郷だから、育ててもらった親だからという理由で、無条件に肯定されるものではありません。
過去をふり返ったり、家庭をあつかったりする際には、地縁や血縁関係で美化しがちです。
しかし、原監督の作品には、その誘惑に負けまいとするはっきりとした意識が感じられるのです。
さきのコメントだけでなく、たとえば『オトナ帝国の逆襲』ひとつとっても、その姿勢がうかがえます。
「クレヨンしんちゃん」シリーズで伝説的人気作品
『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』(2001)
大人たちが、子ども時代を懐かしむテーマパーク「20世紀博」に通いつめることから、ついに“子どもがえり”してしまうという本作。
その世界は俗悪ともいえ、「過去」というもののいかがわしさ、欺瞞性を遊びの裏に表現しているようにみえます。
実際に原監督は、日本映画大学の学生が企画した映画祭(「おやこ映画祭 絆と狂気のカルテ」、2018年2月10日~12日、川崎市アートセンターで開催)において、このように語りました。
「あの時代は良かったけど、いまのほうがもっと良いよね。それはたえず意識しています。」
まさにこの言葉に尽きるでしょう。しんちゃんも東京タワーを駆けのぼる有名なラストで、こう叫びます。
「大人になりたい。大人になってお姉さんみたいな人とお付き合いしたい!」
過去を美化すると、現在から目を背けることになる。それを批判するかのごとく、しんちゃんに「未来」をつかませた。
わたしにはそう感じられました。
つまりこうも言えるでしょう。ふり返るべき対象が“なにもない”からこそ、人と人とを取り巻く環境や文化の「自明性」に足をすくわれない強さを持つ。
その脚力で、自分が求めるものが“ある”場所へと歩みをすすめられる。
また、その軌跡が、創造のプロセスにも重なってゆくのだと。
原監督が映画を探しにいった足利も(わたしも同じ経験をしました)、家族と出むいた浅草も、東武伊勢崎線という1本のレールで文字どおりつながっています。
「故郷」というものが仮にあるとすれば、生まれ落ちた“点”ではなく、鉄道で結びつくような“線”なのではないかという見方もできるはずです。
「故郷は作品世界に反映してない」という認識から、逆説的にこの「越境性」の視点が浮かび上がりました。
異邦人(エトランジェ)というマレビト

(C) 2007 木暮正夫/「河童のクゥと夏休み」製作委員会
わたしが思うに、それが土地と作家とのある種の関係性であり、家族を描きながらも家族に縛られない原監督作品に潜む「哲学性」と位置づけられます。
それは「異邦人」の創造性と呼べるかもしれません。
それこそ小説『異邦人』を発表したノーベル文学賞作家のアルベール・カミュは、アルジェリア出身のフランス語圏作家でしたし、おなじく世界中に読者のいるフランツ・カフカは、プラハ出身のユダヤ系ドイツ語圏作家です。
彼らの存在は一例にすぎませんが、「エトランジェの文学」ならぬ「エトランジェの映画」として、作家の持つ越境性と作品の魅力を日本国内でもとらえることができるでしょう。
ときには民俗学がでてきたり(『河童のクゥと夏休み』)、ときには江戸の下町(『百日紅』)がでてきたりしながらも、どこか「邦」の外に構えて物事を観察している原監督の姿が、お話を通して垣間見ることができました。
そしてそういった「国際性」がやはり評価されて、2017年の第30回東京国際映画祭で特集上映「映画監督 原恵一の世界」が組まれるにいたったのだろうと考えます。
さまざまな経験から「家族ものが苦手」という方もいらっしゃるでしょう。
そんなひとにこそ、「それでいい」と無理強いしない軽やかさと深みをもった原恵一監督作品をおすすめしたいと思います。