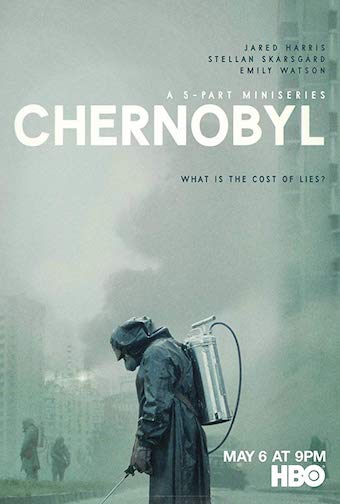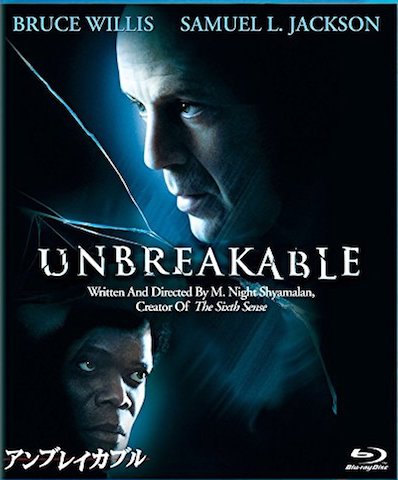講義「映画と哲学」第13講
日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。

(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics
第13講では、第10講にて論じたジル・ドゥルーズの「5つの実在」の類型に付け加えるべき「第6の実存の様態」として、フリードリッヒ・ニーチェが唱えた〈超人〉について考察。
さらに2019年公開の映画『ジョーカー』をはじめ、〈超人〉の陰画、〈超人〉的行為の戯画といえるいくつかの映画作品を分析していきます。
CONTENTS
第6の実存?

ニーチェ『ツァラトゥストラ(上)』(丘沢静也訳、光文社新訳文庫、2010年)
第10講で、ジル・ドゥルーズによる「5つの実存」の類型について述べた際に、本来であれば付け加えるべきことがあった。ドゥルーズは別の文脈で、少なくとももう一つの実存の様態に言及している。それはフリードリッヒ・ニーチェ(Nietzsche 1844-1900)に由来するものである。これを第6の実存に数え入れるのを躊躇した。この実存の様態は、人間学的な地平を超えた実存様態であり、通常の人間の行為の基準では理解しがたいところがあるからである。ニーチェがその実存の類型に与えた名前は、〈超人〉(Übermensch)である。〈超人〉は〈怪物〉などとともに非人間学的な実存の様態を構成するであろう。
有罪性と有責性
ドゥルーズが『シネマ1』で示した5つの実存は、もともとある思想史的な文脈で有効な類型であった。それは、パスカルに端を発し、キルケゴールを経由し、サルトルの実存主義へと至るものである。この思想史は、選択すること(二者択一)を試金石にして、人間の行為の罪とその責任を問うものである。しかし、人間の実存には罪があり、かつその実存には責任があるという対応関係はけっして自明なものではない。ニーチェがいうギリシア的原初とは、実存に罪がないこと、無垢であることである。したがって、実存についてのニーチェ的な問いは、「〈罪ある実存は有責か、否か〉ではなく、〈実存は有罪か、無垢=無罪か〉である。」(『ニーチェと哲学』59頁)。ニーチェの答えでは、もちろん実存に罪はなく、ありもしない罪について、超越的なものによる裁定を待ったり、その許しを乞うたりすることに仕向けるのが、道徳だということになる。有罪性と有責性の関連を離れれば、人間の実存はまったく別のものに見えてくる。
ニヒリズムの諸段階

ジル・ドゥルーズ『ニーチェと哲学』(江川隆男訳、河出文庫、2008年)
(1)ドゥルーズの理解するニーチェによれば、われわれ普通の人間は、反動的な力のなかで、反動的な生の理解をしている。ニーチェは、生を否定し、実存を過小評価する企てをニヒリズム(Nihilismus, nihilism)と呼ぶ。近代の歴史とはニヒリズムの勝利の歴史である。その歴史はおもに5つの段階を経てゆくという。
① 怨恨(ルサンチマン):すべてを他者のせいにして、「お前が悪い」「お前のせいだ」と他者に非難と不平を言う。
② 疚しい心:それが逆に内向して、「私が悪い」「私のせいだ」という内向的な投射になる。疚しい心は、そのことでまず苦しみを増大させ、次にそれを精神化(内面化)する。自分自身を罪深いものだと言い(キリスト教)、自分自身に敵対する。これらふたつは、能動的な力を避けようとする反動的な生である。
③ 禁欲主義的理想:弱い生、反動的な生が望むものは、生を否定することである。弱い生の力の意志は、それができないと思うとき、それは禁止されていると考える。意欲を禁止することが理想化され、道徳化される。これがいわゆる「弱者の道徳」である。その意志は何も生産的なものを産まない。
④「神の死」:神とは超越的な価値のことである。神の死とは、神の自然死ではなく、殺害である。ついに人間が自分こそ神の殺害者であることを発見する。そして、神の死の論理的帰結は、人間自身が神に取って代わることである。
⑤ 最後の人間と、滅びを望む人間:ニヒリズムの最後の段階として、無への意志は自分自身を能動的に破壊したいという欲望を抱かせるに至る。
(2)ニーチェによれば、「怨恨」も「疚しい心」も実存の心理学的規定ではない。逆なのだ。「怨恨」や「疚しい心」「禁欲主義的理想」などによって作られた「復讐の精神」のもとに心理学なるものが打ち立てられているのだから、あらゆる心理は自ずと「復讐の精神」の心理学になってしまう。そればかりか、「復讐の精神」は、われわれの歴史、形而上学、自我、道徳などを構成する力であり、「超越論的な原理」(『ニーチェと哲学』82頁)である。
(3)ニーチェがやろうとすることは、実存の新たな解釈と新たな理想を探すことであり、別の思考の仕方を探ることである。ニヒリズムの歴史の中から、ニーチェは「一切の価値の転倒」を引き起こす人間の超克、すなわち人間が人間を超えてゆく契機を考える。それが〈超人〉という形象である。「実存を糾弾も過小評価もしない人間はなおも人間であろうか。彼はなお一人の人間として思考するであろうか。それはすでに人間とは別のもの、ほとんど超人ではないのだろうか。」(『ニーチェと哲学』82頁)。
(4)ドゥルーズによれば、パスカル的な「二者択一は、まったく禁欲主義的理想と生の過小評価との影響下にある。」(『ニーチェと哲学』86頁)。そもそも、パスカルが神の存在問題で賭けている賭け金は、神の実存ではなく人間の実存である。「神」の名を盾にして決断を迫る人間の実存、そのいかがわしさ。そこで、ニーチェがパスカルの「賭け」に対立させるのが、「戯れ」である。
偶然と戯れること
『ノーカントリー』(2007)予告編
ニーチェが戯れるというとき、何と戯れるのか。それは偶然とである。偶然を一つの肯定にし、必然と為すことである。偶然の肯定こそ、戯れるという行為そのものなのである。悪しき戯れ、あるいは戯れでないのは、目指すサイコロの目を当てにして、何度もサイコロの一擲を繰り返すことである。つまり、一回限りサイコロを振るのではなく、目的のために因果性と確率に訴え、何度もサイコロを振ることである。サイコロの目に「賭ける」こと、すなわち、選択を決断に結びつけることは、果敢な行為に見えるかもしれないが、その実、実存の弱さを隠しているにすぎない。戯れることは臆病な決断主義とは対極にある。なぜなら、戯れることは、選択によって生ずる「AではなくBを」という限定的な否定すらない、全くの肯定であるからだ。二者択一の一なるものも多のなかで肯定すること、すなわち多という差異の肯定。〈超人〉の実存の様態は、賭けるのではなく、あらゆる偶然を肯定することであり、全選択肢を必然と見なすことである。
第3講で取り上げたコーエン兄弟の『ノーカントリー』(2007)には、恐るべき殺し屋アントン・シガーが登場していた。シガーは、非人間学的な実存類型のうち、〈超人〉というよりは、〈怪物〉の方だろうが、一回限りのコイントスの偶然に絶対的に従い、それを楽しんでいるという意味では、偶然の肯定を絵に描いたような実存である。カーラ・ジーンのみが、このシガーにかろうじて拮抗できたのは、彼女が相手のコイントスの誘いを「賭け」だとみなし、「賭ける」ことを拒否したからだった。
〈超人〉はスーパーヒーローではない
〈超人〉の陰画、〈超人〉的行為の戯画は映画のそこかしこにある。ハリウッド映画では、これでもかというほど、超人映画流行りである。手っ取り早く、だれが超人なのかを知りたければ、超人全員集合の『ジャスティス・リーグ』(DCコミック系)や『アベンジャーズ』(マーベル・コミック系)を見ればよい。それらの超能力をもったスーパーヒーローたちは、すべてニーチェのいう〈超人〉ではまったくない。ニーチェは〈超人〉を、社会ダーウィニズム的に淘汰を勝ち抜いた「英雄」のような意味で、つまり英雄主義や英雄崇拝の文脈で理解することを明確に否定している。
また、前回「愚か者」の転倒性について言及したが、〈超人〉の価値転倒は、愚か者のそれとはまったく性格を異にしている。愚か者の転倒性とは、自分自身による価値転倒ではなく、愚か者の愚行を見る者たちに生ずる転倒である。愚か者の同一性は微塵も変わらない。しかし、〈超人〉の価値転倒は、〈超人〉に発する、〈超人〉の行為による価値の変換でなければならない。それは通常、簡単に人々の賛意を得られるようなものではない。
〈超人〉の意図とは、従来の人間を超克するとか、乗り越えるということなのであって、本来それを人物形象で具現することはむずかしい。われわれが映画に確認することができるのは、あくまでも〈超人〉的行為の片鱗である。
『ジョーカー』を観る試み
『ジョーカー』(2019)予告編
(1)トッド・フィリップス監督の『ジョーカー』にはもちろん様々な前史があるが、先行するコミックスや映画はこの際すべて脇においておこう。『ジョーカー』は、孤独なクラウン(プラカードをかかげる道化師)アーサー・フレック(フォアキン・フェニックス)が怪人ジョーカーに生成するに至る過程を描いている。これを、ある人間がニヒリズムの諸段階を経て〈超人〉に近づく過程として見ることができるか、がここでの問題である。
(2)アーサー・フレックは出生不明の養子(あるいは大富豪のトーマス・ウェインの非嫡出子)であり、養父によって激しい虐待を受けた「あらかじめ失われた無垢」の経験者である。また、アーサーは、コメディアンとして他人を笑わせたいという強い願望をもっているにもかかわらず、発作的に笑い出す病いをかかえていて、笑わせる前に自分の方が笑ってしまうという逆説的な生を生きている。
(3)アーサーの行動原理は、「復讐の精神」によって貫かれている。アーサーには、母親が関係を持っていた大富豪のトーマス・ウェインに対して激しい怨念がある。その母親は、「弱者の道徳」(「奴隷道徳」)のこの上ない信奉者であり、未だにトーマス・ウェインへの妄想的な期待にしがみついている。アーサーは足かせである母親を窒息死させ、「道徳」と決別し、何ひとつ憂慮することなくテレビのコメディショーへ向かう。
(4)コメディアンを目指すアーサーからすれば、コメディ界の大御所マレー・フランクリン(ロバート・デ・ニーロ)は、神のごとき存在である。「神の死」とは人間による神の殺害にほかならず、神の位置を奪うことであった。「父」であるトーマス・ウェインを撃たずに、なぜフランクリンを撃つのかは、「神の座」が賭け金になっている以上、当然のことと言えるだろう。アーサーはこの場で、「善/悪」と同様に「笑える/笑えない」の新たな線引きを提案し、価値の転換という真にニーチェ的な行為を試みている。地下鉄で証券マン三人を殺したことを告白し、それが「笑えるか」というジョークの思考実験をしている(自分をジョーカーと紹介させる真の理由)。そして、案の定、スタジオの観客からブーイングを受ける。
(5)振り返って、証券マン三人を殺したあとに、慌てふためいて逃走するアーサーの姿は、単なる偶発的な殺人犯にすぎないが、逃げ込んだ公園のトイレでアーサーに変化が起こっていた。そこで我知らず行う行為は、見紛うことなく、ディオニソス的な陶酔の舞踊である。ドゥルーズによれば、舞踊、軽やかさ、笑いがディオニソスの諸特徴だ。また、警官二人に監視されながら、見上げるような百段階段の上で、いとも軽く、重力に逆らうように踊られる舞踊は、この陶酔のジェスチャーの完成形である。
(6)この映画が好んで繰り返すもうひとつのジェスチャーは、こめかみに銃を突きつけて暴発させる仕草である。このあからさまな『タクシー・ドライバー』(1976)への言及は、その主人公トラヴィスの境地と行動への参照だ。つまり、ニヒリズムの最終段階である「最後の人間」が自己破壊の暴力として示す典型的なジェスチャーである。自己を自己と敵対させるニヒリズムの極み、能動的なニヒリズムは、自己破壊の衝動を抱えながら、目指すのは他者の破壊(政治権力者の抹殺、ゴロツキどもの退治)なのか、他者の救済(少女娼婦の奪還)なのかいまだ判然としない状態にある。
(7)だから、アーサーが破壊されたパトカーのボンネットに乗って熱狂する群衆に背中を見せ、振り向いたときには血で描いたクラウンの「笑い」を完成しているというシーン(ジョーカーの誕生)は、それがいかに自己演出だとしても、能動的なニヒリズムの段階を完了し、自己を超えることへと一歩踏み出している図に見える(舞踊、軽やかさ、笑い)。だが、アーサーは果たして、暴徒と化した群衆たちの熱狂的な支持を、この偶然のサイコロの一振りを必然として受け入れることができるのか、偶然事と偶然の必然化を肯定できるのか? 群衆に伝播したのは、たんに「復讐の精神」の増殖だったのに。
『アンブレイカブル』と心理学化
『アンブレイカブル』(2000)予告編
(1)『ジョーカー』はそれほどできの良い映画とは言えないが、今この文脈で特にその欠点をあげれば、あまりに実存を心理学化しすぎていることだろう。ドゥルーズが何度となく強調するように、実存は心理学のカテゴリーではない。この映画は、道徳による実存の心理学化のカラクリを暴露するまでには至っていない。それどころか、情動の変化が心理的リアリズムで描かれていることによって、実存的苦悩が異常心理の紋切り型に近くなってしまうのだ。
(2)同様のことが、すでにM・ナイト・シャマラン監督の『アンブレイカブル』(2000)にも見られる。自分が不死身であることに気づき、やがて自警団的な救済の任務に目覚めるまでの主人公デヴィッド(ブルース・ウィリス)の実存的な葛藤は、実に陰鬱な気分として描かれていて、主人公を単なる優柔不断なスーパーヒーローに見せてしまうことを否めない。
(3)けっきょく、妻と息子と和解して家庭の中でも健全な父に戻ろうとする主人公は、もはやいかなる意味でも〈超人〉ではないが、その撤退を決して許さないと考えるのは、不死身の者を見出すためだけにテロを起こし続けていた悪魔的なイライジャ(サミュエル・L・ジャクソン)の方だ。ガラスのような繊細な身体しかなく(「Mr.ガラス」)、歩行すらままならないイライジャは、自分の対極にある〈超人〉を探し求めるのであり、その意図を汲めば、現代的なツァラトゥストラの姿なのかもしれない。だが、〈超人〉はどこにもおらず、導き手自身が病んでいる。
『パフューム ある人殺しの物語』と八つ裂きの身体
『パフューム ある人殺しの物語』(2006)予告編
(1)ニーチェの〈超人〉の原型的なイメージは、やはり『悲劇の誕生』以来お馴染みのディオニソスである。酒神で放浪と狂乱の神であるディオニソス。トム・ティクヴァ監督『パフューム ある人殺しの物語』(2006)の主人公は、いくばくかディオニソスの面影を留めている。
(2)ジャン=バティスト・グルヌイユ(ベン・ウィショー)は18世紀のパリの悪臭が充満する市場で産み落とされた、嗅覚の天才である。長じて調香師となり、香水作りのメッカであるグラースで匂いを脂に移す「冷浸法」を習得する。それは、かつてパリの街でその匂いに惹かれ、誤って殺してしまった少女の体臭を再現したいがためであった。グルヌイユは、乙女の体臭を保存し、究極の香水を作ることに没頭してゆく。その過程で次々と乙女たちをさらい、殺害することに手を染める。完成間近の香水に必要な一人を貴族の一人娘ローラと狙い定め、まんまと目的を遂げると、抵抗することなく警吏の手にかかる。人々はグルヌイユの処刑を心待ちする。
(3)刑場に現れたのは、前日死刑を言い渡されたみすぼらしい人殺しの姿ではなく、貴族が着る青い上着をまとった男であり、グルヌイユが脇を通るそばから、その神々しい香りに人々は一瞬にして魅入られる。死刑台に登り、処刑人に対すると、処刑人はひざまずいて「この男は無罪だ(無垢だ)」と叫ぶ。グルヌイユは舞台のオペラ歌手のようなお辞儀をし、歓声を上げる大衆を指揮するような振る舞いに及ぶ。そして、人々に向けて香水の染み込んだハンカチを優雅に投げ入れると、広場の群衆はすぐさま衣服を脱ぎ始め、集団的な乱交を始める。まさにオージーを司る神であるディオニュソス。
(4)主人公は最後のシーンで、狂おしい香りをもとめて集まるパリの貧民窟の群衆に捕まり、引き裂かれ、その肉を食われ、跡形もなく消滅してしまう。これは、オルペウス教に伝わる伝承、八つ裂きにされるディオニソス(もとはザグレウス)の真骨頂である。消滅する〈超人〉の行為の断片、〈超人〉の肉片のみを映像は表現して終わる。これは正しい。ディオニュソスの八つ裂きは、一が多に変化することを肯定するにすぎないから、失われた一へのノスタルジアなどとは全く無縁である。過去の状態との決別、二度と元へ戻らないこと、失踪と消滅が〈超人〉の適所なのである。
文献一覧
ニーチェ『ツァラトゥストラ(上)』(丘沢静也訳)、光文社新訳文庫、2010年
ニーチェ『ツァラトゥストラ(下)』(丘沢静也訳)、光文社新訳文庫、2011年
ジル・ドゥルーズ『ニーチェ』(湯浅博雄訳)、ちくま学芸文庫、1998年
ジル・ドゥルーズ『ニーチェと哲学』(江川隆男訳)、河出文庫、2008年
呉茂一『ギリシア神話(上)』新潮文庫、2007年
田辺秋守プロフィール

(C)Cinemarche
日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。
早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。
著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。
『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。