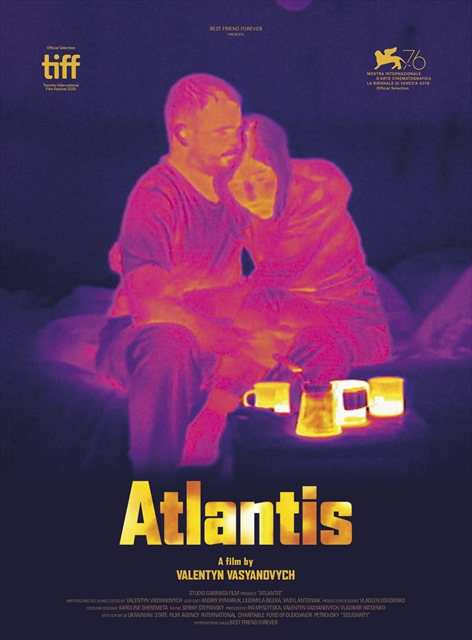第32回東京国際映画祭・コンペティション部門『湖上のリンゴ』
2019年にて32回目を迎える東京国際映画祭。令和初となる本映画祭が2019年10月28日(月)に開会され、11月5日(火)までの10日間をかけて開催されました。

(C)Cinemarche
この映画祭の最大の見せ場となる「コンペティション」部門。今回も世界から秀作が集まり、それぞれの個性を生かした衝撃的かつ感動的な作品が披露されました。
その一本として、トルコのレイス・チェリッキ監督による映画『湖上のリンゴ』が上映されました。作品は本映画祭で審査員特別賞を獲得しました。
会場には来日ゲストとしてレイス監督が来日、映画上映後に来場者に向けたQ&Aもおこなわれました。
映画『湖上のリンゴ』の作品情報

(C)Kaz Film
【上映】
2019年(トルコ映画)
【英題】
Food for a Funeral[Aşık]
【監督】
レイス・チェリッキ
【キャスト】
タクハン・オマロフ、ズィエティン・アリエフ、マリアム・ブトゥリシュヴィリ、シラン・デュズタバン、アルタ・チャヴダル、ディラン・エズキ・アクスト
【作品概要】
1960年代のトルコを舞台に、アシークと呼ばれる民族音楽の歌い手を目指す一人の少年の青春を、彼を取り巻く人たちとの生活を通して描きます。2012年に発表した映画『沈黙の夜』でTIFFにて最優秀アジア映画賞を受賞したレイス・チェリッキ監督が本作を手がけました。本作は7年ぶりの長編となります。
レイス・チェリッキ監督のプロフィール
1961年生まれ、トルコ・東アナトリア地方のアルダハン出身。
中学校卒業後にイスタンブールに移り、国立音楽学校で音楽と演技を修了した後の82年に報道の世界に入り、政治経済記者として複数の国内紙で活動を展開します。以後映画監督を志し、2005年に発表した『頑固者たちの物語』は福岡国際映画祭に出品。2012年発表の『沈黙の夜』はTIFFのほかにベルリンの映画祭でも受賞を果たしました。
映画『湖上のリンゴ』のあらすじ

(C)Kaz Film
1960年代、干ばつに苦しむトルコのアナトリア北東部に住む少年ムスタファは、アシークと呼ばれる民族音楽の歌い手を志しつつも、師匠であるズィエティン親方の厳しい指導にはうんざりしていました。
その一方で、村の一人の少女に恋するムスタファ。親方のお供として演奏の旅に出ることが決まったある日、ムスタファは彼女からお土産としてリンゴを持ち帰ることを約束させられます。その後、どんな運命が彼らを待ち受けているかも知らず…。
映画『湖上のリンゴ』の感想と評価

(C)Kaz Film
本作『湖上のリンゴ』を描いた監督レイス・チェリッキの“人となりが見えてくる”、そんな品格のある作品であります。
決して裕福に満たされた地ではない、そんな場所で古くから存在する歌い手という職を志す少年、ムスタファ。物語はこのムスタファにまつわる話で展開していきます。
師匠の教えをなかなか理解できずやりきれない毎日でありますが、師匠の歌う姿、また別の地域で同じくアシークという立場にいる吟遊詩人の歌を聴いてさまざまな影響を受け、そして心動かされていく。その一方で、自身の生活にも目まぐるしい変化があらわれていきます。
人とのつながりもずっと同じというわけにはいきませんが、なかなかその事実を受け入れることができず、ムスタファ自身の中にもいろいろな感情が沸き立ちます。
その感情は、物語の背景となるトルコとジョージアの国境線の町に見られるボーダレスな環境と、のどかで雄大な風景とは対照的でもありながら、観ていると心を揺さぶられ、どこか落ち着きたくなるような気持ちにもさせられます。
それはQ&Aでレイス監督が述べられていることにもつながるようで、忘れてはいけない、壊してはならないようなものがあることを考えさせてくれるからでしょう。
上映後のレイス・チェリッキ監督 Q&A

(C)Cinemarche
上演時にはレイス・チェリッキ監督がプロデューサーのディレキ・アイドゥンとともに登場、舞台挨拶をおこなうとともに、会場に訪れた観衆からのQ&Aに応じました。
──今回の作品ではレイス監督さんが出身地で撮影をされたというところがユニークに感じられました。この撮影に至った経緯をお話しいただけますか?
レイス・チェリッキ(以下、レイス):この世にはさまざまな生きとし生きけるもの、そして大地というものがあります。そして生きとし生けるものは、いつか再び土地に戻っていくのですが、文化もそうだと思っています。
人間というものは、実際に生きている世界の中でさまざまなことを体験しています。その経緯を通過することで心の中にいろんなものが残り、それを持ち続けていつかは再び大地に戻っていくことになります。
だから私はこの映画を作るときには監督としてではなく、私はストーリーの語り手なのであると自分自身を紹介しています。私はそういう風に生きていかなければならないと思っていますし、だからこそこうして自分が生きた土地、生まれ育った故郷、そこに再び帰っていったのです。
文化もそういうものですから、親身な感情を持って向き合わなければなりません。その意味で、私はただ映画を作るために物事をフォローする、そういったやり方はメンタリティーとしてあまり好きではありません。
──この物語の背景は、展開とともにトルコからジョージアのほうに移っていきますが、その境界線が明確に描かれていません。これはなんらかの意図があってのことなのでしょうか?
レイス:現代の中では境界線というものがあり、これに関わることで多くの問題を起こす人々がいます。だから私はそういうものが嫌いで、境界線というものを使いたくないと思っていました。
例えばグルジアとトルコの間は、どちらも行き来できるようになっています。トルコ人もジョージアに住んでいますし、トルコにジョージアの人も住んでいます。そしてジョージアにおいてはトルコ語も話されているし、クルド語も話されています。
こういった人たちの間での行き来というのは、実際にあることなんです。共通する言語という文化、それによって一つのパイが作りあげられているのだと私は考えています。
映画の中でジョージア語を話している場面もありますが、それを私たちはトルコ語にも訳していますし、理解もできます。実はそれはまったく自由なことではありませんが、「人間を人間にするもの」、それは話すことであると思っています。だから私たちは話をする必要があると考えるのです。
──現地の人は、両方の言葉を使われているのでしょうか?またアシークと呼ばれる人は、トルコにもジョージアにもいるのでしょうか?
レイス:国境地域のところに住んでおられる方はそうですね。私が生まれ育った町は国境に近いところで、その人口の大部分の人々は相手側の言葉を理解することができます。
ジョージアのほうではトルコ系イスラム教徒の人も暮らしていますし、一方でトルコにはジョージア系の方も住んでいます。お互いに話し合いもしていますし、行き来もあります。またアシークという存在も、両方の場所にいます。
ちなみに私のファミリーの中には非常に多くの文化が混じっていて、トルコ、グルジア、ジョージア系といろんな文化が混在しています。
──「Food for Funeral」という英題にも関係していると思いますが、赤いリンゴにはなにかを象徴するイメージがあるのでしょうか?
レイス:リンゴは例えば常に人間が始まるとき、創世記のアダムとイブの話などに元づき、どんな風に人々が始まっていくか、ということの概念のメタファーとしてよく使われます。
つまりはその罪、そして善意、そして実なるもの、そういったものの成り立ちを象徴するのに使われています。
この映画のタイトル「Food for Funeral」ですが、この名前を付けた理由は私自身の恩師に由来します。私が子供のころに村で教えをいただいた先生で、その後に偉大な作家になられた方がいます。たくさん本を書いておられて、この題はその人の作品の、題名の一つなんです。
実はその人と私は約束をしていました。それはいつかその先生の本からインスピレーションをいただき、私がお話を作りあげるということで、本作ではその約束をかなえたことになりました。ドゥルスン・アクチャンという作家の方です。

(C)Cinemarche
──ディレキさんが今作をプロデュースしようとしたきっかけは、どのようなものだったのでしょうか?
ディレキ・アイドゥン:私は若い世代のプロデューサーの一人であり、普段はできるだけコンテンポラリ、モダンでそして都会的なものを作っています。というのも、田舎を描いたものはすでに多く存在していますので。しかし本作の脚本には非常に感銘を受けました。今までの似たように見える作品とは全く違って非常に詩的な部分があると思いました。
この失われつつある文化、技術、歌い方というものがあるという現実を知りませんでしたが、これはまだ今も存在するものであり、是非とも人々にこういった文化を伝えたいと思ったのが、今回プロデュースをおこなったきっかけであります。
まとめ

(C)Cinemarche
物語は氷が張り詰めた湖の風景から始まります。その氷の上を歩く人たち。その上で彼らは、一つの食べかけたリンゴを見つけます。
誰がこのリンゴを食べたのか?このリンゴは、どのような経緯でここにたどり着いたのか?物語はその顛末を描くわけですが、そこにこの物語で表される普遍性、そして無くしてはならないと強く訴えるものが描き込まれているようでもあります。
素朴なアナトリアの風景、そこに住む人たちそれぞれの生きる道。のんびりと進んでいるように見えて、実はいろんな心の動きがある。
あたりまえのように現代の文化、発展で明らかにされたはずのすべての中に、実はまだわかっていなかった一面があった、そんな風に心に強く印象付けられるものを見出せる作品であります。