講義「映画と哲学」第5講
日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。
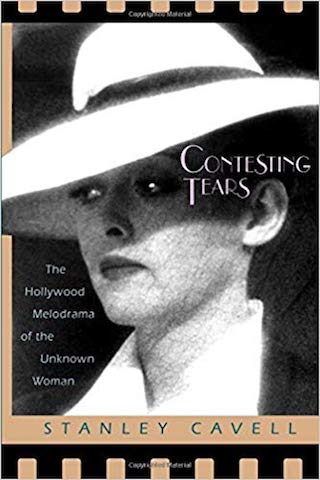
Stanley Cavell, Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman, The University of Chicago
第5講では、スタンリー・カヴェルの「再婚喜劇」論に基づき、いくつかの実例を題材としながらも、コメディ映画の一ジャンル「ロマンティック・コメディ」における行為について考察をしてゆきます。
CONTENTS
ロマンティック・コメディと結婚
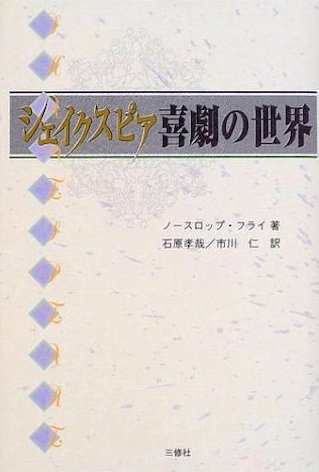
ノースロップ・フライ『シェイクスピア喜劇の世界』(石原孝哉、市川仁訳、三修社、2001年)
コメディ映画には、スラプスティックに始まり、スクリューボール・コメディ、ロマンティック・コメディ、風刺コメディ、風俗喜劇、シチュエーション・コメディ(シットコム)、人情喜劇、不条理コメディ、ブラックコメディと様々なジャンルがあるが(たいていはそれらの混合である)、今回はジャンルに即した身振りから喜劇的な行為にアプローチしてみたい。
「結婚は喜劇的な行為である」、と言ったら失笑を買うだろうか。しかし、あるコメディ・ジャンルの世界では、結婚をめぐるあれこれは、いつも喜劇的な行為の連続である。そのジャンルとは、スクリューボール・コメディ(変人コメディ)という名とともに始まり、いまではロマンティック・コメディとして世界中で見られているコメディ映画のことである。
スタンリー・カヴェルのジャンル論
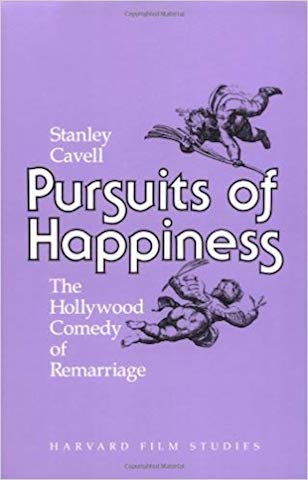
Stanley Cavell, Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage, Havard University
スタンリー・カヴェル(1926-2018)が昨年亡くなった。カヴェルの名は、今でも、かなり異色な日常言語学派の哲学者という像と、英語圏での「映画の哲学」の最高峰という像とで分裂している(前者の紹介が日本ではほとんどない。いずれカヴェルについては詳しく論じるつもり)。その「映画の哲学者」カヴェルがロマンティック・コメディについて非常に独創的な見解を述べている。もともとロマンティック・コメディには結婚が主題になる映画が多いのだが、カヴェルはむしろそこに「再婚」というテーマを見出そうとする。話の出発点はシェイクスピアの喜劇に遡る。
シェイクスピアの喜劇/ロマンス劇の精髄が生き残っているのが近代のオペラであるというノースロップ・フライの見解を介して、カヴェルはさらにこの伝統が映画の二大ジャンル、すなわちロマンティック・コメディとメロドラマに受け継がれていると考えている。そこには、カヴェルの二冊のジャンル論がある。『幸福の追求――ハリウッドの再婚喜劇』(1981)と『抗議の涙――ハリウッドの知られざる女のメロドラマ』(1996)である。
カヴェルの『幸福の追求』は、映画史に通じている者にとっては、なるほどハリウッドのロマンティック・コメディ(スクリューボール・コメディ)のなかに「再婚喜劇」というサブジャンルを読み込む試みだと思われるかもしれない。しかし、「再婚喜劇」はそれ自体が独自のジャンルなのである。同様に『抗議の涙』は、「知られざる女のメロドラマ」というジャンルの研究なのだ。ただし、カヴェルにすれば「再婚喜劇」と「知られざる女のメロドラマ」を補い合うものとして見なければならない。それはなぜか。カヴェルはその理由を次のように述べている。
「私がこれまでに練り上げてきた考えでは、映画の主題は──映画のなかの二つのジャンルである「コメディ」と「メロドラマ」から判断するならば──、女性の創造であり、教育を受けたい、自らの物語に声をもたせたいという女性の要求である(あるいは、かつてはそうであった)。それを結婚の可能性という形で描くのがコメディである。結婚という選択肢を拒否する形で描くのがメロドラマである」(『哲学の〈声〉』216頁)。ここでカヴェルが単にコメディといっているものは、「再婚喜劇」のことである。
カヴェルが『幸福の追求』のなかで「再婚喜劇」として詳細に分析している作品は、順に『レディ・イヴ』(1941)、『或る夜の出来事』(1934)、『赤ちゃん教育』(1938)、『フィラデルフィア物語』(1940)、『ヒズ・ガール・フライデー』(1940)、『アダム氏とマダム』(1949)、『新婚道中記』(1937)の七本である。カヴェルによれば、「再婚喜劇」とはおおよそ次のようなものである。
「再婚喜劇」というジャンルの規定
(1)再婚喜劇の作品群のなかでヒロインは、いったんは別れてしまったパートナーと必ず(広い意味での)再婚を果たす。「再婚」とは同じパートナーとの二度目の結婚のことである。この再婚はヘーゲル/フロイト的な意味での二度目である。つまり本当に正しい「知」とは二度目に再認することであること、この再認こそがヒロインにパートナー(配偶者)との関係が適正なものなのだという自覚を与えてくれる。
(2)再婚喜劇は、シェイクスピア喜劇が発見し先取りしたものの継承である。シェイクスピアではまだ男性主人公の視点が優位だったが、ロマンティック・コメディではそれがヒロインに移っている。再婚喜劇は、ロマンティック・コメディを女性の視点から捉え直すことを主眼としている。
(3)シェイクスピア喜劇では、男性主人公にとっての障害は、口うるさい父親や不公平な法律なのだが、再婚喜劇においては、ヒロインの父親は出しゃばることなく、ヒロインの欲望の側に加担する。ヒロインの夫に対しても好意的な感情をもつ。
(4)それに対して、ヒロインの母親は不在であるか、ほとんど存在感がない。それと関係するが、ヒロイン自身が母であるケースもない。カップルの間に子供はない。子供の存在によって離婚が別の意味を持ってくるのを避けるかのように。ヒロインは、まだ成長しきれていない子供という位置にいる。
(5)カヴェルの主要な哲学的な問題設定は、デカルトに生じた近代的な「懐疑主義」の克服である。それをデカルトに先んじて演劇の形で表現していたのが、シェイクスピアであった。再婚喜劇は、映画という独自な表現で、この「懐疑主義」の克服や乗り越えを、他人同士の結びつきである結婚/再婚に求めようとする。
(6)エマソンやソローの思想的遺産を受け継ごうとするカヴェルからすると、超越主義(transcendentalism)とは決して形而上学的な外部を設定するものではない。結婚の成就とは、超越性などない有限な人生をかろうじて全うする一つのやり方である。それゆえ、「再婚」は現世における「死と再生のプロセス」を象徴するものである。
結婚式と戯れる:花嫁が逃げる/花嫁を奪う
参考映像:フランク・キャプラ監督『或る夜の出来事』(1934)
当然のことながら、再婚喜劇で要となるのは、結婚・離婚・再婚に際して登場人物のとる行為である。それが最も目立った行為として示されるのは、結婚式においてだ。
カヴェルが取り上げる「再婚喜劇」で結婚式の儀礼をまんまと踏みにじるのは、『或る夜の出来事』(1934)が最初である。結婚式当日、内心、変わり者の新聞記者(クラーク・ゲーブル)のことを想い続けている資産家の娘(クローデット・コルベール)は戸惑いを隠せず、父親も浮かない顔をしている。すでに新聞記者の人柄に好感を持ってしまい、冒険飛行家との婚約を破棄すべきだと焚きつけているのは、父親本人だからだ。「異議ある者は申し出よ」という神父の言葉に、つい口を開きそうになる。次の瞬間、じゃじゃ馬娘が豪華な野外式場から駆け出して行ってしまうのを見送る。ここでは真に喜劇的な身振りは父親にある。騒然とする人々の間にあって父親はひとりニンマリと笑う。
一方、結婚式場から「花嫁を奪う」という行為も、すでにトーキー以前から目にする事ができる。『キートンの恋愛三代記』(1923)の現代編で、キートンは恋のライバルが指名手配の重婚者であることをたまたま警察署で発見し、急ぎ結婚式場に駆けつける。いまや神父が二人に誓いの言葉を促さんとするときに、最前列に座っていたキートンが花嫁を奪う。二人は出口に反対向きに止めてあった二台の自動車のうち、手前の方から乗り込んで、奥の車に移り、追っ手とは逆方向にあっという間に逃走する。以後、ハリウッドでは花嫁が逃げ出したり、略奪されたりするという不埒な行為が横行する。ゲーリー・マーシャル監督『プリティ・ブライド』(1999 原題 Runaway Bride)では、ジュリア・ロバーツが4回も結婚式場から逃げ出す。逃げ出すこと自体ががメタ的に取り上げられるまでになった。
『レディ・イヴ』とシェイクスピア喜劇の身振り
参考映像:プレストン・スタージェス監督『レディ・イヴ』(1941)
プレストン・スタージェス監督の『レディ・イヴ』が「再婚喜劇」のなかでもひときわ目を引くのは、シェイクスピア喜劇との繋がりの強さである。シェイクスピア喜劇に頻繁に登場する身振りにいわゆる「マスカレード」がある。文字通りに「仮面舞踏会」で仮面をかぶって、自分の素性を隠すという意味ではなく、要所要所で仮装して別人になりすますことだ(『じゃじゃ馬馴らし』『ヴェニスの商人』『お気に召すまま』など)。これと似ているのが、双子が登場するプロットである。あるいは双子の設定で戯れる事である(『間違いの喜劇』『十二夜』)。二人の役者によって演じられる双子という舞台の設定では、現代的なリアリズムの感覚ではとても納得できないが、二人は識別がつかないことになっている。一方、映画では一人二役によって、絶対的な類似性を保つことができるにもかかわらず、二人の識別はできる。『レディ・イヴ』ではこれが驚くような描き方がなされている。
ビール会社の御曹司(ヘンリー・フォンダ)が、アマゾンからアメリカへの帰途、船上で女詐欺師(ババーラ・スタンウィック)の罠にまんまと落ちて彼女に恋をする。しかし、すんでのところで従者が持ってきた情報で彼女の正体を知り、求婚を取りやめる。ヒロインは失意から一転復讐に燃え、今度はイギリス人の令嬢になりすましコネティカットにある御曹司の邸宅に乗り込む。しかし、下手なイギリス発音以外は、全く以前のままの姿で現れる。御曹司は、自分を騙そうとするなら、少しは変装するだろうと考え、彼女は女詐欺師によく似ているが全く別人だと思ってすぐに魅了される。ところが、今度は新婚のハネムーンに夜行列車のなかで聞かされた数々の男性遍歴に嫌気がさして、勝手に列車を降りてしまう(ヒロインの復讐の完成)。
再度心変わりしたヒロインは、ラストで、元のキャラクターに戻って最初の出会いの時のシチュエーションを再現して、あまりにも強引なやり直しを敢行する。この時ヒーローはヒロインが一人で演じてきた二役が、あくまでも別人だという反応を示してヒロインを抱擁する。「部屋には入れない、僕は結婚してるんだ」、「わたしもよ、わたしも結婚してるの」というやり取りのバカバカしさ。この「再会」の回りくどさを、ヒーローの無頓着な性格だけに帰すべきではないだろう。どう考えても、シェイクスピア演劇の約定「同一のものを違うものとみよ」(変装=分身)、また「違うものを瓜二つとみよ」(双子=分身)と戯れているとしか思えない。そして、まさにカヴェルが指摘しているのは、一連の「再婚喜劇」が女性のアイデンティティの確立を、分身や分裂を通じて描いているということなのだ。
余談だが、プレストン・スタージェスはこの後、『パームビーチ・ストーリー(結婚五年目)』(1942)で、さらにひねりを加えた分身ネタを炸裂させる。奇妙な四角関係を解消して、元の鞘に納まることになったカップル二人が、映画のラストで、自分たちにはそれぞれ双子がいると突然言い出し、クローン人間のような男女の双子2人を含めて、6人で3組の合同カップルを作ってしまう。ラストで6人が一列に並ぶショットの空恐ろしさ。
再婚喜劇としての『最高殊勲夫人』
増村保造監督『最高殊勲夫人』(1959)

©︎角川ヘラルド映画
カヴェルには眼中にもないだろうが、ひねりの効いた再婚喜劇は日本映画にもある。1959年に公開された、増村保造監督の『最高殊勲夫人』は源氏鶏太の原作ながら、棹さしているのは明らかにハリウッドのロマンティック・コメディの流れだ。それというのも、三原家・野々宮家、両家の長男-長女、次男-次女に次いで、三男-三女のカップルとなってしまった川口浩と若尾文子が、結婚式を挙行するのが、映画のラストで見られる。ここには、三男-三女のカップルの未来が、次男-次女の馴致の過程、長男-長女の倦怠期の過程としてすでに目の前に見えているという秀逸なアイデアがある。この映画では、再婚するのは同じカップルではない。反復的に両家で結婚を繰り返す「家」なのだ。したがって、本来個人の再認識となるはずのものも、「家」の認識にしかならない。
されど再婚喜劇は続く
参考映像:マイク・ニコルズ監督『卒業』(1967)
カヴェルはベルイマンの『夏の夜は三たび微笑む』(1955)や、ジャン・ルノワールの『ゲームの規則』(1939)、やや曖昧ではあるがロベール・ブレッソンの『ブローニュの森の貴婦人たち』(1944)などのヨーロッパ映画にも「再婚喜劇」が見出されると言っている。カヴェルが見出した「再婚喜劇」というジャンルは、今もなお連綿と続いている。女性の声が抑圧されることなく、女性のアイデンティティが確立されている場所などどこにもないのだから。しかし、果たして男性にはその場所があるのか。ロマンティック・コメディにとって試練の60年代に、男性主人公に向けてすぐさま投げ返される問いである。
マイク・ニコルズ監督『卒業』(1967)の教会のシーンとそれに続くバスの駆け落ちのシーンは、のちに振り返ってロマンティック・コメディに生じた数々のひび割れの始まりだった。人はそれを称して、やがてウディ・アレンの『アニー・ホール』(1977)に至りつく「ラディカル・ロマンティック・コメディ」の嚆矢だと言う。ヒロインの母親が不在どころか、まずヒーローが性の手ほどきを受けるのが、ヒロインの母親だというだけで場外スレスレだが、バスの中で見せるカップルの不安の表情は、再婚喜劇に再び生じた現代的な「懐疑」の一種である。結婚による結びつきを保証するのは、果たして本当に「再会」だけでよいのか。時期尚早な、未熟な再婚というものがあるのではないか。『卒業』に始まるのは、魔術的なハッピーエンディングによって隠されてきたロマンティック・ラブ・イデオロギーの暴露だ。
ハリウッド製ではないイギリス映画『フォーウェディング』(1994)は、正確には四つの結婚式に一つの葬式が加わることによって、ある意味でカヴェルのいう「死と再生のプロセス」を更新している。しかも、死者を衷心から弔うのが、ゲイカップルのひとり取り残されたパートナーだというところに、今後ロマンティック・コメディの主戦場が、男女のセックス・ウォーズだけでなく、異性愛的ではないトラブルが加わるであろうことが予期された映画である。ハリウッド再婚喜劇の異性愛主義に対する軽い批判とみなせるだろう。
「離婚喜劇」?
参考映像:コーエン兄弟『ディボース・ショウ』(2003)
コーエン兄弟がスクリューボール・コメディをパロディ的に復活させようとして撮った『ディボース・ショウ』(2003)は、ストーリー的には「再婚喜劇」に該当するようでいて、その精神ははるかにシニカルだ。男性主人公がやり手の離婚専門弁護士で、その訴訟相手がやはり名うての富豪狙いの美人妻。設定は、なにやら法廷での争いを男女の駆け引きの場とするジョージ・キューカーの『アダム氏とマダム』を思わせるのだが、愛の駆け引きというよりは、結婚と離婚から生ずる利益配分を争う功利主義的な喜劇であるこの作品は、むしろ「離婚喜劇」(comedy of divorce)ともいうべき黒いジャンルなのではないか。ジョージ・クルーニーとキャサリン・ゼタ=ジョーンズの二人のやりとりは、面白くないわけではないが、スクリューボール・コメディが当初もっていた「無邪気な大人」の童心はひとかけらもなく、ポストモダン的な二次使用の狡猾さに満ちている。もっとも、振り返ればロマンティック・コメディ自体がシェイクスピア喜劇の二次使用なのだった。
文献一覧
ノースロップ・フライ『シェイクスピア喜劇の世界』石原孝哉、市川仁訳、三修社、2001年
Stanley Cavell, Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage, Havard University Press, 1981.
Stanley Cavell, Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman, The University of Chicago, 1996.
スタンリー・カヴェル『哲学の〈声〉 デリダのオースティン批判論駁』中川雄一訳、春秋社、2008年
田辺秋守プロフィール

©︎Cinemarche
日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。
早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。
著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。
『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。



































