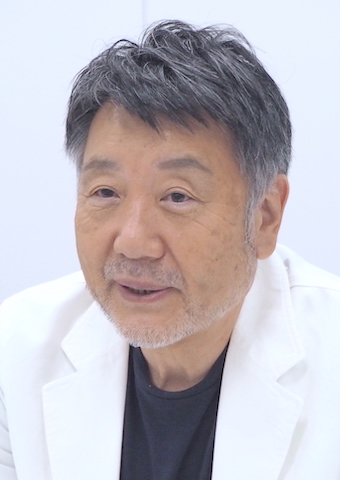Cinemarcheにて独占配信される、映画監督・細野辰興の書き下ろし連載小説、戯作評伝『スタニスラフスキー探偵団〜日本俠客伝・外伝〜』。

©︎ Cinemarche
細野辰興監督は『シャブ極道』『竜二 Forever』『貌斬り KAOKIRI〜戯曲「スタニスラフスキー探偵団」より』といった代表作で骨太な世界観を基調に現代の歪みを映画で問い続けています。
連載に先立ち、小説を執筆中の細野辰興監督に、小説についてお話を伺いました。
映画と小説

『貌斬り KAOKIRI〜戯曲「スタニスラフスキー探偵団」より』(C)2015 Tatsuoki Hosono/Keiko Kusakabe/Tadahito Sugiyama/Office Keel
──小説と映画の脚本の違いはありますか?
細野辰興(以下、細野):全然違いますよ。人に読んでもらうことを前提に書くのは初めてですから。改めて本腰入れて小説や文学のことを探っています。
小説は映画よりも内容と方法論が、もっと濃密な関係にならなければいけない。なれるんだなと実感していますね。
──濃密というのは?
細野:レトリック(*表現巧みな言葉)っていう意味合いじゃなくて、作者がいて、語り手がいて、主人公がいるっていうことです。小説の中には、この3つの要素がいるっていうこと。
作者はもちろん僕なわけだけれども、語り手を誰にするのか、それと主人公を誰にするのか、この3つは物凄く重要なわけ。その部分が映画とはちょっと違うんですね。
映画は監督、原作、脚本があって主人公がいて、対立する相手、そういうのもなければいけない、それで出来ちゃう。
でも小説の場合は作者がいて「語り手」がいる。そこを誰にするのかが重要ですね。もちろん語り手と主人公が一緒っていう場合もありますけど。
例えば「坊っちゃん」は夏目漱石が「作者」で、「語り手」と「主人公」が坊ちゃん。でも漱石は坊ちゃんに自身を託してるところはあっても100%坊っちゃんではないよなと、みんな思って読むわけじゃないですか。どこからどこまでが漱石なんだと。
だから、そこの部分の面白さ。多重構造的なものがあって、もう一つその先に行けるのかもしれないなと。
「語り手」は細野辰興ではなく、「主人公」は『スタニスラフスキー探偵団~日本侠客伝・外伝』作・演出の細野監督。語り手は、回を追うごとにわかるようにするっていう形にしようかなと考えています。
──多重構造のつくりは監督の映画でもみられます。
細野:僕の映画の『貌斬り KAOKIRI 戯曲「スタニスラフスキー探偵団」より』や『竜二 Forever』には「入れ子」、つまり「メタフィルム」っていう手法を用いてる。
それを僕は「二重構造」とか「多重構造」と呼んでるんだけど、何故か、この構造が好きで、それをはっきり打ち出したのが『竜二 Forever』っていう映画なわけです。
俳優・金子正次の『竜二』っていう映画があって、それを作った人たちの話なんだけど、その中で金子さんの私生活を描かなくてはいけない。
金子さんはもう亡くなってる訳だから、調べることは出来るけど、本人に話を訊く訳にはいかない。だから周辺取材しか出来ない。そんなことから始まったんですね。
それで私生活を描くってなった時に二重構造という形で作っていこうかなと思ったわけです。
『貌斬り』なんていうのは、映画としてそれが一番表立って出てるんじゃないですかね。
今回の小説では、その『貌斬り』にも出てくる『スタニスラフスキー探偵団』という、僕が書いた映画の中の劇中舞台になっている戯曲、そもそもその戯曲の構成が多重構造という、その第2弾シリーズとして考えていて、その舞台の評伝をしていくというね。ややっこしいね、そこからして二重構造になってるっていう(笑) 。
──小説にも登場する劇中劇『スタニスラフスキー探偵団 日本侠客伝・外伝』の戯曲も同時に執筆しているんですね。
細野:かっこよく言えばね。それは離れた作品じゃないんで、それがなきゃ小説を書けないから。
戯曲のパートの方もだいぶ固まってはきていますよ。
中村錦之助と高倉健

© 東映
──映画『日本侠客伝』にポイントをおいた理由は?
細野:初代・中村錦之助を描くためですね。僕の生涯のベスト・ワン、ツウーは錦之助さんの『関の弥太ッぺ』と『宮本武蔵』なんです(笑)。
『日本侠客伝』は歴史的な映画で、トップスター中村錦之助が降板して、高倉健が代わって出るんだけど、当時の高倉健はトップスターではなかった。今となっては高倉健の方が有名になっちゃってますけど。
今、10人に中村錦之助を知ってるか訊いても殆どの人が知らない。萬屋錦之介に名前を変えたってこともあるけど、高倉健はみんな知ってますよね。
ウチ(日本映画大学)の学生なんかも授業でたまに訊くと、中村錦之助って言っても誰も知らない。当たり前ですよね。高倉健がヤクザ映画に出演していたことすら知らないんですから。
でもね、錦之助の『宮本武蔵五部作』で高倉健は佐々木小次郎ですからね。それだけでも当時の二人の位置関係が判るじゃないですか。
中村錦之助と高倉健にはいくつか共通点があって、一つは東映の子飼いだったんですよ。東映ではじめて映画に出て、錦之助はその前に松竹で2本出てるけど、スターになってって、やがて東映を出て行くっていうね。健さんもそう。
違いは中村錦之助は歌舞伎出身で、高倉健は明治大学の学生ということ。それがあって、時代劇全盛期に中村錦之助はあっという間にトップスターになっちゃうわけです。
中村錦之助は10年間東映時代劇のトップスターで突っ走ってきて、人気があっただけでなくて名実共に凄い名作をいっぱい残している。挙げればもうキリがないくらいですよ。
そんな中、時代劇がだんだん衰退していって、お客が入んなくなってくるんですね。時代劇だけじゃないんだけど本当は。
緻密に言うと映画人口が一気に下がっていく時だった。『日本侠客伝』が公開された昭和39年の時は、昭和33年に11億2千万人いた観客動員数が、もう半分以下になっちゃった。
昭和39年までには美智子さまと今の平成天皇の結婚式があったり、来たるオリンピック歓迎ブームでカラーテレビが普及して、もう二段打ちで半分以下になったんじゃないですかね。
東映は時代劇を中心にやってきた会社で、お金のかけ方も違う。でも、段々と客が入らなくなってきた。
そこに、皆さんご存知の黒澤明の『用心棒』が昭和36年に出てきて、東映だけでなく既成の時代劇が瓦解していくっていうね。
ダメ押しで翌年には『椿三十郎』が出て、この2本で東映や大映の時代劇なんて、こんなの嘘じゃんみたくなっちゃう。
僕が『貌斬りKAOKIRI~』でモデルにした天下の大スター長谷川一夫が映画界から引退したのもこの頃ですから。
だから、不特定多数の人に観てもらう、家族で観る明るく楽しい東映映画が中心だったのが、そうではなくなってくるんです。
そんな時期に、もう少しいろんなことがあるんだけど、任侠映画が一本当たっちゃったんですよ。『人生劇場 飛車角』が。
それでシフトが少しづつ時代劇映画から任侠映画に移ってきちゃう。トップスター錦之助にももちろん主演で出てくれと『日本侠客伝』の話がきた。
錦之助としては当時、色々な意味で大変だった。まず何が大変だったといえば、時代劇の本数が少なくなってくるし、自分の作品も昔ほどお客が入んなくなってきて、どうもシフトが任侠映画に移りつつある。
といっても、その時の任侠映画はまだ大泉、東京で作っていただけ。本当の東映の本拠地は時代劇だから京都の太秦なんですよね。
その太秦で任侠映画が作られるようになるかならないかっていうのが、一つのターニングポイントになってくるんですよ。

『関の弥太ッぺ』© 東映
時代劇の金看板、中村錦之助がヤクザ映画『日本侠客伝』の主演を受けるか受けないかが大きなドラマのポイントで、結果、簡単に言えば受けないで可愛がっていた高倉健に譲るわけです。
高倉健はその頃はまだトップスターじゃなかったけど、『日本侠客伝』は錦之助用に作った企画だから製作費もあるし脚本もいい。
ほぼ錦之助に当て書きしてあってオールスター作品で、公開する時期もいい時期だったし、思いのほか大ヒットしちゃった。錦之助も特別出演で出るんですけどね。
それから2年後に錦之助は東映を出て行く。
その時には任侠映画がもう全盛期になって、健さんはそのまま任侠映画、ヤクザ映画でいって、ちょうど10年後に東映を出るんだけど、出てまた次の段階にステップアップしていくっていうね。
錦之助さんは東映を出てからは、映画も結構出てたんだけど、だんだんテレビの方になっていって「子連れ狼」とか有名なんだけど、僕なんかから見ると、あれは錦之助じゃないっていうところがあってね。
錦之助がデビューしたのが昭和29年、映画界は上り坂だった。でも皮肉なことにテレビ放送もその前年から始まっている。それで昭和33年で錦之助が年間12本くらい主演映画を撮った時がピークで、そこから一気に落っこっていく。落っこっていく過程で錦之助は東映を去るっていうね。
東映を去るってことは結局は映画界を去るってことですからね。
その悲劇さみたいなものが、一つ、日本映画史に結びついていかないかと考えています。
だから小説で彼をきっちり描くことができれば、ある種、戦後の日本映画史みたいなものを上手く纏められるんじゃないかなという企みではあるんですけどね。
脚本に収まりきらない俳優の演技と魅力

©︎ Cinemarche
──俳優の芝居(演技)にフォーカスを当てて創作するのは今村昌平監督の影響もあるんですか?
細野:今村さんに限らず監督はみんなそうですよ。
今村さんは早稲田で演劇部やってたんですよ。演者として舞台にも立っていたっていうから、芝居の付け方なんか見てるとやっぱりしつこいですよ。
でも僕が出会ったのはもう今村さんが50歳に手が届こうとしてる時だから全盛期じゃないですよね。だから全盛期はもっと大変だったんじゃないかなとは思いますよ。
でも監督って大概芝居にはこだわりますよ。
──演じる上で俳優に求めることは?
細野:細野:予定調和の芝居はいらない。簡単に言えば台本の中でしか芝居が出来ない俳優はダメ。
そうか、そういう表現の仕方もあるのかというものを具体的に見せてくれる俳優、これはもう凄いなあと。
観客が望むものもそうでしょう。まぁそんなとこかな、みたいな芝居されてもしょうがないですよね。
──細野監督の映画は、ある種の「まとめない」力というのを強く感じます。
細野:そういう意味で言うなら、相米慎二さんの現場は刺激的でしたね。めちゃくちゃだもん。
だって何でもかんでもワンシーンワンカットで撮るんだから。要するに、どうなってるか分からない。2分か3分で納めなくちゃいけないシーンなのに、5分以上平気で撮ってるんだから。
それの一番激しかったのが『ションベン・ライダー』って映画でしたね。当時、何やってもいいんだっていうようなアナーキーさは相米さんにありましたよね。
だからあの人は完成度を求めてないっていうことをなんとなく僕は理解していましたね。完成度求めたら昔の監督にかなわないんじゃないかとかね。
製作費も全盛期ほどないし。今はもっとないですけど(笑)。
時代と映画とおふくろさん

©1983 松竹株式会社
細野:相米さんの映画『魚影の群れ』の時にね、僕は就いてなかったんだけど、完成披露試写で相米さんに捕まって「細野悪いけど、おふくろが来るから、ちょっと席の案内してやってくれ」って言われたんですよ。丸の内ピカデリーで。
それで相米さんのお母さんをナビゲートして、観終わってまたタクシーに案内をするところまでやったのかな。
その後で相米さんに『魚影の群れ』お母さん何て言ってましたって訊いたら「言われちゃったよ」って「所詮、お前は(内田)吐夢さんには敵わないね」って(笑)。
これは凄いおふくろさんだなっと思いましたね。だから相米さんの生涯のライバルはもしかしたら内田吐夢監督だったんじゃないかな。
内田吐夢さんの『森と湖のまつり』というアイヌをテーマにした映画を北海道でロケをやっていた時に、子供だった相米さんはロケ撮影を見に行ってるらしいのよ。
そんなこともあってかどうか知らないけど、内田吐夢さんの映画がやっぱり好きだったんじゃないかな。まぁ凄いですからね。そんな事もあってお母さんは『飢餓海峡』と比べたんじゃないのかな。まぁ負けるよな(笑)。それはもうしょうがないですよね。
相米さんの頃には、もう昔のようなシステムで作れなくなってるわけですよ。撮影所にスタッフがいて、俳優がいてと、全て賄えてるというシステムでやってるっていうね、『飢餓海峡』なんかはその中で作られた作品。
だからそこのところをみんな勘違いしてるんですよね。俳優も僕もそうだと思うんですけど。

© 東映
つまり、会社の持ってる力ってやっぱり凄く強くて、例えば東映なら、時代劇の黄金時代が10年間あった。この力って凄いわけですよ。
脚本家から監督から一流どころを全部揃えて、力のある作品がいっぱいある。そういった体制の中で、じゃあこのスターをどうやって育てようとか企画するような人がいっぱいいて、その中で商品という形の作品を作り出してくわけだから、それは凄い総合力ですよ。
その総合力が次に任侠映画、ヤクザ映画を作り出していく、その次に実録ヤクザ映画を作り出してくわけですが、この力を馬鹿にしてはいけないと僕は思いますよ。
そういった人たちが集まって映画が作られてた時代があって、その後、映画の作られ方は変化していく。今はもっと違う形態になってきている。
内田吐夢さんや黒澤明さんがいくら凄いと言っても今の時代ではどうなのかって思いますよね。それは比べようがないし、比べちゃいけないと僕は思うけど、比べるのが人間ですからね。
そんなこともなんとなく気になっていて、今回の小説にもそういうものが滲み出ればいいなと考えてるんですけど、時代性と共にある映画史っていうものを表現するのは難しいですね。そう簡単にはできない。勿論それだけが狙いじゃないから、そんなものも少し滲み出ればいいなと。
まずは、とにかく面白くなきゃいけない。だからその面白さっていうのをどういう風に映画とは違った形で出せるか。
映画と小説も比べようがないけど、面白さが違うとは思うんですよね。
方法論というものがどう面白さに結びつくことができるのかなっていうところが、今楽しいといえば楽しいんだけど、わからない、こればっかりは。大失敗するかもしれないし(笑)。
まとめ

©︎ Cinemarche
映画と小説の異なるストーリーテーリングから、脚本を超えた俳優の演技の魅力。それらを可能にしてきた日本映画の歴史の変遷を大いに語ってくれた映画監督・細野辰興。
新たな試みとなる細野流の小説を執筆するにあたり、膨大なリサーチに時間と労力を惜しまない表現者ならではのひたむきな姿勢が垣間見えます。
また、亡き師匠である相米慎二監督とお母さんのエピソードでは目に涙をにじませながら、貴重な思い出を吐露してくれました。
エンターテイメントの面白さを基軸にした多重構造を用いて、骨太な世界観を映画で問いかけ続けた細野辰興監督は、今度は小説でもひとりの俳優を通して戦後の日本映画史を紐解きます。
壮大な書き下ろし連載小説の一旦を伺い、これからの連載が待ちきれなくなりました。
新たな挑戦に向けられた細野監督の熱い思いと覚悟は、映画監督に留まらず、更に時代と共に進化する表現者の熱量を感じさせてくれます。
それでいながらも自己の創作欲を優先し、時代と共に生きることを拒んだ中村錦之助に焦点を当てる姿勢には、人間を愛おしいと感じる深い慈愛すら気がつかせてくれました。
映画監督・細野辰興の書き下ろし連載小説、戯作評伝『スタニスラフスキー探偵団 日本俠客伝・外伝』。
史実の先に繰り広げられる、多重構造の罠と、小説ならではの虚構の物語をぜひお楽しみに!
インタビュー/大窪晶
写真/出町光識
協力/日本映画大学、森田悠介(日本映画大学 広報部)
細野辰興プロフィール
細野辰興(ほそのたつおき)映画監督
神奈川県出身。今村プロダクション映像企画、ディレクターズ・カンパニーで助監督として、今村昌平、長谷川和彦、相米慎二、根岸吉太郎の4監督に師事。
1991年『激走 トラッカー伝説』で監督デビューの後、1996年に伝説的傑作『シャブ極道』を発表。キネマ旬報ベストテン等各種ベストテンと主演・役所広司の主演男優賞各賞独占と、センセーションを巻き起こしました。
2006年に行なわれた日本映画監督協会創立70周年記念式典において『シャブ極道』は大島渚監督『愛のコリーダ』、鈴木清順監督『殺しの烙印』、若松孝二監督『天使の恍惚』と共に「映画史に名を残す問題作」として特別上映されました。
その後も『竜二 Forever』『燃ゆるとき』等、骨太な作品をコンスタントに発表。 2012年『私の叔父さん』(連城三紀彦原作)では『竜二 Forever』の高橋克典を再び主演に迎え、純愛映画として高い評価を得ます。
2016年には初めての監督&プロデュースで『貌斬り KAOKIRI~戯曲【スタニスラフスキー探偵団】より』。舞台と映画を融合させる多重構造に挑んだ野心作として話題を呼びました。
『貌斬り KAOKIRI~戯曲【スタニスラフスキー探偵団】より』は2018年11月10日(土)より横浜【シネマノヴェチェント】にてロングラン上映。