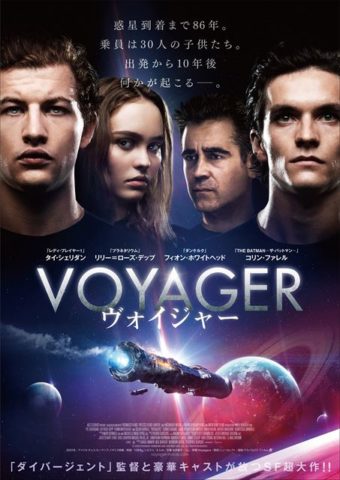近未来のデトロイトに蔓延る悪に立ち向かうのはサイボーグ警官?!
母国オランダを飛び出し、ポール・バーホーベン監督の世界観がハリウッドで爆発した傑作SFアクション『ロボコップ』をご紹介します。
映画『ロボコップ』の作品情報
【公開】
1987年(アメリカ)
【原題】
Robocop
【監督】
ポール・バーホーベン
【キャスト】
ピーター・ウェラー、ナンシー・アレン、ロニー・コックス、カートウッド・スミス、ダン・オハーリー、ミゲル・フェラー、ロバート・ドクィ、フェルトン・ペリー、レイ・ワイズ、ポール・マクレーン、ジェシー・D・ゴーインズ、デル・ザモラ、カルビン・ファン、リック・リーバーマン、リー・デ・ブロー、マーク・カールトン、エドワード・エドワーズ、マイケル・グレゴリー
【作品概要】
『ルトガー・ハウアー/危険な愛』(1973)で第46回アカデミー外国語映画賞にノミネートされるなどの実績があったオランダ人監督ポール・バーホーベンが監督したSFアクション映画。
エドワード・ニューマイヤーとマイケル・マイナーの手による見事な脚本や、バーホーベンの巧みな手腕により低予算ながら凄まじいメガヒットを記録。第60回アカデミー賞(1988年)編集賞、音響賞にもノミネートされた作品。
映画『ロボコップ』のあらすじとネタバレ
近未来のアメリカ、ミシガン州デトロイト。かつて自動車産業で栄えた姿など影も形もなく、警官殺しのクラレンス・ボディッカー率いる犯罪組織が蔓延る暗黒の街へと化していました。
この街に本社を置くオムニ・コンシューマー・プロダクツ社は警察運営すらも支配下に収めていた巨大企業。彼らは人員不足で悩む警官の待遇などお構いなしで、労働組合からの抗議など一切耳を貸しませんでした。
そんな時、この街に転任してきた一人の男マーフィ巡査がデトロイト警察の西分署を訪れます。リード巡査部長に迎えられ、この街を生き抜く厳しさを伝えられた後、彼とコンビを組む女性巡査ルイスと早速パトロールへと出掛けることに。
一方オムニ社で開かれた会議では、副社長のジョーンズが新型警察用ロボットED-209をお披露目していました。しかし、未完成にも関わらずジョーンズの独断によって発表されてしまったために故障を起こし、重役の一人を誤って殺してしまいます。
失望の色を隠せないオムニ社会長。副社長のジョーンズの出世を阻もうという野心の持ち主であった若い重役のモートンは、ここぞとばかりに彼自らが開発を指揮していた“ロボコップ(サイボーグ警官)・プロジェクト”を進言し、会長からの承認を受けました。
その頃、パトロールをしていたマーフィとルイスの下へ強盗事件発生の一報が入ります。犯人はクラレンス一味。カーチェイスの末の銃撃戦となり、一旦は逃げられたもの、再び工場跡地で発見しました。
無謀にも応援を待たず、二手に分かれて突入した二人。袋小路に陥り、囲まれてしまったマーフィ。クラレンスたちは容赦なく彼を撃ち抜きました。何発も何発も彼の身体を銃弾が貫いていったのです。
ルイスが駆け付けた時、かろうじてまだ息が合ったものの瀕死の状態だったマーフィ。すぐさま病院に運ばれるも、すでに手遅れでした。
“候補者”を探していたモートンはマーフィを格好の材料として利用し、かくして誕生したサイボーグ警官“ロボコップ”。マーフィとしての記憶や感情は全て消去され、機械として生まれ変わったのです。
早速西分署へと配属されたロボコップは、搭載されたプログラムと攻撃動作のチェックを行いました。射撃練習場で披露した専用銃「オート9」の圧倒的な破壊力に感心する署員をよそに、ルイスは別な角度から注目していました。
生前のマーフィが見せていた西部劇のガンマンのように銃を回しながら格納する動作とロボコップのそれとが非常に似ていると感じていたのです。彼女は、もしかしたらロボコップの正体はマーフィなのではないかと思い始めるのでした。
その夜からパトロールを始めたロボコップは、次々に凶悪事件を解決していきます。どんな難しい局面にも対応可能なロボコップの存在は、やがてニュースにも取り上げられ、街のヒーローとして賞賛を浴びるようになりました。
一方、今回の成功で副社長に出世することになった開発者のモートンはこの事態に大喜び。そんな彼に恨みを募らせていたジョーンズは、お前は間違った相手を怒らせたと彼に脅しをかけるのでした。
映画『ロボコップ』の感想と評価
ポール・バーホーベンが母国オランダからハリウッドへと渡り、『グレート・ウォリアーズ/欲望の剣』(1985)に続いて発表されたのが本作『ロボコップ』です。
キャラクターとしての“ロボコップ”というものは、おそらく日本でも知らない人はいないというくらい高い知名度を誇っていると思います。
しかし、このポール・バーホーベンが描いた映画としての『ロボコップ』というものがどんなものであったかを正確に認識している人はそう多くはないでしょう。
この作品は単なるSFアクション映画ではないのです。バイオレンスと皮肉にまみれた世界観に加え、“人間”と“人間に似たもの”の境界で苦しむ一人の刑事の悲哀に満ちた作品なのです。では、順を追って見ていきましょう。
同時代のSFアクションもの(例えば『ターミネーター』など)と比べてもそのグロテスクな残虐性は際立っており、どちらかというとジョージ・ミラー監督の『マッド・マックス』(1979)や、デヴィッド・クローネンバーグ監督の『ザ・フライ』(1986)の世界観に近いでしょうか。国によっては、公開時に一部をカットせざるを得ないような事態になったほど強烈な暴力描写が非常に多いのが特徴です。
また、随所に散りばめられたTVコマーシャルによる痛烈な皮肉が込められた演出は、ポール・バーホーベンの持ち味ともいうべきもの。後の『トータル・リコール』(1990)や『スターシップ・トゥルーパーズ』(1997)でも見られるように、こういった広告媒体は彼の作品では欠かせないアイテムなのです。
劇中で披露されるCMは、家族で盛り上がれる核戦争のボードゲームや、オゾン層が消えても使える青い日焼け止めクリーム(ただし皮膚ガンを発症する恐れがある)、はたまた盗難防止に電気ショックを与える機能がついている車など様々。
これらの広告は本編に直接関わってくるという訳ではないものの、劇中の世相を反映させることに一役買っていることに加え、当時の西側諸国=行き過ぎた資本主義社会への大いなる皮肉が込められているのです。
それは、商品を売るためなら何でもするという企業の危険な姿勢であり、実際にそうなり始めていた社会への警鐘の意味が込められていたのではないでしょうか。
そもそものストーリーの大前提であるオムニ社という民間企業が警察署を所有していること自体にもこのことが良く表れています。彼らがやっているのは不正行為=犯罪行為であるにも関わらず、同時に司法をも包括していることで起きたジレンマは、現代及び近未来において人類が陥りがちな傾向であるといえるのかもしれません。
さらには、この作品最大の魅力ともいうべき“ロボコップ”というキャラクター造形に関しても興味深い側面があります。
元々、『宇宙刑事ギャバン』からデザインを引用した(許可を得て)ことでも有名ですが、そういった面も含めたキャラクターのフォルムから受ける印象によって、世間ではヒーローアクションものと認識されがちなのが否めない所でしょう。
しかし、ロボコップが抱えていたジレンマは、そういった単純なヒーローものとは一線を画しています。
警察官であったマーフィが人間としては完全な死を迎えているにも関わらず、なぜか朧気に残ってしまった生前の意識のせいで「自分は何者なのか?」ということについて彼を苦しませることになったのです。
彼の抱えたジレンマは、P・K・ディックが小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(リドリー・スコット監督『ブレード・ランナー』の原作)で提示したものに非常に近く、ディックの生涯に渡るテーマとしていた「人間と人間に似たものを分けるのは何か」という問いこそ、まさにロボコップを悩ませていたものでした。
次作『トータル・リコール』がディックの『追憶売ります』という短編を原作としているという点から、バーホーベンも少なからず影響を受けていたのではと推測出来ます。
最終的に自らを“マーフィ”だと名乗ったことで、アイデンティティのジレンマに決着をつけたロボコップでしたが、昨今の人工知能やロボット技術の急速な発達によって、人類がこういった問題を抱えることはそう遠くないはでしょう。
このように、SFアクションやヒーローものという体裁の下に描かれたポール・バーホーベンのブラックな皮肉と近未来への警鐘の意味が込められているのが『ロボコップ』という作品なのです。一度ご覧になった方も、改めて見直してみるとまた新たな発見があなたを待っているかもしれません。
まとめ
『ロボコップ』はその後シリーズ化され、1990年に『ロボコップ2』、1993年には『ロボコップ3』が公開されましたが、いずれもポール・バーホーベンが関与していないこともあってか、お世辞にもあまり良いとはいえない仕上がりとなってしまいました。
それから20年ほどの時を経た2014年、ブラジル人監督ジョゼ・パジーリャの手によってリメイクかつリブート作品として復活を果たした『ロボコップ』。
スピード感とエネルギーに満ち溢れたスタイリッシュな犯罪アクション映画『エリート・スクワッド』(2007)が第58回ベルリン映画祭で金熊賞を受賞するなど高い評価を得ているパジーリャ監督が新生ロボコップを一体どのように描いているのでしょうか?
ポール・バーホーベン版『ロボコップ』と比較しながら鑑賞するのも、また一つの見方かもしれませんね。