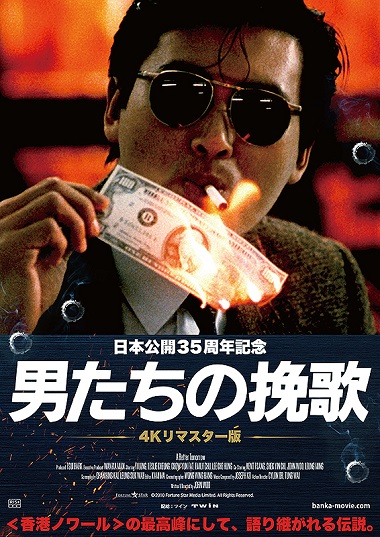第32回東京国際映画祭・コンペティション部門『ラ・ヨローナ伝説』
2019年にて32回目を迎える東京国際映画祭。令和初となる本映画祭が2019年10月28日(月)に開会され、11月5日(火)までの10日間をかけて開催されました。

(C)Cinemarche
この映画祭の最大の見せ場となる「コンペティション」部門。今回も世界から秀作が集まり、それぞれの個性を生かした衝撃的かつ感動的な作品が
披露されました。
その一本として、グアテマラのハイロ・ブスタマンテ監督による映画『ラ・ヨローナ伝説』が上映されました。
会場には来日ゲストとしてハイロ・ブスタマンテ監督も登壇し、映画上映後に来場者に向けたQ&Aもおこなわれました。
CONTENTS
映画『ラ・ヨローナ伝説』の作品情報
【上映】
2019年(グアテマラ、フランス合作映画)
【英題】
La Llorona
【監督】
ハイロ・ブスタマンテ
【キャスト】
マリア・メルセデス・コロイ、マルガリタ・ケネフィック、サブリナ・デ・ラ・ホス、フリオ・ディアス、フアン・パブロ・オリスラヘル
【作品概要】
夫の横暴により子を殺し入水自殺した母親が、神に罰せられて現世を泣きながらさまよう、という「ラ・ヨローナの怪談」をモチーフに、長年内戦を続けてきたグアテマラでの事件にまつわるエピソードから得た発想から、一人の男の運命を描きます。
この作品はハイロ監督が三部作として作られている作品群の最後のものとなります。
ハイロ・ブスタマンテ監督のプロフィール

(C)Cinemarche
1997年生まれ、グアテマラ出身。アティラン湖畔のマヤ先住民の多い地域に生まれました。2015年、初監督作『火の山のマリア』が第65回ベルリン映画祭の銀熊賞を受賞、他にも各地の国際映画祭で50以上の賞に輝きました。
二作目の『Temblores』は2019年に公開予定、三作目となる本作は監督の最新作となります。
映画『ラ・ヨローナ伝説』のあらすじ

(C)COPYRIGHT LA CASA DE PRODUCCIÓN – LES FILMS DU VOLCAN 2019
マヤ先住民の大量虐殺から30年後、グアテマラの武装勢力を指揮していた退役司令官エンリケは、今まさにその当時の事件に対しての裁判に引き出されていました。
一方、エンリケの頭に残るのは「泣いたら殺すぞ」という言葉の中で殺された、マヤのアルマと息子たちのイメージ。その記憶も引きずってか、エンリケは夜に女のなく声を聞くようになりました。
それを、エンリケのアルツハイマーの兆候であると心配する妻と娘。そしてある日、一人の新人家政婦アルマがエンリケの屋敷にやってきます。彼女が果たされなかった復讐を遂げに来たとは、誰も思いませんでした…。
映画『ラ・ヨローナ伝説』の感想と評価

(C)COPYRIGHT LA CASA DE PRODUCCIÓN – LES FILMS DU VOLCAN 2019
作品としてはホラーというジャンルに分類されていますが、これはグアテマラにまつわる「ラ・ヨローナの怪談」にインスパイアされて描かれた作品であるという点からでしょう。
しかしこの作品の恐怖、本当に恐ろしいものとしてハイロ・ブスタマンテ監督が描こうとしたものは、ホラー作品として具体的に表現されるものとは、少し違ったものであるように見えます。
Q&Aでも言われていますが、ハイロ監督は「マヤというテーマを使ってこの差別というものを描く」ことを目標とされました。もともとマヤ原住民の多い地域で育ったハイロ監督だけに、このポイントは作品の中でも重要なものであります。
一方でかつて起こった大量虐殺の首謀者に対して「大量虐殺をおこなった」「おこなわない」と同じような判断を繰り返し、その罪を明確にできない状況があります。
そしてそういった状況にたいして被害者たちが抱く思い、それこそがこの物語に描かれている大きなテーマとなるものでしょう。なので、あくまでラ・ヨローナという存在はその顛末の中で一つの象徴として描かれています。
劇中で描かれるヨローナのイメージは、決して人を直接殺めるような残虐な表現をされているわけではありません。しかし何か得体の知れない存在として、主人公エンリケにつきまとい、なかなか目の前に出てきそうで出てこない、そんな描き方をされていますし、だからこそ映画で描こうとしているテーマがはっきりと生きて見えます。
上映後のハイロ・ブスタマンテ監督 Q&A
31日の上演時にはハイロ・ブスタマンテ監督が登壇、舞台挨拶をおこなうとともに、会場に訪れた観衆からのQ&Aに応じました。

(C)Cinemarche
──本作はハイロ監督が前に公開された作品と合わせて、三部作になっているとおうかがいしました。三本全体を通したテーマはあるのでしょうか?
ハイロ・ブスタマンテ(以下、ハイロ):どちらかというとテーマ以外の関わり合いはないのですが、「侮辱」に関するテーマというものを考え、その三作品で描いた三つの世界において、いろんな差別が生まれてきているということを、作品を通じて描きたいと思っていました。
最初の『侮辱』は「マヤの人々」。マヤの人々はグアテマラの総人口の約75%に当たりますが、それがかなり差別的な扱いを受けている面があり、そういった側面を描きたいと思っていました。そしてそれが最初の『火の山のマリア』という作品となりました。
二番目のテーマは「ゲイの男性」の方。この社会でゲイというのは若干フェミニンな要素があるので、マヤの人たちとしては下に見られがちになっており、それをコンセプトとして扱っています。
そして三つ目が「共産主義」というテーマになります。これは政治的な意味での共産主義というより人権や社会的権利のことを指しており、この腐敗に満ちた世界で害されている状況を描いています。
そこでいわれる人権というものを受け入れてしまうと、すでに権力を持っている人たちが権力を失ってしまう。そんな構図を、この映画のエピソードとして描かれている大量虐殺みたいなことで示しました。

(C)Cinemarche
──過去の事件をテーマにされる際に、敢えてホラーという手法でこのテーマを扱った理由はどのようなものでしょう?
ハイロ:「ラ・ヨローナ伝説」は中央アメリカではかなり有名な伝説で、もともとある男性に捨てられた女性が狂気の沙汰に陥ってしまい、ほかの夫婦の子供を仕返しとして殺してしまうという物語です。
この伝説というのは地元でも愛されていますので、この伝説にインスパイアされ作品を作り上げることを考えました。
グアテマラの社会には、三世代の人種がいるという風に思っています。最初の世代の人種はいわゆる年配の方。この作品でいえば大佐とその奥さんですが、彼らは人に共感する心を持っておらず、自分たちはヒーローだと思っているんです。
なので「国を守る為に人間というものを殺さないといけない」と考える方であり、最後まで自分たちはヒーローであり犯罪なんかしていないと思っている。そしてその一方で戦争、内戦という間違いを起こした人たちです。
この人たちは共感の気持ちが無いので、他の世界から何か精神的なものをもらっていかないと反応ができないんです。そしてそういうことをしないと自分たちが最高であると思い過ぎてしまう。だからそれを『ラ・ヨローナ伝説』という作品の中で示したいと思いました。
──冒頭のご挨拶の中でおっしゃっていましたが、監督自身はマヤとアジアとの間にどんな共通性があると考えられていますか?
ハイロ:最初に共通点として実感するのは火山です。大変小さい国に関わらず、私の母国にも33個、その中には活火山もあります。
もう一つは伝統を大変重んじるということです。私たちの社会も大変伝統を重んじていて、母なるものを大切にしていると。そういうところが、私の作品を前回上映したときにもすごく評価していただきました。
また日本の方々と食事をしたときにも、同じようなものを尊んでらっしゃると感じることが多々ありましたので、今回もこの作品も受け入れていただけることを願っています。

(C)Cinemarche
──この映画は水が印象深く描かれていますが、この点に関してはどのように考えられたのでしょうか?
ハイロ:確かにこの水は、もともと「ラ・ヨローナ伝説」でも大変重要な要素になっています。伝説の中でも自分の子供を溺死させるというエピソードがありますし。
またマヤ文化でも水は「母なるもの」ととらえられているので、大変重要なものです。そういったこともあり今回の作品でも、水をかなり多用しました。
それに加えて主演女優のマリア・メルセデスもこの水のことについて、「心を見洗い流すにはたくさん水が必要ですから、もっと水が必要ですね」と言っていたので、もともと想定していたよりもかなりの水を使っています(笑)。
──例えばこの物語の結末のように、法の力が及ばないところに、直接手を下すということに対し、監督はどのように思いますか?
ハイロ:この作品自体はグアテマラで実際に起きたことをファクトベースにしてます。
グアテマラでは10年以上前から「果たしてあれは大量虐殺だったのか」と改めて検証するプロセスが進んでいて、一度「これは大量虐殺だった」と認めたんです。
でも後に最高裁のプロセスで「実は大量虐殺だったかどうかはわからないので、本当にまた確認するなら裁判の手続きをやり直さなければならない」みたいなことがずっと続いているんです。
それがこの作品のとっかかりになりました。その虐殺の被害者となった人たちとお話をしていたら、亡くなられた方々のことを「殺されたのではなく、ラ・ヨローナに連れていかれたのではないか」と言われたんです。そこからヨローナというアイデアがすごく強くなっていきました。
だからそんな風に正義が通用しないところで、人はその他の形による正義の示し方というのをいろいろ探していくわけです。
そこで物語ではこのヨローナという、いわゆる精霊が登場するわけですが、私としてはこれを使ってその目的を果たす、みたいなことはしたくなかったので、ヨローナをカルマ(業)みたいなものとしてその人をおさめていく、という風に考えました。
そもそもはマヤの人たちが大きく差別されているので、そのマヤというテーマを使ってこの差別というものを描きたかったわけです。
まとめ

(C)Cinemarche
またこの物語はエンリケの親族女性による祈りの場面から始まりますが、祈りの言葉を輪唱のように唱え続ける女性たちの声は非常に不気味二も感じられ、不安感を覚えさせるものであり、作品全体の雰囲気に大きな影響を及ぼしています。
この箇所が無ければ、物語は単に過去に大きな罪を犯した男性が、ある女性の呪いによって死に追いやられていくという構図だけが見え、内容的には薄いものになってしまうでしょう。
直接的な恐怖感をちりばめている作品ではないですが、何かが今にも出てきそう、起こりそうと不安な気持ちがずっと後を引きそうな作品であります。