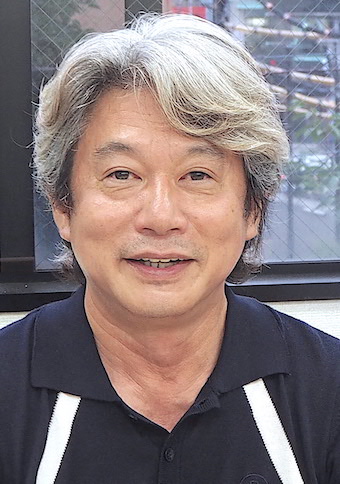映画『テルアビブ・オン・ファイア』が11月22日(金)より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開!
映画『テルアビブ・オン・ファイア』は、イスラエルとパレスチナの問題の深刻な課題を、あえてユーモア満載に描いた貴重な作品。
本作の演出を務めたのは、ニューヨークに在住するサメフ・ゾアビ監督。

ルクセンブルク・フランス・イスラエル・ベルギー合作映画だけあって、世界各国の評価も高く、既に第75回ヴェネチア国際映画祭の作品賞(InterFilm部門)と男優賞(オリゾンティ部門)の受賞や、第45回シアトル国際映画祭で作品賞受賞。2018年には、第31回東京国際映画祭「コンペティション」部門にも出品されています。
さらに米アカデミー国際長編映画賞(旧:アカデミー外国語映画賞)ルクセンブルク代表に決定しています。
今回、映画『テルアビブ・オン・ファイア』の日本公開に向けて来日をした、サメフ・ゾアビ監督にインタビューを行いました。
本作の劇中で重要な役割りを果たした「検問所」のことや、スタッフと一緒に作り上げた演出法。また、サメフ監督の学生時代の秘話など、映画への想いを伺うことができました。
CONTENTS
“検問所”という装置

(C)Samsa Film – TS Productions – Lama Films – Films From There – Artemis Productions C623
──本作『テルアビブ・オン・ファイア』は、特に「検問所」がユニークな位置付けになっています。そこについてのお考えをお聞かせ下さい。
サメフ・ゾアビ監督(以下、サメフ):パレスチナとイスラエルの「検問所」を舞台にする時に、観客はこの映画に対して期待するストーリーがあります。でも、実際の検問所は、暴力や侮辱に満ちており決して軽々しく扱える場所ではありません。
当初、検問所にいるアッシの役柄をユニークで好意的な人物描くことへの反論もありました。しかし、リアルな検問所はみんな既に知っているし、他の人でも伝えることはできます。だからこそ私がやるべき仕事は、この悲劇的な場所をプロパガンダにせず、
「検問所」を映画にどう反映させるかということだったのです。
1993年当時のオスロ合意では、イスラエルとパレスチアは2つの都市国家という形になりましたが、決裂し実現には至らなかった。だから私たちは現代において、どのような「ストーリー」を伝えるのか、という課題がありました。
イスラエル側からのストーリーは既に十分に伝わっています。例えば、パレスチナ政府はないも同前で、政府といっても一部の力をもった政権が、パレスチナを牛耳っている。占領パレスチナと呼ぶべきで自治的な政府というのは存在していない、などです。
だからイスラエル人のアッシは、ドラマの脚本に干渉し、出演するアラブ人とユダヤ人の2人の結婚を望むわけですが、パレスチナ人のサラームは、現在のパレスチナとイスラエルの関係性を理解しているから、その筋書きでは無理だ、というわけです。
共同脚本をおこなった経緯

──本作は脚本家ダン・クライマンとの共同脚本になっていますが、お互いにどのように執筆を行い作品をつくっていったのでしょうか。
サメフ:作品の骨格は私が作りましたが、シーンごとに互いに分担し、メールでのやりとりを重ねていきました。
3年ほどかけて骨組から肉付けをしていった感じです。メールだけでは解決しない場合には、直接連絡をとり、互いに説得し、合意形成を行ってきました。
──脚本家ダン・クライマンからアドバイスがありましたか?
サメフ:各々の強みがありました。私は、この土地を理解していました。彼は75歳という高齢でもありましたから、現地での検証はすべて私が担当しました。
一方で、彼は私とはメンタルの部分が異なっているという利点がありました。彼は非常に分析的で、シーンの構成力に長けています。その点についてディスカッションを通じて学べたことは有り難かったです。
映像の世界観はカメラマンと作り上げた

(C)Samsa Film – TS Productions – Lama Films – Films From There – Artemis Productions C623
──カメラワークに魅了されるシーンが多かったのですが、撮影監督のロラン・ブリュネとはどのようなコミュニケーションをとっていったのでしょうか?
サメフ:ロランはとても経験豊富なカメラマンで、困難な状況にも柔軟なことに対応してくれました。
彼はあれこれ指示を出すタイプではなく、例えば検問所のシーンについても、とても狭いコンテナのような場所で撮影したのですが、「私はここにいないものだと思って、好きにやってください」という感じで非常に自由に私たちを動かす機会を与えてくれました。
ただ、撮影のスタイルに関しては、入念に決めた部分もあります。最初は劇中のドラマ部分のシーンを、「パレスチナの予算の少ない中でのドラマ製作」という演出を凝らし、わざとプロモーションビデオ的な撮影にしようと提案したら、彼はドラマも実人生も同じカメラ用いて、逆に撮影のスタイルを変えることで、ドラマとの違いを表現しようと決めました。
劇中ドラマでは、ハリウッドのクラシカルな感じを出していく。例えば、映画『カサブランカ』(1942)を感じるようにね。
逆に、実生活の町のシーンを手持ちカメラで撮るようなこともありました。そうするとだんだん、主人公の実人生とドラマとが融合していくような印象を与えることになっていったのです。
目的を持たずに何かを探す主人公

(C)Samsa Film – TS Productions – Lama Films – Films From There – Artemis Productions C623
──サメフ監督が映画で描いた笑いは、チャップリンのような作風に見えました。他者を傷つけるような皮肉なユーモアでなく、またナンセンスではなく、生きる知恵を感じるユーモアを感じましたが、その点についてはいかがでしょう?
サメフ:映画を撮影している間は チャップリンの映画を意識していたわけではなかったのですが、撮り終わった後、作品を改めて観た時、チャップリンの映画『キッド』(1921)との間での気づきがありました。
キャラクターが何かを探している。でも、何を探しているかはわからない。主人公が経験を積みプロセスを経ることで気づいていく。
大抵の人は、チャップリンの演じた主人公のように、人生において何を欲しているかを確信していないと思うのです。現代に生きる人々の約80%くらいはグレーな部分で生きている。自分の欲望はこれだ!という人はどれだけいるのでしょう
けれども映画というのは、その20%の何を欲しているのか目的がわかっている人が主人公として作られています。そこが嘘っぽくみえてしまうのです。
アメリカに行き映画を学ぶ

──サメフ監督は、フルブライト・プログラムで奨学金を得て、ニューヨークにあるコロンビア大学で映画を学ばれましたが、それはなぜですか?
サメフ:実は私は映画を観て育ったという境遇ではありませんでした。家族は農家でしたし、特に父は、「アート=仕事」だとは思ってもいませんでした。
私自身、高校では数学と物理を専攻しており、非常に優秀な成績を治めていたので、周囲からは将来は医者か弁護士を嘱望されていました。しかし、テルアビブ大学に進学し、映画と英文学を専攻しました。
映画を観てはいませんでしたが、セオリーというのはこれから世界中の作品を観たら学べるし、英文学を専攻しておけば、もし映画の道で成功しなかった時に、教師になる道があるだろうと思ったからです。ちょっとした保険です。
映画を学んでいくうちにどんどん映画を好きになりました。ですが、教室にいた周囲の生徒は全員がユダヤ人で、唯一私だけがパレスチナ人だったのです。こうなるとたとえ映画を作っても、彼らが見る「パレスチナ人」として描かなければ、ここでは映画を作れないと気づいたのです。
ちょうどその時、教授からフルブライト・プログラムを紹介されました。幸い英文学を専攻していたこともあって、英語もできる。面接時に気に入られて、最年少で奨学金を受けて、コロンビア大学で映画を学べたわけです。それが唯一私がイスラエルを出る手段であり、私がありのままの私として生きる道だったわけです。
フィクションに見つけた自由な想像力
参考映像:『アルジェの戦い』(1966)
──アメリカに行って、強く影響を受けた映画や作品はありますか?
サメフ:『アルジェの戦い』(1966)は強い衝撃を受けました。はじめに観た時はドキュメンタリーかと思ったくらいです。それがドキュメンタリー映画ではないと知った時、フィクションにはそれだけの力があるんだと思いました。
あとはイタリア映画です。フェデリコ・フェリーニやルキノ・ヴィスコンティ、ヴィットリオ・デ・シーカですね。私も結局、地中海の気質があるので、それらの映像には心惹かれます。
他にもエミール・クストリッツァ、ケン・ローチ、ロベルト・ロッセリーニのネオレアリズモ映画も好きです。いろんな地域の良いところを取って、自分の作品に反映していこうと思いました。
でもアメリカに行ったら全く違いました。映画はビジネスです。売るための脚本、商業主義、スター主義…。今はその中間に自分を置いているような感じです。
私の『テルアビブ・オン・ファイア』は、まさにその「中間」にある映画ですね、娯楽でありながら、映画の声というのをもっています。

──フィクションのパワーとは何でしょうか?
サメフ:より自由に、想像的に広げられるということでしょう。もちろん、ドキュメンタリーであっても、リアルなものを撮りながら自分の色を出すことはできます。
しかし、フィクションは、観客が自分自身で考え得る「余白」を与えられるのです。ドキュメンタリーはシュチュエーションからの自由度が、フィクションに比較して低いのです。
学生時代、テルアビブで勉強していた時に、パレスチナ関連のドキュメンタリー映画がトレンドのように撮られて、それ以外のものを撮りたいという反抗心もあったのです。何を撮ったとしても、それはドキュメンタリーではないという形で伝えたいと思うようになったのです。
インタビュー/ 出町光識
構成/ くぼたなほこ
サメフ・ゾアビ監督のプロフィール

1975年、イスラエル・ナザレ近くにあるパレスチナ人の村・イクサル生まれ。
1998年、テルアビブ大学を卒業後、映画研究と英文学を学ぶため、ニューヨークにあるコロンビア大学でフルブライト奨学金を受けM.F.A(美術学博士号)を取得。
2005年に、短編映画「Be Quiet」がカンヌ映画祭に出品され、翌2006年、フィルムメイカー・マガジンによって、「インディーズ映画界の新しい顔のトップ25」の1人に選ばれる。
本作『テルアビブ・オン・ファイア』は、ヴェネチア、トロント、ロカルノ、サンダンス、カルロヴィヴァリほか世界各国の映画祭で上映・受賞し、世界から新たな才能として注目を浴び、今後の作品も期待される映画作家である。
【フィルモグラフィー】
2018:『テルアビブ・オン・ファイア』
2015:『歌声にのった少年』*脚本のみ
2013:『UNDER THE SAME SUN』*TV映画
2012:『MAWSEM HISAD』*共同監督
2010:『MAN WITHOUT A CELL PHONE』
2005:『BE QUIET』*短編
映画『テルアビブ・オン・ファイア』の作品情報
(C) Samsa Film – TS Productions – Lama Films – Films From There – Artemis Productions C623
【公開】
2018年(ルクセンブルク・フランス・イスラエル・ベルギー合作映画)
【原題】
Tel Aviv on Fire
【監督】
サメフ・ゾアビ
【キャスト】
カイス・ナシェフ、ルブナ・アザバル、ヤニブ・ビトン
【作品概要】
サメフ・ゾアビ監督の『テルアビブ・オン・ファイア』は、第31回東京国際映画祭のコンペティション部門にエントリーされたコメディ映画で、イスラエルとパレスチナの問題をユーモアと風刺を効かせた作品。
主人公のパレスチナ人のサラーム役を『パラダイス・ナウ』(2005)でシリアスな演技を披露したカイス・ナシェフがコミカルに演じました。
また、アカデミー国際長編映画賞(旧:アカデミー外国語映画賞)のルクセンブルク代表、第75回ヴェネチア国際映画祭では作品賞(InterFilm部門)と男優賞(オリゾンティ部門)受賞など、各国で映画賞を受賞しています。
映画『テルアビブ・オン・ファイア』のあらすじ

(C)Samsa Film – TS Productions – Lama Films – Films From There – Artemis Productions C623
パレスチナのアラブ人である30歳のサラームは、エルサレムに暮らしていました。彼は金なし、彼女なし、仕事もなし…。何をするにも上手く立ち回ることができないサラームは、自分の意思を他人にうまく伝える言葉を持っていませんでした。
そんなサラームは、テレビドラマの番組プロデューサーをしている伯父のつてで、『テルアビブ・オン・ファイア』という、国民的人気メロドラマの現場で働きます。
彼はパレスチナ人としてアラブ式な微妙な言葉指導を、フランス人の女優タラにアドバイスするのが役割でした。
サラームは、毎日、自宅から撮影所に通うため、面倒なイスラエルの検問所を通なければなりません。それはパレスチナのアラブ人の彼には、自国というものがないから仕方ないことでした。
ある日、サラームは、検問所のイスラエル軍司令官を務めたアッシから尋問にあいます。そこで彼は自分の職業を人気メロドラマ『テルアビブ・オン・ファイア』の脚本家だと偽りました。
するとアッシは、人気ドラマの熱烈なファンでの妻に自慢するため、サラームから脚本を奪い取ってしまいます。
その後、毎日サラームを呼び止めるアッシは、脚本に強引なアイデアを出し始めます。
サラームは困りながらも、アッシの助言するアイデアは、軍人としてのリアルさだけでなく、ラブロマンスの機微も、女との交際経験の少ないサラームよりも魅力的な台詞でした。その甲斐もあり、サラームは正式に脚本家へと出世します。
晴れて仕事を得たサラームは、撮影所でのキャリアアップに火が付き、かつての恋人とも再会を果たしますが、そんな矢先、ドラマが終盤へと近づくにつれ、イスラエル側を良く見せたいアッシと意見が対立します。
他にもパレスチナ側のドラマのスポンサーやリアリティを求めるドラマの制作スタッフと、脚本の結末をめぐって対立するイスラエルとパレスチナの間で、サラームは窮地に立たれ…。
映画『テルアビブ・オン・ファイア』が11月22日(金)より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開!