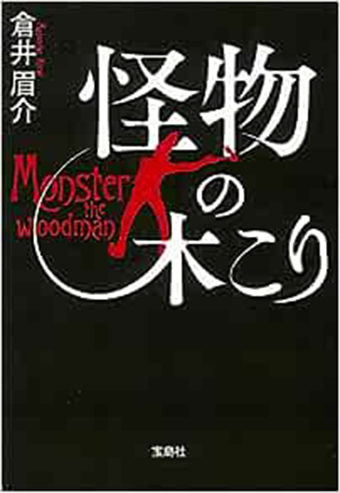それは運命などではない「因果応報」という破滅の道!
映画『1922』はモダンホラー作家スティーブン・キングの同名小説『1922』を映画化したものです。
舞台はアメリカのネブラスカ州にある、広大な農村地域。
妻と長男の3人家族で、トウモロコシ栽培を中心とした農場経営をしている男の妻に、肥沃な広い土地の遺産が入ったことで、一家の運命が大きく狂っていきます。
物語は男が妻を殺害したことを告白するホテルの1室から始まり、その短絡的で愚かな悪だくみが生んだ、彼の顛末を描きだします。
映画『1922』の作品情報
 Netflixオリジナル映画『1922』
Netflixオリジナル映画『1922』
【公開】
2017年(アメリカ映画)
【原題】
1922
【監督/脚本】
ザック・ヒルディッチ
【原作】
スティーブン・キング
【キャスト】
トーマス・ジェーン、モリー・パーカー、ニール・マクドノー、ディラン・シュミット、ケイトリン・バーナード、ボブ・フレイザー、ブライアン・ダーシー・ジェームズ
【作品概要】
主演は『パニッシャー』(2004)、『ミスト』(2008)をはじめ、スティーブン・キング原作では『ドリームキャッチャー』(2003)にも出演している、トーマス・ジェーン。
監督は『Transmission』(2011)が、2012年のAACTAアワードで、Best Screenplay in a Short Filmを受賞し、オーストラリア版SFパニック映画『ファイナル・アワーズ 』(2013)の脚本・監督を務めたザック・ヒルディッチです。
原作者スティーブン・キングの小説は、デビュー作の『キャリー』(1976)から、『ドクタースリープ』(2019)まで、数多くの作品が映画化されています。その中でも『1922』は、Netflixオリジナル映画として、『ジェラルドのゲーム』(2017)に続く、2作品目となります。
映画『1922』のあらすじとネタバレ
“マグノリアホテル 209号室”「ウィルフレッド・リーランド・ジェイムズ、私はここに罪の告白をする」
ことの発端はウィル(ウィルフレッド)の妻アルレットが、両親から100エイカーの肥沃な土地を、相続したことから始まります。
ウィルは元から所有していた800エイカーの土地と、妻が相続した土地を合わせた農場として、息子のヘンリーや子孫に残してあげたいと願っていました。
1920年代の男にとって、広大な土地を所有することや息子(跡取り)を持つことは、当たり前のように抱く誇りだったからです。
しかし、妻のアルレットの考え方は違っていました。
アルレットは農場の仕事や経営に全く興味がなく、むしろ嫌いだったため、土地はすぐに売却し、オマハ(ネブラスカ州の都市)に越したいと思っています。
さらに、そもそも夫婦仲は冷え切っていたので、アルレットはその土地を有力企業に高額で売却し、遺産分けをしたら離婚すればいいと、ウィルに話していました。
また離婚後は、まだ14歳のヘンリーをアルレットが引き取ると言います。
そのヘンリーは父親の仕事は前向きに手伝い、農場での生活に不満はありません。むしろ都会での暮らしは望んでいません。
ウィルは妻と法廷で戦うことも考えましたが、妻の後ろ盾として、土地を買い取りたい有力企業のフェリントン社がいて、勝ち目がありません。
また、法廷に訴え出るのを留まらせた理由は他にありました。
妻アルレットへの深い憎しみが、ウィルの中に別の人格を生み、陰謀や悪だくみをけしかけていったのです。
そのもう一人の自分は、コッタリー家のシャノンに恋をする、ヘンリーの心理を利用して、悪だくみを実行させようとしました。
ヘンリーはシャノンと離れて暮すことは考えられません。ウィルはそんな息子を共犯者にするため、あらゆる言葉で口車にのせようとするのです。
「神から与えられた寿命を奪われたものは、それまでの罪は許され、天国へ行ける」
ウィルはヘンリーに自分達が住んでいる土地から、離れたくないという意思を無視し、土地を売ろうする母親を悪者に仕立てようとします。
ヘンリーは夕食時に土地を売らないでと哀願しますが、アルレットは激怒し、ヘンリーの頬を平手打ちしました。
次の日、ウィルはアルレットに、「ヘンリーは街で暮らすと言っている。自分も街で自動車修理の仕事でも探す」と、言います。
アルレットは「ウィルがヘンリーを説得したとは、信じられない」と疑いますが、ウィルは「説得したのではなく、ヘンリーから街に行って、幸せに暮す方法を見つけた方がいいと説得された」と、話しました。
アルレットはウィルの言葉を信じて有頂天になり、祝杯をあげ酷く酔っ払い、ヘンリーにシャノンとの性交には気をつけるよう、下品で淫らな言葉で忠告します。
ヘンリーはシャノンを酷く侮辱されたと、傷つきアルレットに激しく嫌悪感を抱くのでした。
ウィルは酔いつぶれたアルレットを寝室に寝かせると、ヘンリーに言います。
「神は母を淫らなことを言う人間にしてしまった。」
ヘンリーは「この道(殺害)だけは避けたかった」と言い、ウィルは「2人の住む土地は、2人で守るため戦うしかない」と説得します。
1922年、ウィルはヘンリーの手を借りて、妻アルレットののどをナイフで切り裂き、殺害しました。
しかし、彼は殺人をしたことよりも、犯罪に息子を巻き込んだことの方が心に重くのしかかっていると、告白の理由について述べています。
映画『1922』の感想と小説との比較
主人公のウィルが抱いたのは、古い風潮に従わない妻への不満、成功者にしか得られない優越感への嫉妬でした。
自分の理想や残したい土地のために邪魔な妻のアルレットを殺害し、勝手にいなくなったことにする。
それはあまりに短絡的で、愚かな発想だったとしか言いようがありません。ウィルは思い通りにならなかったことを「誰にも運命を変えることはできない」と、語っています。
しかし、それはスティーブン・キングが、彼に言わせた言い訳であり、東洋風に表現するとしたら、「因果応報」で、自分のした悪事は、自分に返ってくるということです。
映画にはない事実と事件後の8年間
ヘンリーの顛末や、1922年以降の8年間のことを、小説では詳細に描かれています。
ウィルは最後の数カ月にヘンリーが訪れた場所を巡っていますが、最初に強盗に入った用品店は“売り店舗”になっています。
その金でヘンリーは銃を質屋で手に入れますが、ウィルも同じ質屋で銃を購入します。
その銃を持って押し入った“農業銀行”を訪ね、当時の行員に事件のことを聞くと、“お金を渡すと、お礼を言ったのです。しつけがよかったんですね”と、言われました。
シャノンが入っていた養護院にも行きますが、建物を眺めるだけで職員には会いません。
ヘンリーがシャノンを連れ出す時、手引きの手伝いをしてくれた、同じ養護院の問題児、“ヴィクトリア”という、少女の消息を調べ会いに行っています。
ヴィクトリアは養護院から連れ出せたことを、“幸運な事だ”と言いますが、逆に問題児だった彼女の方が、閑静な住宅街の家で3人の子供に囲まれ、幸せに暮らしていたのです。
次にヘンリーは別の銀行を襲い、警備員の足を打ち、彼はその足を失っています。ウィルはその警備員の両親に会います。
警備員の両親は“命があっただけでも幸せ。あなたの息子は、歳も重ねられないのだから”と、死を悼んでくれたのです。
ヘンリー達はゴシップネタとなり、逃亡生活に追い込まれていくうちに、容赦のない犯罪者になっていきました。
それでも、盗んだ車を返そうとしたり、最後の食堂ではお金を払って出て行こうとして、背後から打たれシャノンが凶弾に倒れています。
ヘンリーの罪を犯しながらも、几帳面な行動をしたのは、彼が信仰していた、規則正しい生活法(メソッド)を重んじる、“メソジスト教会”の教義に、殉じていたからと思われます。
ヘンリーは作中で「もうお祈りはできない。祈れば神様に打ち殺される」と言いますが、それは“救いは罪の自覚とともにすでにあるもの”と、いう教義から発せられたのでしょう。
ウィルフレッド・リーランド・ジェイムズの最期
ところでウィルは、4カ月働いていた工場を、他の人には見えていない“ネズミの存在”が見えると言ったことで、クビになっていました。
その後、彼は紹介状を偽造し、図書館員になって仕事をしますが、やはりネズミの存在に気がついてから、無断で仕事に行かなくなり、終焉の場所として物語の冒頭に出てくる、“マグノリアホテル”に部屋をとりました。
映画のラストは無残な姿となった、アルレット、ヘンリー、シャノン、そして大量のネズミに追い詰められるシーンでブラックアウトします。
のちにウィルの死体がホテルの1室から発見されます。ウィルの部屋から悪臭や泣き声うめき声などがすると、隣室から苦情があったからです。
しかし、机上にピストルはあったものの、死因は銃による自死ではなく、体のあちこちを噛みちぎられ、手首を噛み切り、大量出血したのが致命傷になっていました。
そして、ウィルが書き残した“告白文”も、解読が不能になくらいに細かく噛みちぎられており、告白文くらいでは罪は消えないと、示していたのでしょう。
ウィルは身元不明の死者ということで、新聞に掲載されますが、引き取り手があらわれることはないという孤独な顛末を表し、終わっています。
まとめ
『1922』は、家長の定めともいえる、先祖から受継いだ土地を守り、それをさらに拡大させ子孫に受継がせる風潮が、1人の男を固執した考えで縛り、愚かで浅はかな悪だくみへと、憑りつかせてしまいました。
ウィルの思考はアメリカ開拓時代に広まった、メソジスト教会の教義である、“この現世において神の国を実現しよう”と、いう社会変革の熱意が、根底にあったと思います。
そんなウィルの選んだ道は、彼の一家だけではなく、近隣の家族をも巻き込む悲劇の物語でした。
しかし、主人公には幸せな道を選ぶこともできたのに、“なぜできなかったのか?”と、ラストシーンからは考えさせられます。