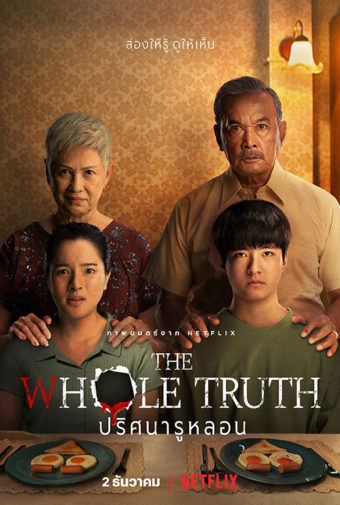映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』は2022年3月19日(土)よりシアター・イメージフォーラムほかにて全国順次公開!
タイやラオスの密林でバナナ葉の住居を作り、ノマド(遊動民)として生きる「ムラブリ族」の生活の実態を、ムラブリ語を研究する言語学者・伊藤雄馬とともに2年の月日をかけて追った映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』(以下、『森のムラブリ』)。
タイ人からは「黄色い葉の精霊」と呼ばれ、多くの謎に包まれた少数民族であるムラブリ族の中でも、ラオスで狩猟採集を続けるグループのの撮影に世界で初めて成功したドキュメンタリー作品でもあります。

(C)Cinemarche
このたびの劇場公開を記念して、映画『森のムラブリ』を手がけられた金子遊監督と、ムラブリ語を研究する言語学者であり本作の現地コーディネーターを務めた伊藤雄馬さんへのインタビューを行いました。
ムラブリ語の特徴とそれが生じた要因、ムラブリ族の在り方から見えてくる「森の生活」と現代社会の関係性、金子監督・伊藤さんそれぞれが思う「言葉」の意味など、多くの貴重なお話を語ってくださいました。
CONTENTS
運命的だったムラブリ語研究者・伊藤雄馬との出会い

(C)幻視社
──はじめに、金子監督と伊藤さんの出会い、ひいてはドキュメンタリー映画『森のムラブリ』の制作経緯をお聞かせいただけますでしょうか。
金子遊監督(以下、金子):私は映画評論家として活動しながらもドキュメンタリーを撮り続けていて、奄美大島や沖縄、海外では中東やアフリカなど様々な場所を旅してきたんですが、2017年に2ヶ月ほど東南アジアの少数民族が暮らす村々を巡っていたんです。
その際に私も、文献でのみその名を知っていた「黄色い葉の精霊」ことムラブリ族の集落の捜索を試みたんです。タイ北部のナーン県で現地ガイドを雇い、多くの苦労をして作中に登場するフワイヤク村へたどり着いたんですが、そこに日本人がいたんです(笑)。驚きのあまり「何をしているんですか」と尋ねてみると「自分は言語学者で、ムラブリ語を研究しています」と返ってきたんです。
世界的に見ても、ムラブリ語を10年以上継続的に研究しているのは伊藤さんだけとわかり、その出会いにまた驚かされつつも、ラオスにはまだ森の中で暮らすムラブリ族がいること、三つの集団におけるムラブリ語の方言差に注目していて、100年近くいがみ合っている各集団の人々をどうにか再会させられないかと考えていることを伊藤さんから聞かされました。
伊藤さんとの出会いは、偶然でもあり運命的でもあると直感しました。結果、その日・その場で今回の映画を撮ることを決断しました。
同じ言語の「変異」による集団の区別化

(C)幻視社
──そもそも、伊藤さんがムラブリ族の人々、そしてムラブリ語を知られたきっかけとは何でしょうか。
伊藤雄馬(以下、伊藤):大学の学部生時代、文字のない言語をそれが用いられているフィールド(現地)へ行って調査・研究するフィールド言語学を学びたいと考えていたんですが、どの言語・どのフィールドについて研究するのかは決めていませんでした。その頃に、たまたま人類学の講義の中でムラブリの人々が触れられ、ムラブリ語も聞いたんです。
イントネーションがどんどん上がっていくことで生じる、ムラブリ語の「響き」が私にはとてもきれいに感じられました。そうして興味を抱いたのが、ムラブリ語を研究し始めたきっかけです。
──世界各地の言語において「イントネーションがどんどん上がっていく」という発音の特徴は、言語として珍しいものなのでしょうか。
伊藤:珍しいですね。アフリカの言語でも見られるアップ・ステップという特徴に近いものなんですが、基本的に多くの言語で文の最初が最も声が高く、文末に向かって低くなっていきます。ムラブリ語はそれが逆で、どんどん高くなっていくんですね。
またムラブリ語の特徴において、一番僕が関心を持っているのは「個人差」ですね。日本語にも方言がありますが、「鼻」はどの地域でも大抵「鼻」と表現されるように、言語にはそれぞれ日常で使用される頻度の高い基礎語彙というものが存在し、それらはどの地域でも大体語彙の形が同じなんです。ただムラブリ語における方言は基礎語彙でも全然違う形をしていて、それはとても珍しい。恐らくかつてムラブリ族の中で何かが起きたことに要因があるのではと僕は推測しています。
またムラブリ語は、同じ方言の中でもまた表現に差があります。それどころか、昨日はこう発音していたはずなのに、今日同じ人に訊いてみたら違う発音をしている例すらある。研究にあたって語彙とその発音の採集を行う言語学者はとても困ってしまうわけです。そうした言語の「変異」のバラエティに富んでいる点も、ムラブリ語の特徴の一つでもあるんです。
そこまでの言語の変異が生じた要因として僕が考えているのは、やはり映画作中でも触れられている通り、かつてムラブリ族のコミュニティー間がお互いを嫌い合いながらも、その外見や住居では差異を見出せない中で、言語によって各集団の特徴を形成していったという説です。
ムラブリ語では俗にいう男言葉・女言葉もコミュニティーごとに明確な違いが作られていて、会話をするだけでも無意識に自身が属する集団が見えてきます。そうして意図的に言葉を変え、集団の区別化を図ろうとしたのが有力な要因なのではと推測しています。
タイ/ラオスでみたムラブリ族の現在/過去

(C)幻視社
──金子監督は映画を撮り進められる上で、ムラブリ族のどのような点に注目されたのでしょうか。また現地で実際に撮り進められる中で、金子監督がムラブリ族について新たに気づかされたこと、実感されたことはありますか。
金子:タイにはいくつかの少数民族が存在しますが、その中でもムラブリ族は特に人口が少ないんです。それにも関わらず、ムラブリ語という独自の言語を現在まで用いて、集団の中で様々な物を共有する生活を今日まで続けています。
僕はもともと民族学者のベルナツィークが残した『黄色い葉の精霊』 を読んでいたこともあり、タイの他の民族にすらも「滅多に姿を現さない森の民」「住居に用いるバナナの葉が枯れ、黄色くなったらその場所を離れて消えてしまう、精霊のような神秘の民族」と認識されているムラブリ族の人々を、現在さらに人口が減少しつつある状況もふまえ、映画に撮りたいと考えていました。
また実際にたどり着くことができた、ラオスにおけるムラブリ族の集落の生活を見つめていると、住む場所に違いはあれど、その狩猟採集民族としての在り方や、どこかゆったりとした精神性はタイのフワイヤク村で暮らす集団と共通していました。
国家からも離れ、ある意味では自由で無政府的な社会が森の中で今も営まれ続けていることには、純粋に驚きと魅力を感じられました。ただその一方で、森の中で暮らし続ける人々という「過去」、森から離れる選択をした人々という「現在」もラオス・タイのそれぞれの集団の生活を撮る中で実感しました。
ムラブリ族の生活から学ぶ「持続可能な生活」

(C)幻視社
──映画作中ではムラブリ族の人々の口から「森の中の方が過ごしやすい」という言葉が登場します。金子監督・伊藤さんは映画の撮影や現地での調査を通じて、その言葉の真意をどのように捉えられたのでしょうか。
伊藤:「森の中の方が過ごしやすい」という言葉はラオスで出会ったムラブリ族の少年ルンだけでなく、タイのフワンヤク村で暮らす人々も同じように話していました。そして何故そう感じるのかと聞くと、一様に「町は暑い」と答えるんです。
そして、僕が実際に森で過ごしてみて思ったのは「人から離れている」という感覚です。自身の家族といった慣れ親しんだ人々はいるけれど、その他の集団や民族はまずいない。それに対して町で生きる以上は、人口の密集度の増加はもちろん、より多くより複雑になる社会における人間関係を受け入れなくてはならない。
深い森の中に入ると、そうした町の生活と自身をつなぐものがふっと切れて、何かが軽くなる瞬間を感じられる。しがらみから解放されるかのようなその体験を味わうと、ムラブリ族の人々が語る森の生活の「楽さ」を理解できるようになるんです。
金子:タイ出身のアピチャッポン・ウィーラセタクン監督は『ブンミおじさんの森』(2010)という映画を撮っていますが、様々な何かをそこにある不定形のものとして描いているんですよね。また作中、ムラブリ族の一人が夜に焚き火の前で民話をうれしそうに語っていたように、不定形であるがゆえに森は「想像」が生まれ「物語」が生まれる空間にもなるんだと感じています。
そして伊藤さんが触れた通り、森の生活では町の生活で強いられるストレスがほとんど存在しないんです。外部とは物々交換で取引しているので貨幣は基本的に必要としていないし、物や貨幣を手にしてもそれを貯蓄しようとはしない。またラオスの森の中で暮らしている集団は数世帯の家族で構成されている通り、非常に限られた人数で生活しているため、いわゆる「他人の目」がほぼないんです。
何より、ラオスのムラブリ族はノマド(遊動民)であり、嫌なことがあったり採集する食物がなくなった際にはその場所を離れ、別の場所で新たな生活を始められるんです。私たちは家という空間に縛られた上で寝食や労働といった生活を続けざるを得ないですが、ムラブリ族には生活のリセットとリスタートができる空間として森が存在する。
それは非常にプリミティブな生活の在り方ですが、同時に私たちが今後「持続可能な生活」を考える際のモデルケースでもあり、学ぶべきことが多くあるものだと捉えています。
約100年ぶりの再会が教えてくれたもの

(C)幻視社
──「離れて暮らしていたムラブリ族同士の約100年ぶりの再会」によってもたらされた結果を、その再会の第一の発案者である伊藤さんご自身はどのように受け取られたのでしょうか。
伊藤:言語の調査と研究を続けるうちに、ムラブリ族自体の人口の圧倒的な減少と「集団そのものが消えてしまう」ことを痛感した僕は、集団同士を何らかの形で「統合」をすることで、ムラブリ族の生活と文化の可能性を探れないかと感じていました。集団同士を会わせようと考えたのはそうした理由にあります。
それぞれの集団は会おうと思えば会える場所で暮らしていた中で、それでも当初は「人食い」の民話も相まってお互いの集団を怖がっていました。
ところが、僕がそれぞれの集団に事情を説明した上で実際に会ってみると、決して怖がることはなく、お互いの言葉や生活の違いについてどんどん会話を交わしていくという意外な結果が生まれた。むしろどこか「慣れている」とさえ感じられました。
ただよく考えてみると、いがみ合いが起こる以前の森の中でも、人数が少なくなった集団同士がつながって新たな集団を作ったり、逆に一つの集団が複数の集団に分かれるといった出来事はいくらでもあったはずなんです。そう考えると今回の再会の結果にも納得がいきましたし、その結果を目にするまで見落としてしまっていたことでもありました。
言葉がもたらす誤解から、言葉の役割を見直す

(C)Cinemarche
──金子監督と伊藤さんにとって、「言葉」とは一体何でしょうか。
金子:作中で交わされているムラブリ語やラオス語での会話は、撮影当時にその意味全てを把握していたわけではなく、撮影後の編集の過程で伊藤さんに会話を翻訳してもらい、その時にようやく全ての内容を知ったんです。
ただ言葉は分からないながらも、撮影時にムラブリ族の人々が話していたこと、伝えようとしていたことはそれとなく理解できていたんです。言語だけではなく、その前後の文脈や抑揚、身振り手振りの仕草など様々な要素が複合されることで初めてコミュニケーションが生まれるということが理解できました。
伊藤:金子監督の「言語自体の意味は分からなくても、伝えようとしていたことは理解できた」という話には、とても共感を抱いています。
この世界には多くの言語が存在し、それらが氾濫の状態にある時代といえますが、多分すでに「折り返し」の地点にたどり着いていると感じています。そして言語が好きである僕は言語学者であり、言語についての調査や分析などの研究を続けている反面、日常で用いる言葉を減らしていった方がいいのではと感じています。
どんな言語であれ、何かを伝えるためには言葉を尽くし続け積み上げていく過程が必ず存在します。ですがその過程が、かえって物事を見えなくしてしまっているのではとも捉えられます。
たとえば「このコーヒーは苦い」と言った時、「苦い」という情報は共有できても、人それぞれで感じ取り方に差異がある。「どんな苦さなのか」という情報は個人の経験であって、どれだけ言葉を尽くしても、自身と他者が別の存在である以上、正確に共有することはまずできない。認識の違いが必ずあるはずなのに、同じ言葉を用いてしまうことでお互いを理解した気になってしまう状況が生まれるんです。
そうした誤解が生じることを前提として、言葉はどう伝えればいいのかを今考えています。もちろん、言葉を多く重ねることで「網目」を細かくし、情報がこぼれ落ちることを防ぐという方法もあるんですが、そもそも言葉はとてもふわっとした、曖昧なものでもあります。
むしろ、お互いが言葉を分からない状態でコミュニケーションをとった方が、物事の本質や関係性へよりダイレクトに近づけることもある。そのような観点から、言葉を見直していきたいと考えています。
インタビュー/河合のび
金子遊監督プロフィール
映像作家、批評家。多摩美術大学准教授。劇場公開映画に『ベオグラード 1999』(2009)『ムネオイズム』(2012)『インペリアル』(2014)。近作『映画になった男』(2018)は東京ドキュメンタリー映画祭、田辺・弁慶映画祭などで上映。プロデュース作『ガーデンアパート』(2018)はロッテルダム国際映画祭、大阪アジアン映画祭で上映された。『森のムラブリ』(2019)が長編ドキュメンタリー映画の5作目。
著書『映像の境域』でサントリー学芸賞《芸術・文学部門》受賞。他の著書に『辺境のフォークロア』『異境の文学』『ドキュメンタリー映画術』『混血列島論』『悦楽のクリティシズム』など。共編著に『アピチャッポン・ウィーラセタクン』『ジャン・ルーシュ 映像人類学の越境者』、共訳書にティム・インゴルド著『メイキング』、アルフォンソ・リンギス著『暴力と輝き』など。
ドキュメンタリーマガジン「neoneo」編集委員、東京ドキュメンタリー映画祭プログラム・ディレクター、芸術人類学研究所所員。
伊藤雄馬プロフィール
1986年生まれ、島根県出身。言語学者。京都大学大学院文学研究科研究指導認定退学後、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所にて日本学術振興会特別研究員(PD)。2018年より、富山国際大学専任講師。2020年に退職後、独立。
学部生時代からタイ・ラオスを中心に現地に入り込み、言語文化を調査研究している。ムラブリ語が母語の次に得意である。論文に「ムラブリ語の文法スケッチ」(『地球研言語記述論集』)、“The heart’s downward path to happiness: cross-cultural diversity in spatial metaphors of affect.”(Cognitive Linguistics、共著)など。
映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』の作品情報
【公開】
2022年(日本映画)
【監督・撮影・編集】
金子遊
【現地コーディネーター・字幕翻訳】
伊藤雄馬
【出演】
伊藤雄馬、パー、ロン、カムノイ、リー、ルン、ナンノイ、ミー、ブン、ドーイプラ、イワン村の人々、フアイヤク村の人々
【作品概要】
タイやラオスの密林でバナナ葉の家をつくり、ゾミアでノマド生活を送る「ムラブリ族」の生活の実態を、文字のないムラブリ語の語彙を収集する言語学者・伊藤雄馬とともに2年の月日をかけて追ったドキュメンタリー。
タイ人からは「黄色い葉の精霊」と呼ばれ、多くの謎に包まれた少数民族であるムラブリ族のラオスで狩猟採集を続けるグループの撮影に世界で初めて成功した作品でもある。
映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』のあらすじ

(C)幻視社
タイ北部ナーン県のフワイヤク村周辺は、400人のムラブリ族が暮らす最大のコミュニティ。男たちはモン族の畑に日雇い労働にでて、女たちは子育てや編み細工の内職をする。
無文字社会に生きるムラブリ族には、森の中で出くわす妖怪や幽霊などのフォークロアも豊富だ。しかし、言語学者の伊藤雄馬が話を聞いて歩くと、ムラブリ族はラオスに住む別のグループを「人食いだ」と怖れている様子。
伊藤とカメラは国境を超えて、ラオスの密林で昔ながらのノマド生活を送るムラブリを探す。
ある村で、ムラブリ族が山奥の野営地から下りてきて、村人と物々交換している現場に出くわす。それは少女ナンノイと少年ルンだった。
地元民の助けを得て、密林の奥へとわけ入る。はたして今も狩猟採集を続けるムラブリ族に会えるのか? 21世紀の森の民が抱える問題とはいったい何なのか?
編集長:河合のびプロフィール
1995年生まれ、静岡県出身の詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。
2021年にはポッドキャスト番組「こんじゅりのシネマストリーマー」にサブMCとして出演(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介