連載コラム「新海誠から考える令和の想像力」第6回
新海誠監督の最新作『天気の子』の主題歌は、『君の名は。』につづきRADWIMPSが手がけ、そのタイトルは「愛にできることはまだあるかい」です。
新海監督が「音楽」に強いこだわりをもっていることを考えますと、それは『天気の子』のテーマをそのまま反映させている可能性が高いといえます。
連載の第2回でも触れましたが、音楽は新海作品を読み解くうえで重要なポイントですので、もう一度引用します。
たとえば「トレモロ」の、「悲しみが悲しみで終わらぬよう、せめて地球は回ってみせた」という歌詞。人間の感情という小さなものと、宇宙という極大なものがつながっていく音楽です。「こんな音を奏でられる映画を作りたい」っていつからか思っていたんでしょね。(新海誠『新海 誠Walker』、KADOKAWA、P22)
新作には題名にも曲中にも「愛」という言葉が散りばめられています。引用部分にならっていえば“愛を奏でられる映画を作りたい”となるかもしれません。
今回はこの点から、作品テーマをめぐる愛についての考察を深めていきます。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力』記事一覧はこちら
不寛容な愛について

(C)2019「天気の子」製作委員会
ここまでの連載で、ふたり(二者関係)の“愛”がだれかを排除してしまう暴力性の問題を指摘しました。
これは国内外の人々や社会を見渡しても気づく具体的な情況であり、令和はその趨勢を変えられるかどうかの分岐点となるでしょう。
たとえば、「愛国」という言葉の裏には、他国を「憎悪」する感情がないか。
あるいは、「保守主義」が守る対象は、その他大勢の「守られない対象」を生んでいないか。
新海監督が描こうとしている“愛”は、そういった意味ではないはずです。
また、ふたりの“愛”を成就させるために「世界」そのものを破壊する(『雲のむこう、約束の場所』や庵野秀明作品)といったことも、『君の名は。』を経た今では考えられません。
二者関係のなかに芽生える“愛”でありながらも、“第三者”を排除する暴力に抗い、変えてしまった“世界”のかたちを守れるか。
『天気の子』の問いが、より明確になってきました。
愛する主体について

(C)2019「天気の子」製作委員会
そもそも、新海作品からこのような問いが可能になるのは、登場人物たちが往々にして傷を抱えた弱き者であり、他者を無理やり自分のものにできない繊細さが土台にあるからでした。
まずはそこを固めるべく、「愛にできること」を考える前に、「愛することのできる者」について、前回につづきレヴィナスの知見を借りながら確かめていきます。
たしかに、人間にとって傷つくということは、自分が弱いことを露呈するようなものです。
しかしそれは同時に、だれかに対してコミュニケーションをとったという事実も明らかにします。
自分だけの世界を享受して生きている人間は、そもそも傷を負うことはありません。
逆にいえば、「弱い者」とはそのリスクを冒した者、すなわち「自分を他者に曝した者」と受けとめられます。
コミュニケーションには二つの意味がある。「メッセージの伝達」としてのコミュニケーションと、「暴露」(exposition)としてのコミュニケーションである。(…)「暴露としてのコミュニケーション」はそれとは水準を異にする。それは、コミュニケーションを起動させること、コミュニケーションを「解錠」すること、それ自体である。(内田樹『レヴィナス愛の現象学』、文春文庫、P80)
この“暴露”によってはじまったコミュニケーションのなかで「主体」が生まれます。それは自分だけが享受していた世界の一部を、他者に明け渡すときです。
レヴィナスが「倫理」と呼ぶのは、この「暴露のモード」を選び取る、という決断のことである。(…)決断が下された後になって、そのような行為を起動させた「始点」が事後的に確定され、それを人は「主体」と名づけるのである。(同上、P82)
新海作品の切なさを演出するのは、傷つきやすい少年少女たちの煩悶ですが、自分を曝しだした結果という意味においては、“強さ”が確認できます。
その“強くなる瞬間”とは、こんな場面です。
それはまず、人間が語りだすときである。人間は他者に無関心ではいられないために、人びとに向かって言葉をかける。コミュニケーションは、「リスクを犯しながら自己をあらわにすることのうちに、真摯さのうちに、自己の内面性の砦を壊し、あらゆる避難所を放棄することのうちに、外傷にさらされることのうちに、脆弱性のうちに」行なわれるのである。(中山元『思考のトポス』、新曜社、P241)
連載の第4回では、“宮崎的な「愛の押しつけ」を避けつつ、「淡い恋」から弱いもの同士つながるにはどうすればいいのか”という問いを見いだしました。
まさにその“脆弱性”のうちに、他者とコミュニケーションを開き、(愛することのできる)主体が誕生する契機が含まれていたのです。
ではつぎに、傷をさらしながら立ち上がった「主体」の「愛」とはなにかをみていきます。
愛にできること

(C)2019「天気の子」製作委員会
レヴィナスは主著のひとつ『全体性と無限』(1961年)の序文で、こう述べています。(以下、熊野純彦(訳)『全体性と無限』、岩波書店、2005年より引用。)
本書は、こうして、〈他者〉を迎えるものとして、他者を迎えいれることとして主体性を提示することになるだろう。P26
“他者を迎え入れること”と「主体」の関係は前述したとおりですが、レヴィナスのいう他者とは自分のものになりえない絶対的な他者、『天気の子』における“100パーセントの晴れ女”のように超越した存在です。
それを迎え入れるとは、どういったことでしょうか。
主体性とはつまり、含みこむことが可能である以上のものを含みこむという、驚くべきことがらを実現するのである。P26
主体は自分の容量以上のものを含みこめる者である、ということです。
それは「倫理にあって本質的なものが、超越するその志向にあるから(P32)」であるというレヴィナス独自の見方に基づきます。
論旨を先取りしますと、“超越する志向”に“愛”というものがでてきます。主体は完全に、十全に認識しきることのない“愛”を、みずからのうちに抱くことができます。
別の言い方をすれば、愛される対象は、愛する感情のなかにあって、明確な姿かたちをあらわすものではありません。
ペンをみてペンだと認識することとは違って、愛のそれは絶えず彼方(無限)に開かれています。
レヴィナスはそれをもたらす他者との出会いに、倫理の基礎を求めます。
〈他者〉の現前によって私の自発性がこのように問いただされることが、倫理と呼ばれる。〈他者〉の異邦性──《私》に、私の思考と所有に〈他者〉が還元されえないということ──が、まさに私の自発性が問いただされることとして、倫理として成就される。P62
“私”に“他者”が還元されえないこと。前述の“愛”を念頭に置きつつ、この関係にもうすこし踏みこんでいきましょう。
ふたつの項がその関係のなかで境界を接しておらず、〈他〉と〈同〉が関係しているにもかからわず〈他〉が〈同〉に対して超越的でありつづけるような関係である。P53
難しい言い回しですが、ひとことであらわすと、こうなります。
〈他者〉は私との関係において超越的でありつづけるのである。P84
これはじつに非対称な関係です。それによって、どんな視座が得られるのでしょうか。
非対称性とはつまり、じぶんを外部から見て、自己と他者たちについておなじ方向から語ることが根底的に不可能であるということであり、したがってまた全体化が不可能であるということなのである。P86
“全体化が不可能”であるとは、“無限にむかう”ことを意味します。そのなかで二者関係は、同一化の暴力を避けながら、“愛”を成就させる可能性をたたえます。
これを新海作品に照らしあわせてみましょう。
『君の名は。』での愛の起点は、ふたりの身体が“対称的に”入れ替わることでもたらされました。いってみれば、これは“同一化=全体化”の危険性をはらんでいます。
一方で『天気の子』の陽菜は、繰りかえしの言及になりますが、天気を晴れにできる超越的な力をもった存在です。
帆高にとって陽菜は決して入れ替わることのできない「他者」であり、その関係は『君の名は。』の二者関係を乗り越えたところ、レヴィナス的な倫理と愛をめざす地平を想像させます。
セカイ=内=存在
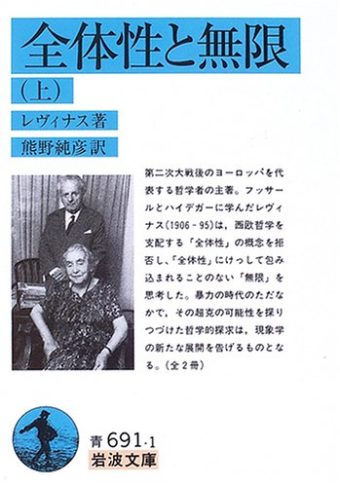
レヴィナス (著)・熊野純彦 (訳)『全体性と無限』(岩波書店、2005年)
「ほんとうの生活が欠けている」。それなのに私たちは世界内に存在している。形而上学が生まれ育まれるのは、このような不在を証明するものとしてである。だから形而上学は、「べつのところ」「べつのしかた」「他なるもの」へと向かっていることになる。P38
これは『全体性と無限』の第1部の冒頭です。
新海誠監督の短編漫画『塔の向こう』では、「世界はあたしを受け入れてくれない。あたしは今日も、今までだって、ちゃんと歩いてきたのに」と語る少女がいますが、哲学的な文脈で捉えなおせば、彼女はみずからの本質(何者か)に先立ち“セカイ”に投げこまれてしまっていることに、とまどいを覚えているのでしょう。
哲学者のハイデガーによれば、わたしたち人間は“世界内存在”であり、それは意味や記号でつながりあう世界の内に、その世界を了解しつつ存在せざるをえないという実存を示しています。
それに対して、“ほんとうの生活が欠けている”と、べつのところ(塔のむこう)をめざす新海作品における少年少女たちは、“セカイ内存在”と呼べるかもしれません。
第3章第2節にあたる次回は、引きつづきレヴィナスの他者論を援用し、「他者」との愛が“セカイ内存在”を導くところ、連れだす外部、その可能性を明示していきます。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力──セカイからレイワへ──』記事一覧はこちら







































