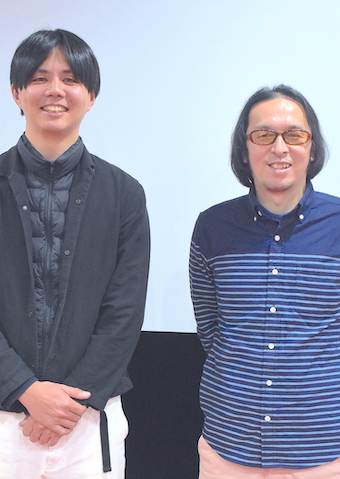連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』第9回
「Cinemarche」編集長の河合のびが、映画・ドラマ・アニメ・小説・漫画などジャンルを超えて「自身が気になる作品/ぜひ紹介したい作品」を考察・解説する連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』。
第9回で考察・解説するのは、2022年4月22日(金)よりテアトル新宿、アップリンク吉祥寺ほかにて全国順次公開の映画『山歌』です。
かつて日本の山々に実在した漂泊の民「山窩(サンカ)」を題材に、孤独な少年とサンカの一家の交流、そして時代の移ろいという現実との葛藤を描き出す本作。
本記事では、作中に登場するサンカについて、そして“現代を生きる漂泊の民”を映し出したとあるドキュメンタリー映画とリンクさせることで新たにみえてくるサンカの姿を考察・解説していきます。
連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら
映画『山歌』の作品情報

(C)六字映画機構
【公開】
2022年(日本映画)
【監督・脚本・プロデューサー】
笹谷遼平
【キャスト】
杉田雷麟、小向なる、飯田基祐、蘭妖子、内田春菊、渋川清彦
【作品概要】
かつて日本の山々に実在した漂泊の民「山窩(サンカ)」を題材に、孤独な少年とサンカの一家の交流を描いた作品。ドキュメンタリー映画『馬ありて』で注目された笹谷遼平監督が、第18回伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞を受賞したオリジナル脚本を基に本作を手がけた。
『半世界』の杉田雷麟が本作にて映画初主演を果たしたのをはじめ、『未成仏百物語 AKB48 異界への灯火寺』の小向なる、漫画家・小説家の内田春菊、ドラマ・映画に多数出演する飯田基祐、寺山修司作品で知られる蘭妖子のほか、『ばるぼら』『ちょっと思い出しただけ』の渋川清彦が出演。
映画『山歌』のあらすじ

(C)六字映画機構
1965年夏。都会の中学生・則夫(杉田雷麟)は受験勉強のため、東京から祖母の家がある山奥の田舎に来ていた。
父・高志(飯田基祐)と祖母・幸子(内田春菊)の圧力の中勉強を強いられている則夫は、近所の山で漂泊の旅を続けるサンカの男・省三(渋川清彦)、その娘・ハナ(小向なる)と出会う。
則夫は彼らに強く惹かれ、やがて省三の母・タエばあ(蘭妖子)とも交流を持ち、蛇やイワナを獲り食べるという、自然の中での体験を通して改めて「生きる」ことを体験する。いつしかハナとその家族は則夫にとって特別な存在になっていた。
しかし則夫は、彼らが山での生活を続けられないほどに追い込まれいること、自分が彼らに対する加害者の一人だと知り、ある事件を引き起こす。
映画『山歌』の感想と評価

(C)六字映画機構
真に語られることなく、誤解だけが遺された民
映画『山歌』に登場する、かつて日本の山々で暮らしていた漂泊の民「サンカ」。
定住地を持たず、流動的に拠点を移動しながら狩猟採集による生活を営み、川魚や箕・竹細工などの交易を近辺の村々で行う際にだけ山を下りる。家どころか戸籍も持たず、限りなく国家から離れて生きていたサンカは、まさに「山の民」とも言うべき人々でもありました。
しかし、その生活形態により家はもちろん、土地などの私的所有権の概念に疎かったサンカの人々は、他者が所有地に知らず知らず入ってしまうなど、サンカではない人々との価値観の違いによるトラブルを起こすこともあったそうです。

(C)六字映画機構
そうしたトラブルの発生が時としてあったこと、そして何よりも明治期の近代化によって、サンカは当時の行政機関や警察にも「戸籍のない犯罪者の集まり」「関わってはならない危険な人々」という偏見に満ちた認識をされたことで、サンカという呼称も差別用語として長らく使用されてきました。
明治期には全国で約20万人、昭和期の終戦直後に約1万人ほど存在していたというサンカ。しかしそれらはあくまで「推計」でしかなく、行政による人口調査どころか、サンカの研究者自体も限られていたことからも、その多くが謎に包まれています。
ただ一つ言えるのは、価値観による違いなどに起因する差別、国家と離れていたがゆえの歴史からの疎外、そして戦後の三角寛らの完全創作小説またはファンタジー小説で描かれた幻像によって、サンカは真の意味で「語られる」という機会がないまま姿を消してしまった民であるということです。
「流転」をまとい生きる民

(C)六字映画機構
明治期から次第にその人口は減ってゆき、映画『山歌』の舞台である昭和40年(1965年)以前の昭和30年代には目撃証言すらも減少していったサンカ。その主な要因は、戦後日本における戸籍制度の徹底、そして昭和30年代からの高度経済成長とそれに伴う山の開発・森林の伐採であるとされています。
2022年3月に劇場公開を迎えたドキュメンタリー映画『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』でも、元々は森で生活する漂泊民であり、同じくその生活形態が謎に包まれていたタイ・ラオスの少数民族「ムラブリ族」の“選択の結果”が描かれています。
森を出て村(または周辺)で暮らすことを選んだタイの生活集団と、現在も森で暮らし続けるラオスの生活集団。地域は違えど、共生する自然環境の変化に対する選択を経たそれぞれの集団の生活は、「映画『山歌』で描かれるサンカもまた、ムラブリ族のように同じ選択を経たのだろう」と想像させられます。

(C)六字映画機構
また映画『山歌』で描かれるサンカ、『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』のムラブリ族の最も重要な共通点は、「流転とともに生きている」という点です。
近代化の20世紀、そして21世紀に突入してもなお、人間の物理的・心理的な“流動”の速度は増し続けています。しかしその流動はあくまでも人工的なものであり、石や水が上方から下方へと転がり流れてゆくかのような“流転”……自然の理としての“流転”とは異なるものでもあります。
その一方で映画『山歌』で描かれるサンカは、決して目には見えないものの、確かに“流転”をまとっていると観客に感じさせます。それは『森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民』が映し出す、ムラブリ族の人々がまとっているものと非常に似ており、劇映画とドキュメンタリーという違いこそあれど、漂泊の民ゆえに触れられる“何か”があるのだと実感させられます。
映画『山歌』を通じて、現代社会を生き続ける自己が“在りし日”に脱ぎ落としてしまった“流転”を思い起こす。それは同時に、本作の主人公・則夫の心の流れを辿る体験でもあるのです。
まとめ/あの時、人々は止まれなかった

(C)六字映画機構
サンカの人々がまとう“流転”を感じ取ったのか、彼ら彼女らとの交流を深めてゆく映画『山歌』主人公・則夫。しかし彼は一方で、サンカの人々を取り巻く厳しい現実、そしてその現実をもたらしている原因に自分もまた加担していることに気づきます。
サンカの人々を取り巻く厳しい現実をもたらしていた原因。それはサンカの歴史的背景のみならず「“流転”を捨ててでも早く、早く動き続けなくてはならない」という戦後の日本社会全体に取り憑いていた巨大な感情と深くつながっています。
そして則夫はそれでも、そうした巨大な感情に立ち向かおうとしますが、彼が最終的に選んだ手段もまた、昭和初期に憂国の念から軍事クーデターを計画・実行したものの、最終的には政府内における軍部の権力を強め、戦争の遠因を生み出してしまった青年たちの姿を連想させるものとなっています。
終戦から20年後の時代にあたる、1965年夏。多くのものが流動しながらも、戦争の影が未だ色濃く残るその時代で、則夫とサンカの人々はどのような選択をするのか。その答えは、戦争を「遠い国の出来事」を認識する者が日々増え続ける2022年現在の日本ともリンクしています。
次回の『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』も、ぜひ読んでいただけますと幸いです。
連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら
編集長:河合のびプロフィール
1995年生まれ、静岡県出身の詩人。
2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。

photo by 田中舘裕介