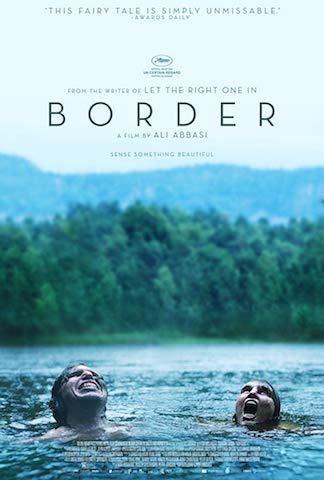動物を嫌う人間が持つ《獣》の心
異端の父子がたどり着く《命/魂》の絆とは?
映画情報サイト「Cinemarche」編集長・河合のびが気になった映画・ドラマ・アニメなどなどを紹介し、空想・妄想を交えての考察・解説を繰り広げる連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』。
第14回でご紹介するのは、「フランスのアカデミー賞」ことセザール賞で最多12部門ノミネートを果たし、フランス国内で大ヒットを記録した映画『動物界』です。
「原因不明の突然変異により、人間の心身が動物と化していく」という奇病が蔓延している近未来の世界で生きる父子の姿を描いた、SFスリラーでありヒューマンドラマでもある『動物界』。
本記事では映画『動物界』のネタバレ言及とともに、本作に登場した祭り「聖ヨハネ祭」などが象徴する「人間と動物の差別化」というキリスト教的価値観、それらを通じて描く《子羊》な人間が今なお持つ《獣》の心などを考察・解説していきます。
連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら
CONTENTS
映画『動物界』の作品情報

(C)2023 NORD-OUEST FILMS – STUDIOCANAL – FRANCE 2 CINEMA – ARTEMIS PRODUCTIONS
【日本公開】
2024年(フランス・ベルギー合作映画)
【原題】
Le regne animal
【監督】
トマ・カイエ
【製作】
ピエール・ガイヤール
【脚本】
トマ・カイエ、ポリーヌ・ミュニエ
【撮影】
ダビ・カイエ
【音楽】
アンドレア・ラズロ・デ・シモーネ
【キャスト】
ロマン・デュリス、ポール・キルシェ、アデル・エグザルコプロス、トム・メルシエ、ビリー・ブラン、サーディア・ベンタイブ、ナタリー・リシャール
映画『動物界』のあらすじ
近未来。人類は原因不明の突然変異によって、徐々に身体が動物と化していくパンデミックに見舞われていた。
突然変異が生じた人々は《新生物》と呼称され、その凶暴性ゆえに施設への隔離処置と、肉体変化の進行を抑制するための治療がが行われていた。
フランソワの妻ラナもその一人だったが、彼の16歳の息子エミールは人々に「獣」と蔑まされ迫害される新生物の一員となった母のことを受け止め切れず、周囲にも明かせずにいた。
しかしある日、施設への移送中の事故によって、ラナたち新生物が野へと放たれてしまう。
父と子はラナの行方を必死に探すが、次第にエミールの身体に、変化が現れ始める……。
映画『動物界』聖ヨハネ祭&ラストシーンの意味を考察・解説!

(C)2023 NORD-OUEST FILMS – STUDIOCANAL – FRANCE 2 CINEMA – ARTEMIS PRODUCTIONS
聖ヨハネの前夜祭と「猫焼き」の供犠
フランソワとエミールの父子が引っ越してきた町で「新生物の出没のせいで開催できないかもしれない」と危惧され、映画終盤にて実際に催された聖ヨハネ祭。
作中では大きな焚き火も行われている点からも、それは『新約聖書』に登場する古代ユダヤの宗教家・預言者である洗礼者ヨハネの誕生日(6月24日)を祝う祭りであり、のちにキリスト教普及以前のヨーロッパ圏の五月祭や夏至祭と結びつけられ「火祭り」として催されることが多い「聖ヨハネの前夜祭」であることが窺えます。
またエミールの転校先の同級生ニナが、聖ヨハネ祭について「かつては焚き火で猫を焼いていた」と説明していますが、それは18世紀以前のヨーロッパで実在したとされ、虚栄や魔術、悪魔の象徴として扱われた猫を厄除けと娯楽を兼ねて焼き殺す風習「猫焼き」のことであり、聖ヨハネの日の前夜祭の開催時にもよく行われていたと伝えられています。
魔術や悪魔といった「異端」=前キリスト教/反キリスト教的価値観の排斥を風習化した猫焼き。そもそも『旧約聖書』『新約聖書』においても、ともに「贄としての動物」がたびたび描かれていますが、そこには古代ユダヤ教の供犠の習慣という歴史的文脈だけでなく「『人間と動物の差別化』を見せしめる」という意図が強く込められています。
人間と動物の差別化──《神の子羊》と《獣》の違い
『旧約聖書』の「創世記」では「神ヤハウェが全ての生物を創造した最後に、自分たちの姿に似せて作り上げた」そして「海の魚、空の鳥、家畜、地の全ての獣・這うものを治める者になるよう神に任じられた」とされている人間。
その描写だけでも人間は「動物とは異なる特別な存在」ひいては「神に仕える者として、動物を従える存在」として扱われていることは明白であり、『新約聖書』でもイエス・キリストが自らを「善き羊飼い」と喩えた逸話は非常に有名です。
無論「イエスは『人間』を『羊』という動物に喩えているじゃないか」と考えることもできますが、古代ユダヤ教では贄として度々用いられてきた子羊は、キリスト教でも「洗礼者ヨハネがイエスを『神の子羊』と喩えた」=「イエスを『人間の罪を贖う贄の役目を持つ者』と認識した」という逸話などで登場します。
そして羊……その中でも特に子羊が、キリスト教において《神の子》イエスや信仰の在り方の喩えに選ばれるほどに聖なる象徴を担う動物に選ばれたのも、「羊飼いという人間の命令に従う、まだ幼い動物」というイメージが「獣のごとく何の教えも知らなかった中で、キリスト教の教えにより『神に仕える者=真の人間』になろうとする者」の姿と結びつけやすかったためであり、そこでも「人間と動物の差別化」という意図は存在しています。
《神の子羊》の皮を被った人間という《獣》
チャールズ・ダーヴィンの『種の起源』以降、キリスト教的価値観を持つ人々から多くの反感を買いながらも「人間は神が土くれから作った人形ではなく、進化の過程を経て誕生した動物の一種に過ぎない」が常識として定着した現在。
しかしながら、それでも「人間は他の動物より優れているのは明らかであり『他の動物とは異なる特別な存在』であることは、キリスト教的価値観が無意味になっても変わらない」と考えている人間は決して少なくはないはずです。
「人間は、地球上における生物進化の最終到達点にして頂点の存在だ」「人間は他の動物とは違う存在だ」と信じるがゆえに、人間と異なるもの……動物、あるいは非人間と認識した者を排斥しようとする人間。その姿こそが、教えという名の固定観念にただ従い、その固定観念と異なるものは異端として思慮なく排斥・迫害する、神の子羊の皮を被った《獣》ではないか……。
映画『動物界』は「生物進化の最終到達点であったはずの人間が、動物へと退化する……のではなく、人間以外の動物に似た姿の《新生物》へと進化する」という設定を通じて、キリスト教的価値観が古臭いものと認識されるようになっても人間の心に残り続ける「人間は動物とは違う」という固定観念を揺るがします。
そして、その固定観念という種によって芽生える、「進化」という言葉とは程遠い人間の「獣」の心を指摘するのです。
まとめ/異端などではない、普遍な《anima》の絆

(C)2023 NORD-OUEST FILMS – STUDIOCANAL – FRANCE 2 CINEMA – ARTEMIS PRODUCTIONS
映画結末、《新生物》として肉体も精神も変化していったエミールは、固定観念に塗れながら新生物の排斥・迫害を抑えられない人間の社会からの追跡を逃れるため、森へと向かいます。
父フランソワは「行け」「生きろ エミール」と涙ながらに励まし、愛する息子の旅立ちを受け入れました。そこには、遠い昔の誰かが生み出した「人間と動物は違う」という固定観念では排斥できない……決して異端などではない、どこまでも普遍な父子の絆が描かれていました。
それをふまえると、キリスト教に関する要素が多く登場する映画『動物界』が「動物へと姿を変わっていく息子とその父の物語」であるのも、『旧約聖書』にて息子イサクを神の贄に捧げようとした父アブラハムの物語になぞらえた上で「新生物は隔離しなくてはならない」という人間の社会の《教え》に抗った父子の姿を描きたかったからとも考えられます。
なおフランス語・英語ともに「動物」を意味する語であるanimalは、ラテン語で「命」「魂」を意味するanimaに語源があるとされています。
フランソワとエミールの普遍な父子の絆は、種の違いを超えた「命」あるいは「魂」に基づく絆であり、映画『動物界』の「Le regne animal」という原題も、本来は「命の世界」「魂の世界」と訳すべき言葉なのかもしれません。
連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら
編集長:河合のびプロフィール
1995年静岡県生まれの詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部として活動開始。のちに2代目編集長に昇進。
西尾孔志監督『輝け星くず』、青柳拓監督『フジヤマコットントン』、酒井善三監督『カウンセラー』などの公式映画評を寄稿。また映画配給レーベル「Cinemago」宣伝担当として『キック・ミー 怒りのカンザス』『Kfc』のキャッチコピー作成なども精力的に行う。(@youzo_kawai)。

(C)田中舘裕介/Cinemarche