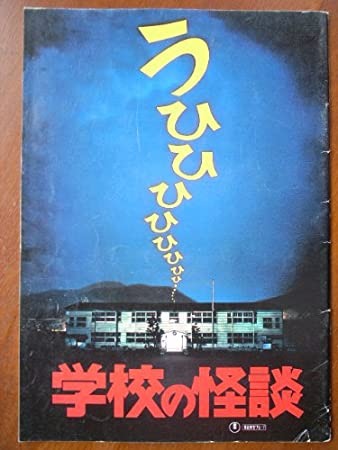連載コラム「アジアン電影影戯」第3回
今回は、2019年3月23日(土)より新宿K’s cinemaにて公開されるベトナム映画『漂うがごとく』を取りあげます。
急速な経済発展を背景に年々製作本数が増えているベトナム映画ですが、その多くが娯楽作品ばかり。
アート色の強い本作はひと際異彩を放っていますが、それはいよいよ到来した“ニュー・ウェイヴ”の本格的な始動を意味しています。
ベトナム映画が今どのように変化してきているのか、それを『漂うがごとく』の映画体験を通して読み解いていきましょう。
映画『漂うがごとく』の作品情報

(C)Vietnam Feature Film Studio1,Acrobates Film
【公開】
2009年
【監督】
ブイ・タク・チュエン
【キャスト】
ドー・ハイ・イエン、リン・ダン・ファム、ジョニー・グエン、グエン・ズイ・コア
【作品概要】
ベトナム・ニュー・ウェイヴを代表する鬼才ファン・ダン・ジーの脚本を、ドキュメンタリー出身のブイ・タク・チュエンが映画化。
トラン・アン・ユン監督の『夏至』(2000)にデビューしたドー・ハイ・イエンが主人公・ズエンを演じています。
また本作は第66回ヴェネツィア国際映画祭国際批評家連盟賞受賞作品です。
映画『漂うがごとく』のあらすじ

(C)Vietnam Feature Film Studio1,Acrobates Film
舞台はベトナムの首都ハノイ。
旅行ガイドとして働くズエンとタクシー運転手のハイは、3ヶ月の交際を経て早々と結婚を決めます。
ズエンはハイにぞっこんですが、迎えた初夜でハイはさっさと寝てしまいます。
ある日、親友のカムのところへ結婚の報告に行ったズエンは、具合の悪い彼女のかわりに手紙を届けてほしいと頼まれます。
怪しいアパートに着いた瞬間、突然両腕をつかまれ、部屋に連れ込まれるズエン。
しかし彼女は、まだあどけなさの残るハイとは違う男の色気を放つトーに惹かれていくのです。
彼の誘いで通訳として現地旅行ツアーに同行するのですが……。
“ベトナム・ニュー・ウェイヴ”と北部の芸術映画
参考映像:“ニュー・ウェイヴ”作品が集結したベトナム映画祭2018予告編
ベトナム映画と言えば、日本でもトラン・アン・ユン監督ばかり取りあげられますが、この国の映画界にも実は“ニュー・ウェイヴ”が存在します。
すでに鬼才としての呼び声が高いファン・ダン・ジーはその代表的な監督の1人で、本作の脚本はハノイ映画演劇大学の卒業制作として執筆されました。
ベトナム戦争の最中にフランスへ移住しているトラン・アン・ユン監督は完全にヨーロッパ的感覚の持ち主ですが、ベトナム・ニュー・ウェイヴはもっと土着的なアジアの感性に根付いた流れです。
ベトナム映画の歴史的変遷としては、主に南側の地域で商業映画が発達し、ベトナム社会主義共和国建国後に映画局が設置された北のハノイは芸術性の高いインディーズ映画の拠点になっています。
ファン・ダン・ジー監督と同じハノイ映画演劇大学で学んだブイ・タク・チュエン監督は、ニュー・ウェイヴの旗手としてドキュメンタリー制作の道を歩みます。
ベトナム戦争の爪痕として残された地雷を撤去する男性の姿を追ったドキュメンタリー映画『土を掘る手』をドラマ化した『癒された地』(2005)は第6回NHKアジア・フィルム・フェスティバルで上映され、高い評価を得ました。
第6回NHKアジア・フィルム・フェスティバルで上映された『癒された地』(2005)
この作品で長編デビューしたチュエン監督は、その後も続々と野心作を発表し、現在は若手の育成にも力を注いでいます。
“ショット”の映画

(C)Vietnam Feature Film Studio1,Acrobates Film
まず、ファースト・ショットからしてすでにただならぬ雰囲気があります。
路地の一角を捉えたカメラがじりじりと移動を始め、物語の開巻をダイレクトに印象づける見事な冒頭部分。
しっとりと湿り気を帯びた画面からはアジア特有の官能美が感じられます。
そこから躍動感をもったショットが次々繋ぎ合わされ、常に弛緩することのない刺激的な映画体験に観客は酔いしれるばかりでしょう。
確かな演出力

(C)Vietnam Feature Film Studio1,Acrobates Film
さらにカメラは、俳優の演技をまるごとフレーミング出来る的確な位置に据えられています。
被写体との距離を一定に保つあたりに、この監督の人間への深い理解と慎ましい芸術的感性の洗練が垣間見えるでしょう。
こうした正確無比な演出力から、映画を単にストーリーを語るためだけの手段にはしないニュー・ウェイヴの創意と工夫が読み取れます。
また、ハノイの街並のリアルな表情を捉えたロケーション撮影に拘る彼らは、基本的にイタリアのネオ・レアリズモやフランスのヌーヴェル・ヴァーグの系譜に属するリアリズム志向の作家たちだと言えます。
官能の発露

(C)Vietnam Feature Film Studio1,Acrobates Film
必ずしも言葉になるとは限らない人間の複雑な感情をすくい取るのに映画ほど適したメディアも他にないでしょう。
本作では人間の性(さが)を取り巻くあらゆる要素が重層的に折り重なっています。
そのリアリズムがひとつの芸術的達成として実を結ぶのが、出張帰りの新妻ズエンが風呂場で見知らぬ女を目撃する場面です。
この決定的瞬間で、ズエンは一切取り乱すことなくカーテンを静かに閉めます。
抑制の利いた演出には品格があり、ここに言葉(台詞)が入り込む余地などありません。
画面に常に漂っている官能の薫りを感知さえすれば、瞬時に把握出来てしまう感情の襞。
そうしてエロスとタナトスの奔流へ誘われた観客たちは、もうただ“みることの快楽”に身を委ねるだけでよいのです。
それが映画のラストで大洪水のイメージとして実際に表象され、一気に魂が洗わられていく映画体験は壮観そのものでしょう。
まとめ

(C)Vietnam Feature Film Studio1,Acrobates Film
これはどまでに高い芸術性をもつ作品を発信し始めているベトナム映画は、すでにアジア有数の映画大国に数えられています。
その意味で本作は、ベトナム映画の“現在地”を指し示す重要な作品です。
今回同時公開される『ベトナムを懐う』と見比べ、芸術映画と商業映画の持ち味の違いを体感してみるのもよいかもしれません。
いずれの作品も今年必見のアジア映画であることはまず間違いないでしょう。
ベトナム映画に限らず、アジア映画の奥深さを理解するためには、前人未踏の“神秘性”に体当たりでに迫っていくより他に方法がないのです。