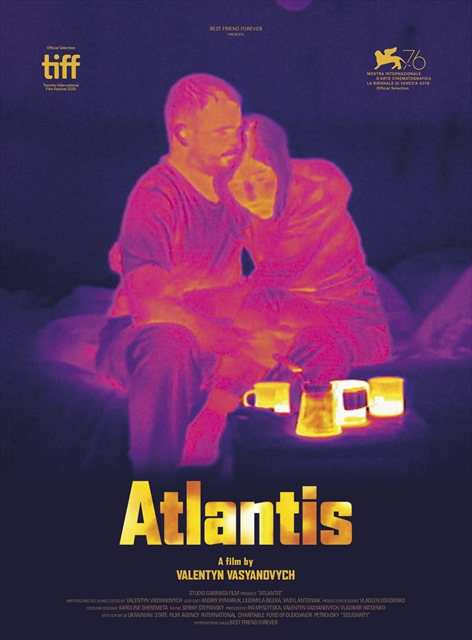第32回東京国際映画祭・コンペティション部門『戦場を探す旅』
2019年にて32回目を迎える東京国際映画祭。令和初となる本映画祭が2019年10月28日(月)に開会され、11月5日(火)までの10日間をかけて開催されました。

(C)Cinemarche
この映画祭の最大の見せ場となる「コンペティション」部門。今回も世界から秀作が集まり、それぞれの個性を生かした衝撃的かつ感動的な作品が披露されました。
その一本として、フランスのオーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー監督による映画『戦場を探す旅』が上映されました。
開催期間中にはゲストとしてオーレリアン監督とともに主演のマリック・ジディらも来日。映画上映後には来場者に向けたQ&Aもおこなわれました。
CONTENTS
映画『戦場を探す旅』の作品情報

【上映】
2019年(フランス・コロンビア合作)
【英題】
Towards the Battle(原題:Vers La Bataille)
【監督】
オーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー
【キャスト】
マリック・ジディ、レイナール・ゴメス、マクサンス・テュアル、トマ・シャブロル、オリヴィエ・シャントロー、セバスティアン・サシャーニュ、コスメ・カストロ、ネルソン・カマヨ
【作品概要】
内戦が激化していた1860年代前半のメキシコ。戦場カメラマンの黎明期でもあったこの時代に戦場へ赴き、被写体を求めて旅をしたフランス人と、その旅の途中で出会ったメキシコ人の出会いを通じて、戦争に巻き込まれる人々の悲劇、それを報道するジャーナリストの職業倫理を描きます。
作品を手掛けたのは、本作が長編初監督作となるオーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー監督。そして主人公であり戦場カメラマンのルイを、フランスの俳優マリック・ジディが務めます。
オーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー監督、マリック・ジディのプロフィール

(C)Cinemarche
オーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー監督(写真左)
フランス出身。短編、ドキュメンタリー、双方向インスタレーションなど多ジャンルの作品を監督し、多数の映画賞にて賞を獲得。「廃墟やそこに住む亡霊から強くインスピレーションを得ている」といいます。本作は彼の長編初監督作となります。
マリック・ジディ(写真右)
1975年生まれ、フランス出身。『クララ・シューマン 愛の協奏曲』『ダゲレオタイプの女』『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』ほかドラマ、映画で活躍。2001年開催の第51回ベルリン国際映画祭ではシューティング・スター賞を受賞しました。
映画『戦場を探す旅』のあらすじ

1860年代前半、フランスの写真家ルイは、カメラマンとしての名を上げるため戦場カメラマンを目指し、フランス軍司令官を説得してメキシコを荒廃させている植民地戦争の撮影に出向くことになります。
そして現地に到着すると、ひとりで2頭の馬を連れ、大量の撮影道具を抱えながら戦場を探し求める旅に出ることに。しかし肝心の交戦現場どころか、事前に確認していたフランス軍の部隊ともなかなか合流することができず、旅は難航します。
そんな中、ある場所で現地人のピントと出会います。最初は敵対心を持ち、言葉も通じずギクシャクした関係となっていましたが、その後合流したフランス軍部隊の現地語通訳者の助けを借り、二人は徐々に気持ちを通わせることになっていきます。
そしてそんな中でルイの運命は大きく変わり、彼の旅は金や名声だけを追っていたものから、自分の過去の亡霊に向かう道へと導かれていくのでした。
映画『戦場を探す旅』の感想と評価

戦争の歴史を描き、戦争の愚かさを訴えようとする映画作品において、その多くは戦争に参加している当事者、あるいはその戦争に巻き込まれる人々という視点によって描かれます。
しかし本作の物語における視点は「黎明期の戦場カメラマン」。物語に描かれている戦争の実像を第三者的な視点でとらえています。
戦場カメラマンは戦場の中ではあくまで戦闘には立ち入らず、中立的な立場にいようとしますが、それでも戦場カメラマンたちを蝕んでいく戦争を映し出します。さらに当時の戦場カメラマンたちの実情もリサーチし、この時代の戦場カメラマンが度々していたとされるいわゆる“やらせ”的な撮影のエピソードなど、戦争が生み出す「愚かさ」をさまざまに描き出しています。
物語の終盤では、視点はルイからピントへと移り、観客は戦争の「愚かさ」をもう一つの視点から見つめることになります。当時の歴史的な背景に対してのリサーチの深さを垣間見られる一方で、単に史事をなぞるにとどまらず、しっかりとストーリー作りをおこなっている点には、作品としての完成度の高さを感じられました。
上映後のオーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー監督×マリック・ジディQ&A
本作の映画祭での上映時にはオーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー監督、マリック・ジディが登壇。舞台挨拶をおこなうとともに、会場に訪れた観客たちからのQ&Aに応じました。

(C)Cinemarche
──本作の音楽を担当されたのはオルタナティブロックバンド「ティンダースティックス」のスチュワート・ステープルスさんでしたが、オーレリアン監督はどんなきっかけで起用されたのでしょうか?また音楽に関してはどのような方向で作業を進めたのでしょうか?
オーレリアン・ヴェルネ=レルミュジオー(以下、オーレリアン):私は「ティンダースティックス」の楽曲が前から好きで、是非スチュワートとも一緒に何かをやりたいと思っていたんです。
だから私から彼にオファーをしました。そしてシナリオを読んでもらったんですが、そのときに私が「このシナリオを読んで想像する音楽って、ちょっと怖い印象を受けるんだよね」と話したら、彼から「多分、僕らは気が合うと思う」と言われ、一緒に仕事をすることになりました。
この作品は19世紀半ばのメキシコが舞台ですが、決して昔の時代劇のようにはしたくなかったので、コンテンポラリーな雰囲気の音楽にしてほしいとリクエストしました。
当時の音楽というよりは、エレクトリックでもいいので、現代的でかつマリックさんの演じる主人公の内面も彷彿させるようなものにしてほしいとお願いし、あとは自由に、ともにコラボレーションしていく形で相談しながら制作を進めました。
私は音楽に関して専門的な知識があるわけではないので、メロディー云々というよりはどんな楽器を用いるのか、作った曲をどの場面にどう用いるのかという点でスチュワートとやり取りをしました。

(C)Cinemarche
──物語の終盤では、主人公ルイの息子ラザールが「赤い目」をして登場します。これは何をシンボライズしているのでしょうか?
オーレリアン:赤い目をした人間は実は物語の前半から登場しているんですが、その時点のルイはまだそれがラザールだとはわかっておらず、ただ何かにとり憑かれているととらえています。
実はそれがいずれも亡霊で、のちにラザールであると結びついていきます。ルイ本人のバックグラウンドである「息子が亡くなっており、そのことををどうしても受け入れられないでいる」ということに結びついていくわけです。
つまり最初は息子とわからない、そして物語が進むにつれて次第に気づいていく様を「赤い目」で示しています。そして主人公が長い間息子の死を受け入れられない苦悩を表現しているのです。
──150年前のメキシコを舞台に、「写真家」を主人公の職業に選んだのは何故でしょう?
オーレリアン:映画というものは、知らない時代、場所を描くことを可能としてくれるものだと思っています。だから私自身のエゴかもしれませんが、今回の映画を作るにあたって、敢えて自分が生きている「今」ではない時代、そして知らない場所を描こうと思いました。
またなぜメキシコかという理由ですが、当時のフランスがコロンビアを植民地にせんと参戦していたという時代背景が存在するのと同時に、ルイ本人が自分の内面と向き合いながら戦っていたという、そういった二つの戦いの場面がマッチするのではと思ったからです。そういった部分が、知らない時代の中で合わさっているというところが面白いと感じたんです。
オーレリアン:写真家を主人公にしたのは、私が昔の時代の先駆者たちに対して敬意をもっているというところにあります。初めて飛行機で海を渡ったという人間はもちろん、本作の主人公のような黎明期の戦場カメラマンもです。
かつて、戦場カメラマンたちは重く大きな機材を戦場へと運んでセッティングも行い、じっと待っていなければいけなくて…という風に、撮影自体のハードルが非常に高かったんです。
また、ルイという男性がいろんなものに付きまとわれ、その荷が重くのしかかっている、さらに多くの機材を持って常に移動しなければいけないという肉体的に困難な状況も描きたくて、あのような演出にしました。
一方で今回主人公に「写真家」を選んだのは決して偶然ではなく、写真家には「“そこにある現実”を撮って残す」という役割があります。主人公は息子を戦争で亡くしているけれど、メキシコに赴いてからも若い兵士、これから死ぬかもしれない、死ぬ運命にある人たちのその姿を永遠に残す役割を持っているわけです。
今回はいろんなものからインスピレーションを受けましたが、ベルギーのモーリス・メーテルリンクが自身の文献で、のちに亡くなる人々の姿を残すことを彷彿させる文章を書いており、それにも感銘を受けたので、そういったものを描きたいと思いました。

(C)Cinemarche
──マリックさんは、どのような思いの中で主人公のルイを演じられましたか?
マリック・ジディ:オーレリアン監督とは今回、役作りについていろいろと話を重ねました。これは監督が語られたことなんですが、ルイは「常に模索を続けている人、自分の亡くなった息子も探し続けているし、何かしらの形で死に向き合い続ける人物」なんです。
写真というツールを使い、亡霊にとり憑かれる一方で、強い意志を持ちながら何かに立ち向かって自分も何かを成し遂げたい、残したいと考えている人がルイであり、結構もろいところにいながらも強い意志を持って突き進んでいく人間です。そして彼を取り巻く環境、彼が存在したであろうその場に立つことで、私はルイに成り切って演じました。
──戦争写真家という職業に対して、監督はどのような思いを抱いていますか?
オーレリアン:今回はサリバンという、「偽物の戦場」を撮る人物が登場します。サリバンにように当時の戦場では、ある意味「演出」ありきで撮るということがあったらしいんです。
でもルイは「自分がやりたいのはこれじゃない」「“現実”を撮りたい」という思いがあり、映画の中でそれを批判しつつも、結局彼が撮りたかったのは自分が置かれている現実、戦場にいるかもしれない亡き息子だったということに気づくんです。だからこそ、実際に撮りたいものは見つかりませんでした。
そういった意味では、微妙なところにあった職業だったと言えます。ルイにとって、彼が立ち向かっているのは、ある意味死にも向かっているわけですが、そうしながらも彼は求めていた「現実」にありついた、という画が書きたかったんです。
まとめ

Q&Aでもオーレリアン監督が述べられていますが、劇中でルイは戦場を探す旅の中で、ひとりの赤い目をした亡霊のような存在に直面します。その亡霊の存在は、ルイが単なる第三者ではなく、この戦場に足を踏み入れたときにすでに兵士たちと同じように苦しみを背負ってしまう運命の象徴と言えます。
そんな存在を描いたからこそ、ルイのような「第三者」は単なる傍観者などではなく、同じく戦争という恐怖の中に足を踏み入れた者であることを明確にしています。
本作が「戦争に正義など存在しない」と断言し、あくまで争うことへの批判的な思いがたっぷり詰まった映画であると感じられるでしょう。