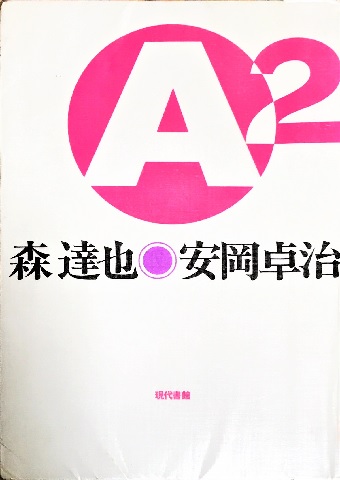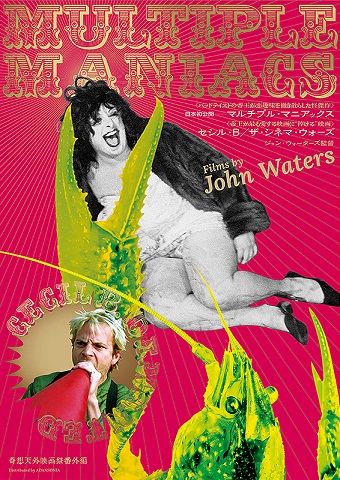連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第38回
こんにちは、森田です。
今回は4/6(土)よりポレポレ東中野にて公開される映画『沈没家族 劇場版』を紹介いたします。
90年代半ばの東京で、あるシングルマザーの母親がはじめた共同保育の試み。
“沈没家族”と名づけられたそのコミュニティで育てられた加納土監督が、自身のルーツをたどりながら“家族のカタチ”を問いかけるドキュメンタリーです。
そのコミュニティに関係のあった若者たちの集団「だめ連」や、そこから間接的に発展していった「素人の乱」などの思想に焦点をあてながら、現代の生存戦略、共生の方法を考えていきます。
CONTENTS
『沈没家族 劇場版』のあらすじ(加納土監督 2019年公開)

(C)2019 おじゃりやれフィルム
映画『沈没家族』は、加納土監督が武蔵大学在学中の卒業制作作品として発表したドキュメンタリー映画で、PFFアワード2017で審査員特別賞、京都国際学生映画祭2017では観客賞と実写部門グランプリを受賞しました。
各映画祭で高い評価を得た本作を再編集したものが、この劇場版となります。
加納監督は1994年生まれ。1995年、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件が起きて、バブル経済崩壊後のカタストロフィが決定的になったときに、母親の加納穂子が「共同保育」の試みを開始しました。
“開始”といっても最初から理念があったわけでなく、穂子(当時23歳)はシングルマザーのため、自分が家にいないあいだ息子を代わりに保育してくれる人を募集したのがきっかけでした。つまり生活の必要に迫られて、スタートしたものです。
場所は東京の東中野。彼女が撒いたビラを見て、10人ほどの若者たちが集まってきました。なかには同様に幼子を抱えた母親の姿もありました。
その保育人たちが、子どもの面倒を見ながら一緒に「共同生活」をすることになります。この取り組みはやがて「沈没家族」と呼ばれ、加納監督は何人もの大人たちに見守られながら育っていきます。
彼が「ウチってちょっとヘンじゃないかな?」とようやく気づいたのは9歳のころ。そして大学生になって改めてこう思ったそうです。
ボクが育った「沈没家族」とは何だったのか、“家族”とは何なのかと。
かつて一緒に生活した人たちをたどりつつ、型破りな母の想い、また不在だった父の姿を追いかけて、“家族のカタチ”を見つめなおしていきます。
さまざまな若者がひとつの“家”に寄りあい、子育てに奮闘した実践的な共同保育。
それは「新しい生活形態」かもしれませんし、「オルタナティブなライフスタイル」かもしれません。
ここでは「沈没家族」の軌跡から、その可能性の中心を見いだしていきましょう。
加納土監督のメッセージ

(C)2019 おじゃりやれフィルム
そもそも「沈没家族」という名称は、当時の政治家が「男女共同参画が進むと日本が沈没する」と発言したのを聞いて腹を立てた穂子が命名したもの。
その後、アパートが手狭になったこともあり、他の数組の母子や保育人とともに一戸建てアパートに引っ越しました。
今度は「沈没ハウス」と呼ばれたそのアパートでは、生活をともにしながら育児も分担し、居住者だけでなく多くの人が出入りする場所になっていきます。
まず、その“居場所のようなコミュニティ”を監督自身はどのようにとらえているのでしょうか。
「沈没家族」の意義

(C)2019 おじゃりやれフィルム
インタビュアーに「監督から見て当時の空気や家族観、また2019年現在のそれらも含めてどう感じますか?」と問われた加納監督はこう答えます。
僕が生まれたのが1994年でその翌年に、地下鉄サリン事件とか阪神淡路大震災が起きるんですよね。(…)僕は高校2年生の時に森達也監督の『A』を観てドキュメンタリーって面白いなあと思い始めたんですが『A』では特に、オウムを徹底的に糾弾する日本を通して、人が信じられなくなっている時代を映しているように僕は感じました。(映画公式サイトより)
“人が信じられなくなっている時代”、その対象は「既存の家族」であり「正しいとされる生き方」であるしょう。だれもが「普通」という価値観や概念を失ってしまったのです。
90年代半ばをそう顧みる一方で、加納監督は「現代」を以下のようにみています。
僕は2019年の日本は「理由が求められる時代」だと考えています。何か強いモチベーションがないとできない、気持ちが落ち込んでないとできない、夢がないとできない、目標がないとできないっていう風に社会が動いていってるんだと思います。
たしかに経済的な凋落の裏を返すように、精神面ではより良い暮らし、より素敵な夢を持つことが“普通”の感覚であるよう、強迫観念のごとくつきまとっています。
でも、沈没家族にはそういったものが必要なかった。(…)そういう時代だったからこそ、集まった人たちにとって沈没家族は「排除しようとする社会」からのシェルターだった部分もあると思います。
わたしたちは経済成長後の“うまい下がり方”をいまだ知らずにいます。過去の姿勢のまま今を生きることは、なにかと無理が生じて辛いことです。
もし「沈没家族」が監督が言及するような場所だったとしたら、むしろ時代の“最先端”を行っていたといえないでしょうか。
もっと卑近な例をあげれば、“モテない”、“職がない”、“うだつが上がらない”、それでも大丈夫だというコミュニティ(シェルター)こそ、つぎの社会のあり方が垣間見えます。
つまり「沈没家族」は必要に駆られてできた場所である一方で、その実践は「社会運動」の側面も持ちあわせていました。
たとえば「だめ連」との関係がそうで、そこをすこし掘り下げてみましょう。
ゆるく寄り添う「だめ連」

(作品社/1999)
「だめ連」とは、文字どおり「だめな人たちの連合」です。
普通の人のように働かない、恋愛しない、家族をもたないといった若者たちが、それを否定的にとらえるのではなく、互いに寄り添って自由に生きていこうと模索した集団です。
1992年に誕生し、その代表格のひとりであるぺぺ長谷川氏は、本作にも登場しています。

(C)2019 おじゃりやれフィルム ※写真中央 ペペ長谷川氏
「共同保育の実践」と「新しいライフスタイルの模索」をする人々が重なりあうのは、じつに自然なことでした。
「だめ連」は早稲田大学近くに「あかね」という交流スペースをもっていますが、いずれも「居場所」を軸に共生を目指すことが共通していますね。
その実際については、世代を下り、高円寺を拠点に同様の試みをしている「素人の乱」の運動から確認していきます。
「素人の乱」から考える生存戦略

(筑摩書房/2008)
「素人の乱」は、「法政の貧乏くささを守る会」という“闘争”を展開していた松本哉氏が、卒業後の2005年に高円寺でリサイクルショップを開店したことにはじまります。
ここでもやはり、「居場所」をつくることが先決だったようです。
著書『貧乏人の逆襲』で、松本氏は「あかね」をこう述べています。(引用は単行本から)
「あの『だめ連』(今の世の中ダメ人間になるのが当たり前じゃねぇか。ダメで何が悪いんだよコンチクショーという、最強の軍団)が中心になってOPENした店なのだ」P154
沈没ハウス、だめ連、素人の乱とつながっていることがうかがえます。
「街ぐるみ、地域ぐるみでのびのびやっていければ、助け合いなんかもできて、より楽になってくる。ついでに、仕事や遊びも自前で用意していけばストレスや浪費もぐっと減ってくる」P11
わたしたちの暮らす社会は、「自助」「公助」「共助」の3つの次元から成り立っています。
「自助」は“自助努力”という言葉があるように、だいたいが「自己責任」とセットで語られます。
「公助」は国からの再分配です。それは税金であったり、社会保障であったりしますが、昨今の政治状況をみると国自体が信用できるかという問題もありますし、公助に頼れば国の言うとおりにするしかなくなります。
そこで「共助」という次元が大事になってくるのです。それは「国」に対して「社会」の枠組みでおこなわれます。
いわば「町を拠点に生きる」ということですが、松本氏は面白くこう表現しています。
「地域ぐるみ、貧乏人ぐるみの自給自足作戦! これはすごい。要するに、職場、遊び、家などをひっくるめたとんでもないマヌケエリアがあって、なんでもかんでも自分らでできるようになっていけば何も怖い物がないのだ」P56
「沈没家族」は東中野から、「だめ連」は早稲田から、「素人の乱」は高円寺から、共生のコミュニティを形成していきました。
たとえ“だめ”な自分であってもいい。「国」ではなく「社会」の次元を厚くし、互いに助けあっていけば、みんな生きていけるのではないか。
そういう思想が読みとれます。共同保育も間違いなく、その一環としてとらえられます。
共助から生じる文化

(C)2019 おじゃりやれフィルム
「生存戦略」というと、かつかつの生活のイメージをもたれるかもしれません。
しかし、社会にコミュニティがあると、こんなことも起きてくるのです。
「ここまでコミュニティが出来てくると、店だけではなくいろんな企画も出てくる。近所の映画好きが集まり、『素人映画館』を名乗って映画の上映会を路上で勝手にやり始めたりした」P60
人が集まれば、おのずと「文化」が生まれてきます。「上映会」などはとても良い例でしょう。
またそれは、作り手にも恩恵があるようです。
「演劇をやったり映画を作ったりする人は高円寺なんかだと結構いて、よく小道具を捜し歩いてたりする。当然、こういう貧乏劇団や貧乏映画監督は100%金がなく、よくリサイクルショップなんかに探しに来る」P68
自分ではどうすることもできないことが、社会=コミュニティが提供してくれることがある、ということです。
「映画」はじつはそんな「社会」に支えられて、作られ、観られているのかもしれませんね。
そこで松本氏は「劇場作戦」なる戦略を打ちだします。
「とりあえず、多目的劇場を近所に作ろう。そこで自主映画の上映会をやったり、小さな劇団の芝居をやったり、面白い人を呼んできてトークイベントをやったりできる。(…)まったく違う分野のものと接する機会ができるので、今まで縁のなかったことに目覚めてしまったりするかもしれない」P86
革命後の世界を生きる

(C)2019 おじゃりやれフィルム
共同保育の実践を、社会における共助の試みに集約してきました。
加納監督は「沈没家族をどう捉えるか、それは多くの人によって違うと思います」と述べたあと、こうつづけます。
ただそれでも子育てをしている方や子どもと交流がしたいって思っている方はもちろん、そうじゃない方も、あ、こんな世界があったんだって知って欲しいです。自己責任とか、人に迷惑をかけるなとか、息苦しい世の中でこの映画が、見た人にとってポッとロウソクのように灯る希望の映画になったら嬉しいです。
本作の可能性の中心は、まさしく“こんな世界があったんだ”というのを提示することに尽きます。
かっこよく言えば「革命後の世界」を勝手につくって生きていたということです。
おそらく、近い将来、現実が「沈没家族」の後を追うことになるでしょう。