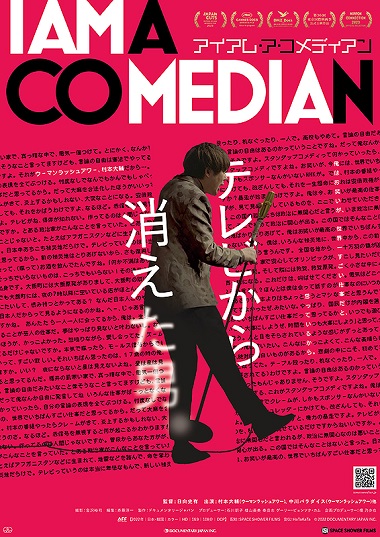連載コラム「映画道シカミミ見聞録」第52回
こんにちは、森田です。
今回は、4K修復版が2020年10月23日(金)よりYEBISU GARDEN CINEMAほか全国ロードショー公開される映画『天井棧敷の人々』を紹介いたします。
作品誕生から75年、フランス映画史にいまも燦然と輝く本作の見どころはもちろんのこと、当時の時代背景を顧みることで、その美しさの裏側に潜む重要なテーマも探っていきます。
映画『天井棧敷の人々』のあらすじ

(c) 1946 Pathé Cinema – all rights reserved.
舞台は19世紀前半のパリ。
劇場が立ち並ぶ「犯罪大通り」に生きる人々の数年間にわたる愛憎劇が、2部構成、190分の規模で描かれます。
とくに中心となるのは、天才パントマイム師のバチスト(ジャン=ルイ・バロー)が所属する「フュナンビュル座」で、彼が女芸人のガランス(アルレッティ)に恋に落ちることから、さまざまな“見せ場”が演じられていきます。
まずはその最初の場面をみていきましょう。
第1部「犯罪大通り」

(c) 1946 Pathé Cinema – all rights reserved.
通りの名が示すように、ここは犯罪多発地帯でもあります。
本作ではラスネールが悪漢の代表格として終始描かれ、その日も余興に見入っていた紳士から懐中時計を盗み去ったところでした。
濡れ衣を着せられたのは、その場に居合わせていたガランスで、紳士から一方的に犯罪者呼ばわりされてしまいます。
しかし、目撃者がただひとりいました。目の前で余興をおこなっていたバチストです。
彼はそれまで劇団では認められず、日々眠りつづけているような状態でしたが、突如、スリの一部始終を正確にパントマイムで再現してみせたことで、彼女の疑いを晴らしました。
この出会いにより、バチストの才能が開花しただけでなく、ガランスへのひたむきな愛も芽生え、彼の運命を大きく翻弄していくことになります。
深い眠りから覚め、また長い夢を見はじめたのです。
またこのガランスをめぐっては、女たらしの俳優ルメートル(ピエール・ブラッスール)や、先述したラスネールも夢中になり、それぞれの恋模様を紡いでいきます。
天井棧敷の意味
画像:『寺山修司劇場美術館』書影

PARCO出版 (2008/5/1)
作中の劇場は、そんな群像劇を取りこむ舞台装置です。
つまり、上演される芝居だけでなく、そこに集う人々の喜怒哀楽も舞台の要素に加えられます。
フュナンビュル座の座長が劇場の最上階を指さし「人生模様だ」と言ってみせるのがじつに印象的です。
そこは通常より安い料金が設定された“天井”の“桟敷(観客席)”であり、声援や野次を飛ばす民衆の姿が見えます。
その姿が無邪気な子どもたちのようだということで、本作の原題は「天国のこどもたち」となっています。
主役は意外にも、役者ではなく“子どもたち”のほうなのです。ここにテーマを読み解くヒントがあります。
劇場の「上下」が、人間社会の階級や貧富の差の寓意であることは、想像に難くありません。
また、本作にその名を由来する寺山修司の劇団「実験演劇室 天井桟敷」は、旗揚げ時に“怪優奇優侏儒巨人美少女等募集”のコピーを掲げ、多くの家出人が集まったといいます。
これらの対象から共通して浮かび上がってくるのは、“社会に入れない人たち”あるいは“棄民”へのまなざしです。
このことを踏まえ、つぎは「声なき声を演じるパントマイム」という視点に移っていきましょう。
パントマイムの意義
言うまでもなく、本作の大きな見どころのひとつは、名優ジャン=ルイ・バローのパントマイムにあります。
4Kでは劇中劇が映えるのは間違いなく、まるでバローの舞台そのものを鑑賞している感覚に浸れることでしょう。
動作で物語るというパントマイムの特徴とあいまって、往年のサイレント映画の気品も漂い、映画の原点の美しさも感じられます。
一方で、バチストは「なぜ声を出さないのか」とルメートルに問われた際に、こう答えています。
貧しい人たちには伝わるんだ。僕も同じだからね。生活はささやかだが、大きな夢がある。楽しませるだけでなく、感動させたい。怖がらせ、涙を誘いたい。
“天井桟敷”という舞台装置と、“パントマイム”という表現が、おなじテーマでつながってきました。
ジャック・プレヴェールの問う格差
画像:ドラクロワの絵画『民衆を率いる自由の女神』
 Eugène Delacroix – La liberté guidant le peuple
Eugène Delacroix – La liberté guidant le peuple
実際にはバチストの台詞を書いた脚本家の思想を追っていく必要があります。
フランスの国民的詩人ジャック・プレヴェール(1900‐77)は本作の脚本のみならず、シャンソンのスタンダードナンバー「枯葉」の作詞家としてもよく知られています。
プレヴェールが本作を書いた時代は、ナチスドイツによるフランス占領期にあたり、フランス共産党をはじめとするレジスタンス運動が絶えず進行していました。(戦後「枯葉」を歌ったイヴ・モンタンは、同党の活動に参加していました。)
また19世紀前半という作中の時代は、激しい階級対立をはらんでおり、1830年には復古王政を、1848年には王政そのものを市民が蜂起して倒しました。(前者をモチーフにドラクロワは『民衆を率いる自由の女神』を描きました。)
プレヴェールが格差や抑圧を映像美の裏で告発していたことは明らかであり、ある場面では「人間とは上流階級の人々だ」という台詞も残しています。
それに対する“子どもたち”の存在。バチストはある晩、路上で出会った男に、「あの店に行けば世間がわかる」と酒場に案内されます。
そこには劇団「実験演劇室 天井桟敷」のコピーのような老若男女が集い、古着商ジェリコのように偽名を使い分ける者たちがいました。
まさに「人生劇場」の様相を呈していたわけです。バチストは自分が見たものを芸の肥やしとし、犯罪大通りきっての人気俳優となっていきました。
一方そのころ、ガランスのもとにはモントレー伯爵が現れ、彼女は富豪との事実上の結婚を選びます。
第2部「白い男」
数年後。座長の娘ナタリーとの間に一児をもうけたバチストは、傷心癒えぬまま、フュナンビュル座の看板俳優として日々舞台に立っていました。
ガランスもガランスで、スコットランドで上流階級の暮らしを送るうちに、バチストを懐かしむようになり、ついにはパリの劇場までお忍びで通いだします。
ボックス席に座りながら、天井棧敷の人々を笑わせているバチスタを眺める日々。それに気づいた伯爵は、一緒に住むだけなく、自分のことを愛してほしいと、彼女に告げます。
なぜ貧しい者のように愛を欲しがるの? 貧乏者から愛までとらないで。
これが彼女の返事です。プレヴェールらしい洒落た言い回しですが、やはり愛という表面上のテーマにも格差の問題を投げかけてきます。
天国の子どもたちの勝利
貧しいからこそ、求めることができる。
この逆転の発想は、人生劇場における“子どもたち”の勝利を謳っています。
バチストがパントマイムの意義で述べたように、ささやかな生活には大きな夢が膨らむ余地があり、舞台も愛も謳歌できるものです。
終幕に向かうにつれ、ますますこの点が強調されていきます。
モントレー伯爵はガランスに付き添って『オセロ』を観劇してみましたが、「低俗」と嘲笑するばかりです。
階級対立と必然の結末
動画:オジリナルネガと修復後の比較映像
王侯にとっては「血塗られた悲劇」で、貧乏人にとっては「道化芝居」。現実でもこの対立をなぞるように、2つのエンディングが訪れます。
ひとつは伯爵と悪漢ラスネールとの間に、もうひとつはバチストとガランスの間に。
前者は“子どもたち”の勝利(革命)を直接的に示してくれるものですが、後者は革命を遂行するためにはこうならざるを得ない、という形です。
告発の行方は「愛の結びつき」よりも「融和できない対立」に向かいます。
それは狂言回しの役割を担ってきた古着商のジェリコが、群衆に紛れて「芝居は終わった、家に帰れ!」と叫ぶシーンに象徴されています。
主役は、最後まで天井棧敷の人々。一人ひとりの姿が鮮明に映し出される「4K修復版」では、そのポイントがより明確になると、期待が高まります。
彼らが演じる舞台は悲劇か喜劇かわかりませんが、ただひとつ、歴史と同様やり直し(再演)はできないというリアリズムをもって幕を閉じるのです。