講義「映画と哲学」第8講
日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。
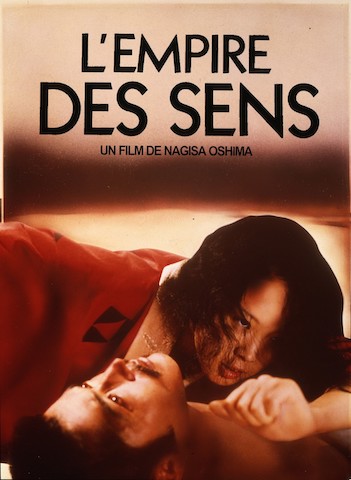
(C)大島渚プロ
第8講では、性的関係と享楽をジャック・ラカンの精神分析的観点から再考。それを踏まえた上で、大島渚監督の映画『愛のコリーダ』(1976)を分析してゆきます。
眼と眼差し:サルトルとラカン

ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』(小出浩之、新宮一成他訳、岩波書店、2000年)
今回は前回との関連から、性的関係と享楽について考えてみたい。ジャック・ラカン(Jacques Lacan 1901-1981)がセミネール『精神分析の四基本概念』(1964–1965年)で、「眼差しは同時に二つの眼差しであることはできない」というサルトルの見解に真っ向から反対して、「眼差しは見られるのです」と言っている(112頁)。しかし、この場合の眼差しとは、サルトルがいう意味での普通の他者の眼差しではない。
ラカンはそこで「眼差し」〔視線〕について、非常に印象的なことを語っている。我々には知覚器官としての「眼」があり、当然それは自分に属している。しかし、眼差しについては、あらゆる対象が眼差しを持っているというのだ。私が対象を見るとき、対象はそのずっと前から私を見つめている(逆に、我々は自分の眼差しを見ることはできない)。
ところで、あらゆるとき、あらゆる場所で私を見ているこの眼差しの主体はだれなのか?それは、我々がそうであるところの小文字の他者(l’autre)ではなく、決して現れることのない大文字の〈他者〉(l’Autre)である。大文字の〈他者〉とはラカンが無意識を位置づける場所であり、神が見ていると思ったり、良心の声が聞こえたり、我々を恥じ入らせたりするあの強迫的な存在である。サルトルは他者が与える恥辱を強調していたが、大文字の〈他者〉という観点はなかった。大文字の〈他者〉は現実存在という意味では、存在しないものである。
享楽とは何か
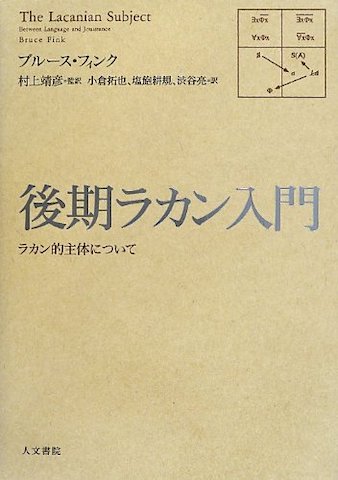
ブルース・フィンク『後期ラカン入門 ラカン的主体について』(村上靖彦監訳、人文書院、2013年)
ラカンを理解するのが難しいのは、その基本的な概念がことごとく存在欠如しているものを中心に編成されていて、それらを奇抜な言語表現(記号表現)によって受け取らねばならいことである。現実の男性器とは異なる幻想の「ファルス」によって喪失/欠如を喚起させるのもそうした表現である。誤解されがちな「去勢」も、性器切除のイメージからはほど遠く、人間が発達段階で大文字の〈他者〉、すなわち象徴秩序に参入する際に、禁止を言い渡され、多くの享楽を断念せねばならないということである。
ここでいう「享楽」(jouissance)も、厳密に精神分析的な用語である。「享楽」は、直接的な緊張の放出などとは違う、つまり単純な快感とは違う何かである。それは、かつてフロイトが快感原則の向こう側にある満足と名付けたものに当たる。普通われわれは快を求め不快を避けるが、その原則に反して、苦痛に満ちた経験が快をもたらすことがある(例えばリストカット)。また、われわれは自分の症状から快を得ることがある。それは何も神経症のような症状に限らない。風邪を引いた時、そこから得られる快とは、仕事をサボれることである。その満足こそが「享楽」である。もう少し一般的に言えば、ラカンのいう「享楽」は、直接的な快の表出が、象徴的な方法によって抑制されたものである。快楽にはすでに大文字の〈他者〉が関与している。大文字の〈他者〉の禁止、欲望、価値観をすでに体内化しているわれわれにとって、純然たる快のようなものはほとんどない。子供が親の禁止に反してやってしまった行為を反省し、自分に罰を与えている時、その時感じているであろう快感こそ享楽である。
もう一度言えば、精神分析でいう「去勢」とは、この満足ないし享楽の喪失のことである。それは、〈他者〉(まずは両親)から押しつけられた喪失だが、逆に禁止のプロセスを通じて、その失われた享楽は、単なる身体的な快から、いっそうエロティックで、不純で、猥褻なものに変化しているのである。それを次に追い求める時には、はるかに強度が増している。
「性的関係はない」

ジャック・ラカン『アンコール』(藤田博史他訳、講談社選書メチエ、2018年)
さて、ラカンのいう通常の「コミュニケーション」とは、すれ違いや出会い損ないのことなので、サルトルがいう一方的な恋愛に近い。同じ一つの性的な行為の中で、男性は男性の満足を求め、女性は女性の満足を求めている(快ではなく、満足)。それは一致するはずがない、それはうまくいかない、という直感にラカンは精神分析的な説明を与えている。その究極のテーゼが「性的関係はない」という表現だ。
ラカンが『アンコール』(1966-1967年のセミネール)で示している性別化の定式(139頁)は、言語存在である人間が自分を男・女として書き込むときに生ずる性別化の論理を表している。そもそも性別とは解剖学的にあらかじめ決まっている属性のようなものではない。それは、それぞれが去勢およびファルスとの関係で自己をどう規定するかによって決定される。男の側ではあらゆる主体が去勢の作用(象徴的な禁止、父の「否」)に服従している。この普遍法則には一人だけ例外者がいる。去勢をほどこす当の主体である(原父という神話的な存在)。なるほど、去勢されない一人の男だけは女と性的な関係を持つことができるだろう。しかしそれ以外のすべての男の享楽は、基本的に自慰的であり、向かっているのは欲望の原因となる部分的な対象(対象a)である。しかし、その性的なパートナーは幻想の仲介なしにはない。だから、男が直接的だと思っているパートナーとの関係は、幻想としての対象との関係である。男の享楽は身体に関係づけられる限り性器的なもの+幻想にしかならない。その単調な享楽をラカンは、ファルス的享楽と名付けている。
一方、女性の去勢はまずファルスの欠如そのもから始まるので、去勢の法則に普遍的に従っているわけではない。そこに示されるのは、女性を全体としてまとめることはできないということである。したがって、それに例外を対置することもできない。女性的な享楽は、それぞれが「一つ一つ」という欲望のあり方をしていて、つまり「すべて–ではない」(pas-tout)というあり方である。女性というカテゴリーに属する享楽は、ファルス的享楽だけには限られない。ラカンによれば、それは大文字の〈他者〉の享楽に参入する可能性が残されている。その享楽をラカンは〈他なる〉享楽という。いずれにしろ、男性の側からの一つだけの享楽のベクトルと、女性の側からの二つの享楽のベクトルはお互いに交わることがない。おおよそこれが「性的関係はない」ということの意味だ。しかしそれは同時に、男の構造を持つ女がいることと、女の構造を持つ男がいることをまったく排除するものではない。
貴婦人とドン・ジュアン
参考映像:『愛に関する短いフィルム』(1988)
前回言及した『愛に関する短いフィルム』は、最後にマグダが望遠鏡の向こうに幻想を見るという体裁になっていたが、これをラカン的にいえば、幻想のシナリオの出現とは、その幸福な光景の現前によって、「性的関係はない」を隠蔽することなのである。
歴史的には、ヨーロッパにあって恋愛の幻想のシナリオとして最も強固な伝統をもつのは、ラカンによれば「宮廷愛」である(セミネール『精神分析の倫理』)。11世紀に起源を持つ「宮廷愛」は、宮廷の高貴な女性に愛を伝える方法として、自ら障碍を作り、婦人たちを敬して遠ざけ、ひたすら詩によって伝達する騎士道的な振る舞いであった。それはいまだに現代人の恋愛幻想をいくばくか拘束している(トメクにもこの傾向があった)。ラカンにすれば、これは「性的関係はない」という根源的事実を巧妙に隠蔽するために設えられた文化装置なのだ。だが、より重要なのは、宮廷愛に登場する「貴婦人」という人物像に注目することである。人間が言語を習得することによって失ってしまった、物との原初的な関係を取り戻したいとする欲望がある。そうした失われてしまった対象を、ラカンは大文字の〈もの〉(le Chose)で表している。「貴婦人」とは、崇敬の対象としてこの大文字の〈もの〉の位置にまで高められた形象である。男から見て、言語以前的な〈もの〉の享楽を「貴婦人」が体現しているなら、おそらくそれが〈他なる〉享楽のイメージになろう。
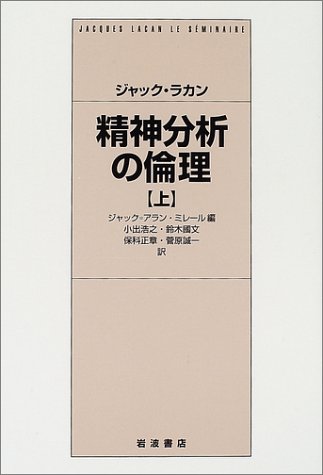
ジャック・ラカン『精神分析の倫理(上)』(小出浩之、鈴木國文他訳、岩波書店、2002年)
一方で、男の側でその対極をなすのが、ラカンのいうドン・ジュアンという形象であろう。ラカンは、『不安』(1962−1963年のセミネール)のなかで、「ドン・ジュアンは女性の夢である」(下58頁)と言っている。この場合のドン・ジュアンとは、一人一人の女性たちの欲望に応じて、それぞれ別の幻想を演じることのできる誘惑者である。ドン・ジュアンはすべての女を等し並に所有する原父の享楽とはまったくかけ離れている。原父とはすべての女を同じカテゴリーへとひとまとめにする機能であり、それらに同じようにアクセスする権限である。とすれば、ドン・ジュアンの方は「女なるもの」はないことをその実践で示す機能ということになろう。もちろん、このドン・ジュアンは物語やオペラを越えた神話的な幻想の人物である。ドン・ジュアンは女性たちにとって「完全に対等な男」であり、「ドン・ジュアンは何も欠如のない〔去勢されていない〕男です。」(同上)。要するに、ドン・ジュアンは、女の構造を持つ男なのではないだろうか。
さて、以上のラカンの所説を前提に、今回は大島渚(1932〜2013)がフランス製作で撮った映画『愛のコリーダ』(オリジナル・タイトルは『官能の帝国』である)を取り上げてみたい。この映画を倒錯的な行為の観点から見るか、愛の行為の観点から見るかは、二者択一ではない。フロイトもラカンも、人間の行為は、多かれ少なかれ倒錯的であると考えているのだから。
大島渚監督『愛のコリーダ』
参考映像:大島渚『愛のコリーダ 4Kリストア版』予告編
カンヌ国際映画祭2017「カンヌ・クラシック」部門上映に際して
時代は1936年、二・二六事件の起こった年、戒厳令下での出来事である。中野にある小料理屋に阿部定(松田瑛子)という若い女が仲居としてやって来る。ささいなことで仲居同士の喧嘩となり、包丁を手にした定を帰宅した主人石田吉蔵(藤竜也)が止める。定と吉蔵はその瞬間から惹かれあい、ほどなく隠れて待合で逢瀬を楽しむようになる。定は人並みはずれた強い欲望をもち、吉蔵の方はそれに応えられるポテンツを有している。彼らは芸者たちの歌舞音曲に合わせて交わり、それを見せて恥ずかしがらない。また、結婚の真似事をして、その床入りの一部始終を見せる。芸者たちを交えた乱行となる。定には名古屋にパトロンがおり、市会議員をしているその男に会いに行きもするが、金づる以上の意味はない。駆け落ちした二人の性交はますますエスカレートしてゆく。寝食を忘れ交わり続ける二人は次第にやせ衰えて行く。定の要求がエスカレートし、性交の最中に相手の首を絞めるという行為に及ぶようになる。束の間の外出の折り、吉蔵は戦場に動員される兵士の一群とすれ違う。宿に帰り、そこで最後の定との死を賭した宴が始まる。定は腰紐で吉蔵の首を絞め、殺してしまう。その直後、吉蔵の男根と睾丸を肉切り包丁で切断する。
『愛のコリーダ』をラカン的な観点から見る

(C)大島渚プロ
(1)ラカンは、セミネール『サントーム』の1976年3月16日の講義において、一本の日本映画を数人の仲間たちと見たことを伝えている。ラカンはそのタイトルを言わないが、内容からして『愛のコリーダ』である。ラカンはこの映画を見て、まず、女性のエロティシズムが描かれている事に驚かされ、次第に「日本女性の力」を理解するようになったと言っている。なんの「力」なのか。女の欲望の力であろう。定のリビドーは並外れており、欲望の主体として現れている。
(2)それに対して、「お前のためなら俺は何でもしてやるぜ」と言ってはばからない吉蔵の振る舞いは、一見すると「宮廷愛」の流儀を思わせる。定の命令口調に対して、逆らうことなく、そのほとんどの要求を恭しく受け入れる。娼妓上がりの定は「貴婦人」に列せられている。しかし、「宮廷愛」は本来、讃美者を「貴婦人」から遠ざけておく装置なので、二人の関係にはうまく当てはまりそうもない。しかし、必ずしもそうとも言えない。
(3)『アンコール』の一節に「ファルスとは、二つの性別化された存在の一方による、他方への奉仕に対する良心的兵役拒否のことなのだ」(16頁)というのがある。この一節と映画の印象的な1シーンとが妙に符合する。それは、吉蔵が戦場に動員される兵士の一群とすれ違い、伏し目がちになるが、途中から決然と眼差しを前方に向ける挿話的なシーンだ。実際の戦場へ赴くことへの「拒否」は、映画に見られる通りなのだが、ラカンを介すると、吉蔵がファルス的享楽を維持しているかぎり、定に対してもやはり「兵役拒否」を行っていると理解できる。あれだけ性交を繰り返しても、吉蔵と定との間には「性的な行為はない」。
(4)だがしかし、別の見方もできそうだ。吉蔵の性の奉仕は、必ずしも定にだけ向けられているわけではない。吉藏は嫉妬する女房を抑えるために交わり、宿の女将の欲望を察知してその「空き家状態」を埋めてやり、母親ほど年齢の離れた老妓を相手にして失禁させる。「すべて–ではない」女性の享楽に、一つ一つ対応する吉蔵には、ドン・ジュアンの面影がある。稀に見る吉蔵の奉仕的な愛は、むしろファルス的な享楽からズレるものではないのか。吉蔵の享楽は、〈他なる〉享楽に参入しているのかもしれない。
(5)それでは、あらためて、定の方から見るならば、定の欲望は経験が反復されることによって、その質が蓄積されていくようなものではない。むしろそれは毎回同じように始まり、毎回同じように終わる。毎回行われることが、何かセックスの失敗例として刻印されるような、つまりセックスというものの象徴化に失敗する行為のように見える。それは繰り返される麻薬摂取のようなもの、一種の依存症的な欲望である(ラカン言うところのサントーム)。したがって、定の無意識的なさまよいは、自分自身とその症状との同一化、症状がもつ享楽(症状と戯れること)の核へ向かうということになるだろう。その過程で、十分予想される「事故」が起こる。定の吉蔵との一体化への願望は激しく、窒息させるまで首を絞めたいという欲望と、吉蔵の諦念にも似た死への欲動が一致して、吉蔵の死(殺害)が出現する。
(6)最後のシークエンスについては、ラカンに従って、またラカンに反して「去勢」を考える必要があるだろう。ラカンの「去勢」はあくままでも幻想的なファルスの喪失/欠如のことであって、性器を切断するという出来事ではない。文字通りペニスを切り取る描写はラカンにはほとんど理解を絶する光景ではなかったか。ラカンはこのくだりを定の幻想だと解釈している。そのうえで、ラカンはなぜ定が吉蔵を殺す前に、男性器を切断しないのかと、訝しがる。ラカンからすると、定の幻想は、出会い損ない、つまり「性的関係はない」についての幻想でなければならないということになる。これはラカンにしてはやや初歩帰りのような印象を受ける。定によるぺニスの切断は、幻想のファルスとの一体化への慾望なのだろうか。
(7)ところで、定は実際にも吉蔵のペニスと睾丸二つを切断した(完全去勢、羅刹)。定はファルスと一体化し、ペニスが不要になったから、それを切断したのだろうか(ヴィトゲンシュタインの不要なハシゴ?)。事柄の順序が逆のように思う。たまたまペニスを切断することによって、ファルスと決別できる道を見つけたから、定はその後も生きることができたのではないだろうか。大島渚がどこかで言っているように、この映画はまったく心中ものではない。定は吉蔵を殺害した後、もうひと仕事成し遂げて、意志的にも生きようとしたのだ(三島由紀夫『金閣寺』の最後に似ている)。
(8)これは分析家たちが言うアクティング・アウトである。象徴化できないことを、行為が代わって表現すること。定はなぜ吉蔵のペニスを携えて歩かなければならないのか。捕まって、それを大衆という名の〈他者〉に見せるためである、誇らしげに。映画の最後に大島監督自身の声で、「事件は日本中を震撼させ、定には不思議な人気と同情が集中した」というナレーションが入る。大衆は受け取ったのである、欲望において屈しない者が一人はいるということを。本来自分たちの中にあったメッセージを。
文献一覧
ジャック・ラカン『精神分析の倫理(上)』(小出浩之、鈴木國文他訳)岩波書店、2002年
ジャック・ラカン『不安(下)』(小出浩之、鈴木國文他訳)岩波書店、2017年
ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』(小出浩之、新宮一成他訳)岩波書店、2000年
ジャック・ラカン『アンコール』(藤田博史他訳)講談社選書メチエ、2018年
Jacques Lacan, Le sinthome,Le Séminaire Livre XXIII, Le Seuil, 2005.
R.シェママ B.ヴァンデルメルシュ編『新版 精神分析事典』(小出浩之他訳)弘文堂、1995年
ブルース・フィンク『ラカン派精神分析入門 理論と技法』(中西信之他訳)誠信書房、2008年
ブルース・フィンク『後期ラカン入門 ラカン的主体について』(村上靖彦監訳)人文書院、2013年
Nagisa Oshima, In the Realm of the Senses, 1976 (The Criterion Collection) DVD.
田辺秋守プロフィール

(C)Cinemarche
日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。
早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。
著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。
『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。



































