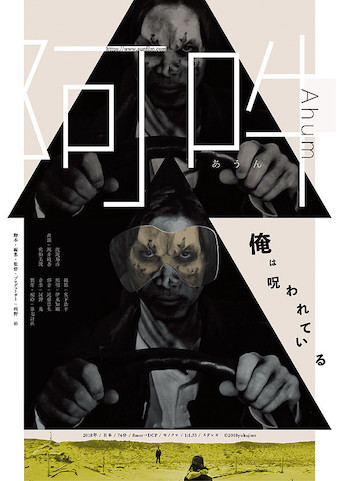映画『歌ってみた 恋してみた』は2019年7月6日(金)より絶賛公開中
東京・高円寺を舞台に、小心者でニートなサブカル女子と奇妙な仲間たちが繰り広げる日常を描いた西荻ミナミ監督のファンタジードラマ映画『歌ってみた 恋してみた』。
そして、“女装男子”として注目を集め、現在はタレント業・文筆業を中心に活躍中の大島薫さんとともに本作の主演を務めたのが、『ゴーストスクワッド』『あの娘が海辺で踊ってる』などで知られる女優・上埜すみれさんです。

(C)Cinemarche
このたび映画『歌ってみた 恋してみた』の劇場公開を記念して、上埜すみれさんにインタビューを行いました。
本作への出演経緯や役に対する様々な取り組み、役者としての原体験と映画に対する原体験など、貴重なお話を伺えました。
CONTENTS
当初は別役で出演する予定だった

(C)Harunohi Records
──本作を手がけられた西荻ミナミ監督との出会い、そして本作に出演されるまでの経緯についてお聞かせ願えませんか?
上埜すみれ(以下、上埜):西荻監督の前作で、いわゆる“百合”を描いた映画『CHUCHUあいす♡苺味』(2015)がある映画祭で上映された際に、私が百合好きということもあって観に行ったことがあります。
また私が井口昇監督の『キネマ純情』(2016)で主演をさせていただいた時には、西荻監督もそれを観に来てくださっていて、そこでお話したのが始まりですね。
本作への出演はSNS上での西荻監督からのダイレクトメッセージがきっかけだったんですが、実は当初オファーをいただいた役は、本作で実際に演じた主人公・ゆうこではなかったんです。
本当は別の役を演じる予定だったんですが、当時ちょうど西荻監督が主演オーディションを同時進行で進められていて、残念ながらその参加者の中にはゆうこのイメージに合う方がいなかったらしく、後日直接お会いした時に「主演やりませんか」と打診されたことでゆうこを演じることになったんです。
これまでになかった「普通で、イタい女の子」

(C)Harunohi Records
──そのような経緯を経て主人公・ゆうこを演じることになったわけですが、役柄に対してはどのような印象を抱かれましたか?
上埜:今までは結構アクの強い役を演じることが多くて、本作のような「現代に住む普通の女の子」という役はあまりなかったんです。幽霊などすでに死んでしまっている人間とか、プロレスラーとか(笑)。「現代に住む普通の女の子」を演じること自体が自分にとっては挑戦でした。
一方で「高円寺に上京してきたサブカルクソ女」と言われているように、普通の女の子とはまた違う“残念”な部分も多く描かれています。その点はなるべく、本当に“残念”な感じられるように演じたいと考えていました。
またキャラクター自体がいわゆる“二次元”チックな描かれ方をしていて、普通に可愛らしく演じてしまうとただ二次元のキャラクターをなぞったような女の子になっちゃうかなと感じたことから、ニートであるがゆえのダメさ加減や、モテなさそうなイタい感じを大事にして人間的な生々しさを出そうとしました。
──ゆうこを演じられたご自身は、“サブカル女子”と呼ばれる女性たちをどのように捉えていますか?
上埜:私もどちらかといえば、サブカル系・アングラ系女子なんです。メインカルチャーよりもサブカルチャーの方が好きですし、聴いている音楽もサブカル寄りですね。
大学時代の周囲の友だちもそういう方が多かったので、身近に見てきた“サブカル”感や“残念”感は本作への出演にあたって少なからず参考にしました。
「クリエイティブ」があった撮影現場

(C)Harunohi Records
──撮影現場の雰囲気はいかがでしたか?
上埜:監督によっては自身のやりたいことがはっきりしていて、その“再現”を役者に求められる方もいらっしゃると思います。
ですが西荻監督は、役作りや動作、セリフのニュアンスについても「いいよーやってみて」という感じでまず役者に委ねるんです。それゆえにとてもクリエイティブな現場で、自身のやってみたいアイデアもどんどん試させていただける、すごく楽しい現場でした。
また撮影ごとに西荻監督は少しずつ脚本を改稿されていたんですが、その都度改稿された脚本を私に送ってくださいました。ストーリーが少しずつ、けれどより良い形で変わっていったので、毎回「次は何が来るかな」というワクワク感をともに読ませていただいていました。
──劇中での上埜さんはいわゆる“姫カット”で演じられていましたが、その髪型も上埜さん自らが西荻監督にご提案されたとお聞きしました。
上埜:サブカル女子って結構姫カットにしているイメージがあったので、なるべく「二次元に憧れてやっているけど、なり切れていない」という感じを出すためにも、それに近い髪型にすることを西荻監督に提案させていただきました。それに、私も一度やってみたかったんです(笑)。
またセリフについても、西荻監督は「一言一句そのままの形で言わなくても大丈夫だよ」と言ってくださったので、細かい所は言いやすいように変えたりしましたが、セリフ自体を変えることはなかったです。
やっぱりルックスに関する提案が一番多くて、衣装もすべて私が提供していました。ただ衣装もサブカル女子っぽくしたくて、「Innocent World」というロリータブランドの服を少し着崩して着ていました。
「女装男子」大島薫との共演

(C)Harunohi Records
──本作は“女装男子”で知られる大島薫さんとのW主演となりましたが、大島さんに初めてお会いした際の印象や現場でのご様子はいかがでしたか?
上埜:「本当に綺麗だなぁ」というのが第一印象でしたね。事前に大島さんをご紹介された後にお会いしたので男性ということは知っていたんですが、街ですれ違っただけだったら女性だと思うだろうなと。
また美しさを保つためのストイックさは撮影などの中でも感じられましたし、ストイックさの原動力といえる美意識にもすごさを感じられました。
そして、性格がとてもイケメンな方でした。本作は11月頃に撮影が始まり、その後も3月など寒い時期での撮影が多かったんですが、待機中に「寒いですね」と話していたら温かい飲み物を買ってきて、私にさりげなく渡してくださったり。「ああ、イケメンや」と心の中では思っていました(笑)。
芸事の世界に触れて
参考映像:山戸結希監督『あの娘が海辺で踊ってる』(2012)予告編
──上埜さんはいつ頃から役者としての活動を始められたのでしょうか?
上埜:演劇の世界へ本格的に足を踏み入れたのは、大学に入ってからです。初期はサークル内で活動をしていたんですが、次第にサークル内だけじゃ物足りなくなって外部の劇場で活動するようになりました。
また大学には映画研究会もあったんですが、そこで山戸結希監督と知り合いました。その後自身が出演した山戸監督の『あの娘が海辺で踊ってる』(2012)がたまたま東京学生映画祭に出品させていただけることになり、それから多くの自主映画に出演するようになりました。
──役者としての活動を始められたきっかけ、あるいはそれに深く関わっている役者としての原体験などはあるのでしょうか?
上埜:私には幼馴染の男の子が二人いたんですが、一人が歌舞伎俳優や日本舞踊をやっている家の子、もう一人が能楽師の家の子だったんです。
そのため子どもの頃から能や歌舞伎、日本舞踊の舞台に誘われて観ることが多くて、その中で「芸事の世界って素敵だな」と感じたのが役者としての原体験ですね。スポットライトを浴びながら人前で何かやっている人が美しいと思えたんです。
また俳優さんや女優さん、歌舞伎俳優の方と接していると、普段はとても人当たりが良く優しい方なのに、舞台上ではなかなか話しかけられないような強いオーラを発していて、そのギャップに惹かれましたね。そして「自分もいつかこうなれたらいいな」と思い、役者としての活動を始めました。
母が教えてくれた映画

(C)Cinemarche
──映画についても子どもの頃からよくご覧になられていたのでしょうか?
上埜:そうですね。母が結構な映画好きで、母について行って映画館で作品を観ていく内に、自分も映画が好きになっていました。
本当に小さい頃だったので物語全てを理解してはいなかったと思いますが、スティーブン・ダルトリー監督の『めぐりあう時間たち』(2002)やアラン・J・パクラ監督の『ペリカン文書』(1993)、キャロル・リード監督の『第三の男』(1949)など「名作」と呼ばれる洋画たちを母はよく観ていて、私も一緒に観ていました。
今の私は邦画を観ることが多いですね。『四月物語』(1998)や『リリイ・シュシュのすべて』(2001)など岩井俊二監督の作品がとても好きで、目黒シネマでの特集上映にも行きました。
またミニシアター系の映画館に通って、知らない監督の映画を観たりしていました。そこで観た作品ではバフマン・ゴバティ監督の『ペルシャ猫を誰も知らない』(2009)が特に好きだったんですが、周囲では作品を知っている方が少なくて「面白いんだよ!」と言ってもあまり伝わらなかったです(笑)。
傷つくことなく生きていけてしまう社会で

(C)Harunohi Records
──ゆうことひかるが盲信し続ける“歌い手”タクローは非常に謎めいた存在として描かれていますが、上埜さんはタクローという存在をどのように捉えられていましたか?
上埜:タクローは作中でも全くその容姿などが描かれていませんし、実際に存在したかどうかも怪しいキャラクターです。
だから彼がどんな人物なのかを理解することもほぼ不可能なんですが、SNSや“歌ってみた”動画など、顔が見えない匿名性を持っているからこそ、ゆうこはひかるやSNS上での人間関係、そしてタクローを縁(よすが)にして生きてこれたんだと思います。
特定され“知ってしまった”生身の人間よりも、ほとんど何も知らない存在の方が自身の幻想を重ね合わせやすいですし、理想の相手にしやすい。その分だけ、タクローを盲目的に信じることができたんですよね。
“彼に会えたら、何か自分も変わることができるかもしれない”。そういう意味では、タクローそのものを曖昧な存在として描いたのは正解なのかなとは感じています。

(C)Harunohi Records
──ゆうこの台詞からは“傷つくことのない生き方”或いはそれ故に生じる“絶望”などを感じました。上埜さん自身は彼女を演じていく中でそういったものを感じられていたのでしょうか?
上埜:まず今の社会って、場合によりけりではありますが、傷つくことなく生きていけてしまう社会じゃないですか。
自ら行動を起こさなかったとしても、それなりに日常生活を送ることができてしまう。普通に学校へ通い、アルバイトをしながら生活することも全然できてしまう世の中ですから。
「行動しなくては!」という思いも、“なんとなく過ごせてしまう人生”の中で次第にゆるくなって、生きていってしまう。劇中、ゆうこが「タクローの正体が分かるかもしれないから行こう」と言うと、背中から翼が生える場面があるじゃないですか。でもやっぱり、自分から「やっぱやめた」と言ってその翼をもいでしまう。
自ら行動を起こそうとする人生と、なんとなく過ごせてしまう人生。その両面に自分が共感するものがあるなと思います。
祝祭的な映画

(C)Harunohi Records
──本作はカナザワ映画祭2018「期待の新人監督」でも上映されましたが、その時の観客の反応はいかがでしたか?
上埜:本作を観てくださったお客さんからは「面白かった」という言葉をいただけましたし、特に「今まで見たことのなかった上埜さんの姿を観られました」という言葉をいただけたのが記憶に残っていますね。
本作はともに主演を務めた大島さんはもちろん、様々な生き方をされてきた人々に溢れていている、非常に祝祭的な映画だなと感じています。
感動を誘うとか、問題提起を試みる映画とはやはり違って、お祭りのように鑑賞そのものを楽しんでもらえる映画が『歌ってみた 恋してみた』だと思っています。
本作がカナザワ映画祭さんに呼んでいただけたのも、それが一番の魅力だと感じとってもらえたからではないでしょうか。
上埜すみれさんのプロフィール

(C)Cinemarche
1992年生まれ、東京都出身。上智大学外国語学部・英語学科卒業(シェイクスピア研究)。
大学在学中にサークルを通じて演劇活動を開始。その後同学内の映画研究会を通じて山戸結希監督と出会い、実験的短編映画『Her Res 出会いをめぐる三分間の試問3本立て』、第24回東京学生映画祭・審査員特別賞を受賞した『あの娘が海辺で踊ってる』(ともに2012)に出演。以降も彼女の監督作はもちろん、多くの自主映画に出演するように。
また井口昇監督がプロデュースを手がけた女優アイドルグループ「ノーメイクス」の元メンバーとしても知られている。
演劇活動においては“コンテンポラリー能”と銘打ち、女性中心でシェイクスピアを上演する音楽劇団「鮭スペアレ」のメンバーとしても活動。さらに自身の町歩き写真集を三冊刊行したほか、イベントプロデュース、文筆業の分野でも活躍している。
映画『歌ってみた 恋してみた』の作品情報
【公開】
2019年7月6日(日本映画)
【監督・脚本】
西荻ミナミ
【撮影】
玉井雅利、田宮健彦
【音楽】
狩生健志
【キャスト】
上埜すみれ、大島薫、本村壮平、マメ山田、小林梓、深琴、しじみ、衣緒菜、佐藤ザンス、川端さくら、カメレオール、エリマキング、エホンオオカミ、やぶさきえみ、繫田健治
【作品概要】
東京・高円寺を舞台に、小心者でニートなサブカル女子と奇妙な仲間たちが繰り広げる日常を描いたファンタジードラマ作品。
本作を手がけたのは、映画・MV作品の監督の他にも音楽家・寓話作家としての一面も持つ西荻ミナミ。
そしてW主演を務めたのは『ゴーストスクワッド』『あの娘が海辺で踊ってる』などで知られる女優・上埜すみれと、“女装男子”として注目を集め、現在はタレント業・文筆業を中心に活躍中の大島薫。
映画『歌ってみた 恋してみた』のあらすじ
実家暮らしでニートなサブカル女子・ゆうこは、ネット仲間でいわゆる“男の娘”のひかるに誘われて上京。ひかるの家に転がり込みます。
二人は“歌ってみた”の動画で人気の“歌い手”タクローの信者という共通点がありましたが、信者たちの中にタクローの素性や顔を知る人間は誰もいませんでした。
そんなある日、二人のもとに憧れのタクローの正体を知るチャンスが訪れます。
絶好の機会を前に、怖気づいてしまう小心者なゆうこ。ですが自身の“妄想フレンド”たちに後押しされたことで勇気を振り絞り、タクローのもとへと向かいます…。