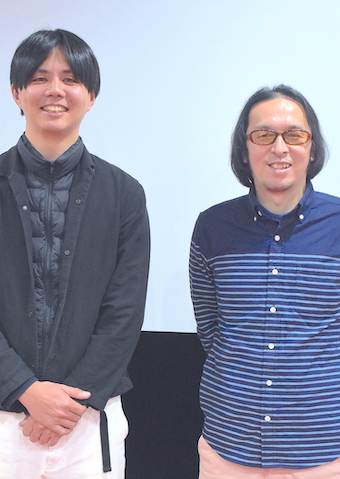日本映画界の伝説的なプロデューサー奥山和由が監督を務めたドキュメンタリー映画『熱狂宣言』。
DDホールディングス代表取締役社長の松村厚久氏を一年間観察し続けた本作は、全く新しいスタイルで撮影されました。

©︎ Cinemarche
松村氏は若年性パーキンソン病を患いながらも、2015年7月に自身の会社を市場第一部銘柄に押し上げた人物。
そんな松村氏を多角的に映し出した撮影手法と、「止まったら死ぬぞ!」の衝撃的なキャッチコピーについて探るべく、奥山和由監督へインタビューを行いました。
CONTENTS
原点回帰を求めた時に出会った怪物

©︎ Cinemarche
──『熱狂宣言』を観て初めに受けた印象は、まさにキャッチコピーの「止まったら死ぬぞ!」。奥山監督ならでは視点で描いた松村厚久さんの青春映画といった感じですね。
奥山:松村さんに会った時、何かインスパイアされるものを欲求している時でした。
原点に戻りたいという想いが潜在的にあり、解放されたいという気持ちと表裏一体に、いろいろなことをブチ壊してでも、自分回帰をしたいと思っていました。
その時に書店で『熱狂宣言』のハードカバーの表紙を見て「いい面構えだな、この人と会ってみたい」と感じました。
時代を動かす人間は、ある種、その世代の怪物でなければ時代に拮抗して動かすエネルギーは持たないし、怪物も魅力的な怪物でなければ引っ張れない。そういう面構えがある気がしました。
映画を作るかどうかは決めずに会うつもりでしたが、ドキュメンタリーにすることも考慮してカメラを背負って行ったら、十人以上の方に囲まれて、その中には小松成美さん(『熱狂宣言』著者)もいらっしゃいました。
さあ映画化!みたいな空気感の中で、松村さんがこちらを観察するように見ている目の奥を覗き込みながら、やはりこの人はある種の怪物だろうな、言葉を選ばないで言えば奇怪な存在でした。
自分が理想とする松村像を作り上げたという感覚

Ⓒ2018 吉本興業/チームオクヤマ
奥山:一年以上付き合ってきて、松村さん自身がイメージし発散しているエネルギーと、客観的に見たエネルギーが違うような気がしています。
松村さんは51歳で、僕より若いとはいえ、昭和の匂いがするディスコとか古いお水の感じも引きずっている。(笑)
今の時代、右も左も蹴っ飛ばすような、破壊力のある人物が皆無になっていますよね。
破壊を目的にしなくても、何らかの目的に向かうためには破壊をいとわずという大物系がいなくなっている中で、そうなる可能性があると思いました。
実像というのは、常に理想のイメージとは若干ギャップがあるけど、結局松村さんを一年間撮る中で、自分が理想とする松村像を作り上げたという感覚です。人に見せたい“松村厚久”という奇怪なる怪物を見せるということです。
松村厚久という人はこういう人だったらよりおもしろいなという画を並べてみて、ひょっとしたら松村さん自身がそれを見て、この松村厚久はおもしろいと思って、そっちに向かってくれるといいなというような想いもありました。
現実の松村さんは、地に足のついたビジネスをやっています。でも、僕から見たら松村さんの人間としてのおもしろさに目がいってしまう。
ビジネスマンとして優れているだろうけど、僕はそのことに興味が行かなかったですね。(笑)
──ドキュメンタリーでこんなに監督の色が出るのかと非常に驚きました。奥山監督も怪物ですよね。良い意味で破壊者。ずっと既存の映画と戦ってきたというか、想像を超えることをしていらっしゃいましたね。
奥山:ひとりで駒としてくるくる回ってみても何の影響力もなく、閉塞感、窒息感というものがありました。
何かやっても影響力がなければおもしろくないので、潜在意識の中でパートナーみたいな人を求めていました。
この人おもしろいなと思っても、次のステップが見えていかない。
そんな時に松村さんに出会ったわけです。おもしろい且つ次のステップに繋がっていくような人を、めちゃくちゃおもしろがりながら自分の鏡にしてみようと思っていた時、松村さんを知り、どうやってうまくやっているのかなということを単純に見てみたいと思いました。
それが例えばズルかったり、計算高かったら、こちらは冷めていきます。人間関係やお金に関して、人の嫌な部分はすぐわかります。
でも松村さんにはそういうところがない。それがないということが救われました。
あとは引き金を引くだけというところまで来ている

©︎ Cinemarche
奥山:人間て「ダメでもともと」じゃないですか。それが銃で言う所のトリガーだと思います。
撃鉄を起こす瞬間は「ダメでもともと」だと思わないと、撃鉄は起こせない。
あとは引き金を引くだけというところまで松村さん来てるから、頑張って引き金を引いてよと思います。
ここで落ち着かないでよと。
松村さんの良いところは、周りからの人間的・精神的なサポートに対して、感謝の気持ちがある人で、ありがとうと言えるところ。
あと照れ笑いをする時の抜群の可愛らしさ。
この映画で松村厚久はこうだよねと松村論を皆で語ったら、この程度だよという感じがしてしまうから、ここからこの延長線上をちゃんと作って欲しい。
映画界を見ていても、順調に儲けている人はピンハネがうまい人だったり、映画そのものがズルく回っている匂いがする時があって、そういう映画が当たってもね。
映画そのものに対してもそんな見方をする自分の歪んだ性格が故に、松村さんに対しても、歪んだレンズで見ているかもしれない。
だけど、僕は自分が描くとしたらこれだということを固定したい。
それが「止まったら死ぬぞ!」でした。
最初このコピーでやりたいと言ったら、皆ノーリアクションでした。
──キャッチコピーの「止まったら死ぬぞ!」は奥山監督の発案ですか?
奥山:僕が話す言葉からポスターデザイナーがピックアップしました。どういう映画にしたいか、どういう映画になるかということを話す言葉の中からポンっと引っ張る。
だから客観的に見てくれるところはすごく良いけど「止まったら死ぬぞ!」にすると言われた時は、さすがに戸惑いました。
でも試しにポスターに当てはめてみたら、ありだなと。
『熱狂宣言』の「熱狂」の意味合いを絞りたかったのです。もっとあがいてる感じに。それは気がついてみると、自分自身の中にありました。
カッコイイことではなくて、当時あがいていて、自分のフラストレーションが溜まっていたのでしょうね。
松村さんはがめつくなくて、お金の匂いがしないところが特別な人ですよね。
だから丸々を見てもらうしかなくて、僕が映画を自分の鏡として作っているのと同時に、自分自身が映画に対して照り返しているという関係から言ったら、もう頭で考えるのをやめて作った作品です。
自分が好きなように『熱狂宣言』を作った

Ⓒ2018 吉本興業/チームオクヤマ
──本編でクリエイティブについて話す場面がありましたが、奥山監督のクリエイティブとはどのようなものですか?
奥山:人生は、紆余曲折あるように見えながら、その人にとっては一直線だと思います。
ものを作るということは、悪く言えばわがままで、よく言えば自己実現。自分はこうだよというだけのシンプルなことです。
ただその中で、人に伝えて初めてクリエイティブだから、どういう範囲の人たちが反応するかということを予測し計算して、そしてこれだけビッグヒットを作りましたでは、個人的にはクリエイティビティとは違うような気がしていて、それはビジネスの正確な計算です。
もっとクリエイティブということのわがままさがあって、且つわがままをする以上は礼儀があるから、人に伝える。
わかりやすく、なるべく人の共通項に到達するという努力をする必要がある。
だから今回はある意味、僕が好きなように『熱狂宣言』を作ったと思う。
あまりに好きなように、ナレーションも入れずに作ったから、なるべくご迷惑をかけないように、できるだけ短くしたということもあります。
よくこの映画を観てくださいって言う時に、ご迷惑をかけても1時間15分で終わりますからと言うくらい、自分が勝手なことを言うことに付き合ってくださいという謙虚さが必要なのだと思います。(笑)
──松村さんの身近な方にカメラを託したことにはどのような考えがありましたか?
奥山:松村さん自身から抽出するもので自分が思う画を作っていきたいということがあった。
松村さん自身じゃなくなったら、材料は全部絵の具にならなくなるわけです。
松村さん自身というものを、ナチュラルに、できたら生々しく撮って欲しいという想いで行ったら、生の松村さんはカメラを向けられると意識してしまった。
身近な人がカメラを構えて、撮影を忘れられるように、その時間を待つしかないということが基本でしたね。
映画は、映す側と映される側の関係性がすごく大事で、どれだけ安心させるか。
カメラは圧ですから、その圧をなるべく減らして安心させて、それで自分がこういうふうに見られたいという意識を忘れてもらうようにしていく。
──素人にカメラを託すやり方は、奥山監督が過去に北野武さんや秋元康さんなど映画界の経験がない人たちに映画を撮らせたことと同じように感じました。そうして撮れた映像が六本木ヒルズで上映されてしまう。本作は偉大なるホームムービーですね。
奥山:間違いなく、まっとうな映画ではないですよ。だけど揺さぶりをかけていく映画も必要。
そこで初めて『カメラを止めるな!』みたいな映画ができると思う。
揺さぶりをかけるものが、正確なものではなくても、どんどん石を水の中に投げてみる。
『熱狂宣言』はある意味ホームムービーだけど、ホームムービーを隅っこの映画館で観てたって広がらないから、意思を明確にするために六本木に入れないとね。
──六本木は松村さんと奥山監督にピッタリ。松村さんを観るということに対してすごく分かりやすく、一対一として書籍を読んで、奥山監督が撮りたい、興味がある、衝動的、そのことが全部繋がっていて、やはりプロデューサーなのだと感じました。
奥山:最初に、僕が一人で映画館(TOHOシネマズ 六本木ヒルズ)の責任者に会いに行って、興行にも一つのストーリーが必要で、『熱狂宣言』は一館でずっとやりたいと言いました。
贅沢は言いません。レイトで一回、その代わり長くやってもらいたい。ガラガラになっても続けてとは言わないから、迷惑かけないところまで長くやってください、そこにこだわりたいと言いました。
最初にイメージした勝負がちゃんと着地できればいいなと思っています。

©︎ Cinemarche
映画『熱狂宣言』の作品情報
【公開】
2018年(日本映画)
【製作・監督】
奥山和由
【キャスト】
松村厚久
【音楽】
木下航志
【プロデューサー】
江角早由里
【作品概要】
制作・宣伝・興業すべての手法において、今までにはない映画を創ることをコンセプトに掲げたフリーシネマプロジェクトの第1弾映画。
被写体の身近な人物にカメラを預け、映画を観る観客の主体性に問いかけるダイレクトシネマという手法を用いた、奥山和由監督の全く新しいドキュメンタリー作品。
映画『熱狂宣言』のあらすじ

Ⓒ2018 吉本興業/チームオクヤマ
松村厚久、51歳。かつて、外食界のスター、革命児、天才、ビックマウス、不思議ちゃんなど、数々の異名を持った人物です。
松村は東証一部上場企業のDDホールディングス代表取締役社長であり、従業員約1万人という仲間を抱えていました。
彼が経営する店舗数は約500店、その年商約500億円だといいます。
ひと昔前のバブリーさを感じさせるほど、彼らは今も派手で賑やかな宴席を開き、その中心に松村はいました。
松村自身は周囲の人物や、その仲間たちに一切の手を抜かず、全身全霊のサービス精神で仲間たちを楽しませる性分でした。
奥山和由は、ひどく落ち込んだ時に古本屋で手にした書籍「熱狂宣言」で松村の存在を知ります。

Ⓒ2018 吉本興業/チームオクヤマ
「果たしてこんな立派な男が実在するのだろうか…」と感じた奥山は、とにかく一度会ってみたいという衝動から、この映画作りはスタートしました。
奥山は松村を前にして、3日前にドキュメンタリー映画を撮りたいと考えたと、自身のブレーンに映画化企画を話したというと、応対した松村は二つ返事で取材交渉を成立させます。
13年前から難病の若年性パーキンソン病を患っている松村ですが、それでも自らを“幸運な人間”だと断言して、日々を楽しみ生きていました。
しかし、そんな松村もキャメラを前にすると、「撮れ高」を気にしたような外連味を見せてしまうことから、この作品では映画作りのプロではない、松村の周囲にいる会社の仲間たちにキャメラを託すと…。

Ⓒ2018 吉本興業/チームオクヤマ
この映画は書籍「熱狂宣言」をなぞらえて作られた作品ではありません。
ドキュメンタリー作品に明確なストーリーもなく、ナレーションも入っていません。
また、松村が何を話しているかも時に聞き取れない場面も多くあるが、それでも松村に寄り添う感覚を観る者に感じさせていく…。
まとめ

©︎ Cinemarche
奥山和由監督のインタビュー前に、プロデューサーとして製作をした過去作品を見返しからお会いしました。
奇しくも『熱狂宣言』の被写体である松村厚久さんと自分は同年代。奥山映画と共に育ち、80年代の日本映画界の閉塞感を突破する作品に魅せられ、常に脅かされ続けてきました。
今インタビューのなかで印象的だったのは、松村厚久という人物に対して、「松村さんはこれからのある」と、五十路を迎えた男の伸び代を見出したスケールの大きさです。
今を生きる松村さんを「止まったら死ぬぞ!」と挑発し、完成させた作品やその興行のひとつひとつで、松村さんという人間の生き方を勇気付ける視野の広さ。
そのことは奥山流の映画人としての他者への仁義であり、人間作りの眼差しなのだと実感させられました。
また、奥山和由さんにとって映画とは、「ダメでもともと」という後先ないの青春のギラギラそのもの。“映画という銃”のトリガーを躊躇なく引く生き様は今後も続きそうだ。
映画『熱狂宣言』は、2018年11月4日(日)よりTOHOシネマズ六本木ヒルズにて熱狂ロードショーです。
インタビュー/出町光識
写真/苅米亜希
奥山和由監督のプロフィール
1954年12月4日、東京都出身。
20代後半からプロデューサーを務め、『ハチ公物語』『遠き落日』『226』などで興行収入40億を超える大ヒットを収めます。
一方、『その男、凶暴につき』で北野武、『無能の人』で竹中直人、『外科室』で坂東玉三郎など、それぞれを新人監督としてデビューさせます。
『いつかギラギラする日』『GONIN』『ソナチネ』などで多くのファンを掴む他、今村昌平監督で製作した『うなぎ』では、第50回カンヌ国際映画祭パルムドール賞を受賞しました。
1994年には江戸川乱歩生誕100周年記念映画『RAMPO』を初監督、1998年チームオクヤマ設立後第1弾の『地雷を踏んだらサヨウナラ』は、ロングラン記録を樹立。
スクリーン・インターナショナル紙の映画100周年記念号において、日本人では唯一「世界の映画人実力者100人」のなかに選ばれています。
近年も中村文則原作「銃」などをプロデュース。
受賞歴は、日本アカデミー賞優秀監督賞・優秀脚本賞、日本映画テレビプロデューサー協会賞、Genesis Award(米国)他多数。