ちば映画祭2019「清原惟監督特集」
「初期衝動」をテーマに掲げ、2019年で10回目の開催となった「ちば映画祭2019」で特集された清原惟監督。
2018年には、東京藝術大学大学院の修了制作として手がけた初長編作品『わたしたちの家』が渋谷ユーロスペースにて公開され、彗星のごとく現れたその才能に多くの映画ファンが驚きと恐怖を覚えました。
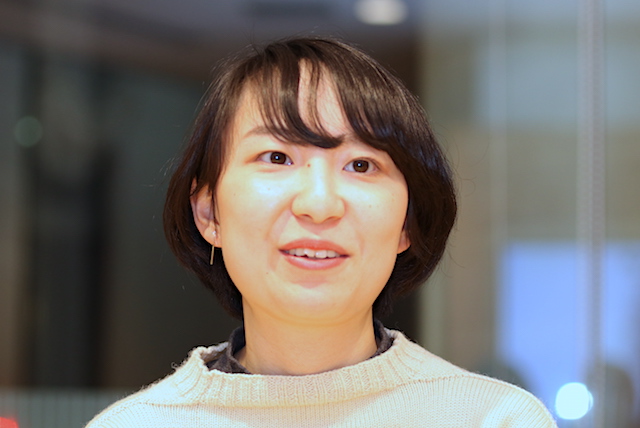 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
並外れた表現力で映像と音響の宇宙を自在に想像(創造)していくイマジネーションは一体どこから沸き上がっているのでしょうか。
今回は、清原監督の頭の中に広がる発想(宇宙)の秘密や映画制作のモットーについて詳しいお話を伺うことが出来ました。
“清原ワールド”の立ち上がり

──特有の世界観はどのような発想から初まるのか教えてください。
清原惟(以下、清原):作品ごとにそれぞれ違うのですが、大学の卒業制作の『ひとつのバガテル』でいうと、自分自身の物語でもあると言えるかと思います。
当時の自分は美術大学でものづくりをする環境にいて、いろんな困難はあったのですが、それなりに恵まれた環境でものづくりが出来ていると思っていました。でも、もしかしたら人生のどこかで分岐してしまった、そうじゃない自分もいたかもしれないなと考えたりする時がありました。
主人公のアキという女の子は、ピアノを弾いているのですが、経済的な理由などで学校に通って勉強をできない境遇にあります。それでも毎日自分のペースでピアノを練習しているんです。どんな境遇にあっても、その状況にいるひとなりのやり方で、やりたいことをやり続けるというのは、困難なことだけど、切実なことだと思っていました。
あとは、普通に生きているだけで面白いこととか、変だなと思うことがいっぱいあるじゃないですか。別に映画を作ったり表現をしていなくても、そういう瞬間に立ち会う時ってあると思うんですよね。そういうものをたくさん集めて、散りばめていくように作っていきました。
──撮りたいものを撮るという感じでしょうか?
清原:そうですね。私も映画は好きで、過去作から近年の映画までいろいろと観て、その中で自分の映画作りを培ってきたことが大きいので、意識下でも、潜在意識下でもたくさんj影響を受けていると思います。
でも、どちらかと言うと、自分自身の個人的な感覚とか人生への考え方から出発していたり、身近な人物、友達であったりとか場所だとか、そういうものからインスピレーションを受けているのが強いです。
ただもちろん、鑑賞してきた作品が反映されているというのは自分でも感じますし、それも自分にとっては大切なことの一部なのでミックスされている気がします。
ヌーヴェル・ヴァーグからの影響
 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
──具体的に影響を受けた作品を教えてください。
清原:高校生の頃から、ヌーヴェル・ヴァーグのジャック・リヴェット監督が好きでした。
一番最初に映画を撮ったのが、高校二年生の時だったんですが、映画を撮りたいと思ったきっかけはリヴェット監督の映画だとか、大きな映画館でかかることのないような映画をみたことが原体験としてあります。
──作るよりも先に見ることがあったわけですね?
清原:そうですね、やっぱり見ることから映画が好きになって、それも小さい頃からではなくて高校生くらいになって、昔の映画やミニシアターでかかるような映画を観た体験というがありましたね。
──ジャック・リヴェット監督のどの作品がお好きですか?
清原:『セリーヌとジュリーは舟でゆく』(1974)とか『北の橋』(1981)、『彼女たちの舞台』(1989)がすごく好きですね。パリの日常的な景色の中に魔術的な空間が生まれちゃうという、日常と魔法がいとも簡単に地続きになって接続されているのがほんとうに素晴らしいなと思います。
パリの街と私たちの住んでいる東京の街とは全然違う場所ではあるんだけれど、日常と魔術的なものが繋がってしまう感覚は、自分自身のリアリティとして感じられるものでした。
参考映像:『セリーヌとジュリーは舟でゆく』(1974)
ロケーションの選び方をすごく参考にしていて、ただただ身の回りのものを撮るのではなく、映画はワンショット、ワンショットで全く別の場所を同じものとしてみせられるわけですね。それによって新しい場所というのか、現実には存在しないけど現実が写っているような、別の空間が立ち上がってくる感じをヌーヴェル・ヴァーグの人たちは、特にセットを立てているお金もなかったのにやっているので、そういうロケーションの使い方に影響を受けました。
だから自分もたくさんロケーションハンティングを重ねて、好きな場所を全然離れた場所と繋げて、自分自身の街を作り上げるような気持ちがありました。
──映画好きが実際に映画を撮る時に、フランソワ・トリュフォー監督の『映画術』を参考にすることは多いですが、清原監督の場合はいかがでしたか?
清原:本を読んで映画の技術についてちゃんと勉強しようと思ったのは大学に入ってからですね。(笑)
学生映画の醍醐味
 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
──高校生で初めて映画を作られた時はどうでしたか?
清原:初めての時は、映画の作り方が全く分かりませんでしたね。
ただただ映画を観ていただけで、こういうものが撮りたい、でも自分が撮るにはどうしたらいいのか、手探りで探さなくちゃいけない。撮った作品も凄く日常的な物語で、友人に出演してもらって、自分の通っている学校で撮ったりとか、家の周りの景色とか、そういう自分に近いものを撮っていました。
面白いなと思ったのが、自分が普段みている平凡な日常、退屈な日常とか、何気ないものたちが、映画に撮ると、別の見え方をして、知らなかった良さが見えはじめる瞬間があって。それが一番の手応えとして、もうちょっと続けてみたいなと感じていました。
──武蔵野美術大学の卒業制作と、東京藝術大学大学院の修了制作での違いはいかがでしたか。
清原:学部の時は、役割はありましたが、少ない人数でやっていたので、持ち回りで流動的に色々やっていました。カメラは自分で回していましたし、美術や衣装も自分でやっていました。
大学院に入ってからは、撮影領域、脚本領域、プロデュース、美術など部署ごとに分かれているので、それぞれの部署の人が集まって一個の座組みを作って制作するという体制になりました。今までフォーマット的に映画業界が積み上げてきた映画の撮り方を学ぶ場として大学院がありましたね。
学部の時より細かい分業スタイルになって、人に任せる部分が大きくなったので、最初は戸惑いもあったんです。
そこで起きるコミュニケーションの取り方もわからなかったし、拘りが強いところがあるので、それを人にどう伝えたらいいのか、あるいは各部署でその人自身のやりたいことがあったりして。学生の映画だから仕事で割り切るというのとも違いますし、他者と自分のやりたいことの折り合いの付け方を勉強させてもらいました。
結果として『わたしたちの家』は、自分以外の人たちのセンスや力みたいなものが入っている作品になったと思っています。
私が細かく指示しているところもありますが、一方でかなり任せている部分もかなりあったりして。美術も担当の子が自分で考えてやってくれて、最初に大きなイメージを渡してそこから膨らませてくれるわけで、一人で考えるよりももっと豊かなものが濃密になっていった感じでした。
それが、『わたしたちの家』のテーマでもある、「他者への想像力」と繋がって、よい作用になったいうのは今だから思うことですね。(笑)
フレームと演技
ちば映画祭のトークショーで来場者に作品の想いを伝える清原惟監督
 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
──学部時代は撮影をご自分で行なっていたということですが。
清原:そうですね、カメラはほとんど回していましたね。写真はずっとやっていたんです。
中学生くらいからフィルムで写真を撮っていて、日常をあるフレームの中に切り取っていくということが面白いなと思ってました。
動画とスチールは全然違うものではありますが、カメラを使うという根っこの点では似ているところがあるから、あまり抵抗感なく最初から自分で撮影していました。
──カメラのフレームに被写体を捉えていくという感覚はすでにあったわけですね。
清原:映画を見ていてもフレームの取り方などは気になって見ていました。どういうふうな画を作るのか、すごく意識していましたね。演出しながらカメラも自分で回すので、最初はカメラを通して芝居を付けていく作業になっていたのかな。
それが『わたしたちの家』などの藝大作品からは、他の人にカメラをやってもらうようになって、もう少しカメラのフレームの外を意識して生のその人をみて演出することを学んでいったような気がします。
演出家の距離感
──『ひとつのバガテル』と『わたしたちの家』の芝居を比較すると、演技の持続に変化があるように感じますがいかがですか。
清原:おそらく一番の違いは、本業で演技をする俳優か、全くの素人かどうかというところだと思います。あとは、私と出演者との関係性の距離というのがありますね。
『ひとつのバガテル』は本当に身近な人しか出ていなくて、八百屋役の方は役者さんでしたが、もともと積み上げてきたお互いの関係性があって、相手のパーソナリティ、喋り方の癖、歩き方、テンポ感などを理解し合いながらやっています。
参考映像:『わたしたちの家』(2017)予告編
『わたしたちの家』はそれとは違い、ほとんどの方がオーディションで会っていて、リハーサルもそんなに時間が取れませんでした。もともと演技をやっているという素地があるということと、私との距離がまだ遠いこともあって、その違いが多分画面には明確に出ているのでしょうね。
ただ、自分の意識の中で変わらない点もあります。俳優は演じるスキルは持っているんだけど、その人自身というのがやっぱりいるわけじゃないですか、その人のキャラクターというのはいつも重視したいです。その人の役ではないけれど、その人自身でそこに立っているという事実は大事にしています。
──演出家として俳優自身の生々しさを撮っていきたいということですね。
清原:演技している時よりも、普段会話している時の方がこの人魅力的だなと思う瞬間があります。それは俳優からするといいのか悪いのか分かりませんが、でも少なくとも自分はそちらの方がいいなと思ってしまいます。演技らしさみたいなものを削ぎ落としていく傾向はどうしてもありますね。
【清原惟インタビューの後編⑵はコチラから】
につづく……。
インタビュー後半では、いよいよ清原惟監督のパラレルな世界観の秘密へ踏み込んでいきます……。
インタビュー/ 加賀谷健
撮影/ 出町光識
清原惟監督プロフィール
 ©︎Cinemarche
©︎Cinemarche
1992年生まれ。東京都出身。
武蔵野美術大学映像学科卒業、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻監督領域修了。黒沢清監督、諏訪敦彦監督に師事。
東京藝術大学大学院の修了制作として手がけた初長編作品『わたしたちの家』が、ぴあフィルムフェスティバル2017でグランプリを受賞し、2018年には渋谷ユーロスペース他、全国各地で上映されました。
今、最も注目を集めるインディーズ作家の1人です。




































