講義「映画と哲学」第4講
日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。

第4講では、ヘーゲルの喜劇論とともに、1895年にリュミエール兄弟が上映した『水をかけられた水撒き人』から喜劇俳優バスター・キートンやマルクス兄弟の作品まで、いくつかの実例を題材に映画における「喜劇的な行為」について考察をしていきます。
CONTENTS
喜劇について
前回までは、悲劇について論じたので、今回は喜劇的な行為について述べたい。アリストテレスが『詩学』の第2部で喜劇論を展開したことは知られているが、残念ながらその部分は失われてしまって、伝わっていない。悲劇と喜劇、このように一見対立する両項を並べるやり方を、ヘーゲル(1770–1831)も真似ている。事柄を対比的に論じるのはいかにもヘーゲル的である。ヘーゲルはあらゆるものを、いわば対立と矛盾の相のもとに見る(二項の対立は、究極的には三項の対立である)。だから、喜劇について述べたければ、まず喜劇が叙事詩と違う劇詩であるとこと、また劇詩の中でも悲劇と違う喜劇であることを見なければならない。それらは、ヘーゲルが芸術の哲学を論じている『美学講義』(1835〜38)にくわしい。
行為、性格、パトス(情念)
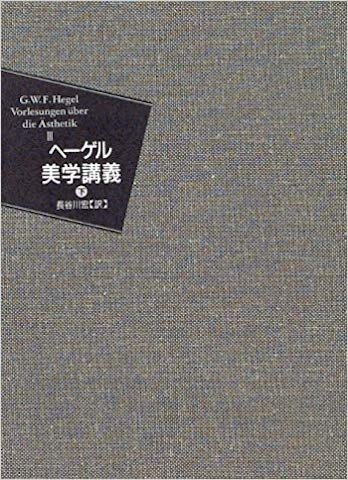
ヘーゲル美学講義〈下巻〉作品社
『美学講義』のなかでヘーゲルは、叙事詩とはある行為の「事件」としての生起を表現することであると述べている。叙事詩的事件とは、関連する一連の事件、出来事、様々な状況、外部の諸事情、あるいは自然界の様子までが含まれる複雑なものである。だから、叙事詩においては本筋と一見無関係な数々の「逸話」が描かれるが、これが意外に重要なのである。やや偶発的に生ずる逸話も叙事詩の本質的な部分だからである。
では、劇的作品の課題とは何かというと、人間の「行為」(Handlung)を描くことには変わりはないが、事件や出来事を外的な事情や個人の立場(男女、大人、教師、金持ちなど)からではなく、個人の内面すなわち「性格」から起こるものとして表現することである。劇の登場人物は、宿命によるのではなく、自分の意図した行為とその結果を受け取るのでなければならない。行為の源は意志と性格であり、行為の主題は目的である。
ところで、劇においては、個人の目的は他の個人の目的と必ず対立する。このことによって、登場人物それぞれの目的と行為の衝突が起こる。これが劇作品の本来の主題と内容である。また、劇において登場人物は内面的な「パトス」(情念:怒り、恨み、憎しみ、愛情など)をもって登場する。このパトスをもつ個人が「性格」をになうものとして描かれるわけだ。これは、現代の劇映画に至るまで依然として変わらない。
悲劇と喜劇の違い
ヘーゲルによれば、悲劇と喜劇の違いは、登場人物による行為のタイプの違いである。悲劇では、共同体精神(家族愛、社会正義、愛国心など)を具体的に表す行為が基本となる。優れた個性をもつ主人公(英雄)は、必ず対立に巻き込まれ、葛藤、闘争を経て罪に陥ることになる。
英雄の行為は、意図しない行為であるのになぜか罪を着せられる。それは英雄の行為が単に個人的、主観的であるのではなく、社会の「実体的」行為だからである。悲劇では各人のパトスや性格は、知らず知らずに共同体や社会の力に限定され、これらの間の対立に巻き込まれる。個人の対立だと思われるのは、実は社会的な対立なのだ。たとえば、ソポクレスの『アンティゴネー』においては、兄弟の愛(家族愛)がアンティゴネーのパトスであるのにたいして、公共的な国家に対する忠誠(愛国心)が叔父クレオンのパトスであり、両者のパトスの対立から悲劇が生まれる。
それに対して、喜劇では共同的精神ではなく「主観的(個人的)な行為」が決定的となる。無制限的で束縛もされず、抑圧もない心情の自由、明朗さが喜劇的な行為の基本である。
喜劇では、意志し、行為する主体とその回りに広がる外界の偶然的な出来事(偶然性)がすべての関係の基本となる。喜劇はすべて偶然起こることと関係するのである。
喜劇の世界では、目的を備えたシリアスな行為が本来の目的を失ってしまうので、シリアスさ(生まじめさ)が崩れてしまう。そこで人はその行為を笑うことができる。登場人物は自分の行為をやり遂げるのが不可能になればなるほどあっけらかんとする。こうした無邪気な幸福のイメージこそ、古くはギリシア喜劇から由来する喜劇性である。
喜劇的行為の問題
(1)喜劇的な行為とは実体のない行動である。実体のない行動とは、馬鹿げた、無意味な、目的に反した行動である。目的とそれに合致しない手段との間には大きな対照があって、目的を達成できないばかりか、目的を取り違え、壊してしまう(飲むという行為は本来口で飲むのに、鼻から飲むと液体を飲むという目的そのものをダメにする)。
(2)人間の典型的な悪徳とは、目指している究極の目的=幸福を生活の破壊や精力の浪費を通じて得ようとすることである。悪徳の一つに「貪欲」(greed 過度な欲望)がある。これは目指す幸福のための手段を目的とみなし、本来の目的を忘れてその手段をすべて所有しようとすることである。例えば、金銭は幸福そのものではないのに、あたかもそれが目的であるかのように(自己目的化)して、ひたすらお金を貯めるとか、生活の役に立たないものをコレクションするとか。良きパートナーを見つけるという口実のもとに次々とナンパするとか。これらの場合、目的設定が最初から間違っているのだから、失敗しても主体はそこから明るく自由に抜け出せるという点に喜劇性がある。
(3)また、それ自体は正当な目的なのに、本来それにまったく適しない個人によってなされる行為も、目的と手段との関係を欠いた馬鹿げた行為となり、喜劇的である。人々は共同体精神を担っているつもりなのに、とてもそれを実現できない人たちだという場合である。アリストファネスの『女の議会』は、本来男たちが担う国家の協議を女たちが行うことによる滑稽さを表現している(今の時代にふさわしくないが、別の意味で風刺になるだろう)。
(4)喜劇においては、ただ観客にとってのみ笑いの対象であるのか、行為する人物がそれ自身として喜劇的であるのかを区別することができる。後者が真の喜劇である。バナナの皮で滑って転んだとき、転んだ自分を笑いの対象にできるのは、自分を笑う他者の視点を借りて自分を笑っているからある。主体が自分自身を他者として捉え、自らに対して反省的な距離を作り出している。
(5)喜劇的なものの本来的な性格は、「明朗さ」である。心情が明朗な人は寛大な人である。寛大な人は、自分の愚かしさや矛盾を心に留めて、自分を笑うことができる。自分自身を笑う余裕(ユーモア)こそが喜劇性なのである。
映画に見られる喜劇的状況/喜劇的行為
参考映像:『水をかけられた水撒き人(原題:L’ArroseurArrosé)』(1895)
映画にはコメディ的傾向が、映画史の当初からあった。リュミエール兄弟が映画を上映した1895年のプログラムには、『水をかけられた水撒き人』という短編映像があった。庭師が水をやるホースのノズルを覗きこんだときに、顔に水をかけられるというギャグを写している。これは、まさに偶然に起こること、偶発事(ハプニング)を映画が最初に捉えた瞬間でもあった。
以下ではヘーゲルによる喜劇の規定を踏まえた上で、喜劇的な行為のパターンと呼べるものを映画作品の中に探してみる(膨大すぎてここに収まるものではないが)。コメディのギャグには、文脈が違ってしまえば、またタイミングが合わなければ、笑えないものもあるが、ヘーゲルの観点では、目的論的な文脈を棚上げするところに喜劇的行為の本質があるわけだから、できるだけそのヴァリエーションを思い出してみよう。
①「だます/だまされる」
参考映像:『マダムと泥棒』(1955)
これは典型的な喜劇的行為である。シェイクスピア喜劇にすでに源流があるから、コメディ映画に使われないわけがない。『マダムと泥棒』(1955)では、悪漢たちが弦楽五重奏の練習と称して、老婆が営む下宿を借りる。その実、5人はそこで現金輸送車強奪を企てるのだが、悪漢たちと老婆のだます/だまされるという関係が、老婆のおせっかいで劇的に変化する。
②「用途ではない使い方」
参考映像:『海底王キートン』(1924)
これもコメディの常道なので、挙げればきりがない。『海底王キートン』(1924)では、海上の豪華客船に取り残されたカップルが、大人数の料理に使う鍋で二人だけのゆで卵を作る。マルクス兄弟『御冗談でショ』(1932)でハーポ・マルクスがスロットマシンでうまくコインをせしめたので、隣の電話機にもコインを入れると、ベルがなり、出るはずのないコインが釣り銭口からザクザクと出てくる。
③「変身する」「見違えるようになる」
それにまったくふさわしくない人物によってなされる行為が、だんだんと変化してゆくというプロットである。バーナード・ショー原作『ピグマリオン』(1938、『マイ・フェア・レディ』の原案)では、ロンドンの下町の花売り娘イライザが、上品な女に変身することを願って言語学者ヒギンズに弟子入りする。ところが、イライザは師匠の期待以上の成果をあげ、変身によってアイデンティティが変わり、自律した女になってしまう。
④「あり得ない偶然の一致」
参考映像:『アパートの鍵貸します』(1960)
モリエールの戯曲『守銭奴』では、父親と息子がたまたま同じ女を愛していながら、お互いにそのことを知らないという設定が出てくる。喜劇には「偶然の一致」や「奇遇」などが平然と繰り返し使われる。特に風俗喜劇にはよく出てくる設定である。
ビリー・ワイルダー監督『アパートの鍵貸します』(1960)では、保険会社に勤めるジャック・レモンが昇進のためにと上司の情事の場所に自分のアパートを貸している。ある日アパートに帰ってみると、ベッドに倒れこんでいたのは、意中のエレベーターガールであった。「奇遇」に立脚するもう一つのジャンルであるメロドラマも、「あり得なさ」が極まるとコメディに近づいてしまう。ダグラス・サークの傑作メロドラマ『心のともしび』は、今見直してみるとところどころ笑いを抑えられない。
⑤「いつも阻まれる」
参考映像:『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(1972)
ジョルジュ・フェドーの芝居『自由交換ホテル』では、不倫をしようとしてホテルにやってきたカップルが、それぞれの夫や妻が偶然の理由から同じホテルに宿泊し、何度も遭遇しそうになる。またカップルが性行為に及ぼうとすると、何度も障害に出くわすことになる。ルイス・ブニュエルは、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(1972)のなかで同じプロットを使っている。ブルジョワの家族が夕飯を取ろうとするが、いく先々で行為を阻まれ、一向にディナーを食すことができない。
⑥「対抗する」「やり合う」
参考映像:『我輩はカモである』(1933)
喜劇の典型的なプロットに、ある行為に対して対抗手段を取るというものがある。対抗手段がだんだんエスカレートしていき、相手とのシーソーゲームになる。マルクス兄弟の『我輩はカモである』(1933)で、チコとハーポが屋台でピーナッツ売りをしていて、隣のレモネード売りと喧嘩になり、毎回いじられるレモネード売りの報復がエスカレートする。『チップリンの独裁者』(1940)では独裁者ヒンケル(=ヒトラー)ともう一人の独裁者ナパロニ(=ムッソリーニ)が、少しでも相手より上位に立とうとして、椅子を上にスライドする。
⑦「瓜二つのものの差異」「二つを取り違える」
参考映像:『チップリンの独裁者』(1940)
これも基本的に「偶然の一致」に支えられている。『チップリンの独裁者』(1940)では、独裁者ヒンケルと瓜二つで、彼に間違われた理髪師の話を滑稽にしたり、シリアスにしたりするのは、わずかに髭の形の違いにすぎない。『殺人狂時代』(1947)のヴェルドゥ氏にいたっては、病身の妻思いの夫と、次々と女を毒牙にかける殺人者との間にほとんど差異がない(ジル・ドゥルーズは『シネマ1*運動イメージ』で、スラプスティック・コメディの原理について述べているが、ある行為が最小の差異をもって、まったくかけ離れた二つの状況を作り出してしまうということだ)。
⑧「予想を裏切る」
参考映像:『チャンス』(1979)
あきらかに普通人よりも知能が劣る主人公が登場する。自意識のない天然キャラクターで野心がまったくない。観客は当然彼が成功するわけがないと思うが、予想に反して行く先々で成功してしまう。当初の誤算にもかかわらず、観客は主人公の完璧な明朗さ(裏を返せば「白痴性」)から快感を得るようになる。ハル・アシュビー『チャンス』(1979)やロバート・ゼメキス『フォレスト・ガンプ』(1994)のような映画にこの状況がある。
⑨「見立てる」
参考映像:『オペラは踊る』(1935)
あるものを別のものになぞらえて表現することを、「見立て」という。喜劇では、ある場所を即興的に別の場所に見立てて、その場にはふさわしからぬ行為で笑わせるというものがある。マルクス兄弟『オペラは踊る』(1935)の後半で、オペラ劇場の舞台裏をあたかもターザンの密林に見立てて、釣り下がっているロープを使ってハーポ・マルクスが何度も空中移動を繰り返す。
⑩「舞台裏をさらけだす」
参考映像:『サーカス』(1928)
チャップリンが『サーカス』(1928)で見せているが、マジシャンのトリックのネタを、誤って最初から見せてしまい、次々と出てくる鳩や子ブタで収拾がつかなくなる。おまけに、隠れている助手の姿もバレてしまって、舞台裏を覗くこと自体が観客の笑いになる。
ドラマという中間領域

喜志哲雄『喜劇の手法 笑いのしくみを探る』集英社新書
これらは、いくらでも続けることができる。喜劇的な行為を列挙するのは、悲劇的行為一般について述べるよりも易しいが、パターンを一通り網羅するのはたいへんだ。それは、端的に喜劇的行為がじつに多様で、多岐にわたるからだ(フロイト風に言えば、多形倒錯的)。喜劇的行為の本質を述べれば、それで自ずとその行為が次々と想像できるというものではない。それができれば、コメディ作家になれる。古いパターンを繰り返し使う一方で、全く新たな笑いのパターンを発見できれば、である。
これはまだ言わなかったことだが、ヘーゲルは悲劇と喜劇との中間にある劇について言及している。ドラマ(Drama)である。われわれがふだん見ている映画は、たいてい悲劇でもなければ、喜劇でもない、ドラマである。われわれは好むと好まざるとにかわからず、いまだにヘーゲルの枠組みの中で映画を見ている。
【参考文献一覧】
ヘーゲル『美学講義(下)』長谷川宏訳、作品社
クーノ・フィッシャー『ヘーゲルの美学・宗教哲学』玉井茂/堀場正治訳、勁草書房
ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』財津理/齋藤範訳、法政大学出版局
小林信彦『世界の喜劇人』新潮文庫
喜志哲雄『喜劇の手法 笑いのしくみを探る』集英社新書
田辺秋守プロフィール

©︎Cinemarche
日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。
早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。
著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。
『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。



































