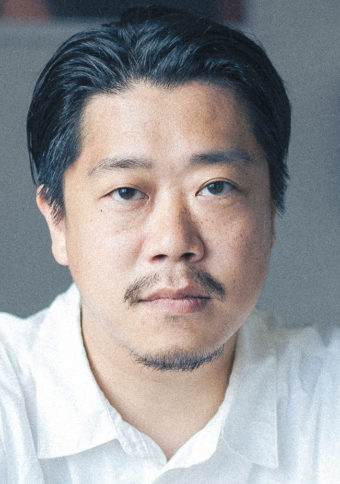2019年3月1日より公開され劇場公開された『岬の兄妹』。
各上映回で満席が続出し、映画を観た観客から日本映画には珍しい完成度の高い作品だという賞賛の声があがりました。その後、すぐに拡大上映の広がりを見せ、連日多くの観客に感銘を与えています。

©︎ Cinemarche
新人監督らしからぬ才気を放っている片山慎三監督は、本作が初長編作品。売春によって生計を立てる障がいを持つ兄妹の姿を通して、日本社会に置ける弱者の生きにくさと同時に、力強く生きる姿を描いています。
Cinemarcheでは、2019年早くも大きな話題作となった『岬の兄妹』を手がけた片山慎三監督にインタビューを行いました。
映画制作を行ううえで、片山監督の作品への思いやその経緯、本作に注いだ情熱を大いに語っていただきました。
CONTENTS
作品タイトルについて

(C)SHINZO KATAYAMA
──片山慎三監督の映画『岬の兄妹』は、海の底に沈んでいくような深さを感じました。
片山慎三(以下、片山):実は最初、『岬の兄妹』というタイトルではなく、本当は『デメニギスの夜』、デメニギスというのは深海魚という意味なのですが、そのタイトルでテロップも全部作っていたんです。
試写の時にこのタイトルで見てもらったら、「ちょっと待って、このタイトルやめよう」 って全員にいわれました(笑)。
──不評だった?
片山:不評だったんです。最初は「岬の兄妹(仮)」といいう形にしておいて、タイトルは終わってから考えようって。「デメニギス」という深海魚がいると知って、それがいいかなと思ってつけたら、総スカンだった。最終的に『岬の兄妹』でよかったなと思っています。
──劇中の赤いタイトルについては?
片山:まずタイトルを大きくしたかった。
赤い文字は、黒澤明監督の映画DVDのパッケージが赤文字の習字の書体であったことや、にっかつロマンポルノや東映などの、ひと昔前の邦画、現代にないような雰囲気を意識して作りました。
映画鑑賞するようになったきっかけ

©︎ Cinemarche
──片山監督は、ポン・ジュノ助監督をしていたこともあって、韓国映画との関係について聞かれることが多いと思うのですが、邦画に関してはどうでしょうか。
片山:邦画を意識して見るようになったのは、19歳の時、大阪から東京に出てきてからです。
それまでも黒澤明監督やいくつか邦画には触れていましたが、ジャッキー・チェンのアクション映画やフランスの映画をはじめとする洋画を鑑賞することの方が多かったです。
ただ高校の時ラグビー部だったこともあって、そんなに映画に没頭したわけではありませんでした。東京に出て学校で学び始めて、相米慎二監督や中村幻児監督の作品など本格的に見るようになりました。
片山監督ならではの“エンターテイメント性”

(C)SHINZO KATAYAMA
──社会的ハンディを持っている障がい映画というよりは、エンターテイメント性をとても感じました。
片山:
僕は少数派の主人公が前向きに生きている事に共感を覚えます。『岬の兄妹』では、良夫や真理子がイジメられっ子に勇気を与えたり、お爺さんがほんの束の間癒されたり…ということを意識して描いています。
キャスティングについて

©︎ Cinemarche
──今回、松浦祐也や和田光沙の演技力もさることながら、脇役のキャスティングを揃えるのにご苦労されたのではないですか?
片山:役者さんはなかなか決まらなかったです。
お爺さん役の杉本安生さんは、エキストラ会社の人でした。役者さんの中で何人か手をあげてくれた人もいたんですが、事務所の許可がおりなかった。
同じように、子役もなかなか決まりませんでした。色々な子役事務所にお願いしたら、「片山さん、勘弁してください」と言われました。
もう無理かなと思っていた時に、トラック運転手役の中薗大雅さんの娘さんに依頼したら、奥さんを説得して、ようやく出演してもらうことができました。
中村君は、松浦祐也さんが紹介をしてくれました。当初別の方にオファーしようとしていることを松浦さんに相談したら、「中村祐太郎という監督がいるから、その人がいいんじゃないか」と推薦してくれたんです。
作品の特徴からも、ロマンポルノの流れは無視できないと思って、風祭ゆきさんにお願いしました。事務所に依頼したら、とても有り難いことに特別出演という形で快く引き受けてくださいました。
──風祭さんが出演されていたことで、往年のにっかつファンの人も喜んだのではないかと思います。なかでも彼女の「逃げないで…」という台詞は、非常に重みのあるものでした。
片山:あの台詞については少し悩みました。ただあの一言くらいは、全体のテーマにかかる部分があったほうがいいのかな、という思いがあって言ってもらいました。
出産させるか、堕胎させるかすごく悩みました。この2人だったら、出産させた方が地獄。これから先不安だけど、子どもがいることによって束の間の幸せを…という形にはしたくなかった。
“母親”が鑑賞の鍵に

(C)SHINZO KATAYAMA
──産むということからもそうですが、「母親」を描いた映画だという感じがしました。
片山:そうですね、それは意識しました。映画の序盤で時任亜弓さんの演じた警官の奥さんは妊婦なんですが、あえて喪服姿にしたんです。
喪服は死の象徴であり、これから生まれるという妊娠しているという「生」と「死」の対比をどれくらいの人が引っかかるかわからないけど、見せたくて。
良夫は、喪服姿をみて「誰か死んだの?」と自身の母親のことを思い出して動揺している。一方、真理子はお腹のほうに興味がいく。あのシーンは、さらっと見せてるんですが、衣装や妊婦という設定で広がりをもたせようと思いました。
意外と僕も伝わらなくてもいいかなと思いながら作っているけれど、伝わっていると思うととても嬉しいですね。作品全体は、ほとんど意図的に、狙っているんですが、それをいちいち説明はしていません。
撮影と編集作業の秘話

(C)SHINZO KATAYAMA
──走るシーンが印象的でしたね。監督がラガーマンということを聞いて少し納得しました。
片山:めっちゃ走ってましたね(笑)。正面から走る様子をカメラで撮る予定でした。
そうしたら、山下敦弘監督の『苦役列車』のラストシーンで主演の森山未來君が走るシーンがあるのですが、正面から撮っている。それと同じになると思い、カットを細かく割ることにして、足元、横など色々撮るようにしました。
松浦さんには、ものすごく走ってもらいましたね(笑)。
──2人のカメラマンで撮った作品でしたね。
片山:カメラマンが2人ということになっていますが、カメラ二台で撮っていたわけではありません。
撮影に関しては、池田直矢さんや春木康輔さんにイメージを伝えて決めていました。2人とも非常に柔軟に対応してくれました。2人から出てきた意見も面白いものがあった時にはそれを採用したこともあります。
全体的にフレーミングのサイズは顔だけというのではなく、広めできちんと足元まで入るサイズで撮りたいと思っていました。俳優さんをきちんと動かして、カメラも動いて撮ることを常に考えていました。顔のアップの寄り画を撮っておけばなんとなる、という考えは嫌でした。
──編集に関してはいかがでしたか?
片山:編集は撮影と並行して全部自分で行っていました。
編集段階で大きく内容を変更したことはありません。というのも撮影段階で、音楽や編集のことをある程度想定していました。時間をかけながら、全部自分でコントロールしながら完成に持っていけたのはよかったですね。
今後の作品について

©︎ Cinemarche
──これからどのような作品を描いていきたいですか?
片山:もっと規模の大きい映画を作っていきたいですね。もちろん映画はエンターテインメント性がないと見てくれる人はいないと思っています。エンターテインメントの作りをしながらも、複雑な人物関係や設定などいろいろなものが同居しているような作品にしていきたい。
現実を見て映画を作る。僕は普通の人が活躍するよりも、ハンディがある人が活躍するようなものに対し胸が震えます。
社会的に不利な立場な人たちが、何か大きいものに立ち向かっていくという構図にしたい。
死ぬまで映画を撮りたいですね。
映画『岬の兄妹』の作品情報
【公開】
2019年(日本映画)
【脚本・監督・製作】
片山慎三
【撮影】
池田直矢・春木康輔
【音楽】
高位妃楊子
【キャスト】
松浦祐也、和田光沙、北山雅康、中村祐太郎、岩谷健司、時任亜弓、ナガセケイ、松澤匠、芹澤興人、杉本安生、松本優夏、荒木次元、平田敬士、平岩輝海、日向峻彬、馬渕将太、保中良介、中園大雅、奥村アキラ、日方想、萱裕輔、中園さくら、春園幸宏、佐土原正紀、土田成明、谷口正浩、山本雅弘、ジャック、刈谷育子、内山知子、万徳寺あんり、市川宗二郎、橘秀樹、田口美貴、風祭ゆき(特別出演)
【作品概要】
ポン・ジュノ監督作品や山下敦弘監督作品などで助監督を務めた片山慎三の初長編監督作品。
兄役は『マイ・バック・ページ』(2011)などでその存在感から爪痕を遺してきた松浦祐也が映画初主演。妹役には『ヤーニンジュの島』『ミカヨのクレヨン』『しあわせ配達人・ユリ子』(2018)の和田光沙。
SKIPシティ国際Dシネマ映画祭の国内コンペティション長編部門で優秀作品賞と観客賞を受賞。
映画『岬の兄妹』のあらすじ

(C)SHINZO KATAYAMA
港町、小さな古い平屋に暮らす兄と妹。兄は右足が悪く、いつも引きずっています。そして頭の回転もそれほど速くありませんでした。
妹は自閉症で、兄が小さな造船所へ仕事に出ている際には、勝手にどこかに行ってしまわないよう、家の中に閉じ込められています。
ある日、妹が姿を消します。彼女が戻ってきたとき、ポケットには1万円が入っており、下着には男の体液が付着していました。
兄は足が悪いことを理由に仕事を辞めさせられます。やがて家の家賃も払うことができず、電気も止められてしまいます。
ふたりが生きて行くために辿り着いた仕事は、罪の意識を持ちながらも、妹のカラダを売るという商売でした。
兄は妹の売春の斡旋をし始めます。「冒険」「お仕事」と笑顔で客の相手をする妹。
兄の友人である警察官が止めても兄妹は止まることができません。ふたりが行きつく先はどこなのか…。
まとめ

©︎ Cinemarche
日本映画界だけでなく、韓国映画界の名匠ポン・ジュノ監督や、スウェーデンのヨーテボリ国際映画祭に集まった観客たちに、新人離れした才能を見せつけた片山慎三監督。
片山監督が主演を熱望した俳優の松浦祐也は、役者としてだけでなく脚本の設定やキャスティングにも協力。一方オーディションで選ばれた女優の和田光沙は、実家から映画美術のために大道具をかき集め、ロケ車の運転手まで買って出たそうです。
また、撮影を担当した池田直矢と春木康輔のカメラワークの画は、光と闇がアクセントになるように収められたり、時に疾走感を見せる移動撮影を行っていました。
自主制作映画とは言え、このようにチームワークの取れた作品ができたのはなぜでしょう。
片山監督に高校時代の話を伺うと、映画よりもラクビー部に明け暮れた時間を過ごしていたそうです。
ラガーマンとしてのポジションはバックスのセンター。攻守に相手ラインとトップスピードでぶつかり合う役割を担い、強靭な足腰と強固なタックルの技能が求められる選手が務める位置です。
またインサイドの場合は第二の司令塔と呼ばれたり、アウトサイドの場合はスピードと突破力のあることでも知られます。
映画『岬の兄妹』は、障がい者というキャラクターを設定しながらもエンターテイメント性の高い作品として描かれていた稀な作品です。
この今の時代に唯一無二の邦画と言ってもよい作品をラクビーの話で例えるなら、“キラキラ映画という脳震盪を起こしている邦画”に、“魔法のやかん”で新たなる映画の生命(いのち)の水をかけたような映画だといえるでしょう。
このインタビュー取材を通して、片山慎三監督とは、閉塞感がある日本映画や自主制作映画にとって立つべきポジションはまさにセンター(重鎮)であると言い切れます。
今後も新た才能あるスタッフや個性的なキャストとともに、チームプレイの司令塔して突破力と才気ある活躍を見せて欲しいと思います。
インタビュー・撮影/ 出町光識
片山慎三監督のプロフィール
1981年2月7日生まれの大阪府出身。中村幻児監督主催の映像塾を卒業後、フリーの助監督として様々な作品を担当します。
『TOKYO!』(2008/ポン・ジュノ監督パート)、『母なる証明』(2009/ポン・ジュノ監督)、また、『マイ・バック・ページ』(2011/山下敦弘監督)、『苦役列車』(2012/山下敦弘監督)、『味園ユニバース』(2015/山下敦弘監督)、『花より男子ファイナル』(2008/石井康晴監督)、『山形スクリーム』(2009/竹中直人監督)などに参加。
自身の監督作としては、『アカギ』第7話(2015/BSスカパー)、青森の斜陽館で上映されているシュートムービーアニメーション『ニンゲン、シッカク』(2017)などがあります。
また、現代アーティスト村上隆のアニメシリーズ『シックスハートプリンセス』の5話、6話、7話の脚本も担当しています。
映画『岬の兄妹』の公開情報

©︎ Cinemarche
映画『岬の兄妹』は、3月1日(金)よりイオンシネマ板橋、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿バルト9等で上映が始まり、好評につき各地で拡大上映が続いています。
4月からも引き続き各地のイオンシネマをはじめ、アップリンク渋谷、アップリンク吉祥寺ほか新たに公開される劇場も待機中。
*詳細な情報は【『岬の兄妹』公式HP→】をご覧ください。