映画『普通は走り出す』は2019年10月25日(金)より、アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開!
2013年、栃木県・大田原市にて映画監督・渡辺紘文と映画音楽家・渡辺雄司の兄弟が旗揚げした映画制作集団「大田原愚豚舎」。『そして泥船はゆく』『七日』『プールサイドマン』『地球はお祭り騒ぎ』など独自路線を徹底した野心作/問題作の数々を次々と発表し、それらの作品は常に賛否両論を巻き起こし、同時に高い評価も得ています。
そして「大田原愚豚舎」5番目の作品として生み出されたのが、渡辺監督自らが主演を務めた長編映画『普通は走り出す』です。

(C)Cinemarche
伝説的巨匠フェデリコ・フェリーニ監督の怪作『8 1/2』を彷彿とさせながらも、ロックバンド「トリプル・ファイヤー」の楽曲および世界観と渡辺兄弟独自の視点が融合することで新たな「映画のための映画」として完成した本作。
そしてこのたび、2019年10月25日(金)からの劇場公開を記念して渡辺紘文監督にインタビューを行いました。
映画制作の経緯やそのこだわり、そしてインディペンデントとして映画を作り続けることへの思いなど、貴重なお話を伺いました。
CONTENTS
トリプルファイヤーの楽曲と向き合う

(C)Cinemarche
──はじめに、映画『普通は走り出す』の制作経緯について改めてお聞かせ願えませんでしょうか。
渡辺紘文監督(以下、渡辺):本作を企画した直井卓俊さんは、自身の作品が上映された東京国際映画祭で知り合いましたが、その当時は「一緒に映画を作ろう」というつもりはありませんでした。
ただ『地球はお祭り騒ぎ』を同じく東京国際映画祭に出品した際の打ち上げで、直井さんが手がけている「MOOSIC LAB」が話題に挙がり、「僕もそこに呼んでくださいよ」と言ったんです。
その場では軽い冗談程度で話も終わったんですが、映画祭が終わった後に直井さんから「トリプルファイヤーの音楽と世界観が渡辺監督の作品が合うから、映画を撮ってみませんか」「まずライブを観に行きませんか」と電話で誘われたんです。
そうして弟の雄司・直井さん・僕の三人でライブに行き、「この人たちは面白い」「この人たちの曲だったら、映画になるんじゃないか」と漠然と感じとりました。それが本作を制作するはじまりでした。
──「楽曲から着想を得ての映画制作」にあたって、トリプルファイヤーさんの楽曲群とはどのように向き合われていったのでしょうか。
渡辺:トリプルファイヤーさんの楽曲については今泉力哉監督の『サッドティー』で使用されていたという程度しか知らなかったので、まずトリプルファイヤーさんのCDを購入し、一年間それを聴き込みました。
そもそも特定のミュージシャンを聴き込み続けることなんて滅多になかったんですが、「映画制作の前に、まずこの人たちの音楽をまず理解しよう」というスタンスを大切にし、とにかく聞き続けました。
そしていざ映画制作をするにあたって、楽曲を作品内で使用する際には、曲への編集はせず、必ず一曲丸々使用することにしました。トリプルファイヤーさんの楽曲を勝手に切ってしまうことは非常に失礼だと感じたからでもありますし、曲の歌詞をしっかりとお客さんに聴いてほしかったんです。
自身が納得できる作品へ

(C)2018 FOOLISH PIGGIES FILMS
──本作は「渡辺」という自主映画監督が主人公ですが、そのような設定にされたきっかけや理由は何でしょう。
渡辺:『普通は走り出す』は元々「映画監督が主人公の映画」ではなかったんです。それ以前の物語がどのようなものだったのかは正直あまり覚えていないんですが、現在とは全く違うものでした。
脚本を直井さんに提出した際には自分でもその物語を「面白い」と感じていましたし、直井さんからも好感触を得ていたんですが、色々と考えていくうちに「これじゃあダメだ」「これじゃ面白くならないし、映画が成立しない」と感じ始めました。「トリプルファイヤーさんのドキュメンタリーにしよう」とさえ直井さんに言ったこともあります。
ただドキュメンタリーにすることは直井さんから止められ、劇映画として何を作るかを悩み続けた結果、「何も思いつかない男」という物語へと辿り着いたんです。
──渡辺監督或いは大田原愚豚舎の映画制作において、「映画が成立する」という判断基準となりうる要素をお聞かせ願えませんでしょうか。
渡辺:自分の尺度に基づくものではあるんですが、まず第一に「映画として面白くなるかならないか」ということに尽きます。そしてもう一つ重要なのが、「長編映画として成立するか否か」です。
大田原愚豚舎の映画制作は、僕と弟の雄司、カメラマンのバン・ウヒョンという三人がメインで、あとは家族や地元の友だちが手伝いに来る程度の完全な「自主制作」の現場です。だからこそ、まずその制作体制で成立できる作品を考えなくてはならない。そのことは常に心がけています。
モノクロという「余白」
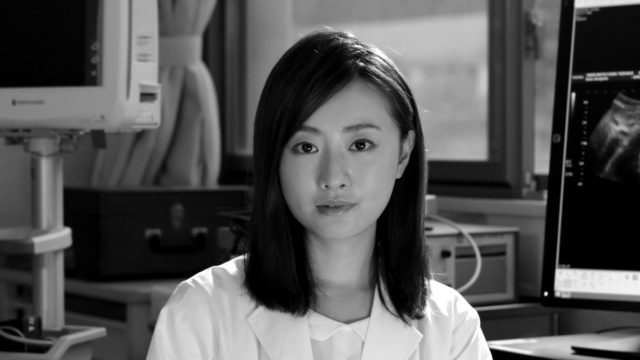
(C)2018 FOOLISH PIGGIES FILMS
──大田原愚豚舎作品の第一作『そして泥船はゆく』以来、渡辺監督はモノクロ映像での映画制作を続けています。渡辺監督がモノクロ映像にこだわり続ける理由とは何でしょう。
渡辺:元々モノクロで映画を撮り始めたのも、規模の大きい制作体制をとれないことも大きな理由にあります。制作スタッフには美術部と衣装部がいなくて、自分たち兄弟で担っているぐらいですから。
撮影用カメラもプール監視員の仕事で貯めたお金で購入して以来、7年近く使い続けている一眼レフカメラで、決して性能の良いカメラは使用していません。だからこそ、カラーでの撮影に踏み切れなかったんです。
ただ一作目の『そして泥船はゆく』の撮影の中でモノクロの魅力や面白さを再発見し、やがてモノクロで撮ることに意味を見出していきました。
結局「色」は情報が多い要素であるため、逆にモノクロにすることで視覚的情報の説明を省くことができます。そして「色」という情報を削ることで、同時にお客さんにとっての映画の「余白」も増え、想像の余地を拡大できると感じています。
「人間の生活」を描くために

(C)2018 FOOLISH PIGGIES FILMS
──先ほど映画制作における美術・衣装は渡辺監督と雄司さんのお二人で担当されているとお聞きしましたが、本作に登場する「空間」は常に映画的・美術的な魅力に満ちています。
渡辺:実は僕は美術部が担う仕事、特に撮影現場の装飾が好きなんです。装飾に関しては、弟とともに「いかにリアルで、かつ映画的な面白さに満ちた空間を作るか?」という考えのもと、撮影のウヒョンがカメラアングルなどを決めている間にいつも試行錯誤を続けています。
そうし続けるのには、お客さんが自分たちの想像以上に「細部」を観ているからであり、何よりワンシーン・ワンカットの映像を成立させるには、その「細部」にこだわらないといけないからです。
また僕の恩師である天願大介監督の父にして、僕が通っていた日本映画学校の創始者でもある今村昌平監督は、「人間の生活」を「綿密」に描くことに重きを置いています。その点では僕も今村監督の影響を受けていて、「人間の生活」を描くのが僕の映画にとって最も重要な要素なんです。
それは装飾でも同様で、「生活空間」を描くためには「どんな人間が暮らし、生きているのか」が一目で分かるようにしなくてはならない。だからこそ僕は装飾が好きですし、疎かにすれば映画が一気にダメになるものだと感じています。
「映画好き」に問いかける映画

(C)2018 FOOLISH PIGGIES FILMS
──劇中には主人公の映画監督・渡辺が幼少期の映画体験に触れる場面が描かれていますが、あの場面は「観客」として映画に関わる人間の一人として、自身の映画との向き合い方を思わず顧みてしまいました。
渡辺:あの場面は『普通は走り出す』にとって非常に重要なもので、僕自身の体験も反映されてはいるものの、それ以上に「みんな、もっと純粋に映画が好きだったんじゃないのか?」という問いが込められています。
純粋に映画が好きだったはずなのに、いつの間にか映画評論家たちからの受け売りの知識に飲まれてしまい、映画を楽しむ以前に、映画に対し何かを言わずにはいられなくなった人々は大勢います。
特に現代は情報が溢れ過ぎていて、まっさらな気持ちで純粋に映画を楽しむことが難しくなっていることにはどうしても違和感を抱いてしまう。あらゆる事象が「ネタ」として消費されていく世の中に、「アンタたちはどうしてそうなっちゃったの?」と言いたくなってしまうんです。
主人公の渡辺も映画が好きだったはずなのに、「映画監督」として映画と関わっていくことで映画が嫌いになり、自分が何をしたいのかも分からなくなっていく人間の「一人」です。
本作を通じて、自分自身も含め「“映画がなぜ好きだったのか”を忘れていませんか?」と観た者に問いかけるためにあの場面を描きました。
褒められようと思うな

(C)2018 FOOLISH PIGGIES FILMS
──渡辺監督と大田原愚豚舎の作品は常に賛否両論と高い評価を同時に得ており、多くのメディアにて度々「問題作」「衝撃作」と評されてきました。そう評される作品を作り続けるその原動力とは一体何なのでしょうか。
渡辺:メディアでの「売り文句」も含め、僕たちが作った映画はよく「エッジが効いている」と評価されがちですが、そもそも無難なものを提示してもしょうがないなと思うんです。
天願監督は以前、「結局日本人の感性は海外では全く敵わなくて、一撃でやられてしまうような軟弱なものだ。だからこそ自身の個性をより強固にしなくてはいけない」と仰っていました。
ですが、その個性に不寛容で、個性的であればあるほど叩かれるとこれまでの映画制作の中で感じてきましたし、逆に広く浅く浸透するものが「いいもの」とされ過ぎていることにも疑問を抱いています。それが映画のみならず、様々なジャンルの作品でもその傾向があることへも。
また天願監督の「褒められようと思うな」という言葉もよく覚えています。「褒められようと思って映画を作り出したら、もう映画は終わりだ」「そういうものを作るのだけはやめろ」と。ですから僕も、映画制作において「こうやったらウケる」と考えたことはないです。
僕は『八月の軽い豚』、そして大田原愚豚舎と映画制作を続け、良くも悪くも様々な評価を受け続ける中で、「自分たちで、自分たちが死ぬまで好きなものを撮ってもいいじゃん」と腹を括れるようになりました。
待つことで時間を無駄にしたくない。何かを待つぐらいだったら、カメラを持って自分で何かを撮り始めてしまった方がいい。「行動こそが一番大事」「とにかく行動する」と考えるようになったんです。
インタビュー・構成/河合のび
インタビュー・撮影/出町光識
渡辺紘文監督プロフィール
渡辺紘文監督(左)と弟であり映画音楽家の渡辺雄司さん(右)

(C)Cinemarche
1982年生まれ、栃木県大田原市出身。日本映画学校(現・日本映画大学)卒業。
2008年の卒業制作作品『八月の軽い豚』は第9回フジフィルムラヴァーズフェスタ・グランプリ、京都学生映画祭・入選、佐藤忠男賞など多くの賞を獲得しました。
2013年には故郷である栃木県大田原市にて、実の弟で映画音楽家の渡辺雄司とともに映画制作集団「大田原愚豚舎」を旗揚げ。そして第一作にして自身初の長編監督作『そして泥船はゆく』は第26回東京国際映画祭をはじめ世界各地の映画祭・コンペティションに出品されて大きな反響を呼びました。
その後も2015年に『七日』、2016年に『プールサイドマン』、2017年に『地球はお祭り騒ぎ』を発表。また2019年の第32回東京国際映画祭にてワールドプレミア上映された『叫び声』は日本映画スプラッシュ部門にて監督賞を受賞しました。
映画『普通は走り出す』の作品情報
【公開】
2019年10月25日(日本映画)
【監督・脚本・原作・編集】
渡辺紘文
【企画】
直井卓俊
【撮影】
バン・ウヒョン
【音楽】
渡辺雄司
【主題歌・劇中歌】
トリプルファイヤー
【キャスト】
渡辺紘文、萩原みのり、古賀哉子、加藤才紀子、ほのか、黒崎宇則、永井ちひろ、久次璃子、平山ミサオ、松本まりか
【作品概要】
映画監督・渡辺紘文と映画音楽家・渡辺雄司の兄弟によって旗揚げされた映画制作集団「大田原愚豚舎」の5作目となる長編映画作品。
「音楽×映像のコラボレーション」を目的に数々の優れた映画を生み出してきた「MOOSIC LAB」の2018年度・審査員特別賞を受賞した作品であり、吉田靖直率いるロックバンド「トリプルファイヤー」の楽曲・世界観から着想を得た作品です。
映画制作に悩み苦しみながら映画について毒を吐き続ける映画監督が、繰り返される日常の中で現実と虚構、過去と現在の狭間を彷徨する様を描きます。
渡辺監督自らが主人公の映画監督・渡辺を演じ、共演陣には松本まりか、萩原みのり、加藤才紀子、古賀哉子らが出演を果たしています。
映画『普通は走り出す』のあらすじ

(C)2018 FOOLISH PIGGIES FILMS
数々の映画たちを弾劾するばかりの映画評論家、「お客様は神様」を信じ続ける観客たち、節操のないクラウドファンディング…昨今の日本映画業界に対する様々な愚痴をボヤキ続ける、大田原在住の自主映画監督・渡辺。
彼はロックバンド「トリプルファイヤー」の楽曲を原案とする新作映画の脚本執筆を続けていましたが、その執筆は一向に進まず、日々かかってくる「直井さん」からの電話から逃避しながらも大田原での日常を繰り返していました。
肉体と精神に突きつけられる現実の生活、常に苦心する映画制作の資金集め、評論家たちや観客たちからの非難や誹謗中傷、脚本を書き進められない自身への苛立ち。
そして、自らが映画を作り続けること、関わり続けることの意味と価値。
焦燥と苦悩の中、渡辺はやがて現実と虚構、過去と現在が交錯する世界へと足を踏み入れてゆきます…。
アップリンク吉祥寺・特集上映「異能・渡辺紘文監督特集/大田原愚豚舎の世界」紹介ページはコチラ→
編集長:河合のびプロフィール
1995年生まれ、静岡県出身の詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。
2021年にはポッドキャスト番組「こんじゅりのシネマストリーマー」にサブMCとして出演(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介




































