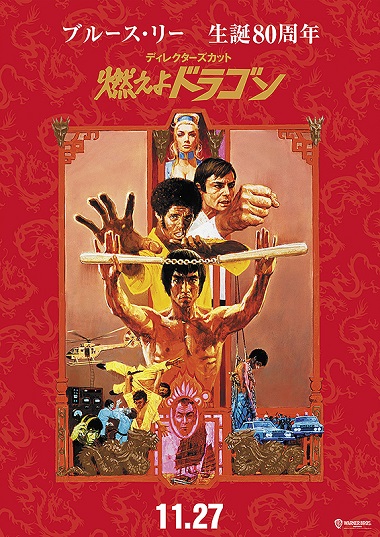連載コラム「新海誠から考える令和の想像力」第5回
7月19日に公開を控える『天気の子』予告編の第2弾が、5月28日に公開されました。
ここであらためて、既出の情報もふくめて、「きみとぼく」の関係を整理してみます。
(1) 夏の日、空の上で、ふたりは「世界」の形を決定的に変えてしまったこと。
(2) 帆高(醍醐虎汰朗)は東京に来た「家出少年」であること。
(3) 陽菜(森七菜)は世界の「秘密」を知る少女であること。
(4) 帆高は「仕事」を探していること。
(5) 舞台は「雨」が降り止まない東京であること。
(6) 陽菜は「100パーセントの晴れ女」であること。
ここまでに論じてきたことが、すべて出そろいました。
(1)は連載の第2回目で、新海誠監督を「セカイ系」の一部に位置づける根拠を提示しています。
(2)は学校をさぼって日本庭園の休憩所で逢瀬を重ねる『言の葉の庭』の設定を想起させます。高校生の孝雄も、休職中の雪野先生も、いったん“家”を出て、自分の“居場所”を求めていました。
(3)は『雲のむこう、約束の場所』で眠りつづける少女・佐由理が、巨大な塔の“謎”を解く鍵をにぎっていることに近いでしょう。
(4)は連載の第4回目で、新海監督と他のアニメーション監督と比較した際に、宮崎駿監督は少年少女を働かせることで「強くあれ」というメッセージを発信していたと述べました。
(5)は多くの新海作品で“天候”が重要な役割を担っていることを過去作からふりかえっています。とくに『言の葉の庭』の雨はふたりを結びつけ、それぞれの感情を表現すべく降りつづいていました。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力』記事一覧はこちら
「100パーセントの晴れ女」が意味するもの

(C)2019「天気の子」製作委員会
さて問題は(6)です。“天候”は自分ではコントロールできないゆえに、新海作品では個人の心情や世界の運命を揺さぶるものとして機能してきました。
実際に今回の「予報2」で、帆高はこのように語っています。
天気って不思議だ。ただの空模様にこんなにも気持ちを動かされてしまう。
つづいて帆高は、こう言い換えます。
心は、陽菜さんに動かされてしまう。
これにより「天気=不思議=不条理=少女=心」という関係が導けます。「新海誠の方程式」と呼んでいいでしょう。
それに対して「もう大人になれよ、少年」という声が入ります。
つまり、このままではいけない、というわけです。
新海監督はコミュニケーションの最小単位は恋愛にあると言っていますが、どうやら今回“きみとぼく”の二者関係に“大人になること”が要請されているようです。
そして、なにかしらの理由で離れ離れになってしまった帆高は「もう一度会いたいんだ」と叫びます。
そのなかで「愛にできることは」「僕にできることは」というテロップが挿入されます。
それらにつづく言葉は「まだあるかい」です。
まとめると、“恋愛”は他者とのコミュニケーションを開くうえで必要な最小単位であるものの、それをより広げるためには“大人”になることが求められ、その過程で“愛”というものが試されている、ということになります。
では、月並みな問いに聞こえるかもしれませんが、愛ってなんでしょう?
『言の葉の庭』とは対照的に、『天気の子』では「100パーセントの晴れ女」が登場するのが特徴的です。
前者の雨が恋模様を描いていたとすれば、後者は愛に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。
そこで、村上春樹の短編小説『カンガルー日和』(講談社文庫、1986年)から補助線を引いてみます。
村上春樹『カンガルー日和』より
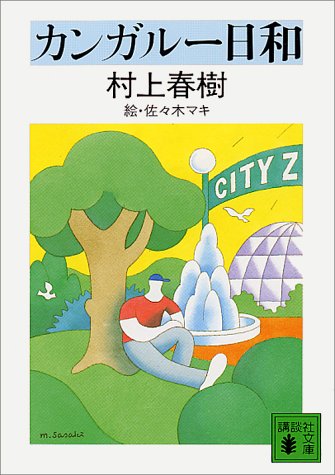
村上春樹『カンガルー日和』(講談社文庫、1986年)
この短編集には「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」と題された掌編があります。
冒頭からこうです。
四月のある晴れた朝、原宿の裏通りで僕は100パーセントの女の子とすれ違う。P19
当然、100パーセントの女の子とはなにか? という疑問がわき起こります。
たいして綺麗な女の子ではない。素敵な服を着ているわけでもない。髪の後ろの方には寝ぐせがついたままだし、歳だっておそらくもう三十に近いはずだ。P19
このあと、足首の細い子、目の大きい子、指の綺麗な子、ゆっくり時間をかけて食事をする子といったタイプが列挙されますが、どれも“100パーセント”とは関係がないというのです。
しかし五十メートル先から僕にはちゃんとわかっていた。彼女は僕にとっての100パーセントの女の子なのだ。P19
なんでだよ、と思わずツッコミを入れたくなる気持ちをおさえ、“僕”の心理にせまっていきましょう。
“僕”は“彼女”の顔も格好も思いだせないといいます。それでも100パーセントだという確信はある。
そこで“僕”はそれを証明するために、こうすればよかったというアプローチを想像してみせます。
ねえ、もう一度だけ試してみよう。もし僕たち二人が本当に100パーセントの恋人同士だったとしたら、いつか必ずどこかでまためぐり会えるに違いない。そしてこの次にめぐり会った時に、やはりお互いが100パーセントだったなら、そこですぐに結婚しよう。いいかい? P24
あくまで想像上の会話ですが、その後、二人は記憶をなくしてしまいます。
二人は通りのまんなかですれ違う。失われた記憶の微かな光が二人の心を一瞬照らし出す。(…)しかし彼らの記憶の光は余りにも弱く、彼らのことばは十四年前ほど澄んではいない。二人はことばもなくすれ違い、そのまま人混みの中へと消えてしまう。P26
察しがいい方は、この展開が『秒速5センチメートル』や『君の名は。』を彷彿とさせることに気づくはずです。
なお、6月14日発売の角川文庫『運命の恋 恋愛小説傑作アンソロジー』のカバー絵に、『君の名は。』の画像が選ばれたことが発表されました。

村上春樹ほか『運命の恋 恋愛小説傑作アンソロジー』(瀧井朝世編、角川文庫、2019年)
村上春樹の短編も収録されており、新海作品との親和性を示しているかのようです。
内田樹『困難な結婚』より

内田樹『困難な結婚』(アルテスパブリッシング、2016年)
「100パーセントの晴れ女」の意味を「晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うこと」の線から、もうすこし考えていきます。
数々の“村上春樹本”を出している内田樹氏の著書に『困難な結婚』(アルテスパブリッシング、2016年)という本があります。
同書においても、前述の掌編を意識した考察があります。
ある日電撃に打たれたように恋に落ちるということがある。四月のある晴れた朝に原宿の裏通りで100パーセントの女の子に出会うことだってある。「電撃」の由来や「100パーセント」の算定根拠なんか、誰にも答えられない。結婚だってそうです。P90
ここで強調されていることは、100パーセントには根拠がない、ということです。
「この人と結婚しようかな」と思ったとき、ことは自分のコントロールを超えているんです。P91
“自分のコントロールを超えていること”という、新海誠論で繰りかえし言及しているポイントがでてきました。
だから、はじめから個人的な出来事じゃないんですよ。生命の歴史のうちに起源を持つことなんです。P96
二者関係が広がりをみせてきました。「100パーセント」の裏をかえせば、「個人的な出来事を超えている」ことが浮かびあがります。
すなわち「100パーセントの晴れ女」は「他者という大いなる存在」であって、“ぼく”の価値観や倫理観を超えてくるものです。
ふたりの出会いでありながら、自分にとっての「他者」に直面し、「世界」の外へ関係が開かれようとしている。
その意味で、『天気の子』は「恋愛」にはない「愛」の諸要素を示唆しています。
ここからは、文字どおり“愛にできること”を考えていきましょう。
レヴィナスと愛の現象学

内田樹『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫、2011年)
内田樹氏はフランスの哲学者・エマニュエル・レヴィナス(1906-1995)の研究者でもあります。
レヴィナスはホロコーストやユダヤ思想を背景に、他者を軸とした独自の倫理学を築こうとした哲学者です。
まず内田樹氏の『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫、2011年)から、レヴィナスの問いをみていきます。
ひとはいかにしておのれ自身の外へ出て、他者に出会うことができるのか。P135
「100パーセントの晴れ女」は、“ぼく”を外に連れだす存在であると言いました。
またそれは、性格やタイプといった認識に先だって訪れる出来事でした。内田氏の言葉を借りればこうです。
私が「あなた」と出会うときに、私はすでに「認識」に先だって「祝福」を行っている。「あなた」の顔を眺め、肌の色や目の色や服装を認識して、「あなた」が何ものであり、どのような属性を持つ者であるのかを特定し、挨拶することが適当であると「判断」したがゆえに挨拶がなされたのではない。認識に先立ち、認識を超えて、私は「あなた」に祝福を贈る。このとき祝福の贈り手である私は、いわば「無からの創造」としてコミュニケーションの場そのものを立ち上げている。P81
レヴィナスの認識によっているので、言い回しがやや難解ですが、「他者」との出会いはコミュニケーションの場を立ち上げます。それと同時に「私」という存在も生起します。
レヴィナスはその出来事を「私が召喚される」というかたちで表現します。
「絶対的に異他的なもの、他なるもの、表象不能のもの、把握不能のもの、すなわち「無限」――それについて、私は無関心でいることができない――それが私を、人間という存在者が現れる表象形式を引き裂きつつ、召喚する。そして他者の顔を通じて、どのような逃げ口上も許さず、私を唯一無二の選ばれたるものに指名するのである。(『観念に到来する神について』 原著P264、内田樹訳)
ここでいう他者とは“絶対的に他なるもの”です。“100パーセントの晴れ女”など、とうてい把握できない存在です。
でも、原宿の裏通りの“ぼく”も、雨が降り止まぬ東京の“帆高”も、そんな100パーセントの存在に“無関心”ではいられません。
コミュニケーションの場に引きずり出され、また引き裂かれながらも、「自分」というものが生じます。
そう考えますと、「ぼく」と「きみ」の関係は、そもそも閉じられることはありえません。
互いの「顔」には、自分以外のだれかの「痕跡」が刻まれているからです。
“他者の顔を通じて”、その相手の顔の背後に、「ぼく」や「きみ」とは異なる“第三者の顔”がのぞかせています。
そこには、ここではない「彼方」が口を開けて待っています。
中山元『思考のトポス-現代哲学のアポリアから』より
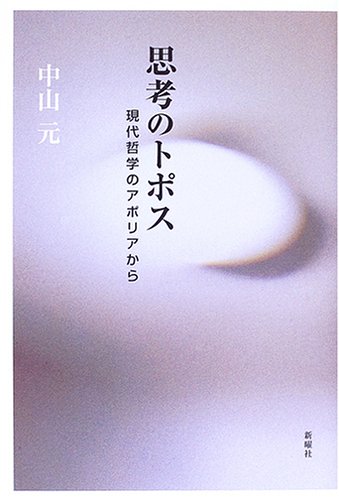
中山元『思考のトポス-現代哲学のアポリアから』(新曜社、2006年)
別の角度から、二者関係に潜む“第三者”をみてみましょう。
哲学者の中山元氏の『思考のトポス-現代哲学のアポリアから』(新曜社、2006年)より引用します。
レヴィナスは「女性」の概念を展開しながら、ぼくたちが他者と親密な関係を結ぶこと、そして「君とぼく」と語りかける関係になることが、ぼくたちがそもそも他者との間で主体として登場することのできる力を生みだすことを認識していた。しかしこの他者は第三者ではなく、二人称で語り合う親しき〈友〉である。P225
序章でその問題を指摘しましたが、いわゆるセカイ系における「きみ」と「ぼく」との二人称の関係には、他者を排除する暗黙の暴力が潜んでいます。
しかしレヴィナスの知見を借りれば、その原初的な暴力の存在を認めながらも、“第三者の顔”が立ちあらわれるとのことです。
二人称で語りあう親しき者の「顔」を通じて、三人称で向き合うべき第三者が、ぼくにその存在を訴えるのである。P226
中山氏の解釈はつづきます。
ぼくたちは友人をその個性において、そのすべての特異性において顧慮し、愛するのである。しかし同時に、友の背後に、排除された第三者の顔が浮かびあがる。P227
次章以降では“愛にできること”の考察を深めていきますが、まずここで言えることがあります。
ひとを愛する感情をもつことが、排除された暴力についての意識を高めるのだと。
「100パーセントの晴れ女」は運命のごとく、絶対的な他者として、帆高に愛の存在を知らせます。
その愛はみずからのコントロールを超え、相手を征服することはできません。
いま、外部に開かれようとしているコミュニケーションの回路を、社会(セカイではありません)のどこに接合すべきか。
第3章第1節にあたる次回からは、レヴィナスの倫理学を中心に、『天気の子』が乗り越えようとしている二者関係、つまりは愛の問題と可能性を提示していきます。
それはいうまでもなく、「令和の想像力」に密接にかかわってくるものです。
【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力──セカイからレイワへ──』記事一覧はこちら