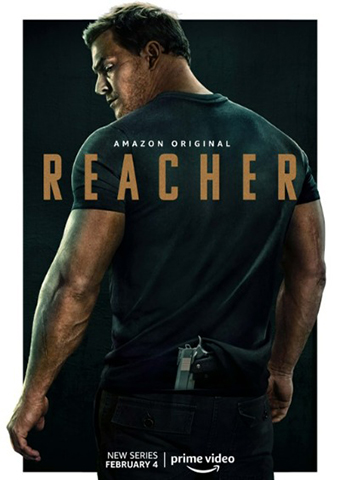連載コラム「偏愛洋画劇場」第4幕
2人の登場人物の片方がもう1人の隠れた自我であり、最後は1人に統合されるといった物語はよく映画、小説で見受けられます。
自分とは完璧に違うもう1人の自分、異なる存在無くしては自分自身も存在することができない…今回取り上げるのはそんな人の心理を恐ろしく耽美的に描いた『戦慄の絆』(1988)です。
監督は『ザ・フライ』(1986)『裸のランチ』(1991)など独自の世界観で人々を魅了し続ける鬼才デヴィッド・クローネンバーグ。
映画『戦慄の絆』のあらすじ
主人公は不妊治療専門の産婦人科医を開業している一卵性双生児の兄弟、エリオットとビヴァリー。
兄のエリオットは野心家、弟のビヴァリーは内気と正反対の性格でありながら一心同体に育ってきた彼らは大人になった今も共に住み続け、何事も全て共有してきました。
ある日彼らの元を訪ねてきたのは女優のクレア。彼女は戸口が3つに別れている特殊な子宮の持ち主でした。
エリオットとイヴァリー双方とも彼女と関係を持つことになるのですが、ビヴァリーは本気で恋に落ちてしまい…双子の兄弟の精神が1人の女性の出現によって均衡を崩していくことになるという、悲劇的なサイコ・スリラーです。
エリオットとビヴァリー、対照的な双子を演じ分けるのはイギリス出身の俳優ジェレミー・アイアンズ。
この後もクローネンバーグ作品に登場する彼はこの『戦慄の絆』での演技が高く評価され、ニューヨーク映画批評家協会賞主演男優賞、シカゴ映画批評家協会賞主演男優賞を受賞しました。
映画『戦慄の絆』の衝撃の実話

本作の原作は小説『Twins』。この小説は一卵性双生児の産婦人科医がマンションで謎の死を遂げていたという実際の事件を基にしたものです。
映画『戦慄の絆』はショッキングな事実だけではなく、人間の深層心理や疎外感、孤独感などにも言及した作品となっています。
真っ赤な背景に怪しげな人体模型図や実験器具、バックにはハワード・ショアの音楽。
そんな不気味なオープニングは“これぞクローネンバーグの世界”と身震いするほど狂気的美しさに満ちています。
2人が身につけるのは真っ赤な手術着、反して彼らが住む家は深く冷たい海の底のように陰鬱な青を基調としています。
『戦慄の絆』の1つの魅力はやはりクローネンバーグ監督のおどろおどろしさと美が共存する世界観でしょう。
拷問器具のようにも見える不可解な形の器具を並べての手術シーンはまるで魔術の儀式のよう。そんな独自の世界で悲哀と鬼気迫る表情を見せるジェレミー・アイアンズがたまらなく艶があり、双子の精神世界へ私たちは引き込まれていきます。
抗いがたいもう1人の自分
クレアという子宮の戸口が3つある女性に出会ったことから徐々に破滅へ向かっていく2人。
しかし彼らは客観的に見れば“破滅”という道を選ぶことになったものの、もともとあるべき姿に回帰したという、ある種のハッピーエンドなのではないかと私は考えています。
1+1+1は3でも、1+1は2でもなく、1になるというのがエリオットとビヴァリーの人生だったのです。
自分が関係を持った男性が双子だったことを知り、2人の元を去るクレア。
純粋に恋をしていたビヴァリーはひどく傷つき、クレアとの関係が回復しても嫉妬に悩まされ徐々に薬物へ依存していきます。
そして弟が自分の元を去ってしまったエリオットも心のバランスをだんだんと崩していくのです。
野心的で自信家のエリオットが精神を蝕まれ弱々しくなっていく姿は弟のビヴァリーそのもの。
兄と離れることを望んでいたビヴァリーも自分たちは精神的に一心同体、互いなくしては生きていけないということを自覚します。
そして全てを捨てて兄と共に狂気に身をまかせる道を選ぶのです。
クローネンバーグ監督作品では様々な異なる存在、世界を徐々に自分自身が受け入れ共鳴するといったテーマが描かれています。
『ザ・フライ』では蝿と人間、『ヴィデオドローム』では1人の男の内面世界と外界、機械と人間。同じ服を着、誕生日を祝い、一緒にケーキを食べ、自分の片割れに刃物を突き立て、後を追う。
残されたのは折り重なった2人の姿…互いに潜行する自我を受け入れ、1つの世界へ帰していくことを選んだクライマックスシーンは悲しくも官能的でとても美しいものです。
精神が外部によって引き裂かれていく悪夢を、彼らは本来あるべき姿に帰結させることによって終えたのです。
彼らの深い海のような部屋は、胎内を暗示していたのかもしれません。
自己の内面を静かに見つめ、深層心理との対話が描かれるこの映画はクローネンバーグ監督にとってもターニングポイントであり、一見悲劇的な結末もハッピーエンドだったと言うことができるかと思います。
まとめ
受け入れがたく相異なる存在が自我の1つ、もう1人の自分が潜んでいる事実。
それが何か出来事によって、第三者の介入によって気付かされる時、私たちはエリオットとビヴァリーのように静かに自分自身と対峙せざるをえないでしょう。
本作は奇妙かつ耽美な世界観に彩られた物語ですが、私たちもこのような内面の葛藤に直面することがあるかもしれません。
静かな狂気に満ちた『戦慄の絆』、クローネンバーグ監督の真骨頂をぜひ今一度ご堪能ください。
次回の『偏愛洋画劇場』は…

次回の第5幕は、フランソワ・トリュフォー監督の『アデルの恋の物語』をご紹介します。
お楽しみに!